「仏教と資本主義」
大学で社会科学系の学部にいると必ず読まされるのが、
マックス・ウェーバーの、
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904年)、
通称「プロ倫」です。
私も学生時代に「プロ倫」の授業が激しく眠かったのですが、
働き始めて、この著作のすごさが身にしみてきました。
職業は神に与えられた「天職」であって
(今でも英語では天職をCallingと言いますよね)、
勤勉と倹約と効率化は天国への道であって、
神のための労働でお金を貯めるのは摂理である。
働いてカネを稼ぐという世俗的なことが、
プロテスタンティズムによって倫理的なお墨付きをもらい、
資本主義がこんなに発展した、というのは、
宗教と世俗の結婚といいますか、かなり衝撃的でした。
では仏教はどうだったのか?
というのが、この本の主要なテーマです。
著者は、ヨーロッパでプロテスタントが起こるより800年も前に、
同じ考えを説く仏教者が日本にいた、と言います。
それは奈良時代の行基(668~749年)です。
行基の師匠の道昭は、唐で玄奘の教えを賜り、2つのことを持ち帰ります。
ひとつは、「地獄のイメージ」。
「瑜珈師地論」「倶舎論」を持ち帰り、そこに書かれた
目に見えるような恐ろしい地獄のイメージを伝えたこと。
もうひとつは、中国の灌漑技術・土木技術。
行基は師の土木事業を引き継ぎます。
当時、平城京の建設で、あちこちの農民が駆り出され(往復は自腹)、
途中で行き倒れて餓死する人も多数あったそうです。
そこで、行基は山陽道の要地に、行き倒れた人を泊めて粥を出す
「布施家」をつくります(今でいう派遣村みたいなものか)。
で、生き延びた民衆を使って、土地改良事業(灌漑や道路工事や橋の建設)
を行います。
民衆は、そういう土建屋仕事を「菩薩行=利他行」と信じてよく働き、
その事業に出資した豪族もうるおいます。
逆に言えば、民衆は「働かなければ、あの恐ろしい地獄に落ちる」
という脅迫観念も抱えていたわけです。
そうやって民衆の中で勝手なことをした行基は、
最初、当局(朝廷)からクソミソに言われますが、
その動員力と土木技術を買われて、
東大寺建立をはじめ数多くの寺の建立にかかわり、
公共事業を担うゼネコンのリーダーのような存在になります。
もともとお釈迦さまの僧団は「労働禁止」だったことを思うと、
ずいぶん遠くにきたもんだという気がします
(もちろんお釈迦さまは在家に対して、労働禁止なんて言いませんが)。
ずっと時代が下って、江戸時代初期(プロテスタントが生まれた頃)にも、
労働=菩薩行と考える人たちはいたそうです。
たとえば鈴木正三(しょうさん・旗本から突然、仏道に入った私度僧)は
『万民徳用』という本邦初の職業倫理を説く本を書いたそうです。
いわく「農業は仏行である」「一桑一桑に、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏と
唱えながら耕作すれば、必ずや仏果に至るであろう」と。
与えられた仕事が「天職」で、働くことは世のため人のための利他行である、
という労働観は、今の日本にも通じているように感じます。
実際にサラリーマンをやっていると、それは、いい面と悪い面があります。
いい面は、「働く以上は人の役に立ちたい」という、職業倫理がどこかで
私たちの心に根付いているということ。
悪い面は、どんなに無意味な仕事(ときには有害な仕事、
本当は利益のためでしかない仕事)であっても、
「世の中のためになる」と自分を正当化して暴走すること。
それから、「業績が悪いのは人間として修行が足りない」みたいなことを言う
悪徳経営者にうまく利用されて、自分もそう思って、過労死したりすること。
その危険は、この本の著者も最後に指摘しています。
それをうまいこと利用した現代の例は、
『カルト資本主義』(斎藤貴男著)などにも出てきます。
私個人としては、宗教と、職業倫理のような世俗的なことが、
過剰に結託するのは、どうも気持ちが悪い気がしています。
- 仏教と資本主義 (新潮新書)/長部 日出雄

- ¥714
- Amazon.co.jp
にほんブログ村
ロックな坊さん
仏教+ロックの映画を観てみたい、と思っていたら、
そういう映画がもうじき完成することを知りました。
タイトルは『アブラクサスの祭』。
禅僧の芥川賞作家・玄侑宗久さんの同名小説の映画化です。
この小説(読んでないのですが)、新潮文庫の帯が最高です。
「ロックで六道輪廻を突き抜けろ!」
主人公は昔インディーズバンドをやっていた
福島にある禅寺の住職さん。
不器用で日常のいちいちがスムーズにできず、
しかも「分裂症まじりの躁うつ病」。
この住職さんが、ロックバンドを結成して
ライブをやることを思い立ち・・・という物語だそうです。
主人公役はスネオヘアー。
(本物のミュージシャンでよかった!
フリだけだと音楽シーンが観るに耐えない)
12月にクランクアップして、編集中らしいので、
来年には封切りになるでしょう。楽しみ。
ロックで解脱だ~。
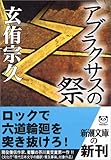
にほんブログ村
座禅クリスチャン
東京禅センター 花園大学公開講座(09年12月)その2
昨日の続きで、安永祖堂先生(国際禅学科)のお話です。
◆ ハビアンはなぜ禅に見切りをつけたか ◆
江戸時代に入る直前、大徳寺(臨済宗)にいて禅に失望し、
イエズス会に改宗してしまった不干斎ハビアンは、
『妙貞問答』(1605年)という衝撃の本を書きます。
仏教の諸宗派・儒教・道教・神道が「いかにダメか」、
それに比べてキリスト教がいかに素晴らしいかを書いたこの本は、
超タブーの禁書として葬られて、現在、日本に上下1冊ずつしか存在しません。
それはそうですよね、超1級のインテリが、
日本にあるすべての宗教をクソミソにかいたわけですから。
(でも結局、ハビアンはイエズス会でも失望して、
1608年に脱会して、なんと修道女と駆け落ち!
今度はキリスト教をケナす本を書くのです=1630年)
ではなぜ、ハビアンは禅に見切りをつけたのか。
ひとつは、当時の禅が「公案を集めて箱にしまって満足」のような、
怠惰・高慢な状態にあったこと。
たぶんハビアンは大徳寺で、ちゃんとした禅体験が得られなかった
のではないか、仏教の知識もイエズス会で勉強したフシがある、
と安永先生。
イエズス会から見れば、禅宗の組織も内幕も知っているハビアンは、
布教のための傭兵として利用されたのではないか、とのことです。
ただ、ハビアンは結局、どの宗教でも救われなかった。
そんなふうに、禅宗がダメになっていた時代、
臨済宗にさっそうと現れたのが白隠禅師(1685~1768年)。
形骸化していた禅を、民衆にわかりやすく広める(慈悲行)
ことで臨済宗を立て直したわけです。
◆ なぜか座禅を組むクリスチャンたち ◆
禅とイエズス会が実は似ていた、という話を昨日書きましたが、
今でもクリスチャンが座禅を組むことが少なくないそうです。
「キリストの教えを深く知るために座禅を組む」という、
ちょっと倒錯した状況が欧米であるそうなのです。
たしかに、ググッて見ると、
日本でもキリスト教会がけっこう座禅会をやっております。
中国などは、禅のノウハウが途切れてしまったので、
カトリックの伝道士に座禅を習うとか。
有名なのは「門脇神父」(上智大学名誉教授の門脇住吉氏)。
イエズス会の神父であると同時に、禅の指導者でもあり、
キリスト教と禅の両方の道を説いておられます。
「でも」、と、安永先生。
「キリスト教と禅は、一人の中で両立するのか?」。
「私は、しないと思う」と安永先生は言います。
禅の基本は、仏と凡夫の関係は「水と氷」。
つまり、小さな我執で凝り固まった氷=凡夫だが、
それが解ければ、水=仏になることができる。
一方でキリスト教は、神と凡夫の関係は「水と油」。
凡夫はどんなにがんばっても神にはなれないし、
つねに油は水の上に存在する。混じらない。
両立している人(門脇神父とか)がいるなら、
それは「水ー氷」か「水ー油」か、どちらかの関係を
変質させているにすぎないのではないか、と。
実際、キリスト教の総本山・バチカンは
警告しているそうです。
「キリスト者が東洋の座禅やヨガなどを
いたずらにやるのは、危険である」と。
禅宗側も、同様の懸念を持っているそうです。
両方から「危険だよ!」と言われつつ、増殖する座禅クリスチャン。
でも一方で、座禅クリスチャンがあまりに真剣なので、
そこから新しい信仰の形が生まれてくるかも・・・
という希望もなくはない、と安永先生は言います。
「チェア・ポジション」。これはアリなのでしょうか?
にほんブログ村




