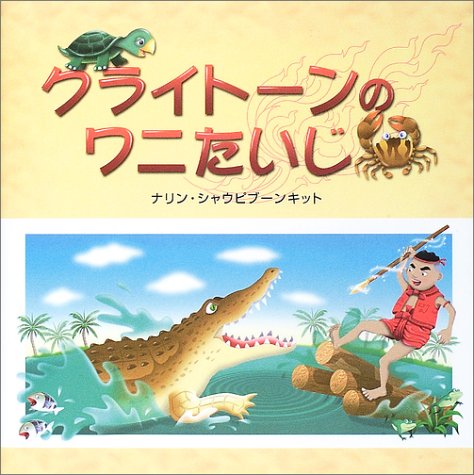2025年に完走したタイドラマ、下半期です。
上半期はこちらです。
配信プラットフォームで観たものは、自分が選んで観たものです。CS放送などテレビで観たものは、放送されたものを選ばず観ました。
主要な出演者は、いわゆる「左右」関係なく記しています。
まずは待ちに待っていたこのドラマ!
『The Ex-Moring』(Krist Singto GMMTV 楽天TV)
SingtoさんのGMMTV復帰第1作にして、2人のW主役作品としてはなんと『SOTUSS』(2017)以来、8年ぶりの再共演!
ということで、この作品は、SOTUSシリーズや実際のKristSIngtoのエピソードへのオマージュも散りばめられていました。
天気予報の人気キャスターKristくんがある行為で人気暴落。
その人気をとりもどすべくオーストラリアからやってきたのは、かつての恋人なのに、不可解な別れを告げてKristくんを絶望に落とし消えたSingtoさんでした。バンコク近県の塩田がロケ地のひとつになっていて、その美しさに塩田人気も高まりました。
たくさんのostも創作され、PERAYAとしては胸がいっぱいでした。
かつて『Romantic Blue』(Channel8と iQIYI )というSingtoさん外部出演ドラマで共演したOhm Thitiwatさんが、GMMTVに入って、再共演しているのも見どころです。

『Addicted Heroin』(August Mac WeTV CS日テレ)
中華ドラマで大人気だったという『ハイロイン』のタイ版です。
『ハイロイン』が未見だったので、CS日テレで放送されなかったら観なかったと思うので、よかったです。
主演のひとりMacくんはかつてSingtoさん主演の名作『清明節 彼は僕のお墓の隣りにやって来た』で、Singtoさんの相手役Ohm Pawatくんの少年時代を演じた子役さんでした。
りっぱに成長して、ということでSingtoさんファン界隈でも話題になっていました。
意外にも重い内容かと思いきや、明るくポップな進み方でつらい試練もあり、最後はオープンエンドでありながら、タイらしい明るい青い海で終わりました。

『The Boy Next World』 (Boss Noeul Me Mind Y, CS日テレ)
おもしろかったです。
平行世界で恋人だった、とやってきたBossくんにほんろうされるNouelくんですが、意外にも不思議なふんいきでBoss
くんのトラウマが描かれ、なんともいえない作品になっていました。

『Memoir of Rati』 (Great, Inn GMMTV, 当時YouTube ファンサブあり。現在は楽天TVで配信が決まりジオブロ)
いやもう!美しいのひとこと!


顔面のよすぎるGreatさんとInnさんが、GMMTV初の「時代もの」ドラマで雰囲気たっぷりに演じます。
時代は第一次大戦勃発のタイ(当時シャム)。
海外諸国の植民地になるまいと外交にふんばっているシャムの伯爵Greatさんと、タイの低い身分の子どもに生まれ、フランス人の養子になってフランスで暮らし、通訳としてタイにもどってきたInnさんの運命の出会いです。
男性同士の愛が認められていない時代でも、思いを貫く2人。
サブカップルのAouさん(人力車夫)とBoomさん(男爵のむすこ)という、もっと結ばれそうにない2人も、だんだんと近づく過程がよかったですし、AouBoomの良さを初めて知りました。
GreatさんとInnさんはカップル役は二作だけと決めていたそうで、最後のカップル役になりました。
Greatさんはなんと『愛の香り』(2024年はまりまくってBlu-rayまで買った)のBrightさんとカップルを組むことになりました。

『High School Frenemy』(Sky, Nani GMMTV YouTubeファンサブあり)
タイ本国でSkyNaniというブロマンスカップルがすごい人気だと知って、長いドラマですが、字幕をつけてくださった方もいらして、手を出しました。
いやーうわさどおり、毎回こぶしとこぶしのぶつかりあい!何かというとまずこぶし!


女子も平手と平手のぶつけ合い!(この女子の間の平手からの友情もとてもよかった)
もう絶対致命傷でしょうという大けがをおっても翌日には立ち直る!いっそ痛快!
そんな中、こんな問題クラスの担任をつとめるジャン先生とFoeiさん先生がとてもよかったです。
退学や停学を他の先生に言われても、しんぼう強く見守り続ける。できることではありません。
とくにジャン先生はスウェーデン系タイ人でミス・ユニバース・タイランド出身だそうで、長身でステキな先生でした。

『My Magic Prophecy』(Jimmy Sea GMMTV 楽天TV)
大好きカップルJimmy先生とSeaくん。医師であるJimmy先生が医者役っていう夢の配役。
美しい手さばきの治療が見られます。
毎回、放送のあと、今回の医療について説明ツイートをしてくれるJimmy先生でした。
そして2人で北タイの村で暮らすのですよね。
この村の子ども役で、Himawari Tajiriちゃんという売れっ子の子役さんが出てきます。その名まえがあらわすとおり、ご両親のどちらかが(どちらとは公表していないそうです)日本人だそうです。

『ケムジラ』 (Keng Namping DOMUNDI 楽天TV)
出ました!たぶん今年1番はまったドラマです!


男子はすべて21歳までに死んでしまうという呪いにかけられたケムジラ(Namping)。
東北タイの村の呪術師パラン(Keng)くんのところに救ってもらいに行きますが・・・
タイの土着の文化、呪術、祭祀、輪廻転生、愛と業、すべてがミックスされ、タイ好きの身としてはぞくぞくしっぱなしでした。
東北タイや、幾層もの過去の時代すべての映像が美しいです。
しかも導師パランが出てくるたびに息をのむ美しさ!これは必見です。
そしてケムくんを救おうとする大学の友人たちとのきずなも良いです
第1話こそ、悪霊がたくさん押し寄せるホラータッチですが、その後はとにかく物語として目を離せません。
1話が2時間の回もありましたが、秒で終わる感覚でした。
しかも子役ちゃんたち、Udonちゃん、Ryujiくん、Himawariちゃんがもう達者でかわいくて!
すごかったですー。

『Beauty Newbie』(Beifern Win GMMTV CS日テレ)
韓国ドラマ『私のIDはカンナム美人』(未見)のタイ版ということで、整形で美しくなって大学に入ったBeifernちゃんがさまざまないじめをのりこえて成長していく物語ですが・・・
このイジワルがつらくて、何度も途中で観るのをやめました・・・
が、それをまた気をとりなおして見続けようという気持ちになったのが、当て馬役のGreatさんのチャーミングさ!
サービスカットもたくさんありました。Greatさんの良さがとてもよく出ていたと思います

『Last Meal Universe』(Ritz , Gun Very Great Channel We TV)
VPNをつながないといけないドラマなのですが(無料)、Xでフォロワーさんたちが、Ritz先生(彼も医師です)が、宇宙人の役で、傘をさしてメアリー・ポピンズのように降りて来る、すごいおもしろいドラマだと聞いて・・・
・・・
すごいおもしろいドラマでした!
地球を破壊する使命をおびて地上に落ちて来たRitz先生ですが、Gunさんの作るタイ料理の数々があまりにおいしくて、ついつい破壊するのを一日伸ばしにしてしまいます・・・
このタイ料理がほんとうにおいしそうなんですよ。
こんな破天荒な設定でも、ハートウォーミングでロマンチックに見せてしまうタイドラマ、すごいです。
大人2人の仲もとってもチャーミング。あと、ぶたねこさんたちもおもしろいです。

『Top Form 』(Smart, Boom WeTVとTailaiEntetainment CS日テレ)
今年最後に完走したドラマです。
日本のBLマンガが原作だそうで、エンディングのostが日本の歌でした。
原作は未見なのですが、独立したドラマとして、おもしろく観られました。
年上Boomさんと年下Smartさんがとにかく顔が良くて、ケミもとてもよかったです。
事務所の違う俳優どうしの恋愛ということですが、攻めていくSmartさんが愛らしいのに誘惑的で魅力的。
俳優としての経験は豊かなのに広い世界を知らないBoomさんも純真でよかった。
おふたりのこれからの活躍もお祈りしています。
【番外編】
『DMD Friendship』
『DMD Friendship It Takes Two』 (DOMUNDI、YouTube 日本語字幕あり)


『ケムジラ』にはまってから、ケムジラメンバーのデビューのきっかけになった、サバイバル番組に手をつけてしまいました・・・
今までボーイズグループ選出のサバ番、Project Alpha、Raz iCon、789Survivalと観ましたが、サバ番、1話が長いのと手をつけはじめたら続きが気になってそればかり見てしまうので、もう観るつもりなかったのに・・・
そうしたらこれがですね!
ボーイズグループでなくて、BLドラマの主演カップルをおたがいに選ぶっていうサバ番だったんです。
もうとにかく、エモい、エモすぎる!!
ここから『ケムジラ』ほかのDMDドラマができたんですね・・・
いやすごいわーーー。
ということで、下半期も充実した番組がたくさんありました。
今途中まで観ているのがNetflixの『ザ・ビリーバーズ2』、楽天TVでリアタイしている『MeandThee』どちらもすごくおもしろいですし、U-Nextには『Shine』が来てるし、テラサではリケードラマの配信が始まったし、これからも良い
ドラマがたくさん出て来そうで楽しみです。
2026年もこのブログともどもよろしくお願いいたします。
ということで、下半期の1曲はこちら。
『DMD Friendship』の『GEN3』メンバーによる『Cuteness Center』です。
このサバ番がめざすところがよく表れている歌とMVだと思います
そして今年最後の宣伝、『タイドラマにときめきながら覚えるきほんのタイ語フレーズ』です
![]() 、ということで観に行きました。
、ということで観に行きました。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()