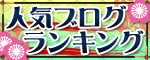【12分で解説!】勝海舟がいなかったら今頃〇〇なことになってた!?
日蓮大聖人様の御書には、法華経の兵法について書かれています。
「なにの兵法よりも法華経の兵法をもちひ給うべし」(四条金吾殿御返事)と言われています。
兵法とは、何でしょうか? 兵法はたくさんあります。一番有名な兵法は、孫子の兵法です。呉子の兵法、六韜三略の兵法などの兵法書がありますが、いかなる兵法よりも、「法華経の兵法をもちひ給うべし」です。
では、どのように用いるのでしょうか? 相手が攻めてきたら、「南無妙法蓮華経」とお題目を唱えるのでしょうか? そのように思ってしまいます。兵法は、人を殺すためにあります。
相手をだまして殺してしまうのが兵法です。或いは、兵隊にも種類があります。強い兵隊と、暴力団的な兵隊がいます。相手が筋もない暴兵の場合は、ふせぎようがありません。暴兵が来た場合は、逃げるのです。体をかわすのです。
反対に強い敵兵が来た場合は、罠にかけてやっつけてしまうのです。ジンギスカンは、相手を罠(trap)にはめたのです。蒙古人は狩猟民族ですが、あれは源氏の戦法だと言われています。
源義経は鵯越の逆落としをして、敵陣地に奇襲をかけたり、嵐の日に船を出して、相手の本拠地を攻撃したのです。義経は、罠(trap)をかける名人です。そのようなことを見ていくと、ジンギスカンは、源義経だったと言えるのです。これを歴史常識論といいます。
ジンギスカンの旗は白旗です。源氏も九本の白旗です。平家は赤旗です。ジンギスカンも、九本の白旗を掲げていたのですから、源氏と全く同じです。まだ、成吉思汗の遺体は発見されていませんから、「どのような剣を持ち、どのような鎧を着ていたのか?」ということは、わかっていません。歴史常識論から考えてみても、源義経は絶対にジンギスカンです。
蒙古の平原に戦争の天才は現れません。義経は鞍馬山にいた頃に、全ての兵法書を学んで知っています。兵法の基本は、人を殺すことです。「どのように殺すのか?」というと、「罠(trap)にかけて追い込んで相手を殺す」というのが、兵法の基本です。普通の兵法は、そのような内容です。
では、「法華経の兵法」とは、一体どのようなものでしょうか? 一言で言うと、「罠(trap)にかけるな」ということです。兵法とは、罠(trap)にかけたり、だましたりするのですから、そのようなことが法華経の兵法ではありません。
相手と戦う場合には、「道理をもって戦いなさい」ということです。これが、法華経の兵法です。
「仏法と申すは道理なり道理と申すは主に勝つ物なり」(四条金吾殿御返事)です。道理というものは、何より強いのです。ロシア、中国、北朝鮮のような道理のない国でも、こちらが道理を通していくと、敵わないのです。
法華経は、人を救うための仏教です。人を救うための仏教が、戦争で相手をやっつけるための兵法であるわけがありません。「南無妙法蓮華経」という旗を立てて、戦に行くのでしょうか? 或いは「南無妙法蓮華経」と題目を唱えて、太鼓を叩いて、人を殺しにいくのでしょうか? 法華経の兵法とは、そんなものではありません。
兵法とは、一般的に人を殺すためのものですが、法華経の兵法とは相手を生かすための兵法です。仏様の戦いは、相手を生かすためです。武将は、相手の命を取るために戦うのです。同じ兵法でも、全然違います。
すると、一時的には、暴力で相手を殺したほうがよいように思いますが、結果的には、道理が勝つのです。
仏様の慈悲は広大ですから、敵であっても「殺してよい」とは考えません。敵であっても、「どのように生かしていけばよいのか」ということを常に考えているのです。「道理とは何か、どのように相手を生かしていけばよいのか」ということを常に考えているのです。これが法華経の兵法です。
戦争になっても、できるならば相手を殺さないほうがよいのです。戦争の場合は、止むを得ない場合もあります。
法華経の兵法をもって、正義の大義がないと戦争をしても負けてしまうのです。先の大戦がまさにそうです。正義と言っても、様々な正義があります。普通の兵法にも正義はあります。儒教にも、孟子の教えにも正義があります。
法華経の兵法は、兵法を超えています。「相手はバカだから、殺してよいのだ」というのは、兵法ではありません。相手を正しく導いていくために、生かすためにやる戦が法華経の兵法です。
普段から、そのようなことが身についてくると、人から害されることはなくなるのです。「あの野郎、ぶっ殺してやる」という暴徒が来ても、殺すことはできません。僕の所に来たら、生け捕りにしてしまいます。手も触れることはありません。手も触れないで、相手のことも考えてあげるのです。
日蓮大聖人様もそうだったのです。「念仏の悪口を言う不届きな坊主だ、殺してやる!」という連中が、何人も来たのです。佐渡に島流しになった時は、阿仏房が日蓮大聖人様を殺しに来たのです。
すると、日蓮大聖人様は、「貴方が言っているのは、経か、論か、釈か?」と聞かれたのです。お釈迦様が説いたものが経です。それを解説したのが論です。論をさらに解説したのが釈です。
これを経、論、釈といいます。「私のことを阿弥陀様の悪口を言う坊主だと言いましたが、貴方は何に基づいて言っているのですか?」と聞くと、阿仏房は参ってしまったのです。
天台大師は、論師です。一念三千とは、論です。それをさらに訳されたのが、伝教大師です。そんなことも知らないで、日蓮大聖人様のところに殴り込みをかけても、通用しません。
昔の人は、素直ですから、それで参ってしまうのです。阿仏房は、「申し訳ありません」と謝ったのです。それで阿仏房は、日蓮大聖人様の御給仕をしたのです。
日蓮大聖人様が佐渡島に島流しにされたのは、極寒の12月です。死体置き場の穴があり、その傍に小さなお堂が建っています。そこに流されたのです。そこには食べ物もありません。ただ、雪が深々と降り注ぐだけです。
「日蓮、極寒地獄を体験した」と言われたのです。そのくらい、冬の佐渡島は寒かったのです。日蓮大聖人様は、阿仏房が御給仕したことにより、生きながらえたのです。法華経の兵法とは、そのようなことです。
日蓮大聖人様は、本当に相手のことを思って言っているのです。相手はわけがわからないで、日蓮大聖人様を攻めているのです。そんなことをしたら、自ら罰を受けてしまうのです。そのようなことがないように、日蓮大聖人様は慈悲をもって破折されるので、相手は歯向かえなくなってしまうのです。これが法華経の兵法です。
それに似た兵法を使ったのが、勝海舟です。勝海舟は、年中人から狙われていたのです。「幕府を売った不届きな奴だ」と言われて、毎日、刺客がやってきたのです。勝海舟の家は、女中さんが20人もいたのです。坂本龍馬も刺客の一人だったのです。「勝はおるか、お前は幕府を売って、外国に魂を売っているのか!」と、刺客がやってくるのです。
勝海舟の家で最初に出てくるのは、女中さんです。「お待ちください。ご主人がでてきますから」と言って、部屋に通すのです。部屋に通すと女中さんが、お茶を持ってくるのです。勝さんの家には、20人も女中さんがいて、女性が対応するので、刺客の殺気も消えてしまったのです。
殺気がなくなってから、勝海舟がでてきたのです。勝さんの刀は紐で縛っているので、刀は抜けないようになっていたのです。勝海舟は、剣術の名人ですが、人を斬ったことは一度もありません。
斬りつけてくる奴もいたのです。「勝はお前か!」と言って、斬りかかってくるのです。それでも勝さんは、刀を抜きません。一撃をかわしてから、「お前の言いたいことを言ってみろ」と言って、相手の殺気をおさめたのです。
もちろん、家の中では女中さんがでてくるので刺客の殺気も消えてしまうのです。坂本龍馬もそれで勝海舟の弟子になってしまったのです。これも法華経の兵法に近いやり方です。昔の人は、スキがありません。
桂小五郎も剣術の名人だったのですが、絶対に斬り合いをしなかったのです。神道無念流の塾頭をやっていたのです。でも、本人が逃げてしまうのです。「逃げの小五郎」と言われたのです。
弱いから逃げるのではありません。人を殺したくないから、逃げていたのです。新選組も「桂小五郎に会ったら、逃げろ」と言っていたのです。そのくらい強かったのです。「逃げの小五郎」と言われるのも、法華経の兵法のうちです。
我々の場合は、逃げるわけにいかないので、法論の勝負です。論を立てて「何処が悪いのか聞きましょう」と言えば、相手はおさまるのです。
「なんだ、テメー、この野郎!」と言ったら、殺し合いの喧嘩になってしまいます。まず、「貴方は経について言っているのですか、或いは論について言っているのですか、釈について言っているのですか?」と相手の言い分を聞くのです。
国の場合は、国の指導者は、法華経の兵法を保たなければいけません。加藤清正の旗印は、「南無妙法蓮華経」でした。それも法華経の兵法のうちに入っているのかもしれません。
相手を生かす活人剣が法華経の兵法です。それは、相手の仏性を明かす戦いです。人々は、仏教のことを知りません。慈悲をもって戦っていくことが、法華経の兵法ではないかと思います。
お読みいただきありがとうございます。
よろしかったらクリックしてください。
応援よろしくお願いします!
↓↓↓
※今年から、『中杉 弘の徒然日記』は、月曜日から、金曜日まで掲載します。
土曜日(0:00)は、正理会チャンネルをご覧ください。
■新番組「中杉弘の毒舌!人生相談」
第18回、12月16日(土曜日)0:00公開!
是非、ご覧ください!
↓

■『正理会ちゃんねる』は、土曜日連載中です。
↓
■『中杉弘のブログ』2006年より、好評連載中です!
↓↓↓
http://blog.livedoor.jp/nakasugi_h/?blog_id=2098137
■『中杉弘の人間の探求』にて、「法華経入門講義」を連載しています!
こちらもご覧ください。
↓↓↓
https://ameblo.jp/nakasugi2020