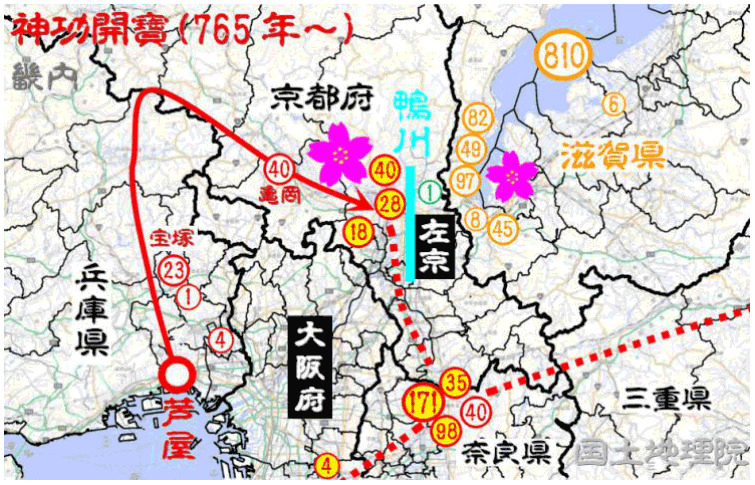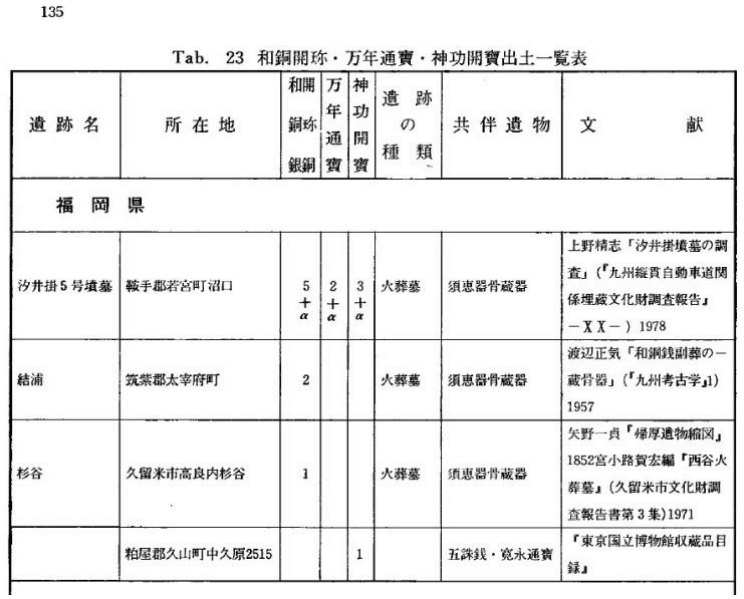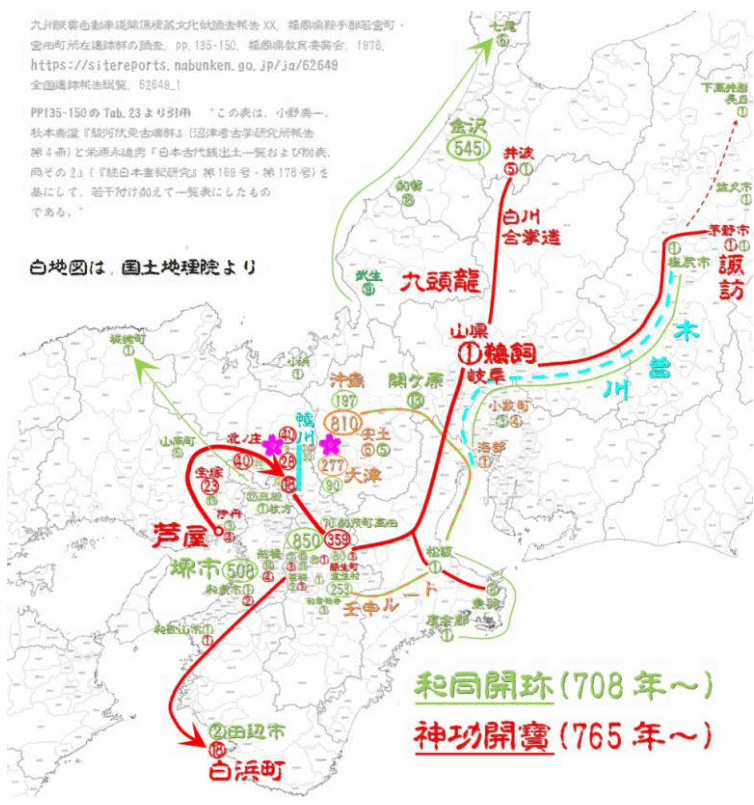Whirlpool of Bhitari Pillar
グプタ朝のスカンダ・グプタの"Bhitari Pillar"石碑です。
[India1871, pp94-95 Plate XXX line 15 and 16]

注目は15行と16行目です。Hunaが、グプタ朝のスカンダ・グプタへ攻め込み、受けたダメージが記されています。
でもグプタ文字で読めません。
ただ、研究されて英語に翻訳したものが次です。
[A. M. Shastri, p379]
"When he (Skandagupta) joined in close conflict with the Huṇas,
the earth was made to tremble due to (the power of) his arms, since
he caused a terrible whirlpool among the enemy by ... of arrows; the brilliant ... is proclaimed ... (which)
sounds like the twanging of (his) bow (sarnga) in (their) ears."
<概訳>
スカンダ・グプタがHunaと実際に戦闘した時、Hunaの力のために
地面が揺れた。なぜならスカンダ・グプタは、敵のHunaの中で、
渦巻き疾患にかかった。(矢の...により) 華々しい...宣言された。 ...
耳の中で、Sarnga(ガンジス川)の濁流の弓のような轟音。
<コメント>
これは病気の話です。
全く同じ病気に、罹った体験談から言うと、
カンジタ(Candida)です。
耳鼻科で聞いた説明ではカンジタ菌により鼓膜に穴が開き、
耳の奥から液が漏れ出してきます。むせる温泉の亜硫酸ガス(SO3)ではなく、硫化水素(H2S)の物凄く臭い液です。御トイレの匂いです。カンジタ性「耳漏」と言うそうです。
さらに耳鼻科での説明では、
耳の奥、内耳の平衡感覚をつかさどる三半器官(耳の奥の渦巻き)もカンジタ菌に侵されて、
平衡感覚を失いフラフラします。
体験談をもとに言うと、
カンジタ症(Candidiasis)です。
体験談と全く同じ症状です。完治するまで、相当期間、薬を飲んでいます。さらに耳浴、点眼、点鼻、全身ローションもしています。あわせて食事療法で、グルテンフリーと食酢の食事が、絶対に必要です。
※ 体験談から言うと、喉が痛くなった場合は、飲み薬を少し減らします。そしてリキッドタイプのGUM(R) PLUS+で、歯磨き・うがい,そして充分すすぎをします。さらに歯茎の硬く痛い部分をオーラル脱脂綿薬で長時間噛んでいました。これは個人差がありそうです。
体験談から言うと、ポイントはリキッドタイプのGUM(R) PLUS+ で、うがい、そして充分にすすぎをして(数分以上)、直ぐにオーラル脱脂綿薬を噛むと効果的です。痛いところに押し付けます。さらにオーラル脱脂綿薬を噛んだまま、横臥で数十分間横になっていると、更に効果的です。夜は朝まで噛んでいます。
一方、食事は、グルテンフリーのために、レシピのバラエティーが制限されます。しかしライスピラフ、ビネガーポテトサラダ等、たくさん食べています。
新レシピとして、米粉野菜テンプラは少し難易度がありました。米粉濃さ、テンプラ油温度、直前のベーキングパウダー添加など、試行錯誤しました。(油分はキッチンタオルでほとんど吸収) そして米酢+グルテンフリー醤油+だし汁希釈(南蛮風のとろみ無)に、数分間ひたして食べる、自身新レシピです。わずかにサクサク感が残っているのを噛みながら食べる食感で御飯のおかずに最適です。
さらに体験談では、潤沢な酢の摂取がグルテンフリーと共に、薬効を強め、回復が早くなると印象を受けました。上がらなかった左腕が上がるようになりました。
飲み薬は脱脂粉乳(商品名スキムミルク)で飲んでいます! Bye Bye
引用文献
[India1871]
Archaeological-Survey-Of-India--Vol-1.pdf
Alexander Cunningham, FOUR REPORTS, MADE DURING THE YEARS 1862-63-64-65, The Archeological Survey of India,The Government Central Press, 1871.
[A. M. Shastri] images
Ajay Mitra Shastri, A Note on Skandagupta's Bhitari Stone Pillar Inscription, verses 8-12
[IN00036]
Razieh B. Golzadeh, Bhitari Pillar Inscription of Skandagupta
↓詳細は以下で