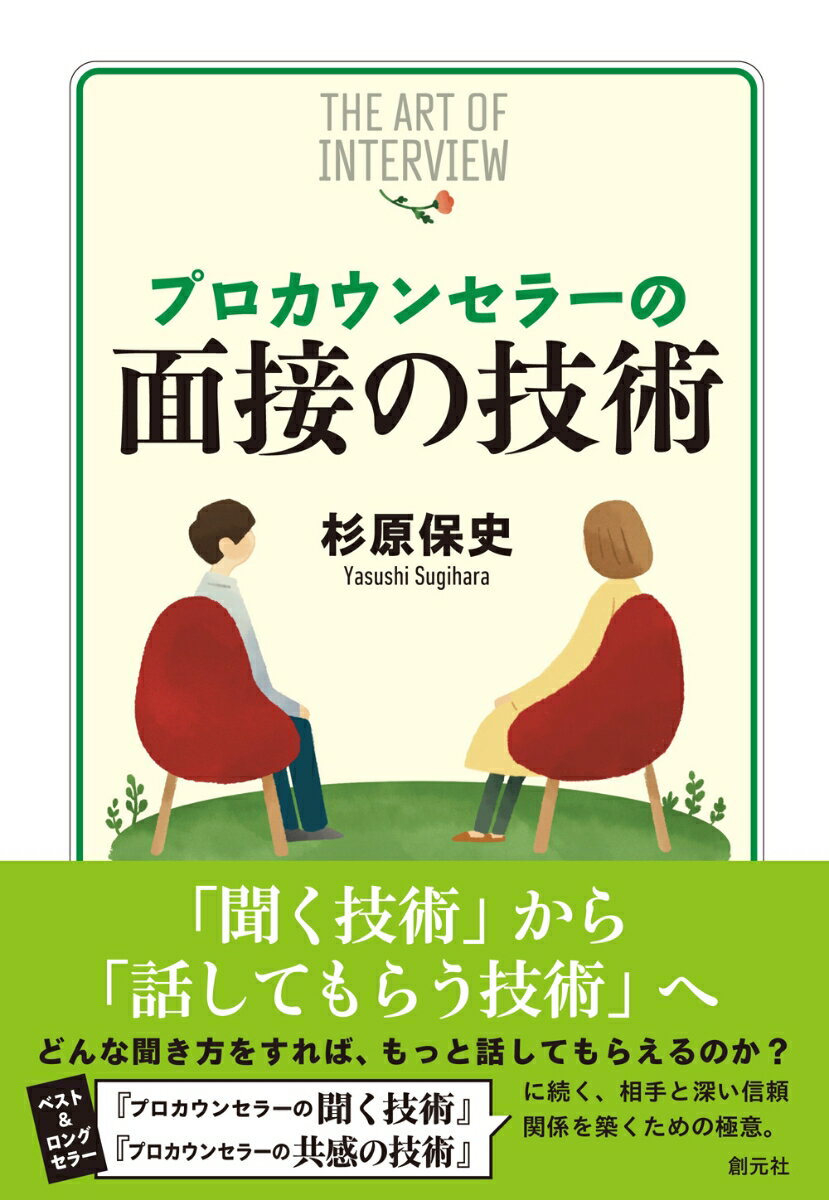こんにちは![]()
地方で中古住宅住まいのブログです![]()
借りた本から、昔話を![]()

昨日はヨガに行き、急いで帰宅後、
前日に急にかかってきた電話で
訪問してくることになった、ケーブルテレビ受信機の交換🏠
ここで危うく詐欺に引っ掛かりそうになりました![]()
受信機の交換自体は無料なのですが、最後に一つだけお知らせを、と流れるように話し出して光回線の契約をケーブルテレビ会社のものにまとめさせようとしてきました。
最初は「手出しはない、キャンペーンのキャッシュバックで解約手数料は相殺」というありがちなコメントに、更には「月額利用料も安くなる」という説明だったのですが、どう考えても高い。違和感しかない。
流れるようにその場でプロバイダに電話させてプラン変更させて、怒涛の勢いで契約書類に記入させようとするので、
その前に
「今の請求状況を確認させて下さい」
と言って確認したら、¥3,000台の利用料が安くなって¥5,000台になるという。
さすがの私でも(←ネットとか疎い奴)、
「夫に相談してからにします」とはっきり言って、事なきを得ました💦
さすがに夫に相談されたらバレると思ったのか、以降あっさりと引き下がりました。
皆さまも気をつけて![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
さて、次のこちらの本は良かったです![]()
![]() 今日の本はこちら📖
今日の本はこちら📖
特に、No.13にある
著者は、長年カウンセリングをしてきた結果、人間というのは本当にわからないものだということをますます実感するようになってきた
というくだりを読んで、著者の方への信頼感が増しました。正直✨
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
01. 信頼関係が最も重要
・情報のクオリティは関係のクオリティにかかっている
・ぎらぎらと眼を光らせるような必死な・能動的な観察は、しばしば先入観に誘導されたものとなる
→リラックスした、受動的な繊細な観察が望ましい。自分の内部に感じられる感覚にオープンになり、自分の内から沸き起こる感情や感覚や思いを自由にさえるような態度、そのような観察によって、微妙な違いが感じ取れるようになる
・「なぜ〇〇しないのか」という質問や「もっと具体的に」といった要求はさけるべき
「あなたが学校に行ってないのには、あなたなりに何か理由があるんでしょう。それを一緒に探していきましょう」という方が信頼関係を作りやすい。「もっと具体的に」と求める代わりに、相手の話が自然と具体的になるような巧みな質問を投げかける
・相手がおろかだ、許せないと感じられる場合でも、相手にそうした考えについて話してもらうには「相手なりにもっともな理由があるのだ」という前提に立つ必要がある
→肯定的意図![]()
![]()
02. 目標について合意する
・なんとなく初めて、なんとなく終わるのはNG
・「この話し合いが終わった時、どういうことが起きていることが必要なのか」「どういう違いがあればよいのか」について双方が納得している必要がある
・壮大な目標を掲げない、目に見える効果を及ぼし得るものにする
03. 面接の目標について
・面接の効果を高めるために、目標についての合意形成は非常に重要。だが、かなり雑にしか扱われていない
・「死人の目標」は不適切。「ケンカしないようになる」「怒らないようになる」「不安でなくなる」、これらは死んでしまえば達成される。そのような消極的な目標でなく「仲良くなる」「相手を尊重する」「リラックスする」「生きがいを感じることをする」など積極的な目標が良い
・「他人についての目標」も不適切。「夫が起こらなくなること」「上司が変わること」など。他人がそのように変化するためには自分が何をする必要があるかに焦点を当て、目標を再定義する必要がある
・主観的・抽象的な目標もあまり適切ではない。「幸福になること」「やる気が出るようになること」など。幸福は結果的に生じるもので、目的ではない。不安に無頓着になることで不安は低下する。やる気が出るのを待っていたらやる気は出ない、やっているとやる気は出てくるというもの
04. 面接におけるリーダーシップのあり方
面接者は相手に手綱を委ね、相手の自発性を引き出して進めていくが、面接者が話題を方向づけたり、焦点づけたり、広げたりして面接をコントロールする事との間でバランスを取らねばならない(ジレンマだが、いずれかが勝ちすぎると面接の生産性は低下)
→面接が生産的になるのは、信頼関係が形成され、面接が共同作業になるとき
・面接では、常に「そこにすでにあるもの」に正当な注目を与えることが有用。今あるものに注目し、すでにある小さな種を育てることによってしか信頼を得られない。フォロワー(面接を受ける側)の貢献をきちんと認識し、それを正当に評価することが必要。貢献を無視して多くを求めてばかりでは信頼を得られない
05. 省略
06. 相手の「私的で内的な世界」を尋ねる
本人によって避けられた体験領域について、いきなり直接的な質問をしても、ただちに有用な答えが返ってくることは期待できない。その前にまず必要なのは、その体験を回避させているもの(恐れや恥)をやわらげること。「それを体験することは大丈夫なんだよ」と伝えることであり、思い切ってその体験に身を委ねるよう勇気づけていくこと
※私的で内面的な情報は本人しかアクセスできないため、修正の機会が自然に訪れることは期待できないため、恐い。学校に来ない生徒に「どうして学校に来ないの?」と問い詰めていけば、その面接自体がその生徒に「自分はやる気がない人間なんだ」と間違った情報を信じ込むように誘導してしまう。
人間はつじつまの合った説明を求める強い欲求があるため、すっきりする説明をつけて納得したくなる。たとえ自分にとって不名誉なものであっても、みんなが納得できる説明がつく方が安心できる生き物
→実際の行動や様子をありのままに観察すれば、そのわかりやすい説明が本当には説明になっていないことがすぐに判明するはず
(ちなみに後述される、望ましい質問は以下)
〇「学校に行こうと思うことはあるの?あるとしたら、そういうときと、そうでないときとは何が違うの?」→これに対する答えから、学校に行かない理由が生徒自身にも徐々に浮き彫りになってくる
07. 話してくれない相手
非言語的なコミュニケーション含めて面接のプロセスそのものが情報。その人がどれだけ話したかによって情報量が増えるわけではない。話すか話さないかが重要なのではなく、どのように話すのか、どのように話さないのかが重要。話させようと頑張らず、話すか話さないかは完全に相手に任せ、相手のありのままを認める構えを持つ事が結局は相手の反応性を高める王道
→話させようと頑張って発話量が増えたところで、得られる「情報」の量が増えるわけではない
08. 「本音」は引き出すべき?
著者は、相手は常に本音を話していると考えているが、ただ「本音」という言葉は使わない。本音と建て前という二面性の存在を前提にした言葉だから。
09. 相手に語らせる
物分かりが悪い態度を取って、相手に力説する機会を与えることも
10. 相手の答えよりも質問が鍵
✖「いったい何がそんなに難しいんでしょうか?」
〇「それですね、確かに難しいですね。難しいにはいろんな要素がありますね。どういう要素が難しいかは人によって違うものです。あなたにとって一番難しいことは何ですか?」
11. 第一印象の重要性
・初回面接が大事=第二印象、第三印象と、引き続く印象形成のプロセスを方向づける重要な要因だから
・さらにいい印象が形成され、いい期待が高められ、相手からいい印象を引き出すというプロセスはごく自然に起こるため(逆もしかり)、出会いのごく最初の数分間に互いが相手にどのような印象を持ち、どのような関係を形成するかは、その後長期にわたってその人達が一緒になすことの生産性を左右する、とても重要な要因になる
12. 省略
13. 人を見る目
著者は、長年カウンセリングをしてきた結果、人間というのは本当にわからないものだということをますます実感するようになってきた。どこまでいっても人間はわかり尽くせない。思いがけないことを言ったり、したりする。
相手のことが「もう全部わかった」と思ったとしたら、そのカウンセラーは「終わっている」。みずみずしい理解力が枯渇したことのサイン。
実際には、どんな人間も、そんなに単純ではない。人間は常に変化を開かれた存在、可能性の存在、意外性を秘めた存在
「人を見る目」よりも、相手が率直になれるような人間関係、信頼関係を築く能力の方が大事
14. 表面的な話をする相手
・相手の言葉が心に響かない、エモーショナルな要素が乏しい、頭で考えたようなトーンとして聞こえてくることはよくある。自分の体験や感情に触れることなく、知的なモードで話している時など
・感情そのものがあやふやだったり、感情に触れたくなかったりする人に、生き生きした話はできなくて当たり前。それに沿った面接をしていけば良い。相手の反応そのものは決して表面的なものではなく、リアリティに近いものであることを認識しておくことが大切
15. 具体的に話してもらう
「どういうこと?もっと具体的に言うと?」と尋ねるよりも
「あなたがパニックになるときは、どんなふうになるの?身体にはどんな感じがある?頭の中にはどんなイメージや考えが浮かぶ?どんな感情を感じる?」と尋ねる方が良い。
もしくは
「そのときあなたの周りにいた人に様子を尋ねたらその人は何というでしょうか?」と他者から客観的に見た様子を答えてもらうと具体的にならざるを得ない
16. 相手のプライドを守る
✖「サボったことは担任の先生には話したの?」:責められていると感じてしまう
〇「担任の先生は、このことを知っているのかな?」:あくまで先生のことを問題にしているため、より気楽に答えることができる
✖「あなたはこの問題について夫と話し合いましたか?」:当然話し合うべきという考えが伝わり、もし話し合っていないなら、責められていると感じてしまう
〇「あなたの夫はこの問題についてどう考えているでしょうか?彼は自分の考えをあなたに話しましたか?」:あくまで夫の責任の範囲のことを問題にしており、妻のプライドは無傷
・面接者側は質問を中立的なもの、確認しているだけだと考えているが、質問される方は決してそんなふうには受け取らない「自分がやっと思われた」「この人は自分を疑っている」「疑惑の目で見られた」と感じる。相手がどう受け取るだろうという観点から考えることが必要
17. 技術としての沈黙
・沈黙は避けるべきものではなく、とても重要なもの
・カウンセリングにおける沈黙は「耐える」ようなものではない、沈黙は積極的な技術
・次の発言を相手に任せきって、ただ待つ。それは相手に対する信頼を伝える行為でもある。相手には質問に答える力があると信じている
⇔沈黙に耐えかねて面接者が自分から話し始めてしまえば、相手の応えるチャンスを奪うだけでなく、面接者が相手にはこたえる力が無いとみなしているというメッセージを伝えるものとなる
18. 「説得」しない
・「説得的」なメッセージに反応して相手が「そうですね」と応じたとしても、そこから自発的な変化は生じにくい。それは「説得的」圧力に応じた動きをどうしても含むことになるから、相手の自発性を損ねてしまう
・相手の心にある感情を感じ取って、それをただありのままに叙述するようにしてそのとき相手が「そうだね」と応じれば、それはその相手の自発的な心の動き。重要なのは、こうした言葉をかけるときに、相手から「そうだね」とか「はい」とかいった答えを得たいという気持ちを放棄すること。どんな答えが返ってきても、それを興味深く聴き、受け容れるような態度を養うこと。説得的にならないためには、相手に対して何かを求める気持ちの一切を手放すことが必要
19. 好奇心をもつ
・相手から生き生きした反応を引き出すために最も重要なものは、相手に対する好奇心
・目の前の人間に対する豊かな好奇心は、どんな小手先の技巧よりもパワフル
ただし✖「好奇の目で見る」「詮索好き」
〇「どうしてなんだろう」←どういうことなんだろう」といった問いに、相手も一緒に取り組むよう誘い込んでいくもの。責めるようなニュアンス、価値判断を下すようなニュアンス、裁くようなニュアンスはなく、何かの役に立つとか、得になるとかいった功利的なニュアンスもない。ただ不思議だなぁ、どういうわけなんだろう、と純粋な気持ちで問いかけていくだけ
・人間に対する信頼感を暗黙の土台としている。どのようにすればそのような好奇心を持つことができるのか?好奇心はだれにでもあるが、大人になるまでの過程で、好奇心が押さえつけられていく。恐れ、恥、不信などは好奇心を抑えてしまう。ほんの少しの好奇心が動き出せば、面白い反応が返ってきてさらに好奇心が掻き立てられる。このように好奇心は「育てられていく」もの
20. 思い通りに人を動かす?
・面接において、相手とパワーゲームはしない。相手が何を話し、何を感じ、何を考えるかは、全く相手の自由。面接者にある「相手にこう言ってほしい、こう考えてほしい」という気持ちを無理に抑え込んだり、そういう気持ちを持たないように頑張る必要はないが、あくまでそれは自分の勝手な思いなのだと自覚することが大事。相手には相手なりの理由があり、正当性がある。それが面接者には理解できないのは、愚かだからではなく、単に人間だから
21. あら探しをしない
・相手の話を尊重的に聴くことは、相手に同意することでも、相手の意見を肯定することでもない
・たいていの人にとって、相手のあらを探さず、意図を汲むように話を聴くということは
意識的に学習し、時間をかけて訓練する必要があるスキル。
相手と対立関係にあるときや、相手を評価したり指導したりしなければならないときには、なおさら
22. 一度の出会いでわかることと、わからないこと
・たった一回の面接で、相手の人柄や性格を見極めることができるか?
→人は状況によってかなり異なった反応を示すことが調査で判明。個人が違った性質をもってはいるが、そうした性質は状況を超えて幅広く一貫しているものではなく、具体的な状況の違いに対して敏感に応答するもの
23. 服装・髪型・装身具
・面接者は外見の「効果」を考慮に入れるべき。たとえ自分のことを一言も話さなくても、ただいるだけで自分を表現していて、それを避けることはできないことを理解しておくべき。服装・髪型・装身具を通して、人は自分の価値観や生き方を表現している
24. 省略
25. 相手の話が聞き取れないとき、理解できないとき
・聞き取れないまま、わからないまま、調子を合わせてあいづちを打ち、話を聴くことを著者は選択する。ひと段落したところで、自分に理解できたことだけを要約して返す。そうした対応ではなかなか展望が開けないときに初めて、「話を聴いていて、残念ながら、ときどき聞き取れないことがあるんです。もう少し声の音量を上げてゆっくりと話して頂けますか?」や「話の流れがわからなくなってきたので少し整理させてもらえますか?」と働きかける
・対話のかなりの部分は非言語的なやりとりにある。相手が面接室に入るだけで不安で落ち着かず、集中することができていないなら、まずは落ち着いて面接室にいることができるように、という目標だけをめざすべき。それ以上を性急に求めないこと
・内容が聞き取れなくても、話が分からなくても、「よく来てくれたね」「よく話してくれたね」と承認することが必要な段階というものがある
26. 省略
27. 省略
28. 省略
29. 省略
30. 直観に開かれる
・近代化の中で、われわれは科学的で合理的な考え方を身につけた。面接においても、相手の雰囲気や気配を感じ取ったり、うまく説明できない印象を大事にしたり、勘を頼りに今度の面接方針を決めたりすることはあまり推奨されないが、面接を豊かなものにするためには、そうした感覚を鍛えていくことが大切
・直観を豊かに育てるためには、まずは心に浮かぶことにオープンになることが大事。すぐに合理的には説明できなくても、浮かんでくるもの、感じられるものにオープンになり、出てくるものに気づきを向け、興味を持つこと、面白がること。意味を見出そうとか、興味深い解釈をしようとかする努力は手放すことが大事、ただ面白がるだけでいい
31. 疲れている時
・キャンセルする選択肢もあるが、元気が出ないなりの会い方。元気がないなりの面接をして、いつもとどこが違っているかを検討してみる
✖疲れを隠そうとする、憂鬱から逃げるように明るく振る舞う、無理に元気を出そうとしたりする
〇疲れている、憂鬱、元気がないということをそのままに認めながら、その上で役割を果たそうと考える
32. 省略
33. 省略
34. 省略
35. 面接者が自分のことを話すのは?
・面接者が自分の思いを話したくなった時にそれをそのまま話すのはNGだが、場合によっては面接者が自分の経験、思い、感情、考えなどを表現することが相手の表現を促進するうえで大いに役立つことがある。面接の目的に寄与することをめざして熟慮のもとに自分のことを話すことは、悪い結果を招くものではない
・自己開示は適切に用いれば、面接を進める上で非常に大きな効果をもたらすことが明らかにされている(カウンセラーが自己開示するほど、好感度が上がることが分かっている)
・一方、カウンセラーの側からは自己開示に対して複雑な反応を示すことが多い。あまり居心地の良いものではない
36. 省略
37. 省略
38. 強く被害を訴えている人の面接
・組織には自己保存の力が働いており、組織のメンバーは、よほど気を付けていない限り、その力の影響を受けている。その中での被害の訴えは、組織を揺るがすため、素直に受け止められない事態が生じがちになる。被害を申し立てている人の方も、こうした反応に打ち勝とうとして普段の言い方よりも強い言い方になっているかもしれない。被害を訴えている人が不自然に強く固い言い方をしている場合でも、それはその文脈における「自然な反応」として理解される必要がある
・中でも家族における問題は、家族メンバーではない面接者には非常にわかりづらい。家族は閉ざされた空間での長期にわたる濃厚な人間関係であり、その中で起きていることは面接者の想像を超えていることがあり得る
→面接者は自分に創造できる範囲が限られたものであることを自覚しておくことが必要、そうでないと、無自覚のうちに相手を疑いの目で見る姿勢になってしまいがちになるから
・人間関係における出来事に関して、事実とは何か。物理学の実験とは違い、人間関係上の出来事に関しては客観的な事実と、それを語る人の「解釈」が入り込んでいる。解釈なしに事実を語ることはできない。事実といわれているものは事実についての社会的に合意された解釈のことであり、解釈の余地のない客観的な事実などではない
→クライエントと他の解釈の可能性を検討する作業に取り組むためには、スタート地点としてはカウンセラーが事実についてのクライエントの解釈を採用し、その見方になってみることが有用
39. 省略
40. 省略
41. 省略
42. 年齢や性別などのギャップをどう超えるか?
・出発点としては、マイノリティについてムチであることは仕方のないことだが、自文化において周辺化されてきた多様な人々が実は身近に存在しているという認識をもち、対等な存在として尊重することは現代の大人の社会性の一部
・相手の文化を尊重するといのは、単に相手の文化に同調することを意味するわけではない。相手の文化に敬意を払い、興味を示すことは大事だが、無理をしてでも合わせなければならないというわけではない。お互いに尊重し合える関係を作ることが大事
43. 省略
44. 共感されることを受け入れる
・近年、共感を深めていくプロセスにおいては、カウンセラーが共感するだけでなく、クライエントがカウンセラーに共感することも必要だということが理解されるように
・共感は、相手があって初めて成り立つ。いくらカウンセラーが共感したつもりでも相手がそれを感じ取っていないなら、一人相撲。共感は成立していない
・共感のプロセスにおいては、クライエントの方も、カウンセラーの心理状態やその表現に対して心を開いて受け取ることが必要
・しかし、カウンセラーはクライエントからの共感を拒否してしまうことが多い。クライエントが自発的に心からの気遣いを示したとき、それをサラリと受け流すのは不適切
・親子関係も同じ。親が子どもを思うように、子どもは親を大事に思っている。小さな幼児でも親に気遣いを示し、その気遣いを親から受け取ってもらえることは、子どもの情緒的発達にとって重要な意味をもつ
45. 省略
46. 動機付けのない相手との面接
・周りから見て問題があるとみなされていても、本人が認識していないことはよくある。そうした場合、面接者からは問題があることは極めて明らかだが、面接の相手は自分に問題はないと言い張る。もしくは面接者が相手に問題があるということを当然の前提として面接を進めるが、しかしそもそも相手はその前提を共有していない→面接がうまくいくはずがない
→まずは相手の考えや気持ち、状況を理解することが必要
47. 省略
48. 省略
49. 相手の立場に立つ
・「相手の立場に立つ」ことがいかに難しいか
・人は自分の立場を離れることが難しい。よほど意識して努力しないと、知らず知らずのうちに自分の立場からしか世界を見ていないということになってしまう。そのことはこころしておくべき
50. あとはお任せ
・面接の主役は相手であり、面接者ではない。面接は共同作業
・面接者には受け身の姿勢、相手を信じて流れに任せる姿勢も必要。ただし、無責任に相手任せで良いということではない。責任をもって役割を担い、主体的に関わることが必要であると同時に、面接相手の主体性を信頼し、面接のプロセスに従う受け身の姿勢も必要(能動性と受動性のバランスがとても大事。バランスは固定されたものではなく、局面によって常に変化する)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()