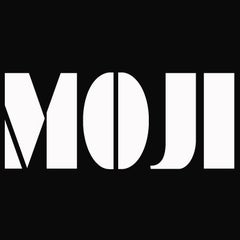①ゴダールの代表作2本
ジャン=リュック・ゴダール監督が亡くなったので、「勝手にしやがれ」と「気狂いピエロ」を観た時に書きかけて、途中でやめてそのままにしていた記事を引っ張り出してきました。
この2本を自主的な同時上映で観たのは2022年6月。2021年9月に亡くなったジャン=ポール・ベルモンド追悼企画でした。
「勝手にしやがれ」は2020年に公開60年を記念して作られた4Kレストア版。
「気狂いピエロ」は2015年にレストアされた2K版。
字幕が新しくなっています。細かな引用がしっかり訳されていたり、いちばん目立つのは「気狂いピエロ」のラストのランボーの詩の翻訳が変わっています。
この2本のゴダール映画は、以前にも映画館で観ていて、いつのリバイバルか忘れましたが、その時も確か「勝手にしやがれ」「気狂いピエロ」のペアで観たはずです。
この2本が上映されることが多いのは、やはりゴダールの代表作と見なされているからだと思いますが。
あらためて続けて見ると、共通点が多いですね。
どちらも、殺人を犯して男女が逃げる話。
どちらもこれと言って当てもなく、破滅へ向けて無軌道に暴走する話。
どちらも車や徒歩で移動し続ける話で、それが映画の疾走感を生み出してる。
そして、どちらも女の裏切りで男が破滅して終わる。
同時に、ネガとポジのように正反対な映画でもある。
夜を印象的に捉えたノワール的な白黒と、真昼の太陽に照らされた海やトリコロールの原色が鮮やかなカラー。
即興的なジャズと、時にミュージカルにもなる映画的なスコア。
パリの都市風景と、南仏の田園風景。
犯罪を犯して破滅を導くのは「勝手にしやがれ」では男だけど、「気狂いピエロ」では女。
ドキュメンタリーのようなリアルな撮影と、作りものであることを強調するような技巧的な撮影。
1960年に「勝手にしやがれ」で始まったヌーヴェルヴァーグが、1965年の「気狂いピエロ」できれいに閉じている。そんな始めと終わりを見た感があります。そういう意味でも、印象的ですね。
②勝手にしやがれ
À bout de souffle(1960 フランス)
監督/脚本:ジャン=リュック・ゴダール
原案:フランソワ・トリュフォー
製作:ジョルジュ・ド・ボールガール
撮影:ラウール・クタール
編集:セシル・ドキュジス、リラ・ハーマン
音楽:マルシャル・ソラル
出演:ジャン=ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグ、ダニエル・ブーランジェ、ジャン=ピエール・メルヴィル
↑4K上映版のポスターですが、あまり好きじゃない。映画に緑のイメージなんてないと思うのだけど。
「勝手にしやがれ」はゴダールの中ではもっともシンプルな、分かりやすい映画ではあります。
ゴダールは「暗黒街の顔役」みたいな「ギャング映画」を撮ろうとしたようですが。
それを、手持ちカメラで、即興演出で、最小限の登場人物で、パリ市街でのゲリラ撮影で作ると、こんな映画になる。
サスペンスの代わりに、混み合った街中をちょろちょろ歩き回る鬼ごっこになって。
銃撃戦の代わりに、女の子のベッドで煙草を吸いながら延々とどうでもいい話をする。
でも、そういう「映画的でない」いちいちのシーンがすこぶるカッコ良い、というね。
ゴダールの映画、分かろうと思って解説文を見ると、政治とか文化とか思想とか、やたら小難しい話が多くて、うんざりさせられることが多いのですが。
「その世代」でもない自分がなぜ惹かれるのかを考えてみると、そういう頭でっかちなところではなくて、何よりまずは絵面のカッコ良さなんですよね。
特に本作は、非常に「ストリート的」でもあると思う。即興撮影のリズムが生々しくて、臨場感があります。
既成の映画のエッセンスを一回バラして、サンプリングしてアドリブ的に再構築する、ヒップホップのような方法論。
時代的には、ジャズなんですけどね。劇中で流れているジャズの即興演奏のような映画。
それが古びていなくて、現代的なストリート文化に通じる若さをいまだに持ち得ている、というのがゴダール映画が今観ても面白いところではないかと思います。
③魅力溢れる主人公たち
2本の映画を続けて観てあらためて思ったのは、主人公たちの人間の魅力。
ジャン=ポール・ベルモンド、ジーン・セバーグ、アンナ・カリーナという人たちの強烈な存在感です。
「勝手にしやがれ」のジャン=ポール・ベルモンド、最初から最後まで徹底してクズです。
息をするように車を盗む。
大した理由もなく警官を殺す。
あちこちに女がいてその財布から金を抜き取る。
もう本当に、何の擁護の余地もない真性のクズ。
それなのに不思議と嫌いにならないのは、ベルモンドの飄々とした物腰と、二枚目半の愛嬌ある表情あってのものなんですよね。
そして、カメラと被写体との絶妙な距離感。
感情移入をしていないから、情緒的になっていかない。じめっとしない。全体を通して、徹底してクール。
それでいて、冷たいというわけでもない。人間味はあるんですよね。
都市で生活する若者の、どこか地に足がつかないふわふわした感じを、ある種のユーモアを込めて描写している。
タランティーノがゴダール好きなのはこういう辺りなのかなと思います。
「勝手にしやがれ」はベルモンドがクズなんだけど、ジーン・セバーグも実は似たようなものだったりします。ベルモンドが犯罪者でも気にする様子もなく付き合ったり、かと思えば唐突に密告する。
パリのアメリカ人としての、どこか異邦人めいた顔。
常に微笑みを浮かべていて、それはよく日本人が揶揄される、攻撃されないための曖昧な微笑であるように見えます。
でもその一方で、本心を分からなくする怖さも感じさせる微笑です。
彼女のクローズアップで、それだけで謎めいたものを感じさせて、名場面になってしまう。それを引き出しているのはゴダールだから、やはり見事ですね。
アンナ・カリーナはゴダールのミューズですが、「気狂いピエロ」はもう彼女とゴダールが別れることになる時期の作品です。
劇中でベルモンドを振り回し破滅へ誘うアンナ・カリーナは、撮る側の強烈な思い入れで怖いほどの凄みある美しさになってますね。
美しさというか、かわいい。この映画のアンナ・カリーナは。狂ってるのにかわいい。
④気狂いピエロ
Pierrot Le Fou(1965 フランス、イタリア)
監督/脚本:ジャン=リュック・ゴダール
製作:ジョルジュ・ド・ボールガール
撮影:ラウール・クタール
編集:フランソワーズ・コラン
音楽:アントワーヌ・デュアメル
出演:アンナ・カリーナ、ジャン=ポール・ベルモンド、グラッツィラ・ガルヴァーニ、ロジェ・デュトワ、ハンス・メイヤー、サミュエル・フラー
↑こっちのポスターはすごくいいと思います。映画の印象通りの青です。
「気狂いピエロ」は「勝手にしやがれ」とは対照的な、カラフルで賑やかな過剰な映画ですね。
トリコロールカラーがテーマのように繰り返され、あらゆる画面がポップアートの作品のようにカッコよく決まっている。
「勝手にしやがれ」にはなかった自然の風景も美しいですね。南仏の田園風景。青い空、青い海。
本作はまた、あらゆる映画のジャンルをごった煮にしたようなミクスチャー映画でもあります。
ベースはファム・ファタールが男を翻弄する犯罪サスペンス映画なのだけど。
悲劇であり、コメディであり、文芸であり、B級アクションであり、政治論であり、前衛であり、場面によってはミュージカルでもある。
主人公がピエロと呼ばれるように、まさにサーカスのような。
シンプルな「勝手にしやがれ」と比べると難解ではある…とは思うのだけど。
ただ、その難解な部分はほぼ当時の政治的・思想的論争に根差したいわば「時事ネタ」なので、今となってはそれほど気にしなくていいんじゃないかな…と思います。
難しいことを考えずに観れば、本作はまずは詩的で色彩豊かな「美しい映画」であり、不条理でぶっ飛んだ「楽しい映画」だと思うのです。
⑤ゴダールの効能
これは個人的な感覚だと思うのですが、ゴダールの映画って、観ていると不思議とクリエイティブなモードにさせてくれるところがあります。
退屈なシーンとかで心がスクリーンから離れていくのだけど(失礼)、でも眠くなることはなくて、自分の創作についてアイデアを考えていたりします。
そんな時間が割と心地よい…というのも、僕がゴダールの映画を観る理由の一つです。極めて個人的な話ですが。
しょうもないことですが、チケット買うときに「きちがいピエロ」って発声するの、ちょっとドキッとしました。
映画館の人がさらっと「きちがいピエロ」って言ってるのも、ちょっとドキッとしました。
日頃から、いかに「禁止語」の呪縛が身に染み付いているか、あらためて知らしめられた気分。
ゴダールは91歳。
エリザベス女王が96歳だったから、5歳しか違わないんですね。
クリント・イーストウッドと同い年だって。だから何だということはないですが。
安楽死が部分的に合法であるスイスで、「自殺幇助」を受けての死だそうです。
「PLAN75」みたいで死さえも映画的…と思うのは、美化し過ぎでしょうか。
個人的には安楽死制度には反対なのだけど、ゴダールほどに強い意志のある人が選ぶのであれば、それはもう誰も止められないだろう…という気はします。
合掌。
ローリング・ストーンズのレコーディングをゴダールが撮影した異色作。