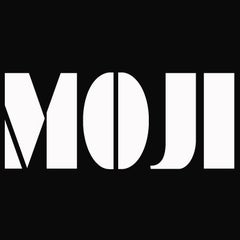日本沈没2020 劇場編集版 シズマヌキボウ(2020 日本)
監督:湯浅政明
原作:小松左京
脚本:吉高寿男
キャラクターデザイン:和田直也
音楽:牛尾憲輔
主題歌:大貫妙子、坂本龍一
出演:上田麗奈、村中知、佐々木優子、てらそままさき、吉野裕行、森なな子、小野賢章、佐々木梅治
①賛も否もある感想
湯浅政明監督による、Netflixで全10話で配信されたアニメ作品の劇場用編集版。
短期間限定で、なぜか特別料金で公開です。なぜ特別料金?というのはやや不可解。
Netflix版は未見です。ちょっと検索すると、結構賛否両論だったよう。
逆に興味が湧いたので、特別料金払って観てきました。
実際観てみて、僕の感想も「賛」もあれば「否」もある。確かにこりゃ賛否両論だ…という感じになりましたね。
力作、意欲作であることは間違いないと思います。非常に強く、やりたいこと、伝えたいことのある映画だと思いました。
現代の日本の様々な「風潮」に対して、強い問題提起をしている。ある意味で挑発的で、だから反発も多く生じるのかもしれない。
大災害がテーマで、次々人が死ぬので観ててしんどい。胸が苦しくなる作品なんだけど。
同時に、先の読めないジェットコースタームービーでもあります。ぐいぐいと引き込ました。
大震災があったので、リアルな災害ものとして観てしまいがちなんだけど、「日本沈没」は本来SFなんですよね。そこを強く意識した作品だと思いました。
一方で確かに、ツッコミどころはとても多い。
つながりが強引だったり、展開が唐突だったり、雑さが否めないところは多々あります。
また、作画が乱れてるなあ…というところも。
大友克洋を思わせるキャラクターデザインが独特で、クセが強いんですよね。乱れてるんだか意図なのか、定かでないところがある。
全体的に出来が良いか悪いか…というと、正直完成度が高いとは言えない作品だと思います。
安易な偶然が多すぎるし、出ただけで回収されない話も多い。いろいろと詰め込み過ぎで、消化し切れていない印象です。
ただ、思想的に偏ってるとか、そういうところはないと思います。
オリジナルがそうであったように、日本列島が沈むというフィクションは、日本とは、日本人とは…ということを問い直すための舞台装置になっている。
今回、その問いを今日的にアップデートして、本当に真面目に取り組んでいる。だからどうしても、政治的に反発を招きやすいところはありますね。
本作に関する否定的な意見を見ていると、「反日的」という意見と、「日本上げウザい」という意見と、両方あるのが面白いところでした。
その両方の反発が出てくるというのがまさしく、本作が右にも左にも偏っておらず、真摯にテーマに向き合っていることを示しているんじゃないかと思います。
②「賛」その1 巨大災害の絶望感
ある日、巨大地震が東京に発生。陸上部員の中学生・歩、ゲーム好きの小学生・剛、二人の父親で建設現場で働く航一郎、フィリピン人である母親のマリは、避難所となった神社で再会します。ネットでは、ユーチューバーのカイトが、沖縄本島が沈んでいく動画をアップしていました。何が本当かわからないまま、武藤家の4人に近所に住む七海、歩の陸上部の先輩の古賀を加えた6人は、西へ向かって歩き出します…。
序盤の、突然襲いかかる大地震と、それによって一瞬で様変わりしてしまう世界。その迫真性は、なかなか凄まじいものがありました。
やっぱり、東日本大震災を経ているだけに…僕は関西なので、報道と空気感だけですけど…大規模な災害で生活が根こそぎ奪われる、足もとが消え去るような不安感は、ものすごくリアルに伝わってきます。
あのスマホの緊急地震速報の、なんとも言えない不安を煽る気持ち悪さ。
自分の街が燃えていくのを見下ろす絶望感。避難所で朝を迎える先の見えない不安…。
日常が非常事態に侵食されていく感覚が、再現されていると思います。トラウマのある人はちょっとキツいかもしれないですね。
社会全体の動きを俯瞰的に描いたオリジナルの「日本沈没」に対して、本作では視点を歩たち家族に絞って、等身大の視点からのみ事態を描いていく。そこが特色になっています。
個人の視点から、主観的に大災害を体験していくことになるので、感情移入の度合いは自然と高まっていくことになります。
本作では、大事な人も善良な人も、分け隔てなく突然に死んでいく。辛い別れが次々に突きつけられて、悲しんでいる暇もなく、次の危険に晒されていく。
終盤に近づくにつれ、周りの人たちが次々と消えていき、望と剛の二人だけが取り残されて、突破口を求めて漂流していくことになります。
この辺の容赦のなさは徹底していて、観ていて胸が苦しくなるし、そこはたぶんブツ切りのネットシリーズじゃなく、ひとつながりの映画の方がより実感できるところじゃないかと思います。
③「賛」その2 アップデートされた日本人の描き方
本作は社会全体を描くような、大きな視点はないのだけれど、今は昔と違って誰もがネットを使えるから、一人一人が簡単に俯瞰的な視点を手に入れられる…というのがミソですね。オリジナル版の時代とのもっとも大きな違いです。
ネットから情報は得られるんだけど、それはそれで膨大すぎて、人によって信じるものが変わる…というのも面白かった。
多くの人は、ネットで拡散される「日本が沈む」という情報に不安を掻き立てられる。
年寄りは、「ネットなんて嘘ばかりだから」と信じない。
日頃から外国の友人とネットゲームで繋がっている剛は、エストニアの友人のSNSでの発言を信じる。彼にとっては、そちらの方がむしろ「顔の見えるもの」なんですね。
視点を家族に据えつつ、その家族の世界との接し方、その家族のあり方には、今日的なアップデートが加えてある。
主人公たちの家族が日本とフィリピンのハーフに設定されているのも、日本人の定義を今日的に問い直す、ある種挑発的な設定と言えます。
彼らは彼らの主観的にも、日本の法律的にも、正真正銘の日本人であって、それをとやかく言うことなど何もない…はずです。
劇中では、誇張された右翼的な人々が、彼らを排除して船に乗せないシーンが出てきます。
僕らはそれを見て醜悪に感じるのだけど、でも主人公一家があえてハーフであることに、「なぜだろう?」と感じてしまうのは、同じ根っこから発していることに気づかされるんですね。
芸能人の誰それの出自がどうだとか、二重国籍がどうのとか、特定のスポーツ選手への叩きとか、そういう発言がそれほど差別的なものだと思われずに、軽々とまかり通っていたりする。
本作には、そういう現代日本の風潮、我々の中の微妙な偏見を炙り出す「踏み絵」みたいなものが、たくさん仕掛けられていて、度々ハッとさせられます。
避難所で物資を奪い合う人たちとか、混乱に乗じてレイプしようとする若者とか…。
それは災害映画ではよくある描写で、日本上げとか下げとかとも関係ないことだと思うけれど、これすらも受け付けない層があるんですよね、今は。
「日本人は民度が高い人が多い」というまあ妥当と言える話が、「災害に乗じた犯罪をする日本人なんていない」という極論に化けて、「ということは犯罪をしている日本人に見える奴はみんな中国人か韓国人だ」というヘイトまでたやすく到達してしまう。
本作の「被災後の混乱」描写は、災害映画としては極めて控えめな方だと思うけど、それでもそういう、現代日本に現にある風潮を炙り出しちゃう。
ここでも本作は非常に巧妙に、災害を通じて現代の日本人の心の問題を描き出していると思います。
④「賛」その3 子供たちの成長と新しい世界
主人公である望と剛の姉弟は、気分の不安定さや考えの足りないところ、独りよがりなところが強調されています。だから時々、不快な人物にも見えてしまう。
でもそれは、彼らの若さ、幼さ、未熟さの表れなんですね。
地震で友達がみんな瓦礫の下敷きになって、パニックに陥って、そのまま家まで逃げ帰ってしまう望。
望は後になって、自分の行動を激しく悔やむことになります。
父親の死に動揺して、母や周囲に八つ当たりする行動にしても、望の年齢を考えれば仕方のないことですよね。非常事態でないならば。
子供であることを許されない状況の中で、望は否応なく成長していくことになる。本作はそんな、若者の通過儀礼の物語でもあります。
家族の中で、剛だけがやたらと英語を使う…お母さんのマリもほぼ日本語しか使わないのに…というところも、たぶん剛の幼さ・未熟さの表現なんだと思います。彼は外国にかぶれてて、だから日本を嫌ってる。
それはちょっと早めの中二病というか、若さゆえの独りよがりなんだと思うんですが、それは終盤のラップ合戦まで誰にも指摘されないんですよね。
だから結構違和感になって、主人公一家がハーフであることへの疑問にも結びついちゃうところがある。そこはちょっと残念で、もう一段届くような表現であれば…と感じます。
辛い旅の中で、若い人たちが少しずつ成長して、独自の世界を作っていくのは良かったです。
ラップで本音をぶつけ合うシーン、好きでした。アドリブであんな上手いことできるかー!と突っ込めるシーンではあったけど、そこは映画的な嘘としてのみこめましたよ。
古い世界がぶっ壊れて、新しい世界へ否応なく移行していく物語なのでね。
これまでの常識にとらわれない、若干理解しがたい新世代が、新しい世界を作っていく。
国籍や、民族や、性別や、そういった古い付属物が日本とともに沈んで、新しい価値観が作り出されていく…
…というような希望が、垣間見えた気がしたりしなかったり。
ラストで「…あれ?」って感じにもなるんだけどね。
⑤「否」のツッコミまとめ
最後に、「賛否」の「否」の方。まとめて突っ込んでおきます。
巨大地震が起こって生きるか死ぬか…というところで、肝心な部分がすっ飛ばされてるところが目につきました。
東京にジャンボジェットが墜落…と思ったら、いつの間にか川に不時着してる。
宙吊りになったお父さんが、次のカットではバイクに乗ってる。
マリが飛行機からの脱出中に津波が迫って来るが、そこからどうやって逃れたのか描写されない。
もっともドラマチックな転機であるはずのお父さんの死。どうして不発弾だったのだろう?
なんでお父さんの死を、災害と何の関係もない突飛なものにする必要があったのか。地割れでも土砂崩れでも、どうにでもやりようはあっただろうに。
旅の途中から、どこに行っても誰とも出会わなくなります。道路はガラガラ。町に出ても、誰もいない。みんなどこに行ったの?
日本中の人々が逃げ場を求めて右往左往してるはずなんだから、あちこちで人に出会うはずだと思うんだけど、なぜか人類滅亡後の世界みたいなんですよね…。
そんなに誰にも会わないのに、唯一出会うのが剛の憧れのユーチューバー、カイト。それは偶然が過ぎやしないか…。
カイトは全編を通じて、相当にバランスを崩すチートキャラなんですよね。いちばん最初の沖縄沈没の動画って、いったいどうやって撮ったのか…?
中盤の舞台になる、カルト的な新興宗教シャンシティ。
この手の物語で宗教が出てくる場合、破局後の混乱に乗じて…というのが多いですけどね。それこそ「AKIRA」みたいに。
でもシャンシティは災害後にできたわけじゃないから、災害とは別段関係がない。
教祖?の女性が死者の声が聞けるというのも、唐突なSF設定である割にはその後特に生かされもせず。「日本を描く」という主題に関係している感じもしなかったなあ…。
そのシャンシティの病院で、キーパーソンである潜水艇パイロットと出会うわけですが、彼がばぜそこにいたのか、なぜ全身麻痺の状態になってるのか、何一つ説明はないですね…。
そういえばおじいさんのモルヒネ中毒の原因も、彼がなぜシャンシティの子供を孫に重ねて連れ出そうとするのかも、ことごとくわからずじまいだったような。
(この辺のわからなさは、元のNetflix版を観ればわかるのかもしれないですが。あくまでも映画の評価ということで…)
全日本人を、3つくらいの港から脱出させるというような話だったはずですが、港はえらく平和なムードでしたね。みんな大人しく並んでる。
船に乗る人が抽選で決まるとか、スポーツ特待生は乗れるとか、そんな話もみんな穏やかに受け入れてる様子。
もっと大群衆が殺到するはずだし、それこそここは暴動じゃないのかな…。
漁船に乗せてもらって海へ脱出。でも、船は日本沈没の唯一の脱出手段なんだから、それこそ熾烈な奪い合いになりそうですけどね。本作の日本人は民度高いどころの騒ぎじゃないなあ…。
船はすぐ転覆して、救命筏で漂流へ。
ずいぶん長い時間を経て、同じタイミングで転覆したはずのお母さんと古賀先輩が助けに来ます。それまでどこでどうしてたのか、どうやって見つけたのか、説明はなし。
この漂流してる間に、日本はあらかた沈んでしまった…という感じであるようなんだけど、肝心のそこが描写されないので、よくわからないのですよね。
気がつけば、いつの間にか沈んでしまってた…という感じ。
モーターボートを見つけて、それを動かすために、心臓ペースメーカーのバッテリーが切れて死を覚悟したお母さんが海に潜ってアンカーを外し、犠牲になります。
それ自体は感動的なシーンなんだけど、直後にカイトが水陸両用車?でやって来て、結局モーターボートは使わず。
何でわざわざ、そんな無駄死にのような展開に…?
カイトの立派な水陸両用車も、何の説明もなし。助けに来たのが自衛隊なら納得でしたけどね…。
潜水艇パイロットの手がかりから、田所博士の残したデータを手に入れて、それが示す緯度経度へ向かいます。
そこは海のど真ん中。そこは「田所博士が予言する、土地が隆起する場所」らしいのだけど、隆起するのは「今日か、10年後か、100年後かわからない」。
それだったら、危険を冒して今その場所へ行く意味ないのでは…?
その場所で、カイトが気球を見つける。「俺は持ってる」とか言ってましたけど、これ偶然たまたまそこにあったってことですよね…。
ラストもなあ…「日本は全部沈んだけど、これから100年かけてまた隆起する」というのは、いくらなんでも安易じゃなかろうか。
そこまで不自然なことにしなくても、脱出して生き残った人々が、人工島を作ったりして少しずつ再建へ動き出す…というくらいで十分に希望は感じられたと思うけどなあ…。
エピローグはオリンピック。日本代表が出場し、日の丸が掲げられることで日本復活が世界に示される…。
そりゃ、スポーツ特待生を優先して助けたわけだからね。
うーん…これだけ新しい価値観を模索してきた果てに辿り着くのが、オリンピックがナショナリズムを誇る舞台になるという、旧態依然とした結末。それでいいのだろうか…?
せっかく古い世界が消え失せたのだから、それこそ仮想世界にバーチャルな国家を築くとか、それくらい思い切った未来を選んでも良かったんじゃないかと思えます。
なんか、列挙してたらすごい貶してるみたいになっちゃいましたね。
これだけ突っ込んでおいて…ですが、僕はこの映画、嫌いになれないんですよね。
現代日本の様々な変な風潮に対して、果敢に挑発している映画だと思うし、古い価値観を脱して見たことのない新しい世界を築く可能性を、垣間見せてくれていると思うから。
だから、それだけに…この古めかしい着地は残念でした。国家なんてもうなくていいんだ!というくらいの、思い切った未来が見たかったな。
湯浅政明監督の前作。