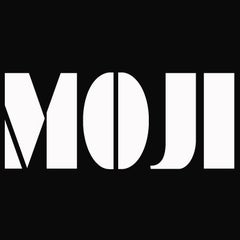Ma vie de Courgette(2016 スイス/フランス)
監督:クロード・バラス
脚本:セリーヌ・シアマ
原案:クロード・バラス、ジェルマーノ・ズッロ、モルガン・ナヴァロ
原作:ジル・パリス
音楽:ソフィー・ハンガー
①実写よりリアルな人形アニメ
実にリアルでした。子供たちがリアル。
実写でもアニメでも、子供たちを主人公にした映画はたくさんあるけれど、その中でも抜きん出てリアリティがある。
画面の中にいる子供たちが、本当に生きていてそこにいる、役柄のような人生を生きている、生命ある人間として息づいている。
実写映画、生身の子役が演じているよりずっと人間らしく感じられる。
人形なのに。頭のでっかい、目玉のでっかいデフォルメされたキャラクターなのに。
何だろう。人形アニメなのに? 人形アニメだから?
「この世界の片隅に」を思い出しました。
あの映画もアニメだけれど、そこら辺の実写映画なんか足元にも及ばないくらいの存在感を持って、登場人物たちが息づいていました。
絵で描かれた登場人物たちが、確かに肉体性を備えていた。その時代、その場所で生きる本物の人間として、そこにいた。
それと同じような感覚を、この映画からも受けました。
そんなことを思っていたらパンフレットに片渕須直監督の文章が載っていて、そのリアリティの正体をリサーチだと看破していたのはさすがです。
監督のクロード・バラスは本作の製作前、実際の孤児院にしばらく滞在して、子供たちと触れ合う経験をしたそうです。その成果を尋ねた片渕監督にバラスは「(映画に出てくる)今日の気分予報(のアイデアを得たこと)」と答えたけれど、でもそれだけじゃない、と。
この映画の子供たちが備えている身体性、生き生きとした存在感こそが、そうして実際の子供たちと触れ合った成果であるはずだと、そう言い切っているんですね。
本当に、その通りだと思う。さすが、超絶的なリサーチの積み重ねで、「この世界の片隅に」の凄まじく実在感のある世界を作り上げた監督です。
もちろんただその滞在だけじゃなくて、日頃から子供たちと触れ合い、話し、しっかりと観察していたんだろうと思います。でないと、この実在感は出ない。
上っ面の、脚本上だけの子供たちでない。ちゃんと子供たちを知って、調べて、学んで、描いている。そう感じました。
②自然体の子供たち
孤児院の子供たちはみんな、親に虐待されていたり、親に捨てられたり、親同士が殺しあっていたり、誤って親を殺してしまったり。それぞれ壮絶な過去を持っています。
でも、上記のようにとてもリアルな、自然体の子供たちとして描かれているから、彼らは大仰に悲しんだり、大げさにトラウマを表出するような行動はしません。
彼らはあくまでも等身大の存在として、当たり前に悲しみ、当たり前に寂しがっている。そして当たり前に馬鹿なことを言って大笑いして、当たり前にいたずらをして、当たり前に互いに支え合っています。
その姿が、胸を打つんですね。演出されたお話じゃなく、本当にそんな境遇に置かれた子供たちの姿をそっと覗き見るような、そんな感覚にさえさせられます。
デフォルメされた人形なんだけど、キャラクターではない。
それに考えてみれば、頭でっかちで目がぎょろり、手足がひょろっとしたフォルムって10歳未満くらいの子供のフォルムそのものとも言えますね。
ストップモーションアニメ特有のちょっとぎこちないひょこひょこした動きが、小さな子供の不器用な動き方にとてもよくマッチしてもいたりする。
声もリアルです。子供たちには役柄の年齢に近い素人の声を、大人たちには役者の声を当てたということなので、子供たちの声は本当に子供が当てているんですね(原語版では)。
どこか力弱い、頼りなげな感じの声が、さらに子供たちの実在感を高めることに繋がっています(原語版では)。
雪山への遠足、ロッジでのパーティーとか、大人の関わりの描き方もとても心地がいいです。
大人の関わりに関しても、ちゃんとわかってる大人が関わっている感じがします。適当ではなくて、子供との関わりについてきちんと学び考えを持った大人たちであるというふうに見える。
劇中の大人たちもそうだし、映画の作り手もそうなんだけど、子供をきちんと対等の人として扱っている。そこが素晴らしいと思います。
大人の従属物や、ただ大人の言うことを聞いていればいいだけの存在じゃない。自分と同じ、意思を持った人間として接している。
もちろん、子供を大人扱いするわけじゃないけれど、きちんと相手を尊重している。
その違いが端的に表れるのが、子供をモノ扱いして意思を認めないカミーユの叔母ですね。彼女のような存在を頑として否定することが、この映画の大きな核になっています。
③邦題もグッジョブ。吹き替えは…
人形アニメならではの美術、デザインもとても楽しいです。
背景のセットや、自動車などの小道具もとてもいいですね。
箱庭のような世界を、マッチ箱のような自動車が走っていく。そんな可愛らしい、絵本のような世界。
サボテン、ブランコなど、細々した小道具もそれぞれの人物に合わせてデザインされていて、かわいいインテリアの向こうにも物語が続いていることを感じさせます。
この映画は2016年の映画祭に出品されていて、一旦は日本でもイベント上映されて、その時のタイトルは「ズッキーニと呼ばれて」だったそうです。
公開までにずいぶん時間はかかっちゃってますが、邦題はより良くなってるように思います。「ズッキーニと呼ばれて」だと心ならずも呼ばれると言うか、ネガティブなイメージがありますよね。「ぼくの名前はズッキーニ」という、自分から名乗るポジティブなイメージの方が近い。
ズッキーニは、本名で呼ばれるとズッキーニと呼んでと訂正します。なぜって、お母さんがつけてくれた大事なあだ名だから。
野菜の名前だから、もしかしたら少し悪意というか、これも虐待の一つに数えられるような、そういう名前の付け方なのかもしれないけど。
でも、ズッキーニにとっては何より大事な、誇らしい名前なんですよね。
その気持ちをしっかりと汲み取っている、良い邦題だと思いました。
邦題はグッジョブ!なんだけど、吹き替え版には疑問が。
僕は字幕版を観ましたが、吹き替え版では峯田和伸がズッキーニを、麻生久美子がカミーユを演じています。
これ、製作意図と違うんじゃないでしょうか。子供たちを子供たちらしく描き出すことが映画の大きなポイントで、そのために「役柄の年齢に近い素人を使った」と公言しているのに、二人ともアラフォーです。
ズッキーニなんて声変わりもしてないはずなのに。なぜこんなにかけ離れたキャスティングをするのでしょう。
上手い下手の問題じゃなくて。いや、お二人とも上手な役者さんだから、吹き替え版だけ観れば違和感なく仕上がっているのだろうと思いますが、僕が原語版を観て感じた、「声まで含めて自然体の子供たちがリアルに描かれている」というこの映画の美点は、確実に失われますよね。
これ、映画の重要な構成要素を変えてしまっているわけで、話題作りのために脇役にお笑い芸人を起用するとかよりずっと、原典に対しては問題ある改変だと思うんです。
何なんだろう。こういうジャンルの映画に対しても、どうしても有名俳優を起用して、話題作りをしないといけないもんなんでしょうか。
それで本質を損なってたら、それこそ誰も得しないことになると思うんだけどなあ…。
とりあえず、字幕版をおすすめしたいです。