▼2022年7月9日
私山田は京アニが手掛ける『響け!ユーフォニアム』アニメシリーズの全てが大好き。
理由は、TVアニメ1期第10話で高坂麗奈の台詞「ねじ伏せる!」があった点と、2期第1話でのぞみぞ百合編の導入にボロディン『韃靼人の踊り』が切なく儚く美しく音響演出された点。
もっともそれは、オンエア当時に第10話の「ねじ伏せる!」で打ちのめされるまで鑑賞を続けてた時点で既に『響け!ユーフォ』から溢れるその他多くの魅力にゾッコンだったと認めた上での話。
ところで、その「ねじ伏せる!」は“才能の残酷さ”という『響け!ユーフォ』に終始貫徹されるテーマ性を凝縮した台詞だ。
そしてそのテーマ性を更に、内なる深奥の普遍性によって“創造的に破壊して”みせた野心的な超傑作こそが『リズと青い鳥』だ。傘木希美による鎧塚みぞれの“才能への嫉妬”でこの百合関係が一旦はギクシャクするも、後にみぞれの無防備な愛の求めに希美がやや温度差を感じつつも、半ば守護者の如く「付き合ってやるか、しゃーない」みたいな、“才能”のそれとは真逆の、“百合”に於ける非対称な力関係が受け入れられ、むしろ二人の絆は百合を超えて強化されたという、こういった一連のテーマ性の弁証法的な止揚に基づいたかの如き脚本の偉業を、私山田は大絶賛したくてたまらない!
そういった解釈の下で『リズと青い鳥』から見出せる最大の魅力とは何か?
まず“才能”に於いては鎧塚みぞれが、又“百合”に於いては傘木希美が、それぞれに圧倒しているという非対称な感情の力学が双方向的に並存し、尚且つ、二人は互いの要求にそれぞれ鈍い。従ってそこに描かれるのは、単純に互いの不足を補い合えるといった類の恋愛関係ではなく、もっとつかみどころがなく、ややもすると崩れ易く、心の行き違いや葛藤が生まれ易いが、これを克服する先の情欲の爆発は恐らくとんでもない事になっちゃうんだろうなぁって類の、極めてスリリングな恋愛関係だ。それを傍から見守る鑑賞者は、その後の二人がどうなっちまうんだと想像を巡らせながらはらはらドキドキさせられっ放し。そういった儚さへの臨場感を余韻として凝縮した、あの結末の脚本と演出の偉業たるや!これこそが、私山田にとっての『リズと青い鳥』の最大の魅力だ。つまり『リズと青い鳥』は、“才能の残酷さ”や“百合”すらも超え、いわば“他者を想う儚さ”といったより普遍性の強いテーマ性を狂わんばかりに極め、あの全編まるで水彩画の如き穏やかなトーンの奥底から、観る者の心をざわつかせて止まない超怪作だと、私山田は身悶えするしかないのである。
因みに、“他者を想う儚さ”のテーマ性で私山田が魅了された他の大傑作として、『人狼』(※沖浦啓之監督作劇場アニメ)と『無限の住人』(※の天津影久と乙橘槇絵の関係性)を挙げておきたい。いずれも『リズと青い鳥』と同様に、天涯孤独の“才能”ならではの憂いを踏み台として恋愛を描くといった、ある種の猟奇的な物語のモチーフが採用されている。
言わずもがな、それらに共通して描かれる“才能への嫉妬”とは、決して“肩書き”や“地位”や“名声”等に対する、この糞の役にも立たない類の嫉妬じゃなく、どこまでも創作で物語る実力によって“ねじ伏せる”事ができる、正真正銘の“才能に対する嫉妬”、このポジティブな向上心の契機そのものに他ならない。そういった“クリエーター”ならではの矜持に対するメタ的な表現を見事に昇華している点も、『リズと青い鳥』含む『響け!ユーフォニアム』シリーズを私山田が大絶賛する大きな理由の一つだ。
劇場版第3作目とTVアニメ第3期が楽しみじゃー!!!
▼2022年8月21日
私山田はこれまで『けいおん!』をあまり評価してこなかった。理由は、努力、失敗、挫折などを経た上での達成を描く様なドラマが不在で、逆にいわゆる“部活エンジョイ勢”の身内だけで盛り上がる馴合いの印象が強烈だと思い込んでいたからだ。
しかし、ついさっき唐突にその思い込みが崩れ去った!
確かに、先述した印象は『けいおん!』の表層から受ける分には間違っちゃいない。が、よくよく思い返すと、そもそも主人公の平沢唯を筆頭にあの軽音部の面子は皆、驚異的な才能の塊だ。どうみたって彼女らは“エンジョイ勢”で、練習もほとんどそっちのけなのに作詞、作曲、演奏技術は完璧に仕上げてくる。
つまり私山田がこの度『けいおん!』から見出し直したテーマ性とは“才能の残酷さ”で、これはエンジョイ勢のほのぼの日常でラッピングするからこそ余計に際立っていた筈の“残酷さ”であり、同時にこれは私山田がその対極としてこれまで位置付けていた『響け!ユーフォニアム』とも、ほぼ同じテーマ性だったのだ(笑)!!!
何故そんな簡単な事に今まで気付けなかったんだ、私の馬鹿ぁー!!!
やばい、今私山田の中で京アニ版『けいおん!』の再評価が大爆発してる!
『けいおん!』がTV放送されていた当時、私山田は先述した浅はかな解釈により、第1期8話で視聴を止めてしまった。唯と律が学園祭で賑わう校舎で「どすこい、どすこい」とおどけ合うシーンがその判断の決め手となってしまった。つまり、あれが当時の私山田にとっては、正に身内だけで盛り上がる馴合いの極みとしてだけ見えてしまったのだ。
しかし違うのだ(熱)!
あれは決して馴れ合いそのもの“だけ”を描いていたのではなく、あんな“エンジョイ勢”でも才能さえ飛びぬけていれば、たとえ馴れ合いにかまけたとしても無敵なんだと、これは『響け!ユーフォ』と全く同じ“才能の残酷さ”を、全く正反対からのアプローチで活写していたのであり、同時にアニメ業界や京アニという精鋭集団自身に対するメタ的な訴えだったのだ!
※あくまで私山田個人の見解です(笑)。
うぉおお゛京都アニメーション様、改めて御見それ致しましたぁああ!!!
語弊を避けるが、上述によって私山田は、何も京アニが『けいおん!』の軽音部みたいな“エンジョイ勢”だと言いたいのではない(笑)。
むしろ全く逆だ!
なら何故それが京アニ自身にとってのメタ表現として解釈し得るかといえば、京アニに限らず制作現場のプロのクリエーターなら誰もが噛み締めている“才能の残酷さ”を見事に描き抜いたという、この一点だ。
つまり実際の彼らは皆、時に“エンジョイ勢”然りの極端なフィクションでもって「そんなの反則ですやん・・・」と茶化さずにはやってらんない位に、地道な努力だけでは到底太刀打ちできないレベルの、自分より優れた他者の天性を常日頃から職場で目の当たりにしている訳であり、又これに対するコンプレックスを、互いに秘め合っている(※“互いに”とは、技能者の天性が必ずしも画一的なベクトルに留まらず、多様で唯一無二の個性を放つので、従って、唯一無二の天性同士がコンプレックスを抱き合う結果となるという事である)。それはいわゆる“互いの才能を尊重し合う”といった程度の柔らかいニュアンスだけでは収まり切らない、職人的なプライドやこれ特有の激情も伴う類の“コンプレックス”だ。しかし同時にそれは、決して嫉妬や足の引っ張り合いなんかに繋がらず、むしろ互いを刺激しあう向上心の契機として、制作現場で生産的に作用する部類の、いわば尊い“コンプレックス”だ。
尚、それは決して“奇麗事”ではない。つまり、結果的に生産的に作用するってだけの話で、そこに至るまでの経緯の悲喜こもごもは唯一無二のケースバイケースで、もはや想像を絶するが、しかしどこまでも生産性に溢れる現場の実際だ。それは“エンジョイ勢”とも“奇麗事”とも全く無縁の、より豊かで高度な“残酷”さの現実そのものだ。
つまり『けいおん!』で描かれた軽音部の面子とは、決して京アニ制作陣の自己投影ではなく、逆に彼らが羨望する“他者”の圧倒的な才能に対する具現だったのだ。動画⇒原画⇒レイアウト⇒作監⇒監督(演出)みたいな実力主義だけがモノを言う制作現場のヒエラルキーに於ける、動画マンにとっての原画マン、原画マンにとっての作監修正、彼ら全スタッフにとっての監督(演出)(※必ずしもこう単純に割り切れる実際という訳でもないが)、そして更に彼が羨望する又別の監督やアニメーターの才能こそが、『けいおん!』に於ける平沢唯という天才キャラに全て投影されていたという事だ。
ところで、TV放送の当時から私山田も含む多くの視聴者から、『けいおん!』は“エンジョイ勢”のご都合主義な才能で物語られる、“他者”が描かれていない“美少女動物園”系のアニメだなどと酷評されたりもしたが、むしろ“美少女動物園”そのものを歓迎する趣味趣向はひとまず措くとして、少なくとも『けいおん!』に対して“美少女動物園”のレッテルをもってする批判とは、上述の様な私山田の再評価に照らし直せば、『けいおん!』が描く“他者”及び“才能の残酷さ”への盲目、無理解、この露呈でしかない。そもそも京アニのスタッフら自身が他の誰よりも平沢唯という“他者”の天才っぷりの不条理や残酷さを身に染みて痛感しているのであって、むしろこれこそが当時の京アニの『けいおん!』アニメ化企画に於ける最大の原動力ではなかったか!
果たして、『けいおん!』は“萌え”な外見とは裏腹に、そういった京アニ自身をいわば諧謔するかの様な、メタ的な思想構造にも富んだ大傑作だった。尚且つ、興行的にも大成功だったのだから、もはや非の打ち所が無い。
従って、『けいおん!』で描かれたメタ表現とは、そんな“才能の残酷さ”という実際に対しても怯まずに突き進み続けるぞといった京アニのクリエーター魂による逆説的な決意表明だったのだと、私山田は解釈を改めた次第だ!!!
つまり、少なくとも私山田はこの度の再評価によって、『けいおん!』は『響け!ユーフォ』とほぼ共通したテーマを格納する物語の構造に於いて、逆説的で、より難解な大傑作だという認識に至った。勿論それは私山田にとっての『響け!ユーフォニアム』に対する評価を一切損なわせない所か、むしろ連動的に強化させる!
京アニ、やっぱ凄ぇよ!
※繰り返し強調するが、以上はあくまで私山田の個人的な見解とか勝手な勘ぐりに過ぎません(笑)。しかし同時に、私山田にとっては大真面目な話なのです。
▼そんな私鏑戯(執筆当時は山田)の犬も喰わぬ勘ぐりはさておき、山田尚子監督が自身の過去作を振返るインタビュー記事を以下リンクから参照あれ(※因みに私鏑戯が本稿執筆当時に“私山田”と名乗っていた理由は、某Vtuberが配信開始の際に“YMD(イェス、マイ・ダーク、略してヤマダ)”と挨拶していたミームにあやかったおふざけに過ぎません)。
▼2022年11月6日
ネタバレ注意!!!
映画『ソルト』をNetflixで初鑑賞。
2010年公開作。
テーマ性の背景をかなり考えさせられたという意味で、面白かった。
尚、私山田にとって主演のアンジェリーナ・ジョリーは『ギャング・オブ・ニューヨーク』『モンタナの目撃者』以来の、極めて印象深い熱演だった。当然、役者側だけでなく撮影する側の才能もずば抜けてるからこその見応えだったのだろう。
本編を概略すると、CIAエージェントとして潜伏していたロシアの工作員達が、アメリカに核攻撃を決行するように誘導し、これにより核戦争が勃発した暁には、旧冷戦以降のアメリカが覇権を握ってきた国際秩序に終止符を打たせようという、この裏工作による壮大な自爆テロ計画を完遂する間際で、工作員個々の、更に狡猾な思惑が裏目に出て、果たして計画は未遂に終わり、核戦争勃発の危機は回避された。完。
尚、“彼”がかつて主人公に蜘蛛研究の権威を知り合わせた目的は、北朝鮮への潜入工作以外に、後の露大統領銃撃等の汚れ役を任せる為の弱みを、彼女に抱えさせる事だったのであり、つまり“彼”は露側の工作計画そのものを利用して、自身だけは米国をロシアから救った英雄として歴史に名を残そうというエゴを究極の目的として秘めていた訳だ。必然的に、主人公の馴れ初めは、そんな“彼”のエゴを達成する為の犠牲として仕組まれていた事になり、この雪辱こそが最後の主人公による絞殺シーンの大迫力で示された。
更に『ソルト』のテーマ性を俯瞰し、この本質を探ると、米国にとってのロシアの軍事的な脅威に対する国防意識や、いわゆる右派、保守的な思想を高揚させ、刺激するプロパガンダ、この程度の浅はかさには到底収まり切らず、もっと根深い、つまりは、旧冷戦の終結以来、国際秩序の覇権を握ってきた立場からいざ撤退したくなったとしても、既に調子に乗り過ぎて多方面から怨みを買ってしまった取り返しのつかなさ、この自業自得の八方塞りに対する悲観、批判というよりも自虐、諧謔こそを強烈に感じ取れる。そもそもの物語の大筋が、あくまでCIAに潜伏していた“元”2重スパイの色恋を踏み躙った事による復讐心が動機となって、一旦は乗っ取られたホワイトハウスの核攻撃システムが、彼女たった独りの力によって奪還され、核戦争勃発の危機まで回避されたという、いわばブラックジョークをベースとしており、つまり、そんな矮小な規模の葛藤が人類の存亡まで左右してしまうと茶化さんばかりに、実際の肥大し過ぎたアメリカの覇権主義を支えてきた“核の抑止力”の本質的な危うさに、尚も拠って立ち続けざるを得ない覇権国家ならではの呪縛に対する嘆きが、私山田には聞こえてくるかの様だった。
従って、私山田にとって『ソルト』は、覇権国家から容易に引き戻せないアメリカならではの悲嘆を究極のテーマとする、ブラックコメディの傑作となる。
勿論、同様の自虐テーマで、且つCIAの欺瞞を訴える題材を『ソルト』以上の巧みさで扱った傑作は他にも無数に存在するが、しかしCIAに潜伏したロシア側の女性スパイにこの世の全てが篭絡され続けている様な雰囲気が、私山田のマゾ気質を刺激した分だけ、評価が悪戯に盛られた(笑)。又、同様の理由で、女性スパイが東西両陣営を手玉に取る『ANNA/アナ』も私山田は大好きだが、“ロシア大統領銃撃”、“アメリカの核を我々が支配する”、“核攻撃目標はテヘラン”等々、ブラックジョークのぶっ飛び具合では『ソルト』に軍配が上がった(笑)。
進むも退くも生き地獄。人類平和は一筋縄じゃいかない。これを考えさせる良い映画だった!
▼2022年9月24日
韓国映画『工作 黒金星と呼ばれた男』初鑑賞の感想。
ところで、浦沢直樹『マスターキートン』が連載された1988~94年当時、私山田は何故旧ソ連、東西ドイツ、ルーマニア等に幾度と言及する同作が、こと南北朝鮮を一度も舞台にしないのか不思議だったし、今もこの理由を推し量る事ができないでいる。というのも、当時の私山田にとって『マスターキートン』ほど世界情勢の複雑さに興味を持たせた良質な参考書は他に無く、これがもし朝鮮半島にも幾話か触れてたなら、日本の現状の様な、いわゆる“ネトウヨvsパヨク”的な安直さで“韓流”の一面だけを云々する文化的なリテラシーの欠如は、幾らか軽減されたのではと残念に思えたりもする。や、別にエアプじゃないけど、もし『マスターキートン』に朝鮮半島に触れた話があったなら、私山田が単純にど忘れしてるだけなので、この場合は謝ります(笑)。
ひとまずそんな事も含め、私山田にとって『工作』は、あれこれ考えさせ、見応えのある映画だった。
以下、感想の本題。
まず念頭すべきは、この映画が基づいたとされる“黒金星”という大韓民国の工作員に関する“情報”は、この機密性ゆえに客観性を欠かざるを得ない。極少数の人間による証言や記録によってしか裏を取れない“黒金星”という超極秘のスパイ、この身元が極めて不確かな人物による証言や記録に基づいた“情報”とは、この出所を怪しんでかからざるを得ないという事だ。つまり極論すれば、それは仮に金大中大統領誕生の歴史があったからこそ、この作為も多分に絡んで語られた“北風工作”であった可能性も決して全否定できず、従って仮に『工作』の脚本は、そんな金大中政権の正に政治“工作”的な思惑によって、大韓民国の機密文書や公文書などの随所に巧妙に忍ばされたでっち上げをかき集めたところの、どこまでもマリオネットな“インテリジェンス”、これに振回されただけのシロモノに過ぎない可能性も、決して全否定できないという事だ。且つ、興行を成立させる為の脚色や演出による映画の総体そのものは、飽くまで“実話に基づくフィクション”として冷静に受け止めるべきだ。だが同時に、いわゆる“北風工作”というスキャンダル自体は、大韓民国の現代史の一部として確かに記録されている事実の客観性も、共に留意すべきと言える。そう私山田が慎重にならざるを得なかった理由は、『工作』が金大中元大統領への見解を根本から覆させる、ある内容を含んでいたからだ。つまり、私山田にとって『工作』は、そんなフィクションの度合いを慎重に見極める部分も含め、飽くまで映画としては唸るほど楽しめたという事だ。
本編の舞台は金大中vs李会昌の構図が懐かしい1997年大統領選挙を前後する大韓民国、北京、そして北朝鮮。当時、仮に与野党の政権交代が実現した場合、それまで北の脅威を政権与党に利する形で政治利用できるように密約の仲介役を重ねてきた大スキャンダルが暴かれ組織解体される事を恐れた大韓民国側の工作機関たる国家安全企画部は、後に“北風工作”とリークされた更なる裏取引で、南北共同警備区域の全域に渡る同時多発的な武力示威を北朝鮮に依頼し、この密約を裏金400万$で一旦は取り付け、これによって金大中候補が掲げる“陽光政策(※対北友好的外交政策)”の出鼻を挫かせ、彼の当選を妨害する為の自作自演工作を図った。が、そんな大統領選の行方を北朝鮮の協力を得てまで左右させようとする身内の欺瞞に気付いた同組織所属の工作員“黒金星”は、彼が予てから北朝鮮の核ミサイル開発の実態を探る為にでっち上げていたに過ぎなかった南北共同広告事業の件を敢えて利用し、これがその密約の効果も虚しく仮に金大中が当選した場合に、全て御破算になってしまいかねないと、金正日総書記に直談判で説得する事で、大統領選に合わせた北朝鮮による武力示威を未然に防ぎ、これによって少なくとも、より矮小な目的で南北分断を利用しようとする国家安全企画部の企てを阻止する事には成功した。・・・というのが『工作』の物語の主軸だ。
尚そこでは、金大中候補の共産主義かぶれのイメージが、実は彼の存在をむしろ不都合に思っていた北朝鮮の工作によるものだったと描かれており、これが不勉強な私山田を驚かせた。
さて、そんな『工作』を一見しただけでは、金大中候補の当選を妨害する為の北朝鮮との裏取引に造反(※実際には金大中陣営にリーク)した“黒金星”だけに、あたかも正義が宿るかの如き勧善懲悪の印象を受けかねないが、実際はそう単純でもなかろうというのが、冒頭に述べた念頭の内実だ。
というのも、確かに当時の国家安全企画部が公僕に徹し切れず保身を優先させてしまった主客転倒は『工作』が描く通りスキャンダルに他ならないが、これと同時に、北朝鮮が核弾頭の脅しによって国際的な経済制裁を突破し、海外企業からの投資を呼び込んだり、南北離散家族再会を含む観光誘致事業で外貨を稼ぐなど、これらをあたかも“南北友好”と装う事も又、見方によっては“祖国と民族”を差し置いて、どこまでも独裁体制を本位とする欺瞞ともとれかねず、こういった不満は他でもない北朝鮮の党指導部からも絶えない筈だ。これに関しては『工作』劇中でも“金父子によって愛する祖国が監獄に変えられていくのが辛い(1:20:30~)”や“共和国300万人の同胞が餓死、凍死に晒されている(1:47:45~)”等のセリフで象徴されている。
又、それはたとえ、同じ朝鮮民族が異なる祖国の体制を互いに尊重し合う最善の外交関係の構築を議論する上でも、飽くまで北朝鮮が非生産的な武力による脅しだけに依拠した外交を展開し続ける限り、決して対等な関係ではないし、“南北友好”とも程遠く、従って少なくとも大韓民国側の民主的な世論からの反発は避けられない。つまり、『工作』劇中の結末を飾った南北共同広告事業は、決して長期的に持続しないその場凌ぎの“友好”に過ぎず、この観点からは、“黒金星”の上司が敢えて裏取引に手を染めるまでして国家安全企画部の存続を優先させた、長期的な戦略上の正当性を汲み取れなくもない。
ここで一つ極論すれば、大韓民国の対北朝鮮外交に於ける問題の本質とは、決して北朝鮮の共産主義や独裁体制や核保有そのものではなく、飽くまで北朝鮮の非生産的な政経論、この産業政策上の怠慢なのであって、これが結果的に“共産主義という精神病(1:44:25~)”に帰結せざるを得なくなる。ましてや、かつて江沢民が改革解放して以降、目覚しい経済発展を遂げた中国“共産党”独裁体制に取り残されて久しい北朝鮮が、今も尚頑なに資本主義の部分的な導入さえ拒絶し続けなければならない理由は唯一つ、金の血族だけに総書記の権限を世襲させる、この権力集中を維持する為だけなのであって、こうなるともはや、北朝鮮に於ける現行の主体思想に基づく統治体制は、北朝鮮固有の地政学的条件や風土性から逸脱した歪なナショナリズムとして看做す他なく、この正当性を疑わざるを得ない。それは現時点の北朝鮮の富のほとんどは核弾頭開発にばかり振り分けられており、決して民族同胞の共産的な日常の営みには向けられていないという、こういった思想と実際の乖離の話だ。つまり、たとえ金融資本主義に民族固有の富を売り渡す訳にはいかないといった風な、北朝鮮独自の保守主義が当然の如く尊重されるべきであっても、ここにもはや金血族世襲のみによる独裁体制を維持すべき必然性は皆無という事だ。それを換言すれば、まず金血族世襲による強権と思想的矛盾を極めた独裁体制の維持と、或いは北朝鮮に於ける共産主義体制の維持とは、必ずしもイコールで結ばれる概念ではないという事だ。そういった金世襲独裁体制を打倒すべきとする長期的な視野に立脚すれば、自ずと金大中の陽光外交は、少なくとも『鋼鉄の雨』の結末で描かれたが如く、大韓民国独自に核武装を達成しない限りは、全くの不毛に帰さざるを得ないし、又、その打倒が達成されない限りは決して朝鮮半島の南北友好はおろか、南北統一など夢のまた夢に過ぎないだろうなどと、私山田は考える。
要は、私山田にとって『工作』の物語の結末は、朝鮮固有の“情”の民族性に対する自画自賛にやや逃避した感が拭い切れないものの、だからこそ興行映画としてのバランス感覚や戦略性には非常に優れていると見受けられた。
しかし率直なところ、そもそも私山田の不勉強が『工作』に対する無理解を助長しているのではと不安で仕方なく、いずれ近い内に、映画の原作という位置付けではないが実在の“黒金星”の証言に基づいた小説(?)が韓国で出版されてるようなので、これに目を通す予定だ。
しかし主演俳優の役作りには終始圧倒されっ放しだった。
又、当時の北京の町並みをCG加工も交えた背景美術でそれっぽく再現していたのも凄いが、北朝鮮のピョンヤンの町並みの空撮や金正日の隠れ家の内装まで、あぁもリアルに描写して見せた背景CG担当(※CGだよね?w)の仕事はあっぱれだった!
又、私山田の『工作』に於ける笑いのツボポイントは、北京のナイトクラブで交渉の席から外された北朝鮮の高官二人が一糸乱れぬ振り付けでダンスに勤しむシーン(51:05~)。その二人、両方とも不憫な運命を後に迎えるので、何ともいえない気持ちになる。
いずれにしても、良い物を観れた気分。
▼2022年9月22日
『KCIA 南山(ナムサン)の部長たち』初鑑賞の感想。
今のご時世に紹介を憚るべき映画?そんなふざけた理屈が通るものか。
かつての大韓民国の軍事革命政権の大統領、朴正煕(パクチョンヒ)の暗殺事件と、この暗殺犯でKCIA“部長”をモデルとした飽くまで“フィクション”。
ところで、“人は皆、いずれ死ぬ”。人はその命題だけに頭が支配されれば、人生の価値や生きる気力を根本から見失い、しかし自殺するに見合うだけの強烈な気力に恵まれる訳でもなく、従って大概は鬱を抱え、身を持ち崩し、よって自律的な生活力の一切を失う。逆に、そんな精神の泥沼とは縁遠く、自らの気力や衝動の奴隷として惰性的に生きられる脳天気な部類や、或いは自らの気力や衝動を客観的に捉え、これを支配するか、翻弄されるかの絶え間ない駆け引きこそが人生だと割り切れる風な、こんな器用な部類も存在する。
果たして主人公の金規泙の場合は、政敵に対する私的な噴飯と、国民に対する公的な忠義との間で翻弄されつつも、最期は大統領暗殺及び大韓民国の民主化の為に自身の全てを賭した後に、絞首刑で散った。
朴正煕政権は、軍事革命決行の当初は共産圏から朝鮮半島の赤化を防ぐ大義で一致結束していたが、軍事独裁体制が長引くに従って腐敗し、果ては民主化デモを空挺部隊で鎮圧する事も厭わないなど、議会や国民への軽視、この専制っぷりが酷かった。その“革命の裏切り”を裁くという主人公の大義は、しかしどこまでも彼が大統領から受けた使い捨ての様な仕打ちに怨念を晴らさんとする上での、ほんの後押しに過ぎなかったのではともとれるくらいに、主人公や前任の元“部長”が朴正煕に繰り返し嵌められていく模様が丁寧に描かれていた。
「お前の傍には常に私がいる。好きなようにやりなさい」(笑)。最低だなwww
つまり、朴正煕に対してKCIAが怨念を募らせたという物語は、上司に対して忠誠を裏切られた部下が怨みを抱くという、こういった世間一般にも広く通じる普遍性が担保されていて、又、登場人物それぞれの使命感や嫉妬心などを直感し易く演出する為であろう巧妙な場面設計(※特に主人公が大統領を壁越しで盗聴するシーン)や背景美術(※特に朴元部長とデボラ・シムがアメリカの亡命先の住家で会話するシーン)が光っていて、従って、大統領暗殺という題材の重苦しさを装わせながらも、人それぞれの立場や運命にそもそも選択肢なんて殆ど限られているのだ、みたいな運命論的な諦観のテーマ性が、私山田には非常に心地良かった。
という具合に、私山田にとって『KCIA南山の部長たち』は、人それぞれの生きる源とは何かみたいな、より根本的な命題まで遡らせてくれる、哲学的な没入感が半端ない映画だった。Netflix鑑賞で一度も一時停止を挟まないレベルの没入感。
▼2022年9月5日
『竜とそばかすの姫』Blu-ray購入。劇場鑑賞から1年と1ヵ月ぶり2度目の本編鑑賞。
まず背景美術のきめ細やかさに度肝抜かれた。Blu-ray、4Kに耐える背景美術。
次に、夕暮れの川辺で鈴がルカに“応援する”とLINEを送るシーンの配色。特に鈴の顔の赤黒く染まった肌色と涙のコントラストに目を奪われた。
次に、『美女と野獣』モチーフのダンスシーン冒頭でベルと竜の衣装が光に包まれ変化するカット。おそらく子供心鷲づかみ。さすが細田守。
次に、鈴が素顔を晒して歌う⇒ベルに姿を戻しクジラに乗って歌う一つ目のクライマックス。劇中歌も相まって五感全てが釘付け。さすが細田守。
次に、鈴が恵くん知くん兄弟の父親から頬に傷を負わされるカット担当のアニメーター様は超絶級の天才。あの瞬間、頬の皮膚が指でえぐられ血の滴が飛び散るエフェクトだけで、あれだけの鬼気迫る恐怖感を演出できる感性は、もはや只事じゃない。
そんな最後のクライマックスは、私山田が独自解釈する所の“タナトス”的なテーマ性が大爆発しており、これによる没入感は、もはや実写かアニメか、虚構か現実かすら忘れさせた。
『竜とそばかすの姫』は人の根源の光と闇を同時にえぐる無類の超傑作。
私山田の一生モノの宝の一つ。
※劇場鑑賞当時の感想は以下。
▼2022年8月12日
『旧劇場版エヴァンゲリオン』。
この大傑作に於ける、いわゆるセム系一神教に通低するエロス禁忌の人間性否定に対するカウンター効果への再評価が、昨今の旧統一協会問題の再燃をきっかけに、私山田の中で爆発した(笑)!勿論、そんな近代西欧諸国の覇権主義のバックボーンとしての、他者の精神領域を土足で蹂躙する野蛮さ、これに対する文化的なカウンターって事以上に、更に奥深いテーマ性が重層的に表現されているからこそ、私山田にとって旧劇エヴァは永久不滅の大傑作の一つとして挙げざるを得ない。それは結局、他者を土足で蹂躙する野蛮さを自己批判できる精神や、これに基づく宗教芸術や近代的な娯楽文化が切り開かれた現代に於いても尚、やはり西欧文化圏が負った所は間違いなく大きかったとか、つまりは敵という他者を知らずして、近代的な舞台への第一歩すら決して踏み出せはしないとか、敵ながらあっぱれといった風な、庵野秀明監督独自の哲学の基礎が純粋に打ち出された大傑作だから、という事だ。
因みに現時点で未だブルーレイ発売されてない『シン・エヴァンゲリオン』を私山田は未鑑賞のままである(涙)!
↓観たよ!!!
▼2022年8月10日
あ~!
巨悪をぶっ潰してぇええええええ!!!
『キングスマン』の花火パーティーみたいに巨悪の幹部を一網打尽にしてやりてぇえええええええ!!!
▼2022年8月7日
山上容疑者宅から、民衆の武装蜂起を民主主義の歴史の一部として描いた“小説”を押収?
ふ~ん。
私山田が最近観た韓国映画で、光州事件を発端とする架空の要人暗殺を描いた『26年』があったなー!
イデオロギー云々以前に、罪は罰で償えって単純明快なテーマ性は見事だったけどなー!
つまりまず言いたい事は、より有力な犯行の背景として、旧統一による法外な規模の献金搾取の社会問題や、これを政治活動上の利益を目算した上で政界から公安トップまでグルになって超法規的に擁護し、反社会的組織の監視対象から外すとか、名称変更の認可を超特例で下すとか、総裁選挙にも影響力を持たせたとか、こういった深刻すぎる政教分離違反の実態こそを、何を措いてもまずもって追求し報道すべきなのであって、逆に容疑者宅から小説だの漫画だの映画だのアニメだのゲームだのが押収された事実程度に報道の焦点をそらして世論をミスリードする様な真似は、只々、当該の報道機関の信用が悪戯に失われるだけではないかという、私山田の疑問である。ましてや、娯楽媒体の虚構性やいわゆる“オタク”という曖昧な属性を敵視する論点には、社会問題を議論する上での如何なる有効性も内在しないのだから。
以下から映画『26年』に対する感想に移る。
まずは当然の事として、『26年』は決して共産主義を正当化する映画ではない!
因みに、共産主義の脅威については日本と比較にならん位に敏感な韓国社会で映画『26年』を製作(※クラファンだったそう)、公開できた事実は凄い。
日本に於けるイデオロギー闘争は手塚治虫『アドルフに告ぐ』や、いわゆる全共闘運動で周知されている程度か?
いわゆる共産主義は理論の検証云々以前に、ボルシェビキ指導部の特権階級化を許してしまった当時のソヴィエトの実際とイデオロギーとの大矛盾と、人民同志らの生活困窮からの不満、不信が募りに募って、最後は連邦体制の崩壊で幕を閉じた。
そこで注目すべきは、腐敗した組織は“保身”のみに執心するという、この歴史的な教訓。
ソ連に限らず、今の日本なら政界の自民党とか、新宗教の旧統一とか、そしてアニメ業界から追放されても尚粘着し続けている債務延滞者“某”のオンラインサロンコミュとか、これら皆全てが、本来守るべき国民や信者や支援契約等からは目を背け、只権威や組織の保身だけを最優先している。つまり、どんな政治思想も時代に適応できずイデオロギー化し腐敗すれば、体制維持を本位とするだけの糞くだらない道具に成り下がるという事だ。
因みに映画『26年』は、原作がウェブトゥーン、つまり漫画だそうで、この画風を踏襲したかまでは未確認だが、とにかく冒頭辺りにアニメパートがある。ちょうどタランティーノ『キル・ビル』みたいに。丁寧なデッサンや中割のタイミングセンス等、もしかしたらロトスコープ併用かもと匂わせる程に見応えがあった!
▼2022年7月27日
『バリー・シール アメリカをはめた男』
1970年代~80年代初頭、アメリカ合衆国のCIAは、中米ニカラグアの共産主義体制を打倒する為に、当地の反共右派ゲリラ“コントラ”に対し、元はイスラエルが押収して横流ししてきたソ連製の自動小銃等の武器を更に横流しし、この代金となるコントラ側の資金源のコカインの空輸にも超法規的且つ秘密裏に関わった。つまり当時のCIAは、アメリカ合衆国の国防戦略の大義名分下で、敵国ニカラグアの反体制武装勢力コントラによる合衆国本土へのコカイン密輸をも実質的に支援した。そんなCIAの国防戦略上の大スキャンダルにまきこまれ、利用された飛行機パイロットの物語。
『バリー・シール』の脚本は実話に基づいているそうだが、どこまでが実話に沿っていて、どこからが脚色なのかを細かく確認する気力は、現時点の私山田には無い。
それを踏まえた上で、次の感慨を記録しておきたい。
まず、中米諸国特有の血の気の多い風土性と陸続きの地政学的条件下で(※密輸ルートは主にカリブ海の空輸だが)、この防衛に臨まなければならないアメリカ合衆国の事情を鑑みるに、この戦略の内実が、仮に『バリー・シール』で脚色交じりに描かれた様に、たとえ超法規的な買収沙汰や自国の麻薬汚染への黙認等の統治的な欺瞞や、更にこれらが空回りして裏目に出るリスクへの想定まで含んでいたとしても、この戦略の究極の目標があくまでアメリカ合衆国の防衛という只1点から逸脱さえしなければ正当化されざるを得ないし、むしろそうでもしなければアメリカ合衆国に特有な防衛事情の過酷さは決して満足に対処されないという事(※劇中ではコントラに横流しされた自動小銃の半数が更にコロンビアの麻薬カルテルに売却されたり、軍事教練の為に入国させたコントラ成員の半数が姿を暗まし祖国の前線に戻らなかったため、CIAの対ニカラグア戦略が方針転換を迫られた風に描かれる)。
次に、そもそも世界一の核武装大国たるアメリカ合衆国が、上記の様な防衛戦略を、対共産主義、対麻薬カルテルで迫られざるを得ないでいるという現実の過酷さ。
次に、しかしそんな防衛戦略上で複雑に入り組んだ欺瞞含みの利害構造を俯瞰すれば、これはあくまでアメリカ合衆国の中米諸国に対する軍事的な非対称性の下で世界大戦級の悲劇や犠牲を未然に防ぎ続けている、このあくまで“平時”のディテールに過ぎないという事。つまりその観点に従えば、『バリー・シール』で描かれた欺瞞の数々は、あくまでアメリカ合衆国が核武装によって勝ち取り続けている厳然たる“平和”の内実の一部に過ぎないとも解釈できるという事。
そして最後に、しかしそれらの観点はどれも、あくまで一般国民の世論にスキャンダルとして暴露されてしまえばたちどころに根本から覆ってしまう脆弱な達観に過ぎず、こういったいわゆる権力を監視する報道の自由、表現の自由による緊張関係も含んだ上で初めて、アメリカ合衆国だけに限らず、我が日本国の民主主義や防衛戦略的な議論に於ける、昨今の“統一教会”の政教癒着の問題、ひいては保守勢力と北朝鮮との癒着問題の欺瞞の根深さにも、より誠実に向き合えるのだろうという観点。
そういった現代の文明社会の限界と理想とに肉薄し続けるよう、観る者を促すかのような、創り手側の気概が伝わってくる清々しい映画だった。
勿論、そういった脚本の卓越したテーマ性だけでなく、撮影手法、編集、劇伴含む音響、舞台美術、キャストの演技力等、どれをとっても超一級レベルだった。だからこそ、私山田はここまで注意深く感想を述べる気にもなれた。
さしずめ、私山田にとって『バリー・シール』は、宮崎駿の『紅の豚』と、マーティン・スコセッシの『ウルフ・オブ・ウォールストリート』との間に挟んで記憶したい超傑作である。
▼2022年7月26日
『グレイマン』
フレディマーキュリーそっくりサイコが登場際にショーペンハウアーを引用(笑)。
ショーペンハウアーはインド哲学(※ウパニシャッドの翻訳で有名)、マーキュリーはゾロアスター教。
従って私山田にとって『グレイマン』は、その両者の接点たるプラグマティズムによってCIA及び米国覇権主義を自己批判する反骨の大傑作。
『グレイマン』製作費は2億ドルwwww
何だかんだアメリカの映画産業って、予算も脚本の奥深さも何もかも全て桁違いじゃぁ! あと、人質の女の子が可愛すぎ!タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に出てたあの子役。
・・・。
可愛さも桁違ぃ♪
※2022年6月22日
私山田が好きな作品の感想を述べる上での自戒について
私山田は、脚本も自前でこなせる監督の映画が特に大好き。
だが、優れた脚本のプロットは幾重、幾パターンにも複雑な構造を備え、更にこの圧倒的な含蓄を瞬時に直感させる類の優れた演出で映画化されると、この思想性への解釈の余地は無尽蔵となり、従って感想を言葉でまとめる徒労感が反比例に爆増する。従って、私山田が超大好きな映画やアニメの感想を述べるか否かの判断は、作品に対する愛の大きさと、作品の優れた構造性に対する見極めとの兼ね合いを踏まえた上でなされる。当然、己の愛どころか知性すらその作品を評価するのに耐える域に遥か及ばずと打ちのめされた場合は、端から感想を言葉にまとめる試みを断念する。
それはややもすると、私山田が感想を述べる対象となる作品をどこかしら舐め腐っている態度の裏返しなのかもしれないが、しかし結局のところ「好き」という主観や感情を言葉にまとめ上げ、これをもって作品の認知度に貢献したいと思わせる衝動の本質とは、たとえ作品への敬意を幾ら払ったとしても、評価主体の分の逸脱を決して排除し切れない限界も含まざるを得ないと考える。つまり、好きな作品の感想を述べたがる己の衝動をより客観視すれば、これが作品の認知度への貢献という“おためごかし”だけに留まらず、いわゆる“自分語り”や、或いは評価者の内省の為の一手段といった自己本位の側面も、当然兼ね備えているという自覚に辿り着く。
従って、大好きだからこそより一層慎重に成らざるを得ない。
尚、既存の作品や他人様のテーマに対する感想を述べる為だけに頭を煩わせる行為そのものは、そもそも私山田独自の創作の為の思想性やアイディアの構築の文脈には、殆ど利益をもたらさない。従って、自分を見失うまで他人の作品に溺れてしまう過ちは、常に自戒していきたいものである。




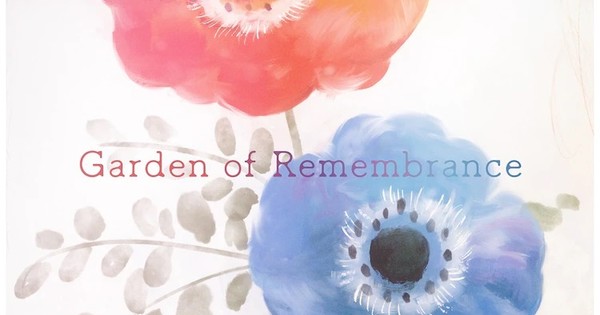



:quality(50)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/ERLFM4CMOBLRLKK4LL5TYWMWRY.jpg)