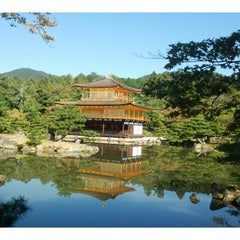サーカスをモチーフなんかな…
家原寺 【えばらじ】
寺伝によると慶雲元年(704年)、行基が生家を寺に改めたのに始まるとされてます。
叡尊が寛元3年(1245年)に再興し、多くの塔頭を有したが、兵火などで衰退しました。
江戸時代には田安家が帰依して寺領の寄進がなされています。
しかし、明治初年の廃仏毀釈で荒廃しました。
1989年(平成元年)に三重塔が再建されました。
2018年(平成30年)に高野山真言宗から独立し、行基宗を創設して本山となっています。

大門(仁王門)
南大門は幾多の戦災や火災から生き延び現在の家原寺で最も古い建造物(昭和40年に修理)
例にもれず廃仏毀釈で荒廃したが、現在安置されている仁王像は明治時代に近郊の寺院より移設されたものとか
一間一戸の門を仁王門にしている例はめずらしいと思います
たいていの仁王門は像を置くために三間一戸の形式(八脚門や楼門)にしている場合がほとんどなんだとか

本来安置されていた仁王像は 運慶 快慶の作で、廃仏毀釈ののち明治時代にフランス人の美術商に売却され、現在は米国ワシントンのフーリエ博物館に収蔵されているんだとか
この…仁王像は?

手水岩
これは珍しいよね
でも…
これは…
飾りで…
手を清めるのは…
隣の蛇口みたいなやつ

本堂
江戸時代初期の慶安元年(1648)再建
行基作と伝えられる文殊像は、日本三体文殊の一つとされ、「家原文殊」「智慧の文殊」と言われ、入試シーズンには受験生が沢山訪れ、自分の名を落書きしていくので、一名「落書き寺」と呼ばれています
御本尊
文殊菩薩
本尊の文殊菩薩は行基作とされてます
説明文に、「行基菩薩の御遺徳をしたって高僧から庶民までおまいりが絶えません。」とあるので、行基への信仰があり、家原寺をいわゆる「誕生寺」の一つと考えれば、行基作の文殊菩薩像が信仰の中心になっていったんやね
文殊菩薩は、大乗仏教の崇拝の対象である菩薩の一尊で、一般に智慧を司る仏とされてます
その他、非人救済などの慈善事業を司るほか、日本の真言律宗では慈母供養の象徴としての一面も重視されたんだとか
これらは行基の伝承ともつながり、行基菩薩 = 文殊菩薩 であるように感じられるよね
行基は日本の文殊菩薩であったのかもしれない
平安時代初期に、勤操や泰善らの僧侶が文殊菩薩の法要と貧者や病者のための施しを行う「文殊会」を始め、最初は私的な催しだったものが、朝廷の援助を得るようになり、828年7月、太政官符によって文殊会を行うようになったとか
毎年七月八日、朝廷が一定の税収から文殊会の費用を拠出し、東寺・西寺を中心に盛んに行われ、貧者や病者に対する布施が盛んになされたんやって
このことは、日本の福祉の歴史においても重要な一幕と言えるが、律令国家の没落とともに文殊会も衰退し、やがて行われなくなったんです
それを鎌倉時代に復興したのが、西大寺の叡尊・忍性らであったんです
本堂が、合格祈願の白いハンカチで埋め尽くされているよね
奈良時代の高僧である行基の生誕地とされる同寺
かつては参拝者が壁や柱に直接願いごとを書いていて、「落書き寺」とも呼ばれたが、建物の保護のため、約40年前からハンカチを貼るようになったとか
貼られたハンカチは受験シーズンが終わる3月末にはがされ、おたきあげされるんやって
ハンカチは千円です

地蔵堂
中のお地蔵様を参拝

地蔵堂の中には
水かけ清水地蔵
古くは現在の三重塔の横にある、井戸(赤龍の井戸)のそばにまつられていたそうで、この井戸の水で農作物を洗うとよく売れたことから、商売繁盛の地蔵さんとして知られていたようです
この顔…
めちゃ…冷めてない?…

鐘楼
只今、メンテ中みたいですね

賓頭盧様
あれ…
この顔…
お笑い芸人の誰かに似てる

不動堂
一願不動明王
ただ一つの願いごとを熱願すれば必ず成就する というとってもありがたいご利益があることで知られています

弁財天は、インドの神聖な川・サラスヴァティに由来したヒンドゥー教の女神を指します
弁財天という名前は、仏教における呼び名
水の神様なので特に農家から信仰されることが多かったですが、今では財運や芸術、学問など多種多様なご利益がある神様として多くの人から親しまれています
また、七福神唯一の女神であり、琵琶を演奏する様子も印象的だよね
もともとはヒンドゥー教の神様であった弁財天は、仏教の広まりとともに取り込まれたとされています
日本における弁財天は日本神話の神様の要素も持ち合わせているので、中国やインドで親しまれている弁財天とは異なる点が多いんよ
弁財天と同じ存在と言われているものには、日本神話に出る市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)が挙げられます
そのため、昔から弁財天を祀る神社では、御祭神を市杵島姫命とする場合も珍しくありませんよね
また、農業の神、宇賀神(うがじん)とも同一視されることがあります
古くから弁財天信仰があったことは今なお残る仏像からもうかがえます
源頼朝が藤原氏の調伏を祈願するために作らせた八臂(はっぴ)弁財天は、江戸時代には勝運守護の神様として信仰を集めました
八臂弁財天には腕が8本あるんだとか
弁才天や弁天、弁財天は同一の神様
本来は弁才天と記していましたが、弁天さまと略して呼ばれたり、弁財天と書かれることが増えました
これは、日本の神と習合され、弁財天のご利益が時代で変わってきていることを示してるんだとか
なお、弁財天は仏教における天部(天界に住む守護神)という存在に当たります
天は、サンスクリット語で神を表す言葉
本来、弁財天は豊作のご利益を授ける水の神様でしたが、日本ではほかにもさまざまなご利益を授かれると考えられています
代表的な弁財天のご利益について
財運向上
名前の中に財という文字があることから、商売繁盛や金運上昇などのご利益を期待できます
自営業を営む人や、これから豊かな暮らしをしたいと考えている人などから広く信仰を集めています
学問・芸術
川を神格化して生まれた弁財天は、川のせせらぎ音にちなんで音楽の神という一面も持ちます
ほかに、流れる水のように冗舌であることから弁才(巧みに話す能力)や、学力・記憶力の向上、芸術にもご利益があるとされています
美人祈願
弁財天は、美人な神様としても知られています
栃木の本城厳島神社は美人弁天という愛称で呼ばれ、美人証明というお守りも評判なんよ
美人証明は、外側から見たときの美しさではなく心の優しさを守るものとして授与されます

「行基菩薩生誕塚」と彫られている
奥には
開山堂
堂内には高僧お三方がお祀りしているはずなんですが……
扉には、右弘法大師、中央行基菩薩、左興正菩薩と書かれています
シンプルな堂内、お二人しかおられませんネ

行基菩薩御影堂
行基(668~749年)は、この地で生まれ、父の高志才智(こしのさいち)は百済から渡来した王仁(わに)を祖先とする一族で、母は蜂田首虎身(はちたのおびととらみ)の娘の古爾比売(こにひめ)とされてるんです
行基は仏教の民間布教と同時に、灌漑用の溜池を造るなどの社会事業を行ったんやって
中に行基さんの絵像がかけられています 重みのない軽々しいお堂の感じがしました
重みのない軽々しいお堂の感じがしました

ぼけ除け観音像
お顔はインド婦人そのもの、ひょっとしてインド製?
これがまた凄い細工の像ですが金銅ではなく鉄製像ではないでしょうか

龍の炉
めちゃカッコいいです

日本随一 文殊菩薩の碑
文殊(智恵)菩薩を ご本尊にしたのは家原寺が日本で初めてなんやね
獅子の顔が可愛いです

お庭も素敵です

梅の花

薬師堂(西国薬師第十五番霊場)
薬師如来坐像とその両側に日光菩薩、月光菩薩、十二神将が安置されているが、一般には公開されていないとか

これは…
何
チベット的な…

三重塔
平成元年建立された仏塔なんです
仏塔古寺十八尊霊場第一番札所
御本尊は不動明王です
新しいくて綺麗です

力強い御朱印です

三重塔の絵葉書を頂きました
最近…手紙って…書かない…
大阪府堺市西区家原寺町1-8-20

JR阪和線 鳳駅から徒歩で約5分の肉料理バルのハピドンさん
店内1階はカウンターで席と4人掛けテーブル2卓
2階は4人掛けテーブル2卓、6人掛けテーブル3卓に加え喫煙可能なテラス席有るんです

チーズトルコライス(サラダ付) 1180円
人気NO.1の料理なんやって
人気NO.1って見たら・・無視出来ない・・
トルコライスとは
トルコライスは長崎のご当地グルメで、ピラフ、パスタ、とんかつをワンプレートに盛り合わせた料理
カレー味のピラフとナポリタンのパスタを並べて盛り付け、その上にとんかつ、デミグラスソースをかけることが多くなっているんや
長崎の喫茶店などの飲食店でよく提供されているメニューで、お店ごとにピラフやパスタの味付けが変わっていたり、かけるソースがカレールウなどになっています
発祥と言われる九州の長崎の他にも、さまざまな地域でトルコライスは親しまれています
人気のある料理をワンプレートに組み合わせた各地域のトルコライス
関西の神戸では、チャーハンにカレールウと生卵をトッピングしたものがトルコライスと呼ばれています
神戸の隣の大阪ではまた一風違い、チキンライスにひとくちサイズのとんかつを乗せ、デミグラスソースをかけたものを指すこと
また、関東の横浜ではチキンライスの間にとんかつを挟んだものをトルコライスと呼ぶことがあるんやって
トルコライスは名前に「トルコ」とついていますが、実はトルコ料理ではないんやぁ
名前の由来は諸説ありますが…
トルコ料理のピラウから
トルコ料理にピラフの語源となったピラウという料理があります
トルコライスに盛り付けられるピラフが、トルコの料理に由来するという説
トルコライスはピラフのことを指しており、他のパスタやとんかつは付け合わせの料理であるとも言われています
トリコロールから
国名のトルコではなく、3色の色を示すトリコロールがなまってトルコライスとなったという説
3つの料理を盛り合わせた料理の特徴から、トリコロールと呼ばれていたものが少しずつ変化したということ
異なる国の料理がワンプレートになっていることから
中東発祥のピラフ、イタリアに起源があるパスタ、そしてとんかつと、さまざまな異なる国の食文化がひとつの皿の中におさめられている料理であることから、同じく異文化が重なり合うトルコのようであるため、トルコライスと呼ばれたという説があります

って事でここは大阪なんで
とんかつを乗せ、デミグラスソースをかけたものです

大分産のブランド卵蘭王使用!ハピドンこだわりの"熟成"豚カツ!
中は食欲をそそるカレー風味ご飯!
さらにじっくり煮込んだ自家製デミグラスソースとチーズの相性抜群で美味しかった
JR阪和線 鳳駅 徒歩5分
大阪府堺市西区鳳東町4-408-2