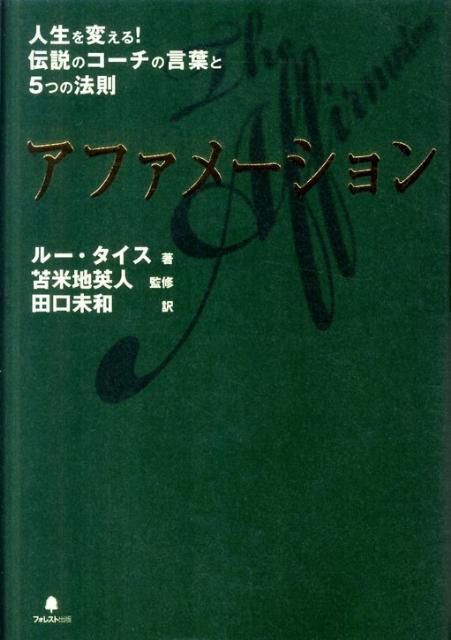コーチングの一番中心の概念はゴールという概念です。
コーチングの作業は自己評価を上げること。
理解するとコーチングが完璧にわかってくる。
ゴールというのは将来こうなって欲しいという自分の姿であり、周辺の姿だと思ってもらってもよい。
その中で極めて重要なのは現状では達することができないってこと。
現状っていうのは今の状態が続いた場合の可能性。
理想的な現状ではだめ。
ゴールというのはどんな理想的な現状でも、絶対達成できないことがゴール。
現状って何かって言うと、これは心の中でとてつもない自分ではそう簡単に乗り越えることができないバリアぐらいに思ってもらったらよい。
通常は現状の外側というのは、思いっきり変わらない限りは達成できない。
抽象度の高い現状の外というのは思いっきり変わらないと達成できないことを本当のゴールだと思ってほしい。
自分や自分の周りの人が変わらない限り達成できないことをゴールと言います。
このゴールを達成することができる奴だ。俺はっていう風に確信している人。それはゴールを達成することができる人です。
自己評価の定義というのは実績とか関係ない。
どうしてかと言うと、未来のことだから過去はどうでもいいのです。
実績って過去の話であり、実績そのものは本人の自信であり、自分自身の一部だから、貴重なもんだから、それを否定することは全然ない。
実績はなくてもいい。
俺は達成できる奴だ。
やったことないから否定するわけじゃない。
他の人が「お前、だめだよねそりゃ無理よ」というわけだ。
いや違います。私には達成できます。それが自己評価、だから根拠はいらない。
本来はゴールというのは現状じゃ達成できないものだから難しいに決まっています。
でも無意識というのはとてつもなくクリエイティブ(新しいものを自分の手で作り出す、創造的)なものです。
たまたま自分のゴールが設定された世界が自分の自己評価の世界と合っているかの話で、他人のゴールだったりすると発揮されないのは自己評価の空間がずれてるから。
ゴールを設定することがしっかりと現状の外側にできて、それに対して自分が達成することができる奴だっていう自己評価を維持することができると、無意識がものすごいクリエイティブに働いて、他の人には思いつかないようなクリエイティブなやり方を思いついて、ゴールを達成しちゃう。
だということは簡単に言うと当たり前だけれども、ゴールに対してよほど自分が好きじゃないと自己評価は上がりようがない。
嘘になっちゃうから、心から望んでることじゃなきゃいけないってこと。
もちろん心から望んでいるゴールに対して自己評価を下げるような要因をなくさなきゃいけない。
下がる要因というのは周りの人が多くなると。
それも自分がつい耳を傾けてしまう人たちが、下げる要因になるから。
そういう人たちとの会話を排除しなきゃいけない。
だいたいは親だったり、学校の先生だったり、友人だったりする。
本来は自分の一番の味方な人たちが妨げる要因になってくる。
意外と自己評価上げるときに、妨げる要因になりますよってこと。
これはまず最初のファーストステップと理解していかなきゃいけない。
あなたじゃ無理とか、君には無理とかいう可能性がある。
コーチング用語ではそういう人たちには単純な言葉がある。
ドリームキラーは意外と身近にいます。
解決法はゴールは人に言うなってこと。
ゴールは人に言わないこと。
これコーチングの基礎中の基礎です。
じゃあ何で言っちゃいけないかっていうのは、ゴールというのは止められても達成したいぐらい、なりたくてなりたくてしょうがないこと。
wont to であるということ。
ところがゴールを人に言ったりした瞬間に have to(なければいけない)に変わってくる。
自分自身が自分の自己評価をどうやって上げていこうか、一番基本なところは臨場感の問題である。
臨場感って何かって言うと。
その世界がどんだけリアル(現実的であるさま)であるかってことを。
私たちは現実世界にいるわけです。
現実世界の臨場感って高い。
五感で感じてるわけだから。
なぜかって言うと我々は五感で認識すると言っても、ものすごい情報を選択してるわけです。
興味あるものしか見てないわけです。
その時、自分が重要だと思っていることしか見ていないわけだから。
我々の世界は元々すごい限られてる世界で成り立ってますよっていうこと。
実際、心の中の自分が重要だと思ってることで成り立っている情報空間とホメオスタシス(生体が一定の状態を維持しようとする調節機能で、自律神経・内分泌・免疫の3大システムが働くことです)を築いている。
そのホメオスタシスのフィードバックの強度を臨場感という。
だから命に別状(普通と変わった状態)があれば臨場感が高いわけだ。
自分が幸せに生きてく空間として重要だと思ってる情報で成り立ってる物理空間がコンフォートゾーン(その人が慣れ親しんでいてストレスや不安を感じずに過ごせる、心理的な安全領域のこと) だと思ってもらいたい。
それが現状のわけだ。
無意識は臨場感の高い空間を選ぶ。
臨場感の高い空間を維持しようとする。
だから勝手にその世界に行こうとしてくれるってこと。
自己評価の高い空間の臨場感を上げればいいってこと。
すごく重要なものをたくさん入れればいいわけだ。
重要なものをどうやって増やすかというとアファメーション(「私は既に理想の状態である」とポジティブな宣言をすること)ということ。
アファーメーションというのは現在進行形で、自分のことで情動を表す。
嬉しいような言葉で自分の情動を表すような言葉で、自分の今の状況を語っていく。
状況っていうのは目の前の世界じゃない。
ゴールを達成した時、今いるに違いない自分、それは未来のことでもよい。
大抵は今そういうゴールを達成するんだったら、今目の前で自分の前に繰り広げるに違いない世界について記述した方がやりやすい。
自分自身であり、自分の周辺の状況を肯定系で、一人称で現在進行形で語ることをアファメーションをすることによって、物理空間よりも、その仮想的な自分の自己評価が高い方の空間の臨場感が上がっていく。
そっちの臨場感空間のほうが現実より高くなってくる。
日々のアファーメションで朝唱えて、夜寝る前に唱えて、昼間とか暇な時唱えるみたいなことをやっていくと、本当にそういった方が当たり前になっていく。
これが人間の無意識のすごいところで、そうすると現状に思いっきり不満が生まれてくる。
無意識が思いっきり持ってくれると無意識がものすごくクリエィティブに動き始めるわけ。
それがまさに自己評価を上げていくってこと。
現在の自分が将来ゴールを達成するんであれば、今きっとやっているに違いない日々の生活だったら想像しやすいでしょう。
それを言葉として唱える。
そしてだいたいは自分について、俺はそういうやつ。それを朝唱える、昼唱える。そして寝る前に唱えるってことをやってると。
本当に目の前の現状が見えてる世界が本来があるべき世界に変わってきて。
でも無意識は「なんか違うな」と思うけど。
それは自分が見えてる世界が臨場感を持ってるから。
現状に不満が生まれる。
そうすると無意識が本当にそれを解決するように。
クリエイティブに働く。
コーチングの一つはアファーメーションという技術を使う。
無意識とは今気づいているところが意識、気が付いてないところが無意識。
気が付いているというのは行動していても気が付いてない。
意識に上げてないけど自動的にできちゃっているやつが無意識。
実際は自分の認識の中にあるけど内省的に今意識しているところを意識、内省的に意識していないとこを無意識していると思ったらいい。
だから、自分が意識的な作業としてやらなくても、無意識がちゃんといかにやりたいことをやってくれているか。
重要なところは無意識がやってくれている。
実際は多くの知的作業ってそうなの、重要なテーマだったり、証明だったり。
そういったものはだいたいはある程度考えても、解決の作業、ずっとやってくれてる。
無意識というのは解決するべき問題を本人が気がついてないうちに勝手に解決してくれるもの。
これが無意識の作業で、無意識化する便利っていうのはそこだよね。
ものすごくたくさんのことを同時に問題解決をやってくれる。
無意識はすごくクリエイティブなのね。
だからコーチングでいうと現状の外側にゴールを設定すると現状の外なんだから達成しようが見えないに決まっているじゃん。
見えないものをどうやってやるんですかって言うと、脳は勝手にクリエイティブに見つけてくれる。
現状の外側は脳が無意識になって勝手にクリエイティブに問題解決してくれる。
達成の仕方なんかわからなくてもいい。
現状の外側に思いっきり本当になりたいゴールを設定できればちゃんと脳がクリエイティブにみつけてくれますよ。
実際にマインドって本当にそういう風に働くのね。
たくさんのことを同時にクリエティブに問題解決してくれてそれも自分でやった気にならないんです。
努力はいらない。それが無意識が味方につけるといいこと。
じゃどうやって味方につけるか。
本当にクリエイティブな無意識状態を作る。
その意識状態を引っ張り出す「環境」がいる。
現状の外に思いっきり本当になりたいゴールを設定できれば、ちゃんと脳はクリエイティブに見つけてくれます。
なんもしないでボケーとしているときと一生懸命、頭の中にビルを建ててる時で使ってるエネルギーほとんど変わらないんだよ。
無意識の中では、整合的なものを組み上げていこうという作業は、しようがしまいが普段使ってるエネルギーは変わらない。
変わってないってこと。
人間の無意識というのは物理空間と逆向きに働いてるわけ。
より整合的なものを作り上げてくれる。気が付かずにやれるわけ。
人間の無意識の力でそれは何かっていうといかに現状から切り離されたゴールを遠くに立てたいか。
ビルでいうと思いっきり高いビルを情報空間に立てようとすると無意識が思いっきり働くわけ。
それをゲシュタルトって言っている。
普段と同じバランスのゲシュタルトをほんのちょっと動かそうとしても戻っちゃって終わり。
ところが一度ゲシュタルトをバラバラびして、思いっきり高いものを作ろうとするとそのバラバラにしたゲシュタルトとが高いところに集まろうとするわけ。
コンフォートゾーンを上げるっていうことでも同じわけです。