プロのライターでいらっしゃる上阪徹さんによる
文章執筆講座(平成進化論/鮒谷さん主宰)に参加させて頂く予定です。
<上阪徹さんご著書(一部)>
- プロ論。/徳間書店
文章は「書く前」に8割決まる/サンマーク出版
書いて生きていく プロ文章論/ミシマ社
リブセンス<生きる意味> 25歳の最年少上場社長 村上太一の人を幸せにする仕事/日経BP社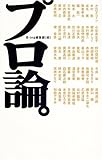


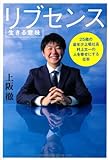
一度は上阪さんの本を読まれたことがある方は少なくないのではないでしょうか?
私自身も「プロ論。」は、前職の時に職場で紹介され、
出会えて良かったと、後々まで記憶に残る本の一つです。
*****
「書く」機会は、メールや提案書などのいわゆるビジネス文章以外にも、
blogやfacebook、イベントの告知文、他己紹介など、沢山あります。
自分で何か渦を巻こうとしている方であれば、
なおさら、少しでも上手な文章を書きたいと思われているのではないでしょうか。
私自身、最近、イベントの告知文や、クラウドファンディングの支援募集文など、
これまで書慣れた提案書とは異なる文章を書く機会が増え、悩むことが多いです。
またblogも開設してから9月で2年となりますが、
まだまだ「ただ書いている」状況を脱することができず、これも悩みの種です。
という訳で、上阪さんご本人から直接お話をお伺いするにあたり、
取り急ぎ数冊を拝読致しました。
*****
印象に残った点をあえて3つにしぼると以下の通りです。
1. 文章の「技術」よりも「心構え」が大切
2. 何の目的で、誰に向けて書くのか、を明確にする
3. 文章で伝える「難しさ」をよく理解する
*****
1. 文章の「技術」よりも「心構え」が大切
「文章が上手くなりたい」と思うと、
「語彙を豊かにしたらいいのかな」とか、
「王道の起承転結で書いた方がいいのかな」とか、
つい、技術に注意が行きがちです。
しかし、技術を高めることばかり注力していると、
「いい文章を書くこと」自体が目的になってしまいかねません。
文章を書く際の心構え、書く前の準備こそが重要、
というメッセージは心にぐさりと響きました。
2. 何の目的で、誰に向けて書くのか、を明確にする
1.の心構えの具体的なポイントの第一がこの「目的」と「相手」を
明確にする、ということです。
思い返すと、前職では、メールや提案書は、誰に読んでもらい、
どのような行動を起こしてもらいたいか、明確にしろ、
と口を酸っぱく教えてもらいました。
例えば、メールの件名は、こんな感じです。
例:【○○さん(cc△△さん)】XXについてのご確認依頼(○/○午前迄希望)
このような件名から書き出すと、自然と本文の内容や構成も決まってきます。
blogやメルマガ、イベントの告知文の場合であっても、
大切なポイントは同じ、ということに気づかされました。
ただ、仕事におけるメールや提案書では、文章がだめでも、対面や電話で
直接話すことで、リカバリーができたり、目的が達成できる機会がありました。
相手の方も、分かりにくい文章を書くやつだと思っても、
仕事上必要なことであれば、やりとりをしてくれます。
下駄を履かせて頂いていたようなものです。
あらゆる文章は「目的」と「相手」を明確にすることが不可欠。
当たり前かもしれませんが、一番大事なことだと思いました。
3. 文章で伝える「難しさ」をよく理解する
2.につながる点です。
そもそも読み手は「必ずしもその文章を読む必要はない」という
当たり前のことをよく理解する必要性です。
時間は有限です。
仮に、自分にとっては2~3分くらい何に使ってもいいや、
と軽く捉えていたとしても
人によっては、死に物狂いで捻出した1分1秒の積み重ねである
可能性は大いにあります。
自分が書いた文章を読んで頂くことの有り難さを肝に命じることが
大切だと改めて感じました。
*****
他にも、上阪さんのご著書には、文書を書くためのエッセンスが
惜しみなく披露されています。
自分に足りないところが沢山あり、途方にくれそうですが、、
明日は、まずはどこから着手していくか、具体的な行動につながる学びを
持ち帰ってきたいと思います。




