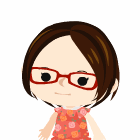■出来るを信じてみたら!(◎_◎;)■
本を読んで一番びっくりしたのが
タイムアウト法です。
並んでいる最中で、もうすぐ自分の番がくる!
という場面でも騒いだりしたら即列を離れる。
癇癪や望ましくない行動を起こしたら
壁際やドアの外等へ連れて行く。
この時、目を合わせたり、声掛けをしてはいけない。
タイムアウトの時間は一般的に年齢につき1分と言われているようですが、奥田先生の本には何分とは明言されていません。
私はその時の状況により、だと思っています。
今まで癇癪や問題行動を起したら、子供の気持ちを代弁するよう学んできていたので、この真逆な方法には本当にビックリしました。
他にも、遊びに行く際、電車で騒いだら一度
「それをしたら降りるよ」と警告し、
その注意を聞かなかったら、即電車を降りて本当に帰る。
など、
とにかく望ましくない行動には喪失体験、
望ましい行動の後には良い結果がくるようにする。
叱りゼロと書いてあるので、優しい内容かと思いきや、なかなか厳しいガーン
癇癪を起さないように、騒がないように等々
子供に振り回されている親が多いとあり、
まさに、私がそのものだと気づかせてくれました。
これでもまだ締め具合の調整に時間がかかり、ワンテンポ遅れることもしばしば。
学童では女の子たちに「はるかくんて、いちいち面倒くさいよね」と言われたそうですチーン
この靴の件を例にすると、線引きはこんな感じ。
普通の子が普通に靴を履くのとは違うので、もちろん時間はかかります。
その時間がかかることは問題にはしません。
これは感覚が私たちとは違うのだからそこは許容。
「癇癪を起せば何とかしてもらえる」ということを許さない
という感じです。
年中の終わりから奥田先生方式を取り入れました。
解決できるものもあれば、できないものもありましたし、今まで許されていたこと、癇癪を起せば思い通りになったことが思い通りにならなくなったことで年長の秋ごろには荒れてしまい、療育でも席を立ったり、寝転がったり、先生に文句を言ったり、お友達にちょっかいをかけたりと、とてもじゃないけど普通級ではやっていけないんじゃないかという状態でした。
それが、年長の冬から突然グッと伸びたのです。
自分のことだけしか見えていなかった息子だったけど、思考回路がパチパチパチっとつながった感じで周りの状況を考えることができるようになりました。
以前は療育の授業中も突然歌を歌い始めたり、思いついたことを突然話し始めたりしていました。
この辺りも療育の先生が、適切でない時間の発言には「頑として相手にしない」としてくれたことで、現在小学校では授業中に突然好きなことを話し始めたり、先生に執拗に話しかけたりはしていないそうです。
本人も「話したいことがあるんだけど、授業中は先生の話を聞かなくちゃいけないから我慢してるんだよ」と言っていたので、理解できているようです。
この本の方法で娘の我が儘に対応しています。
長らく悩んでいた「手伝って」攻撃が、たまたま出来た時に、目を見て思いっきり褒めたら一発で解消してビックリでした。
今までも意識して沢山褒めてきました。
頭をなでたり、抱きしめたりはしょっちゅうしていたけど、目を見ることを意識することは頭になかったんですよね。
でも、ちゃんと目を合わせて、それから「出来たね!」と褒める(すごい、えらい以外の言葉を使って)ことがこんなに効果があるなんて。
我が家はこれプラスタイムアウト法を使うことで、文句や言い訳を言いながらも、5秒のカウントダウンの間に飲めるようになりました。
そして、今はカウントダウンしなくても自分一人で粉薬をサラサラっと口に入れて飲んでいます。
ABAをきちんと勉強している方には今更感のある話なの かもしれませんが、私の読んだ所謂王道?のABAの本と奥田先生の本だと同じABAでも全く違う方法のように感じました。
子供の特性や状態によって、受け止め方も効果も全然違うと思いますので、あくまでもうちの子の場合はということでニコニコ