退職届はいつまでに出せば良いのでしょうか。
これがミニ知識なのですが,正確に答えられる専門家は僅かみたいです。
誤解ありがち度 5(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓
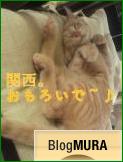
↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
A ズバリ「給与計算期間の前半」です。
末日締めなら15日まで(30or31日の月なら)。
でも,あまりに一方的だと損害賠償が登場するかも。
【退職の予告期間】
勤務先を退職しようと思っています。
どのくらい前に言えば良いのでしょうか。
→賃金計算期間の前半に申し出れば,その賃金計算期間のラストの日で退職となります。
雇用期間が「y年m月d日まで」と決まっている場合は,原則として途中での退職ということはできません。
あくまでも雇用期間の定めがない場合を前提とします。
まず,法律上,労働者側からは,2週間の予告期間を置けば,いつでも雇用契約の解約(退職)ができることになっています(民法627条1項)。
その一方で,「期間によって報酬を定めた場合」には,「当期の前半」に解約申入れ(退職を申し出ること)をすれば,「次期」に解約(退職)となります(民法627条2項)。
一般的には,給与は月給制が原則とされています(労働基準法24条2項)。
そこで,給与の締め日を月末としている会社という前提で,例を示すと次のとおりになります。
<退職の申し出と最短退職日>
5月15日~6月15日までに退職を申し出た
→6月30日(の終業時)に退職
注意すべき点は,627条1項の「2週間」が適用されるのは,結局,「日払い」「週払い」など,給与が月単位ではない場合のみ,ということです。
弁護士,社労士でも誤解している方が多いので注意しましょう。
[民法]
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
[労働基準法]
(賃金の支払)
第二十四条 (略)
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
【就業規則等と民法の優劣(退職予告期間)】
私の勤務している会社の就業規則や労働契約書では,「退職は30日前に申し出る」とされています。
「月の前半に申し出れば月末に退職」という民法のルールとどちらが正しいのでしょうか。
→民法の規定が優先されると考えられています。
民法627条の規定と,就業規則・労働契約の規定の優先関係については,ズバリの公的判断(裁判例)は見当たりません。
学説・通説としては民法の規定を強行法規として捉えています(吾妻・債権各論中巻二p590,品川孝次「契約法(下巻)」p152)。
逆に言えば,就業規則が有効(優先)という解釈もゼロではありません。
結論としては,民法の規定の方が優先という解釈が強い,ということです。
【解雇予告期間との関係】
退職する場合には「30日前に予告する」と法律で決まっているのではないのですか。
→雇用主からの解約(=解雇)については,労働基準法で30日前の予告が義務付けられています。労働者からの解約(退職)についてはこの規定は適用されません。
労働基準法20条において,解雇については30日前の予告が原則的に義務付けられています。
これはあくまでも雇用主からの労働契約の解約(=解雇)にだけ適用されます。
労働者からの解約(=退職)については適用されません。
労働基準法は,労働者の保護(=雇用主の拘束)が趣旨なので,このような方向性の規定となっています。
[労働基準法]
(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
(略)
【実際の不都合→損害賠償】
就業規則などの「1か月前の退職申出」というルールは適用されないということであれば,これを無視してもまったく問題はないのでしょうか。
→原則としては問題ありません。ただし,実際の業務の引継等に支障が生じた場合は,損害賠償責任が生じることもあります。
まさに,労働・職場の問題特有の事情です。
継続的な環境・業務がそれまで存続していたわけです。
退職すること自体の決定については最大限尊重されます。
しかし,民法・就業規則などのルール以前に,実害を生じさせるのは問題です。
退職の際の態様次第では,損害賠償として責任を負うことがあります。
この意味では,就業規則・労働契約における,退職申出予告期間については,有効・無効という問題ではなく,「この程度の余裕を持たないと損害が生じるかもしれない」という状況確認の意味は持っていると思われます。
具体的・現実的な状況を踏まえて,業務の引継等をしっかりと行い,勤務先に迷惑がかからないようにしておくべきです。
退職後は,職場に行かないことになります。
「損害が発生した」と会社から主張された場合,既に現場へのアクセスがしにくいので,防御しにくくなっているということもあります。
<まとめ>
民法の規定が優先ではあるが,就業規則・労働契約の退職予告期間はできる限り遵守した方が良い
<<告知>>
みずほ中央リーガルサポート会員募集中
法律に関する相談(質問)を受け付けます。
1週間で1問まで。
メルマガ(まぐまぐ)システムを利用しています。
詳しくは→こちら
無料お試し版は→こちら
<みずほ中央法律事務所HPリンク>
PCのホームページ
モバイルのホームページ
特集;高次脳機能障害
↓ランキングはこうなってます↓
↓ このブログが1位かも!? ↓
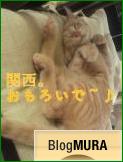
↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑
労働・企業法務に関するすべてのQ&Aはこちら
震災特例法に基づく被災者(会社)の負担軽減策。税金の還付請求など。by国税庁
個別的ご相談,助成金申請に関するお問い合わせは当事務所にご連絡下さい。
お問い合わせ・予約はこちら
↓お問い合わせ電話番号(土日含めて朝9時~夜10時受付)
0120-96-1040
03-5368-6030