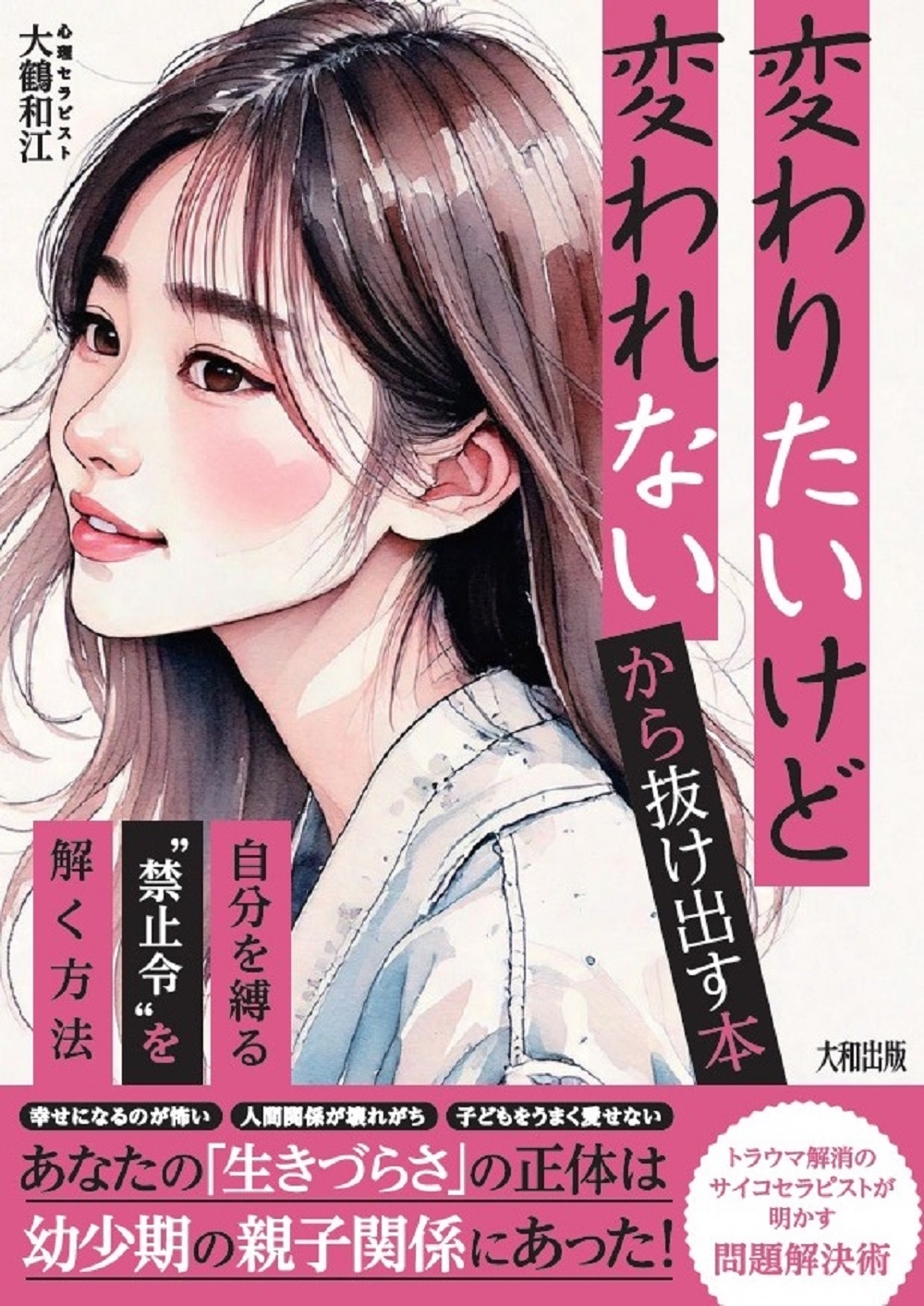こんにちは
心理セラピストの野沢ゆりこです。
おもに東京・千葉で活動しています。
野沢ゆりこのプロフィールはこちら
どんな人に向けて活動しているの?
自己否定が強い
自分責め、罪悪感が強い
そんな人が過去はどうであれ、
「私っていいな」に変わるセラピー
を目指しています。
リトリーブサイコセラピー協会のサービス、
電話カウンセリングを担当しております。
こちらもよろしくお願いいたします。
昨日につづき寒いですね~![]()
今日から新年度ですね。
あまりに冷えるので暖房をつけています。
今日はダウンコートを着ました。
冬物がしまえない・・・
__________________
前回、前々回のブログでは
感情を感じるのが苦手なあなたへ
「感じることを頑張る」のは逆効果
感情を感じるのが苦手なあなたへ②
違和感を大切にする
というテーマで書きました。
今日は続きになります。
感情を感じるのが苦手なあなたへ③身体に聞く
大きな声で怒鳴る人が近くにいると、身体がぞわっとする→怖い
人前で喋ろうとすると、胸がドキドキする→不安
昨日友人に言われた一言が、心に棘が刺さったように痛い→悲しい
出来事→身体の反応(感覚)→感情を感じる→感情を自覚する
感情を感じてそれを自覚するまでの流れです。
詳しく書いてみます。
感情が生まれ自覚するまでの流れ
感情が生まれて自覚するまでをフローチャートにしてみました。
①刺激を受ける
何かの出来事が起こる
(人の言葉・環境・思い出・体調など)
![]()
②体が反応する(無意識レベル)
心拍数が上がる
胃がギュッとする
肩がこわばるなど
![]()
③感情が生まれる(無意識レベル)
悲しい
怒り
嬉しい
不安
![]()
④感情を自覚する(思考につながる)
「あ、私は今悲しいんだな」
「これって怒りかも」
![]()
⑤感情に意味をつける(思考で整理する)
「なんでこんなに悲しいんだろう」
「この人の言葉に引っかかったのかも」
「この前の出来事が原因なのかも」
![]()
⑥行動につなががる
行動を抑える
何かを伝える
涙が出る
怒りを抑える
考え続ける
このフローチャートの注目するところは、
まず体の反応が起こる→そのあとに感情が生まれる
という点です。
人は時に何らかの理由で、チャート④の所に問題があって、
感情を感じてはいるが気づけない(感情凍結)
感情を自覚しているが無きものとして押し込める(抑圧)
感情を自覚しているものの否定する、捻じ曲げる(否認)
ということが起こります。
そして③→⑤と飛んで感情を思考で処理しようとすることがあります。
前々回のブログで書いた思考優位の人、なおかつ
過剰な意味づけをする人だといえます。
感情を「ただ感じる」ことが苦手で、
「なぜこう感じたのか?」と考え過ぎる人がいます。
(私はこのタイプなんですよね。。。)
そして感じたことを長々と説明する人もいます。
「この出来事が起きたのはこれこれこういう背景があるから
だから私はこう感じたのだと思う」っていう風に。
でもこれだと思考優位になりすぎて、
実際の感情からは切り離されてしまっていることが多いのです。
このタイプの人は「感情を思考で理解しよう、処理しよう」
ってするあまり、実際の感情を感じることが難しくなっている
というケースが多いのです。
「その時、あなたは何を感じたのですか?」という質問に、
長々と説明する人や解釈を加える人というのは、
実際の感情とはズレているとセラピストは推測します。
どうして感情に意味づけをしてしまうのか?というと
何等かの不安や恐怖があるからです。
感情をそのまま感じるのが怖い(回避・防衛反応)
感情を感じることよりも理解することが優先である(思考優位)
感情をありのまま表現したら否定された経験がある
自分の感情に意味づけ、分析、解釈をつけることで
感情をコントロールしたい、処理したい
そうすることで落ち着きたい、安心したい
って思っているからです。
それくらい過去に感じることが怖かったということです。
感情そのものが恐ろしいものと認識してしまっているのです。
感情を感じるのが苦手な人が、
感情を感じられるようにするためには、
体の反応に注意を向けることです。
つまり体に聞くことです。
セラピーの現場でも「何も感じません」とか、
自分が何を感じているのか「わかりません」
というクライアントさんに対して、
「体はどんな感じですか?」
「体は何て言ってますか?」
とセラピストは質問して
クライアントさんに自分の体を感じてもらいます。
「足が重いです」とか、
「背中が固まってます」などと答えたりします。
それに対して、さらに
「その足が喋るとしたら何て言ってそうですか?」
「背中があなたに何を伝えようとしていると思いますか?」
このようにセラピーではクライアントさんの感覚にアクセスして
感情を掴もうと模索しています。
感情に過剰に意味づけをする人がするべきことは、
「ただ感じるだけでOK」
「感情には意味がなくてもいい」
「感情は分析しなくてもいい」
と自分に言ってあげることです。それから、
「あえて何も考えない時間を作る」
これも大切かなと思います。
考えることで必死に自分を守ってきた、
考えることで理不尽な扱いを耐えて生き抜いてきた
そんな自分を労ってあげましょうね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
【残席1名になりました】
少人数で心理について話しませんか?
![]()
※オンラインカウンセリングはzoom対応しております。
心理セラピーについて詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧下さい
![]()
リトリーブサイコセラピーを作った人&セラピーの師である、
和姐さんの3冊目の著書です。
![]()
リトリーブサイコセラピーとは?
![]()
心理セラピーとは?
![]()
和姐さんの2冊目の書籍の装丁がこのたび変わったそうです。
![]()
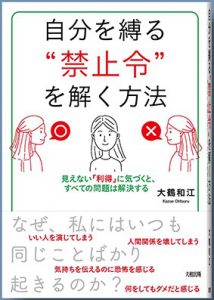
![]()
![]()
![]()
同じ本とは思えません!

京都の京子さんと和姐さんの大阪1dayセミナーです!詳細はこちらです。