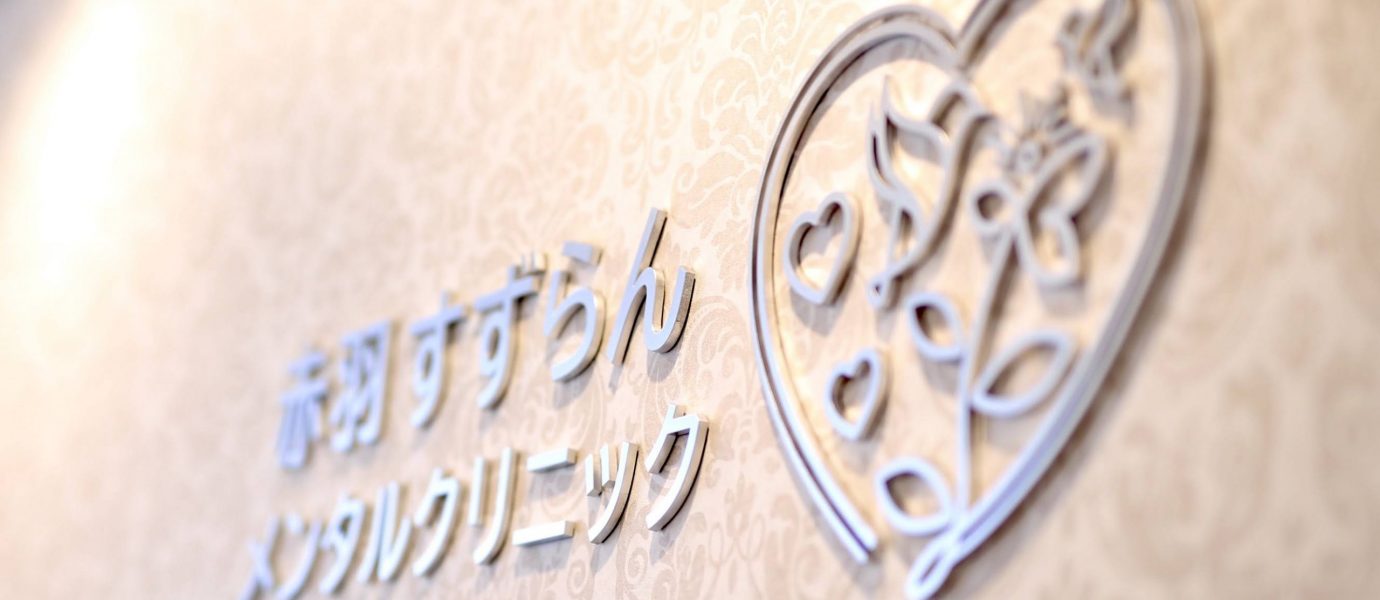以前のこの言及。
これは訂正が必要かもしれない。
********
その判断や瞑想技法の開拓・熟達について今の私に語れる事柄はないが、一つ言えるのは日記などの認知療法は安全基地なくして効果を発揮し得ないということ。
この世での安定した安堵があるから辛い過去を振り返り、トラウマを癒せる。
その命綱なくして(トラウマの宿る)潜在意識という深海への潜水など至難だ。
それゆえ愛着障害を患った誰しもがトラウマとの対峙が必要だと分かっていても二の足を踏む。
********
>ハイヤーセルフにつながった感覚の体験談
>ある日、何度もスケッチを重ねるも満足いく絵が描けず、自己嫌悪に陥っていました。
↑自己嫌悪。
>子育てに疲れ、自分が何を求めているのかすらわからなくなっていました。
↑疲労。
>自分の音楽に自信が持てず、何度も挫折を感じていました。
↑挫折。
つまり、自己嫌悪や疲労、挫折という心身の極限状態からのハイヤーセルフとの接続。
このルールは私も理解している。
ただし、ここでの登場人物は恐らく愛着障害を患っていない健常者だろう。
また、彼らの「追い込み」は別に自らのトラウマを掘り返すという苦行ではない。
それゆえ、こちらの愛着障害に関する発言が引っ掛かる。
>絵を描くという行為も安全基地になるんだよ。
>絵を描いたり日記やブログを書くことで愛着を安定させることもできるんだよ。
>安全基地とは自分が求めたときにありのままに受けとめてくれる存在。
>「書く」という行為は黙って話を聞いてくれる話し相手に似ています。
ここでの日記や創作はどの程度の深度を意味しているのだろう?
心をえぐるような日記や創作なのか、心が痛まない範囲のお遊び的な、セラピー的なものなのか?
あるいは段階的に深度を掘り下げていくのか?
脳のシナプス可塑性の復元力を利用してリハビリ的に少しずつ訓練していくのか?
恐らくはその認識で合っているのだろう。
つまり、日記や創作には二段階あり、最初は安全基地の形成、次がトラウマ領域への潜行と汚染の浄化。
日記での言語表現、創作での非言語表現。
言語は理性であり思考、つまりは理想欲、美意識。
非言語は感覚であり感情、つまりは生存欲、性衝動。
美と恥、性と死。
ゆえに日記は美的でなくてはならず、創作は性衝動を避けては通れない。
ちなみにこれは美と死、性と恥ではない。
美→恥___美←恥
↑⭕️↓___↓❎↑
死←性___死→性
死は美しいものではないし、性は恥ずかしいことではない。
死の美化と性の恥じらいは前世紀のカルト化した全体主義を思わせる。
また美と性、恥と死でもない。
精神の美と肉体の性は混同すべきでないし、恥ずかしいから死ぬべきでも死ぬ(負ける)ことを恥じるべきでもない。
羞恥心から生まれた美意識は歪だし、生命危機から生じた性衝動は粗暴だ。
美と性は生命讃歌の両輪であり、恥と死は苦の直視による意識変容の起爆剤となる。
死を直視することで美意識は磨かれ、恥を超克することで性衝動は更なる高み、聖なるものに昇華され、死に隣接する。
そして死の苗床から再び美が芽吹き、花が散るように恥と落ち性に転換され、昇天の果てに死に接近するという理想欲と生存欲の好循環が回転する。
ここで死と美の間、恥と性の間に補完する性質を置くならば志と恋になるが、共に死や恥で分散した意識が求道、あるいは異性として一点に集中し、美や性に好転する。
これを六行に当てはめるとこうなる。
__恋木
志火__性水
恥土__美金
__死冥
人は自意識の火から大志を抱き、金の美意識に昇華され、夢破れれば恥として土に帰す。
恥を灌ぐのは木の恋心であり、水の性の極みに達すれば生命の本懐を遂げ、冥の死を受け入れる。
そしてまた死の虚無から新たな志が芽生え、生命の回転を続ける。
恥・美は自我の理想欲、死・性は肉体の生存(生殖)欲だが、志・恋は何だろうか?
生命としての欲が生まれる発端。
何かをやろうとする意思、誰かを恋する意思。
自我でも肉体でもない魂から発する光のようなもの。
光源が何かを照らし、それに惹かれ、そこに向かおうとする性質。
それは「光輝性」とでも呼ぶべき実存の根源だと推測する。
インナーチャイルドとハイヤーセルフで言えば、火の深部にインナーチャイルドがあり、木の高次元にハイヤーセルフがいる。
つまり、志は純度を高めれば童心であり、恋は愛(慈愛)となる。
童心と慈愛を光輝と呼ぶなら至極納得ではあるまいか。
物心のついた青年の志から美意識を極限まで高め、その果てに変容し、幼児の童心に還る。
人の恋心から性衝動を極限まで高め、その果てに変容し、神の慈愛に昇華される。
理想欲と生存欲に表れる人の営みは、その最初の意思、光輝を考えれば無垢なる幼神に至ろうとする人の渇望が根幹にあるのではないか?
話は変わるが、この記事は今となっては左脳云々というより愛着障害の回避型が対人関係での弊害を埋め合わす工夫と言えるだろう。
********
人には感情と言うものがありますが、誰でもそれを上手に扱えているというわけでもなく、その発露を疎外されている場合も多々あると思います。
特に理論型の人間はそれが顕著であり、そもそも人に感情と言うものがあるという当たり前の事すら、日常生活において意識に浮上しない人も、決して少なくない数、特に男性におります。
そんな人にも等しく心と言うものはやはりあるわけで、まず理系タイプは「人には心があり、何より自分自身にも、自分にこそ心がある」ことを認め、自覚し、認識する必要があります(心みとめ)。
そして、それを大事に抱え、包み込み、ゆっくりほぐしてやる必要があります(心ほぐれ)。
どうほぐすかと言うと、ただ自分のその時の感情、喜怒哀楽恐好をそのまま認め、解放し、表現してやれば良いのですが、それが果たされた暁には自ずと赤子のように感情の爆発が巻き起こりますので、心をちゃんとほぐせたか否かの判定は非情に分かり易いでしょう。
どんな感情でも感極まれば涙が出ますので、泣けなければやり直しです。
********
また、この弊害は失感情症という名前がつけられているようだ。
その対策にはこうある。
>自分から逃げずに観察する
>日常で感情を見つける
>感情を表現する
この「感情表現」はそのまま日記や創作で実践できる。
つまり、機序としてはこうだ。
①回避型愛着障害→失感情症→セラピー(癒し)としての日記(思考)や創作(感情)→安全基地の形成。
②リハビリ(苦行)としての日記や創作→θ波→ハイヤーセルフとの接続。
③変容→γ波→変性意識状態による閃きや慈愛の湧出。
愛着障害を患っておらず、既に十分な安全基地が形成されているなら②からで良いが、いきなり自身の心をえぐるような試みができる人は少ないだろうから、誰しもセラピー的な浅瀬での水遊びで心身を慣らす方が宜しかろう。
その先の変容が起こるかどうかは現実(苦痛・トラウマ)直視の鋭さと感情振幅の大きさ、そこからの頭頂サハスラーラ昇華の可否に掛かっていると思われる。
また、変容の深度によっても閃きの切れ味や慈愛の総量が変わってくるだろう。
逆に言えば、セラピー的な日記や創作の時点で微量の閃きや慈愛がハイヤーセルフから漏れ出してるのかもしれない。
ハイヤーセルフとの接続において、正攻法である苦痛直視の量的臨界突破による質的変容という側面は大きいものの、それとは別になだらかなグラデーションを描く供給ルートもあるのかもしれない。