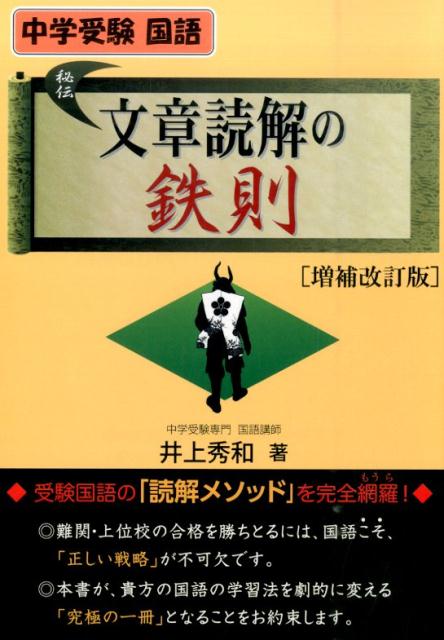最近、サピが人気すぎて、新一年生で入塾しないと募集がなくなり、入れなくなっている校舎があるみたいですね。
授業内容は、1年〜3年まではお遊びなので、4年カリキュラムからの入塾(3年生最後の2月スタート)で十分ですが、サピにどうしても入りたい人達が座席取りで早めに入塾して、を繰り返し、どんどん早まっていったみたいです。
ちなみに今年サピに入ったママ友の話では、大規模校だと割と3年でも入れるみたいだし、例え入れなくても予約だけ入れておけば、100人待ちでも3ヶ月くらいで順番が回ってきます。
また、遠くの校舎でも入塾さえできれば、最寄り校舎に空きが出来次第、移動できます。
息子のお友達も4年最初は最寄校舎に入れず、少し遠くの校舎に入り、空きが出たら最寄り校舎に移動してました。四年生でしたが、半年以内に移動できてました。
サピは勉強習慣がついてない状態や四則演算もまともにできないで入ると、ついて行くのに苦労します。
おすすめは、入塾前に公文で、毎日の勉強習慣と、算数と国語を最低でも小6まで終えて入塾すると予後が良いです。サピ4年では、公文6年までの四則演算を一気に終えるので、ついていけなくなります。
学生時代の友達のお子さんや同級生の友達は、1年から通塾し、2年までは上位クラスでした。しかし、3年後半で公文済の子達が大量入塾すると、真ん中クラスまで下がってました。
我が家の場合は公文を3歳から5年間やって、小3で算数は中1、国語は中2後半、英語は高1まで公文で終えてから、3年夏からサピに入塾しました。
入塾時は真ん中クラスでしたが、その後2回のテストで毎回上限いっぱいまでアップし上から2番目まで上がり(ここで入塾から半年経過)、それ以降、4年からはα1をキープしました。
なので、低学年の宿題が簡単なうちは、例えばサピと公文をダブルでやるか、公文だけを集中してやってサピに入るのがおすすめです。
公文生は最低でも2〜3000題は計算問題をやって、息を吸うように計算できる状態で入塾してきます。
例え公文に通わなくても、書店にある直接書き込みできる計算問題集を買い、3年までに自宅で6年までの四則演算を練習した方が絶対良いです。
4年が始まると忙しくなるので、そこから焦って計算を鍛え始めても遅いのです。
引き算、足し算、掛け算、割り算は当たり前で、分数、小数の混じった複雑な計算も、サピではできて当たり前に進みます。
また、我が家は公文と並行して、2年生の時中学受験用の
●最レベ3年
●スーパーエリート問題集2年
を旅行や長期休みの際に全て終えました。
どちらも多少計算は入っていますが、計算量は少なく、こちらの問題集のメインは公文で習わない図形や文章題です。
最レベ3年の方がスーパーエリート2年より簡単なんで、やる順番は、
公文の計算6年まで→最レベ3年→スーパーエリート2年
でやるのがおすすめです。
うちは学年通りだと思って、おすすめと逆にやってしまい、スーパーエリートは難しくてなかなか進まず、非常に苦労をしました。難問のスーパーエリート2年を終えると、最レベ3年が今度は簡単過ぎて、毎日20ページ位進めて、2週間で終えました。
そして、通塾前の3年前半の時は公文と並行して、こちらもやりました。
本当は最レベが書き込みしやすく、息子も私も好きでしたが、最レベは3年までしかないので、4年からはトップクラス問題集に移行しました。
中学受験塾は4年から本格的に始める為、中学受験向け問題集は基本3年までしかないものが多いようです。
我が家は薄い青の方は簡単なので全てやり、濃い青の方を半分終えて入塾しました。その後、サピ教材をメインにやったので、濃い青の方は手付かずで放置して終わりました。
あとは、お楽しみのため、1年〜3年の時期はSAPIX出版のこちらもやってました。カラーで、子供がやっていて1番楽しそうだったのはこの問題集でした。パズルみたいなものです。しかし、1年からサピに通っていたお友達に聞くと、サピ1年〜3年でやる算数とほぼ同じ内容だそう。我が家は低学年で通塾せず、これで十分でした。
低学年の時、サピに入ってなくとも、暇で何もしてないわけではなく、上位に食い込んでくる層は、その時間に低学年の頃から色々やってます。
我が家は公文やこれらの問題集に加えて、運動にも力を入れており、幼稚園から入塾までに体操5年、バスケ3年、水泳5年、サッカー、テニス、スケート、スキーなどをやってましたし、将棋2年、折り紙5年、ピアノ4年など、趣味系も色々して、息子好みのものをその都度、子供に選ばせて、全方向に子供を伸ばす努力をしました。
ーーーーーーーーー
●他塾への移動●
前置きが長くなりましたが、今回お話したかったのは、サピ入塾後に、塾が合わないと感じて、5年〜6年で早稲アカや日能研、四谷大塚や小規模塾などの他塾に転塾してしまう話です。
サピに入塾できたと安心して、その後の事は塾がなんとかしてくれるだろうと安心してはダメなのです。
サピはわかりやすい授業と、子供を最大限に伸ばすテキストを用意してくれるだけで、基本的な学習習慣と、宿題の管理をするのは親の役目です。
サピでは、毎年、5年〜6年生頭までに下から3分の1の子達がサピを辞めて、他塾へ移動します。
そして定員に空きが出ると、今度は、他塾の優秀層が入ってきます。
難関校を目指す生徒のほとんどがSに所属している為、他塾生はたまにあるS主催の模試を受験し、難関校受験層での自分の立ち位置を確認しなければなりません。
難関校を受ける人達は、ライバルのほとんどがS生となる為、S生と同じテキストをやっている方が安心だし、Sの中にいれば、6年塾内順位で、すぐに難関校受験層
での立ち位置の変化に気付けるし、改善したら改善後の結果確認も組み分けやマンスリーでできるので、非常に楽なのです。
6年頭では7500人→6,500人になり、約千人、減りました。
辞めるのは下のクラスの人で、真ん中クラス以上から辞める人はほぼいません。
なお、息子が通う小学校から一緒にSに通っていた女子は、ほぼ全員、6年が始まる前に辞めてました。(同じ小学校の女子は、ほとんどが半分より下クラスでした。)
通塾の時間帯は同じなので、そういや最近、サピ女子を見かけなくなったなと思っていたら、皆、サピ女子達がNバックを背負って歩いてて、驚いたようでしたが、それがリアルな現実でした。
辞める人は
①授業スピードについていけない
②Sのテキストが大量過ぎてやる気をなくした
③テキストと自分の志望校レベルが合わない
④Sより進度の遅い塾にて既習単元を再復習する
⑤受験自体からの撤退
などのようです。
Sの宿題量はNの10倍、Yの5倍と言われ、とにかく多いのです。
また、一般的に男子校の方が女子校より算数が難しく、Sの算数テキストは男子難関校(S 58くらい)に合わせてるので、算数レベルは最難関を受ける女子に、ちょうど良いレベルだけど、中間層の女子には過剰なのかもしれません。
なお、サピを辞めた女子の中でも上位の人や、宿題をやらない男子の場合は、Wに転塾する人が多かったです。
Wは宿題量多めで拘束時間も多め、宿題をやらないと怒られる体育会系の塾です。
サピはクールな塾で、通塾日数が少なく、弁当不要ですが、とにかく自宅での宿題量が多いので、学習習慣がない親子は苦しみます。また、宿題チェックもなく、テスト結果が全ての為、宿題を管理された方が楽な子はWの方が合うのでしょう。
Nは宿題量も少なく、スピードもゆっくりで、中堅校に強いですが、難関校向けではありません。
難関校を目指す場合、限られた校舎でやるTMコースに所属していないと対策できませんし、TMにいたとして
も、結局、勉強量が足りず、市販の問題集を大量にやったり、N内のライバル数が少なすぎる為、サピのSOや、Wの模試、WのNNなども兼用して立ち位置確認をしないと、難関校にはなかなか合格できません。なので、難関校を目指す人はWかSが良いでしょう。
中堅校を目指すのに、サピに入ってテキストレベルが合わなかった、と思った人は、Nに転塾すると、一度習った単元をもう一度おさらいでき、さらに授業時間に宿題をやる時間をくれたり、授業もゆっくり進みますので、自宅学習時間はかなり減りますし、理解が追いつかないという事は無くなります。むしろ、SからNに行く場合、これまでの勉強量が違いますから、上位クラスになれるでしょう。
またクラス昇降が毎月テスト結果のみで昇降する競争の激しいサピとは違い、Nでは3ヶ月〜半年に一度くらいしかクラス昇降はなく、その基準はテスト結果だけでなく、授業態度なども含まれるようです。なので、毎月のクラス昇降が苦手な人、中堅校を目指す人は最初からNに行くのが良いでしょう。
塾によって、狙う志望校レベルや、子供のタイプによって合う合わないなど、棲み分けがあるので、親御さんはよく自分のお子さんを見定めて、合う塾に入れるのが良いと思います。
●サピ6年からの話●
これは男子も女子も関係ありますが、6年までに下から三分の一がやめて、他塾の上位層が入ってくるので、全体の平均レベルが上がります。
なので、相対的に6年頭の時期に5年から居た人は皆、元の偏差値より、2〜3下がります。
だから6年頭になって偏差値が下がり調子だったり、成績が落ちたなと思うサピ生は実は多いのです。
しかし、この事実を知らずにいると、努力しても下がっていく成績に親は焦り、子供は自信を無くし、そのまま下がり調子になって受験を迎えてしまう場合もあるのです。
でも、これは毎年起こる事で、下がった6年のその偏差値こそが本物の合格判定をする偏差値となります。
5年までの偏差値は、本来の実力より、甘めに出ていると認識しておいた方が良いです。
ただ、偏差値が下がったとしても、子供はそのまま実力をキープしている状態で、決してサボっているわけでも、怠けているわけでもないのです。
塾内の構成要員の質が変わったのに、その事を親が理解せずに偏差値だけ見て、子供を怒ったりすると、頑張っている子は辛くなり、モチベが下がります。
すると、子供はこれ以上なく頑張っているのに、他人より自分は頑張っていないから、競り負けているのだと自信を失います。そこから、志望校がブレたり、やる気をなくして、そのままどんどん下がってしまいます。
我が家はこの事実を事前に息子に話していました。
なので、子供も一時期、偏差値が少し下がりましたが、全く気にする事なく、そのまま努力を続けました。
すると、そこから持ち直し、徐々に偏差値は元に戻り、更に上がっていきました。
なので、親御さんは、この時期、辛抱して、少しおおらかな気持ちで、お子さんをフォローすると良いと思います。
志望校を考える際も、 4〜5年生は、今の偏差値より2下がる前提で考えるとちょうど良いかも。