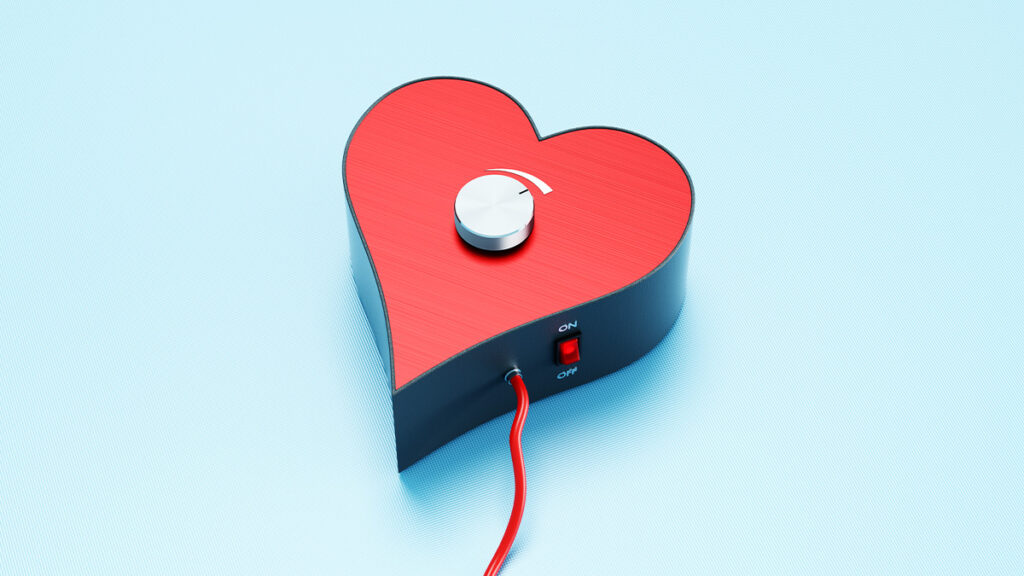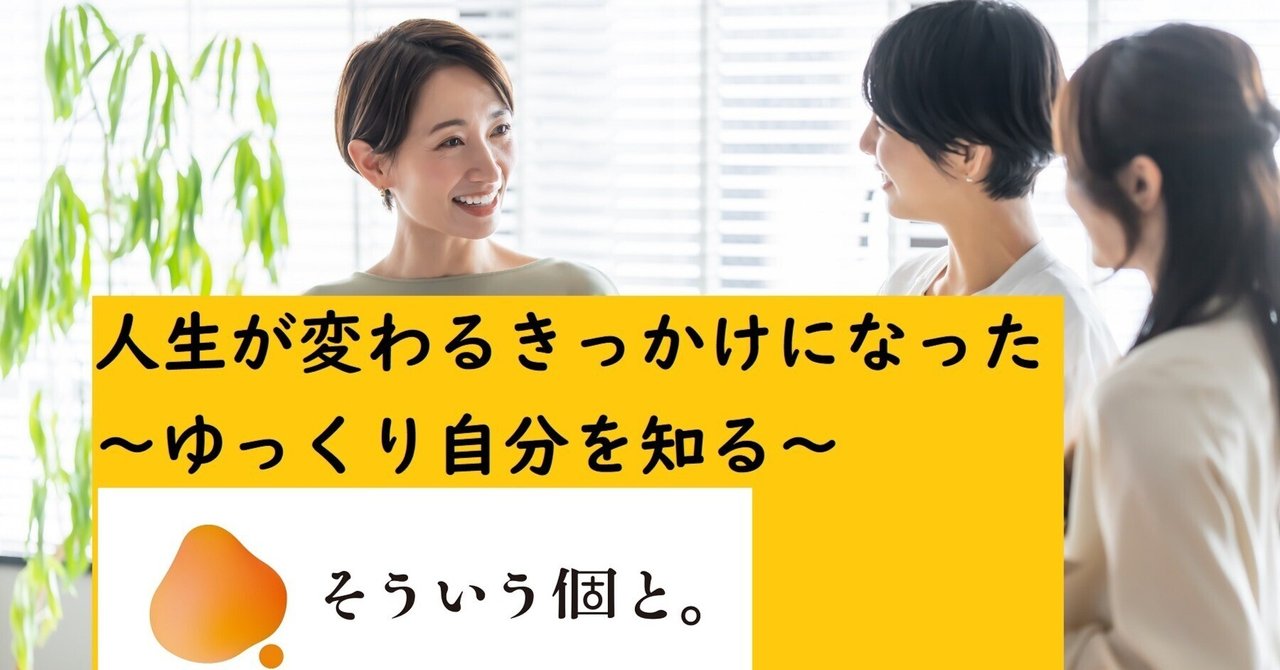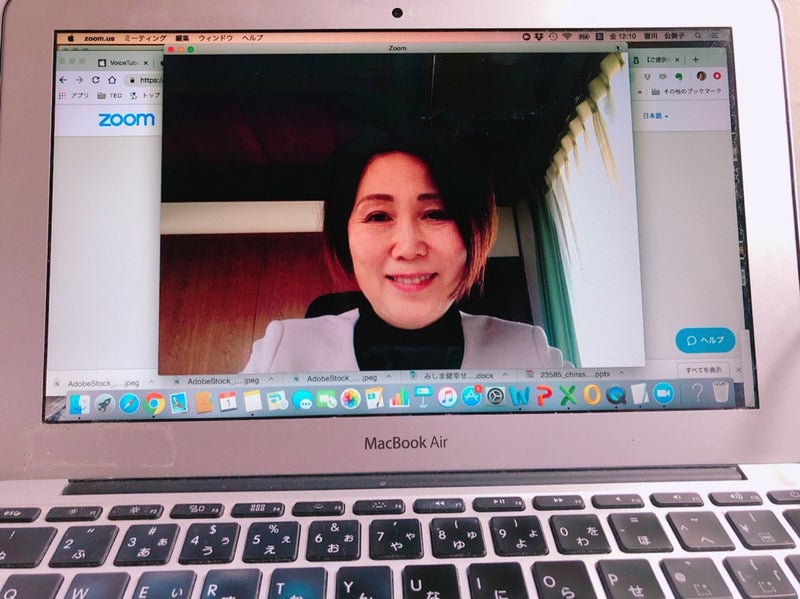・国家資格キャリアコンサルタント・ギャラップ認定ストレングコーチ
・TRE (トラウマ・テンション・リリース)国際認定プロバイダー・(株)サステナミー代表
皆川公美子です。
ポリヴェーガル・アプローチの新講座
これから新しく、ポリヴェーガルアプローチによる、
人を支援したり、人を支えたりする人のための講座をリリースします。というのは
前の記事でもお伝えしました。
キャリコンとして仕事をさせていただいている中で、
HSPさんに伝えることのなかで
生きづらさ、をどうするかは一大トピックです。
それは心の問題だけではなくて
身体からアプローチすることができる一角があるよ、
そして
慢性疲労や
重大な疾患に陥るまえに、
ちょとだけ具合が悪いを
自分でなんとかできるようになればそれで解決するということです。
また、考え方や感じ方のクセも自律神経からきます。
愛着や
人に依存しすぎるクセや
用心しすぎるクセも
その方の性格ではなくて
自律神経のパターンであることが多いです。
生きづらさも含め
手放すことができる、
もっとラクな自分で生きることができることを
お伝えすべきかもしれません。
具合がわるいときに早めにカウンセラーや
お医者さんにかかりましょう、ということではなくて
自分の体調や機嫌の波を
自律神経の活性度なども
ちゃんと見てあげられるようになれば、
誰であっても
自分でコントロールできるものだということを知っていただけたらなと思うんです。
(疾患状態に入って医師の指導のもとで投薬治療を受ける前の段階であれば、のお話です。)
そして自分を甘やかしていいんだよということも💓
先日、Facebookで休んでいいよね、という投稿をしました。
日本人は休めなさすぎだよね、
それはわがままじゃない、という主旨だったのですが
予想以上の反響がありました。
皆様そのことばっかりを考えているわけじゃないんだけど、
うっすらと引っかかっているところなんだなあということを痛感しました。
私たちは「自分の体調の限界値」を見る技術を
人生の前半に教わってないんですよね。
人生100年時代に向けた働き方と心身のケア技術
ここのところがものすごく、重要です。
私はこれから人生100年時代になっていく。
私なんかもきっと90代までは少なくとも生きちゃうような気してるんですよね。
75歳、定年にはもうすぐなっていくでしょう。
いや、実質的になっていっているでしょう。
(厚労省が動かしていってますよね、再雇用とか再就職とかそういう手段を制度化することによってね、みんな75歳までは当たり前に働くよね、っていうところを潜在的にキャンペーンしています。)
これは本当に年金が不安問題として、
年金の受給の年齢をどんどん後ろにしたい意図が伝わりますね、
厚労省は、それじゃないと財源がもたないのかもしれませんね。
多分私たちはなんだかんだ正規雇用でなくなったあと、
75歳くらいになったころ
働く日数や仕事をすすめるスピードがゆっくりになっていったとしても、
多分85歳くらいまでは何らか社会に何かの役務を提供しているという状況になるのではないかなと想像しています。
まあ今もう、
実質的にはそうなっていってるのかもですね。
明るいハッピーな老後を
誰しも送りたい💓
(老後って・・・古い!w余生って言葉も死語かも??( ◠‿◠ ))
そのためには、
感覚過敏や
不安や
人間関係のもろもろは
これまでのその人を守ってきた
神経パターンなので
HSPさんが不便に思っていることは
すべて変わることができるということを
お伝えすることが大事です。
働くことと人生のおわりは、楽しいほうがいい
働くことや人生のおわりのほう
人生の中で楽しく長く働けるっていう身体を、
そして自律神経を作っていきましょう
それを伝えてきましょうっていうのが私のご提案です。
その方が100倍楽しいっていう思うんですよね。
今、感受性が高いことによって、これまでの人生を、
もしかしたら何かきゅうきゅうとして生きなければいけない時期や、
もしかしたら居心地の良くない職場で我慢しなきゃいけなかったりとか、
そういうことがあったかもしれません。
でもそれは環境のひどさやパワハラ上司のせいだったかもしれませんが、
自律神経を扱う方法を知ると
環境の見え方そのものが変わっていきます。
神経の感受性が、防衛寄りから促進よりに変わってくると、
私たちは、たりやすくチャレンジできたり、
人に進言していく喜びを知ったり、
できます。
これどうしようかなと思って恐怖感でぶるぶるするような時って誰でもあります。
(いや全くない人もいますね・・・敏感性が皆無に近い人?)
それをもっともっと楽に超えられたり、そういうことが起こります。
レジリエンスを持って
いきいきと自分を表現できる技術を
社会全体で共有できるといいなと
思います。
ご自身の自律神経の活性度を知って身体も心も扱う技術を学んでいくのが
「そういう個と。プログラム」なんですけれども
それを人へのサポート、
誰か支えたいHSPさんがいる場合にどういう基本原則を持っていると
それができやすいのか。
それがポリヴェーガル理論のアプローチです。
この基本原則を知っているとめちゃくちゃ楽です。
日々こういうことはどうしたらいいんだろう、
こういうことはどうしたらいいんだろうって思うことって、
例えば、
人を育てているとか
育成職だとか
クライアントさんがいるという時に迷うことって多いんじゃないかなと思います。
「なんでやってこないの?やらないの?」
「どうしてここでチャレンジしないんだ?」
「あと一歩なのに・・・!」
そういう思いで生徒さんやクライアントさんを見ながら
祈るのみ!!ということはありますよね。
ポリヴェーガル理論はそこに人間という動物としての機能という
答えを与えます。
・人間の「安心」とはどこからくるのかを理解する
・人間が動けないときは「身体=自律神経」の指令なので動けない。を理解する
・なぜそうなるのか、それをどうやって解除していくのかも理解する
・人間が挑戦したり、探求したり、は身体が安全を感知していないと
絶対にそのモードにはなれない。を理解する。
これは人を育成しているときに非常に大切な視点です。
「こうすりゃいいってわかってるのに、
どうしてやらないの!!」
は
「頭で考えたことごと(大脳新皮質)は、身体の命の状況が起こしていること(辺縁系や脳幹)を制御できない。」
というしくみを理解することで
謎解きが起こりませんか?
ポリヴェーガルアプローチを会社の上司や育成職全員に知ってほしい
働く現場の上司全員に知ってほしい。
教育現場の人全員に知ってほしいって思っています。
みなさんでその波を起こして
社会をエンパワーしていきませんか?というお誘いの気持ちも
込めています。
さきほどちらっとご紹介した
「そういう個と。」もポリヴェーガルアプローチなのですが
自分の反応を見ていく、スキルを体得していく講座と、
人のことをケアしていくっていう講座は全く角度が違っています。
自分の身体反応を扱えるようになったあとでないと
他者の反応は扱えないので、
先に「そういう個と。」をリリースしたかった経緯がありました。
対人支援をやっておられる方は思っていらっしゃることでしょう。
軽い話で相談に来る人ってね、いないですよね。
クライアントさんは
困ったな
困ったなと
何年か思って
スキルを試したり
売れる技術とか
マーケとか
自分の未来を描くワークショップとか
スキルをゲットしてなんとかやっていこうと努力をされます。
それでもどうしてももやもやしたり
転職がうまくいかなかったり
起業がうまくいかなかったり
不安が起こりすぎたりするときに
相談に来られることが多いと思います。
そのときに
どーーーんと安心して
頼っていただけるようなサポート提供でありたいですね!
HSPは、強み
「繊細な人」は最高に輝く社員になれる
〜HSPの特性は弱点ではなく、強みである
ハーバードビジネスレビューに記事が出ました。
よかったらご覧になってくださいね。
少数派だからこそ私たちHSPは何か不都合を人生の前半で抱えたかもしれない。
でもそれを私たちはケアして自分で持ちつつ 、
人生を力強く進めていくことができる。
私はそのように考えています。
人をサポートするとか支援する、育成するという方のための
ポリヴェーガルアプローチによるサポート講座、
7月から開講の記事も下に貼っておきますのでご興味のある方はどうぞご覧ください。
ポリヴェーガル理論のすごさを
これからもお伝えしていきます。
膨大な海のような理論なので
気合いを入れてお伝えします。
これが使えるようになると
サポートの今まで手が届かなかったところに
手が届くようになります。
楽しみにおこしくださいね!
****************
◆
日程:① 7/9(日) 7/10 (月) 7/11(火)
②7/14(金) 7/15(土) 7/16(日)
10:00〜17:00 オンラインZOOM
◆7/1 7/2 名古屋へ伺います!
100名店を受賞しているイタリアン・ランチ会→満席
◆強みと人生の方向グループセッション(対面@名古屋)→満席
◆HSPが持続可能なサステナワークを手に入れる【
ご自身の神経系を扱うスキルで、強みを出して働ける人生にシフトする。
転職や発信にどうしても怖さがでる、という方、
明るく心地よく進んでいきたい方、
もやもやしたり不安がでてくる神経パターンを自分で暖かく見つめ直す技術を身につけましょう。
親子の愛着や幼少期の違和感や疎外感、それらはパターンなのでかえることができます。
4期(満席)5期開催中!
6期4月はじまり 土曜昼クラス少し増席しています!満席→増席
6月20日スタートは火曜夜クラスです。
・説明会動画
https://www.reservestock.jp/inquiry/81632#a123
・総合的な説明ページ
https://www.reservestock.jp/inquiry/81632
▼そういう個と。卒業生の体感、ご感想。
「人生がかわるきっかけになった。ゆっくり自分を知る」
◆3/21発売「HSP強みdeワーキング〜洞察系・共感系・感覚系」
Amazon ⏩ https://onl.bz/8XGTVyc
本の使い方説明動画(約3分)⏩https://vimeo.com/811917526/d399abcfb8
◆取材していただきました!
【自律神経とHSPの関係をとてもわかりやすくまとめてくださいました】
------------------------------------
◆そういう個と。公式ライン
登録いただいた方へ
「HSPさんの3大強み簡易診断」
プレゼント中![]()

noteでは「そういう個と。」にまつわることも発信しています。
https://note.com/souiucoto/n/
◆皆川のセッションは3種類です。まずは皆川と話してみたい、という方へ。
HSPさんのなんでも相談室 と 強みを活かして成果を出す相談室、そしてTRE(ボディワーク)です。 必要だなと思われたら、防衛反応解除のワークなども入れています。
--------------------------------------
おしゃべり裏チャンネル の stand. fmやってます。
ながら聞きができるので、車での往復やご飯作りのときに
お風呂のあとのリラックスタイムなどに聞いてくださっている方が多いです。