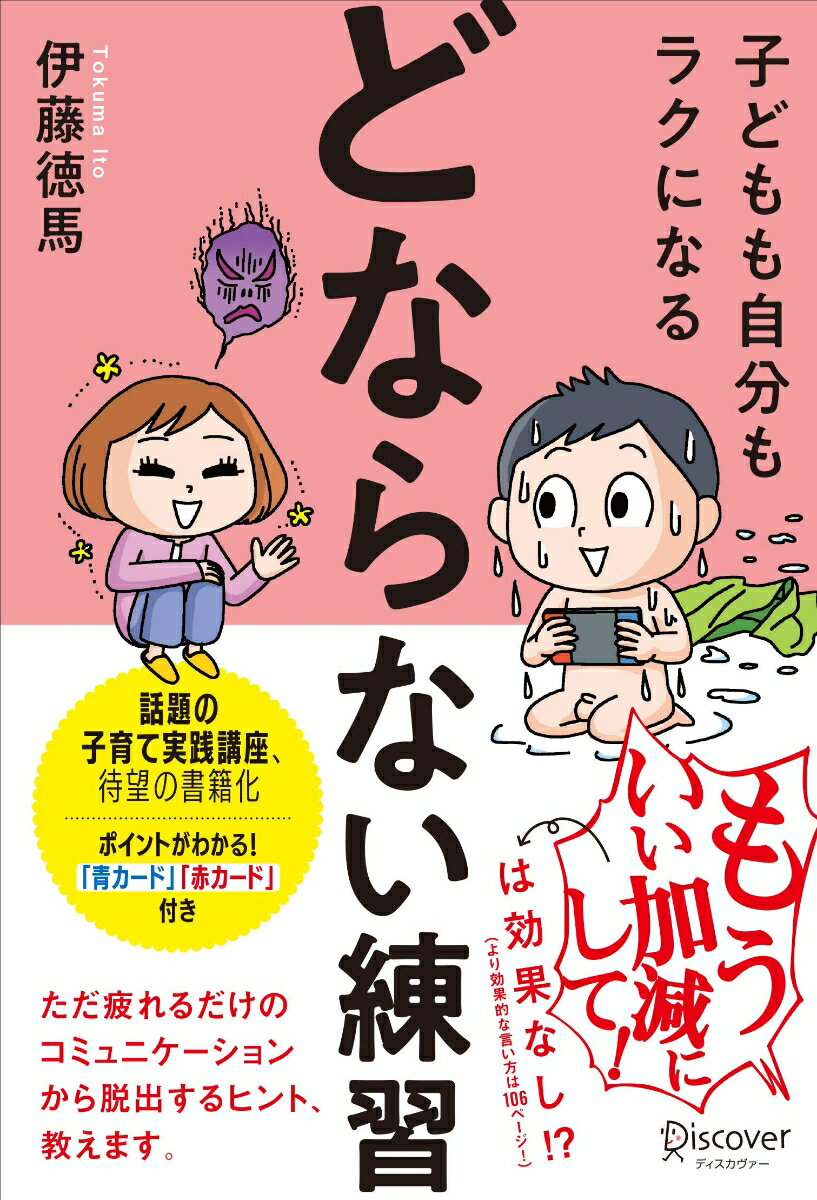3泊4日の沖縄旅行から無事に帰ってきました。
旅行前は、天候やこども達が体調を崩さないか、など気掛かりでしたが、みんな元気に旅行することができました。
お天気は、曇りが多かったですが、晴れ間もあり、海が綺麗に見えるタイミングも何度かありました。
亜熱帯地域特有のスコールのような雨が短時間ザーッと降ることもありましたが、観光するには問題なく、ついてるなと何度も感じました。
曇りは暑すぎず、風がふけば気持ちよく、動きやすかったです。
沖縄で1番夕日がきれいに見える宿、に選ばれたホテルに泊まりました。
旅行中、夕日を絶対見たかったのですが、叶いました。
しかも、長男の誕生日にホテルでケーキのお祝いをするタイミングで最高でした。
ずっと見ていたかったのですが、まぶしすぎるくらいの光の強さで、目が霞んでしまうほど。
ベランダにいるのも暑くて、部屋で夕食を食べながら、夕陽が沈むのを見ました。
長男が、夕陽が海に照らされ、午後行ったビーチハウスにつながっているように見える様子を
「夕日がビーチハウスにぶつかってる」と言い、表現が素敵だなと思いました。
夕日が見れる前は曇り空だったのです。
1時間前はこんな感じの空模様。
どんどん雲がなくなり、綺麗な夕日が見れて、私が1番興奮して「ラッキー、サイコー、ついてる、すごい」と騒いでいました。
夕日を見ながら、今死んでも悔いはないなぁと思いました。
そう思える家族と出会うことができて、本当に感謝です。
夫と出会い、可愛い3人の子供たちを授かり、沖縄の最高のホテルの部屋でのんびり過ごすことができている、本当に幸せだなーと、幸せに浸りました。
沖縄旅行の計画は、綿密にしていて、思うように動けないプランもたてていましたが、計画通りというか、計画以上に動けたことにびっくりしました。
美ら海水族館ではやりたいことがたくさんありました。
8時半、入場
9時、黒潮探検(水上観覧)
9時半、マンタの餌やり見学
10時、イルカの餌やり体験
10時半、イルカショー
11時、ウミガメの餌やり体験
美ら海水族館は広いので、このスケジュールをこなせると思っておらず、ウミガメの餌やりはできないかもしれないし、イルカショーは午後になるかもしれないと考えていました。
水族館の中をテキパキとかけぬける感じで見れたのが、その後のイルカショーや餌やり体験をスムーズに回れた要因かなと思います。
長男が出入り口にあったクレーンゲームがしたいと途中からずっと言っていて、「クレーンゲームは帰るときにするから、もうそのことは忘れて」と説得していましたが、疲れてきたのか
「ウミガメの餌やりはやりたくない。お母さんがやりたいんでしょ」と言い出しました。
子どもにいろんなことを体験させてあげたいという気持ちはエゴなのかもしれないなとションボリ。
でも、ウミガメの餌やりを体験できることなんてなかなかないので、騒ぐ長男をなだめながら、受付に並びました。
双子は、双子ベビーカーに乗っていたので、あまり駄々をこねることもなく助かりました。
餌やり体験中は楽しかったようで、「キャベツ食べるんだね」などと言いながら、ウミガメにたくさん餌をあげていました。
この後、美ら海水族館の近くの海洋文化館まで歩いて行き、プラネタリウムを見たり、木育おもちゃで遊びました。
「銀河鉄道の夜」のプラネタリウムを見るために、1つ上映作品を飛ばしたのですが、夫がそれも見たいと言いだしました。
プラネタリウムで寝る気だなと思いましたが、朝早くから運転で疲れているだろうし、この後も運転しなきゃいけないので快く送り出しました。
「銀河鉄道の夜」は、話の内容が長男には難しかったかなと思いましたが、映像も綺麗で、列車に乗っているような感覚だったり、楽しかったようです。
双子は暗いのが怖かったようで、途中から膝の上で寝ていました。
プラネタリウムを見た後は、フクギの並木や古宇利島に行き、最後に道の駅許田でお土産を買いました。
道の駅許田は、行けたら行こうと考えていたのですが、予定よりも早く行動できたので行くことができました。
そこで、もずくうどんを試食で何度もおかわりをもらい、子どもたちがお腹いっぱいなるほどで、とても美味しかったです。ありがたいです。
もちろんお土産に買いました。
うどんと一緒に買ったもずくは、海藻スープに入れたり、つゆで食べたり気に入っています。
子ども達がもずくを好きになってよかったです。
美ら海水族館方面に行きたい観光地が沢山あり、大人でもいっぱいいっぱいの日程になっていましたが、全部行くことができて大満足です。
子ども達は車で寝たりしていたので、元気に一緒に行動できたのかなと思います。
沖縄旅行が計画以上に動けたのは、子どもの成長のおかげだねと夫と話しました。
双子の体力がついてるし、聞き分けもできるようになっている。
そして、長男が朝食ビュッフェで飲み物を運んだり、キャリーケースを押してくれたり、戦力になってくれている。
来年はもっと楽になるだろうと思います。
双子ベビーカーがあると、エレベーターで移動するため、エレベーターを探したり、小さいエレベーターだと二手に分かれる必要があります。
双子ベビーカーを使わなくなれば、エスカレーターに乗れたり、もっと移動が楽になると思います。
これからどんどんお出かけが楽になると思うと、楽しみでいっぱいです。
ホテル滞在中に感動したことがあります。
ベランダで2人くらいでスクワットをしている人がいるなと思って見ていました。
すると、清掃スタッフの方が、ベランダの手すりの格子一本一本をふいていたのです。
その後、ベランダに掃除機をかけていました。
ベッドの下も綺麗で、清掃が行き届いているなと思いましたが、ここまで徹底的にされているからなんだなと気づきました。
我が家はおもちゃがベッドの下に転がったりして、旅行中、ベッドの下を覗くことがあり、ベッドの下に食べかすのようなものが落ちてるリゾートホテルも過去にありました。
スタッフの方も親切な方が多くて、とても気持ちよく過ごすことができました。