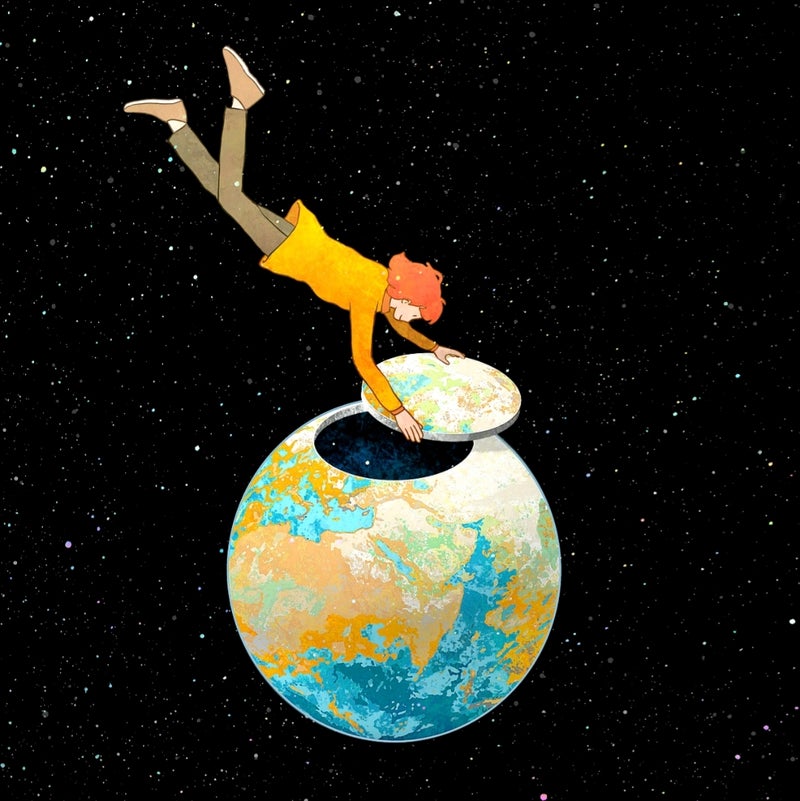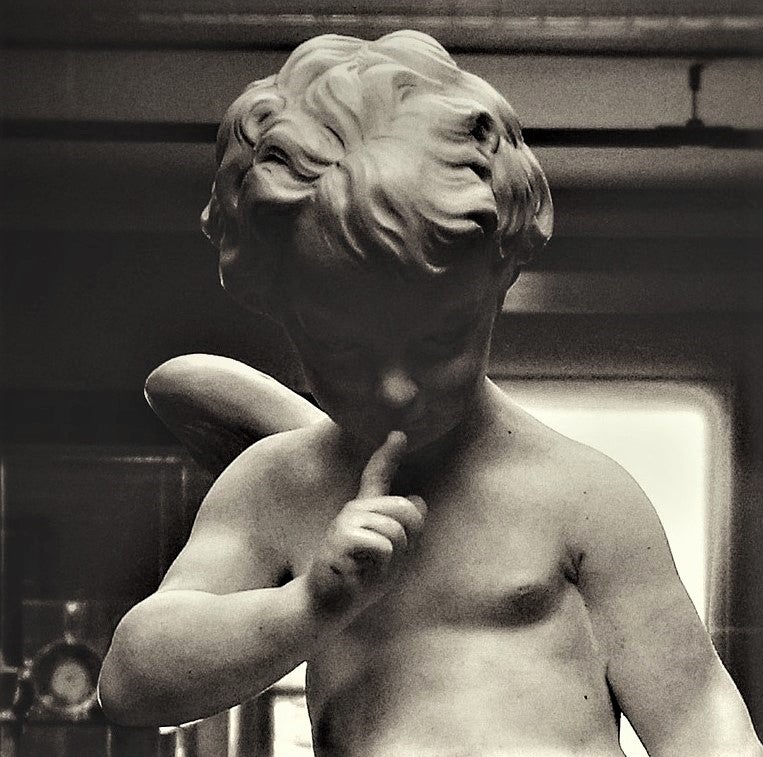『桃花源記』─ 陶淵明
晉太元中 武陵人捕魚爲業
縁溪行 忘路之遠近
忽逢桃花林 夾岸數百歩
中無雜樹 芳草鮮美 落英繽紛
漁人甚異之 復前行 欲窮其林
林盡水源 便得一山
縁溪行 忘路之遠近
忽逢桃花林 夾岸數百歩
中無雜樹 芳草鮮美 落英繽紛
漁人甚異之 復前行 欲窮其林
林盡水源 便得一山
晋(しん)の太元年間(376-396)、
武陵(ぶりょう・現在の湖南省)というところに、
ひとりの漁師がいた。
ある日、谷川に沿って舟を漕ぐうちに、
方向を見失い、
どこまで来たか分からなくなった。
すると突如、桃の花が一面に咲き乱れる林が
すると突如、桃の花が一面に咲き乱れる林が
川の両岸数百歩に渡って広がった。
雑樹がなく桃の木だけが生え、
香しく香る草の上に、
花びらがはらはらと舞っている。
これまでに見たことのない鮮やかな光景。
漁師は引き込まれるように、林の先を探ろうと、
さらに桃の花の中を奥へと進んだ。
そしてついに水源に行きあたった。
そしてついに水源に行きあたった。
そこは見慣れない山がそびえ立つところだった。
山有小口 髣髴若有光
便捨船 從口入 初極狹 纔通人
復行數十歩 豁然開朗
土地平曠 屋舍儼然
有良田美池桑竹之屬
阡陌交通 鷄犬相聞
其中往來種作 男女衣著 悉如外人
黄髮垂髫 並怡然自樂
其中往來種作 男女衣著 悉如外人
黄髮垂髫 並怡然自樂
そのとき、漁師は山影に小さな穴を見つけた。
穴からはかすかな光がもれ出ていた。
漁師は舟を降り、穴の中へと入っていった。
中は、初めはとても狭く、
人ひとりがやっと通れるほど。
さらに数十歩ほど進むと、
突然まぶしい光が射し、外へ出た。
眼前に広がった土地は、平らで広く、
眼前に広がった土地は、平らで広く、
よく手入れされた家々が並びたっている。
田畑も池もみな美しく、
桑の木や竹の類があちこちにあり、
あぜ道が縦横に通じていて、
鶏や犬の鳴き声が聞こえてくる。
道を行き交う人はみな、漁師(外の世界の人)と
同じような衣服を着ていて、
白髪頭の老人や、おさげ髪の子どもたちまで、
白髪頭の老人や、おさげ髪の子どもたちまで、
みな心から楽しんでいるようだ。
見漁人 乃大驚 問所從來
具答之 便要還家 設酒殺鷄作食
村中聞有此人 咸來問訊
自云先世避秦時亂 率妻子邑人來此絶境
不復出焉 遂與外人間隔
問今是何世 乃不知有漢 無論魏晉
此人一一爲具言所聞 皆嘆惋
村中聞有此人 咸來問訊
自云先世避秦時亂 率妻子邑人來此絶境
不復出焉 遂與外人間隔
問今是何世 乃不知有漢 無論魏晉
此人一一爲具言所聞 皆嘆惋
見慣れない漁師に気づき、
驚いた村人のひとりが、
どこから来たのかと尋ねてきた。
漁師がここへ迷い込んだわけを丁寧に答えると、
その話をきいた村人は漁師を家に迎え入れ、
お酒をだしたり、鶏を料理したりして、
お酒をだしたり、鶏を料理したりして、
親切にもてなしてくれた。
やがて、
漁師の噂が広まり、村の人々が集まってきた。
そして漁師にあれこれ話しかけてきた。
その中のひとりが言うには、
「私たちの先祖は秦の時代の戦乱を逃れ、
その中のひとりが言うには、
「私たちの先祖は秦の時代の戦乱を逃れ、
家族や村ごとこの地にやってきました。
そして、それ以来いっさい外へは出ず、
そして、それ以来いっさい外へは出ず、
外の世界とは断絶しこの暮らしを守っています」
と。
さらに、
「お尋ねしますが、今は何という時代なので
しょうか」と問うてきた。
驚いたことに、ここの人たちは秦が滅んで漢が
できたことすら知らず、
それが三つの国にわかれたこと、そして、
それが三つの国にわかれたこと、そして、
いまは別の晋という国になっていることも
知らなかった。
漁師が
外の世界のことをあれこれ聞かせてやると、
みな一様に驚き聞き入るばかりだった。
餘人各復延至其家 皆出酒食
停數日 辭去
此中人語云 不足爲外人道也
既出 得其船 便扶向路 處處誌之
及郡下 詣太守 説如此
太守即遣人隨其往 尋向所誌 遂迷不復得路
南陽劉子驥高尚士也 聞之 欣然規往
未果 尋病終 後遂無問津者
停數日 辭去
此中人語云 不足爲外人道也
既出 得其船 便扶向路 處處誌之
及郡下 詣太守 説如此
太守即遣人隨其往 尋向所誌 遂迷不復得路
南陽劉子驥高尚士也 聞之 欣然規往
未果 尋病終 後遂無問津者
それからも、村の人々はそれぞれの家に漁師を
招いてご馳走してくれた。
そうして滞在すること数日、
いよいよ自分の家に帰ることにした漁師は暇を
告げた。
すると、村人のひとりが漁師に言った、
「ここのことはけっして誰にも話さないで
いただきたいのです」と。
そして漁師を見送った。
穴から出た漁師は舟を見つけ、
穴から出た漁師は舟を見つけ、
先に来た道に沿って、ところどころに目印を
つけておいた。
ところが、川を下って郡下に至ると、
漁師は太守に自分の体験したことを語った。
太守は人を遣わし、漁師に道案内をさせ、
目印に沿って川を遡らせたが、
ついに桃の林も、村への入口である穴も
ついに桃の林も、村への入口である穴も
見つけることはできなかった。
高尚の士として知られた南陽の
高尚の士として知られた南陽の
劉子驥(りゅうしき)は、この話を聞いて喜び、
自分こそがそこを探し出そうとしたが、
願いを成就できないまま病に倒れた。
その後、多くの者が試みたが、
誰ひとりとしてたどり着けた者はいなかった。
意訳はご参考程度に。
気になる箇所があれば、ご自身で原文と
向き合い解釈を探ってみて下さい。
陶淵明(とうえんめい/365-427)の詩文で
一般的に広く知られている作品といえば、
やはり
この『桃花源記(とうかげんき)』でしょうか。
これは日本人にも深く親しまれてきた
中国の伝奇小説になります。
『桃花源記』をあらためて読み返しますと、
桃花が咲き乱れているのは、
行った先ではなく、行くまでの道のり。
物語の舞台は、
満開の桃林を抜けた、その奥に。
これは何を比喩しているのでしょう・・・
作品(この基となる物語には諸説あります)の
なかには、
戦乱の世を逃れてきた人たちが隠れ暮らす村、
外界と隔絶した争いや搾取のない
もうひとつの現実世界(またはそこから転じて、
地上のどこかではなく、誰もが既に知っている
心の奥底に存在している精神世界を指す場合も
ある)がでてきます。
いわゆる、「桃源郷」です。
李白はそこを「仙境」と呼び、
“心の旅”をしながら生涯探し続けました…
「楽園(パラダイス)」ではありません、
「理想郷(ユートピア)」とも少し意味合いが
異なります。
探そうと意識するとかえって見つけられない…
「別天地」とはいっても、そこは、
平らな土地が広がり、家屋が並び、田畑があり、
池があり、桑や竹が生え、路は縦横に通じ、
池があり、桑や竹が生え、路は縦横に通じ、
鶏や犬の声が聞こえる・・・
「何でもないのどかな里山の風景」であり、
「どこにでもある景色」、
「何でもない日常」そのもの。
ただひとつ異なるのは、
そこは、
お年寄りも子どももみな楽しげに暮らす
笑顔の絶えない場所だということ。
それは淵明が求め続けた「人間本来の暮らし」
であり、
「それ以上もそれ以下もない穏やかな日常」
を比喩した世界
であるとも言えるでしょう。
何気ない日常、平穏無事でいられることは、
なにより
「特別なこと」なのかもしれませんね。
いつの世も ・ ・ ・

平安如意
壬寅 三月初
KANAME
訳文一部引用・参考文献
●『桃源の水脈』東アジア詩画の比較文化史
芳賀徹 著 名古屋大学出版会 2019年
●『漢詩を読む①』『詩経』、屈原から陶淵明へ
宇野直人、江原正士 著 平凡社 2010年
●『桃源郷ものがたり』
松居直 著(文) 蔡皋(絵) 福音館書店 2002年
●『陶淵明』ー虚構の詩人ー
一海知義 著 岩波書店 1997年
●『陶淵明とその時代』
石川忠久 著 研文出版 1994年
●『ユートピア』
トマス・モア 著 平井正穂 訳 岩波文庫 1957年
【関連記事】
2022年2月24日 投稿
2022年1月1日 投稿
2021年12月21日 投稿
2021年9月28日 投稿
2021年9月22日 投稿
2021年9月9日 投稿
2021年8月22日 投稿
2021年5月1日 投稿
2021年3月2日 投稿
2021年1月14日 投稿