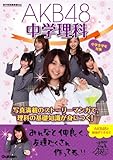先日公開した僕のブログ記事で、
「新学習指導要領が実施されても
地域の公立中学校は数年前から移行措置対応しているので
問題ないだろう」
という見解を述べさせていただいたのですが、
少し訂正します。
改めてこの新指導要領についてとらえ直すと、
僕ら塾講師も、もっと意識する必要があるなと思いました。
さて、中学校の新学習指導要領で、
理科の教育現場はどう変わるのか?
分かりやすく特集しているビデオが、
ScienceNewsで特集されているのでご紹介します。
▼
要するに中学校の理科では、
●これまでの知識詰め込み教育よりも、
サイエンスに対して積極的に取り組み、とらえ、アウトプットする思考をはぐくむ
●これまでよりも深い内容/広い範囲のサイエンスを扱う
この2つの方向転換が起こるだろうと思います。
おそらく、
この転換に対して 中学校の理科授業では
キャッチアップしきれない生徒が増えるんじゃないかと思います。
これまでですら、
「学校の理科がサッパリわからない」と言って塾に来る子供が大勢います。
そういった子供には、僕の講義で
学校の授業でやった内容も
ほとんどゼロから解説しています。
過去の「塾」が担っていた役割は、
テストの点を伸ばすための「お勉強」を担当する割合が大きかったですが、
今後は、より
「学校教育でキャッチアップしきれなかった部分を補う」
という役割を塾が担う割合が増えていくと思います。
僕ら地域の塾講師は、
より 学校教育の現状を理解して、
バックアップする意識を持っていく姿勢が
今後も求められると考えています。
「猿の惑星 ジェネシス」という映画が、
日本では10月7日からロードショーとなりますね。
いま、さかんにテレビでCMやってます。
僕は生物学を専門に学んでいたので
記事のタイトルで「ぶった切る」と書いてますが、
実際この手のSFは大好きです。(笑)
ただ、
「進化」という言葉の意味を、
色々とまぎらわしい感じで勘違いして理解している人が、
多いなと思ったので 解説します。
■この猿は「進化」したのか?
この映画の主役の「一匹の猿」は、
アルツハイマーの治療の研究の副産物として生まれた天才猿。
…というストーリーだと思います。
あらすじ↓
猿の惑星:創世記(ジェネシス) - goo 映画
映画の予告編で「進化は彼らを選んだ」と言ってますが、
「はたしてこれは進化と呼ぶのか?」
という問題です。
■結論:
猿の惑星の場合
①ふつうの猿がいた。
②いきなり知能の高い猿が生まれた。
↑ここまでは「進化」ではなく「変異」と呼びます。
③知能の高い猿が生存競争に勝ち、世の中のスタンダードになった。
↑ここでやっと「進化」と呼べます。
「???
進化と変異の違いって何?」
これを理解するために、
キリンさんの進化の例で話します。
■キリンさんは、どうやって首が長くなったのか?
いまだに子供の話を聞くと、
「キリンさんは、だんだん首が長くなった」
と思っている子が 意外に多いです。
(その方がロマンのある話なんですが…)
生物の「進化」のしくみについて、
いま現在 生物学の教科書に載っているメジャーな考え方(ダーウィンの進化論ベース)的にいうと、
それは違います。
キリンはだんだんと首が長くなったのではなく、
たまたま首が長く生まれた突然変異のキリンの一族だけが生き残ることが出来た
…というのがダーウィン的な進化論です。
(非常に現実的で、ロマンの無い話ですが)
わかりやすくストーリーにします。
■キリンさんの進化ストーリー
①ある地域で 環境の変動が起こり、
背の高い木ばかりが生えるようになってしまいました。
②首の短いキリンさんは、葉っぱに届かないので、餌が食べられません。
③たまたま、生まれつき首が長く生まれたキリンさん達が生き残りやすくなりました。
④長い年月が経ち…
その地域では、首が長く生まれたキリンさんの一族が生き残って繁栄し、
首の短いキリンさんは滅んでしまいました。
そして首の長い遺伝子が、後のキリンに受け継がれるようになりました。
こうしてキリンは首の長い生物種に進化します。
(自然選択説)
■進化と変異の違い
上のキリンさんの場合、
①首の短いふつうのキリンがいた。
②中には、首の長い「変わり者」のキリンもいた。
↑「変異」 (または突然変異)
③環境の変動があって、首の長いキリンの方が生き残りやすくなった
④首の長いキリンだけが生き残り、世の中のスタンダードになった
↑「進化」
■猿の惑星の場合
①ふつうの猿がいた。
②新薬で 知能の高い猿が生まれた。
↑ここまでは「変異」と呼びます
③知能の高い猿が生存競争に勝ち、世の中のスタンダードになった。
↑ここでやっと「進化」と呼びます
■ポケモンの「進化」という言葉は完全な間違いである
ポケモンは、ある生物が生きている間に、
いきなり変化します。
生物学的にいうと、
この変化は、まったく進化とは呼べない代物です。
イモムシがサナギになるような変化と同じで、
「変態」とか「形態変化」呼びます。
さすがに「ポケモンが変態する」とかいうと格好悪いので
あえて「進化」と呼ぶ事にしたのかもしれないですが。
もしかして
多くの子供達が「進化」の意味を勘違いしている原因として、
この「ポケモン」で使われている
紛らわしい「進化」という言葉の使い方が
一つあるかもしれないです。
(キリンさんがある日突然、首が長くなったとか…)
■最後に
結局、ぶった切ったのは猿の惑星ではなくて
ポケモンをぶった切ってしまったんですが、
色んな所で 学問的な言葉は勘違いされて使われています。
(言葉の解釈は常に変化していくので良いと思うんですが)
進化という分野は、すごく奥が深くて面白いです。
SF映画を見るときにも、深く考えをめぐらせる思考の材料になります。

日本では10月7日からロードショーとなりますね。
いま、さかんにテレビでCMやってます。
僕は生物学を専門に学んでいたので
記事のタイトルで「ぶった切る」と書いてますが、
実際この手のSFは大好きです。(笑)
ただ、
「進化」という言葉の意味を、
色々とまぎらわしい感じで勘違いして理解している人が、
多いなと思ったので 解説します。
■この猿は「進化」したのか?
この映画の主役の「一匹の猿」は、
アルツハイマーの治療の研究の副産物として生まれた天才猿。
…というストーリーだと思います。
あらすじ↓
猿の惑星:創世記(ジェネシス) - goo 映画
映画の予告編で「進化は彼らを選んだ」と言ってますが、
「はたしてこれは進化と呼ぶのか?」
という問題です。
■結論:
猿の惑星の場合
①ふつうの猿がいた。
②いきなり知能の高い猿が生まれた。
↑ここまでは「進化」ではなく「変異」と呼びます。
③知能の高い猿が生存競争に勝ち、世の中のスタンダードになった。
↑ここでやっと「進化」と呼べます。
「???
進化と変異の違いって何?」
これを理解するために、
キリンさんの進化の例で話します。
■キリンさんは、どうやって首が長くなったのか?
いまだに子供の話を聞くと、
「キリンさんは、だんだん首が長くなった」
と思っている子が 意外に多いです。
(その方がロマンのある話なんですが…)
生物の「進化」のしくみについて、
いま現在 生物学の教科書に載っているメジャーな考え方(ダーウィンの進化論ベース)的にいうと、
それは違います。
キリンはだんだんと首が長くなったのではなく、
たまたま首が長く生まれた突然変異のキリンの一族だけが生き残ることが出来た
…というのがダーウィン的な進化論です。
(非常に現実的で、ロマンの無い話ですが)
わかりやすくストーリーにします。
■キリンさんの進化ストーリー
①ある地域で 環境の変動が起こり、
背の高い木ばかりが生えるようになってしまいました。
②首の短いキリンさんは、葉っぱに届かないので、餌が食べられません。
③たまたま、生まれつき首が長く生まれたキリンさん達が生き残りやすくなりました。
④長い年月が経ち…
その地域では、首が長く生まれたキリンさんの一族が生き残って繁栄し、
首の短いキリンさんは滅んでしまいました。
そして首の長い遺伝子が、後のキリンに受け継がれるようになりました。
こうしてキリンは首の長い生物種に進化します。
(自然選択説)
■進化と変異の違い
上のキリンさんの場合、
①首の短いふつうのキリンがいた。
②中には、首の長い「変わり者」のキリンもいた。
↑「変異」 (または突然変異)
③環境の変動があって、首の長いキリンの方が生き残りやすくなった
④首の長いキリンだけが生き残り、世の中のスタンダードになった
↑「進化」
■猿の惑星の場合
①ふつうの猿がいた。
②新薬で 知能の高い猿が生まれた。
↑ここまでは「変異」と呼びます
③知能の高い猿が生存競争に勝ち、世の中のスタンダードになった。
↑ここでやっと「進化」と呼びます
■ポケモンの「進化」という言葉は完全な間違いである
ポケモンは、ある生物が生きている間に、
いきなり変化します。
生物学的にいうと、
この変化は、まったく進化とは呼べない代物です。
イモムシがサナギになるような変化と同じで、
「変態」とか「形態変化」呼びます。
さすがに「ポケモンが変態する」とかいうと格好悪いので
あえて「進化」と呼ぶ事にしたのかもしれないですが。
もしかして
多くの子供達が「進化」の意味を勘違いしている原因として、
この「ポケモン」で使われている
紛らわしい「進化」という言葉の使い方が
一つあるかもしれないです。
(キリンさんがある日突然、首が長くなったとか…)
■最後に
結局、ぶった切ったのは猿の惑星ではなくて
ポケモンをぶった切ってしまったんですが、
色んな所で 学問的な言葉は勘違いされて使われています。
(言葉の解釈は常に変化していくので良いと思うんですが)
進化という分野は、すごく奥が深くて面白いです。
SF映画を見るときにも、深く考えをめぐらせる思考の材料になります。

こんにちは。淳chです。
もしかしたら、
「教育をナメんな!」と 怒る人もいるかもしれません(笑)
僕はAKBファンというほどではありませんが、
「どんなに参考にならなそうな参考書からも、
参考になる所を見つけ出す」
という信条で、解説していきます。
■最大の障害
中学生に理科を教える場合、
もっとも大きな障害になってくるのは
「みんな、理科に興味が持てない」
ということです。
・身近に感じられない
・実用性が感じられない
・教師の説明がわかりにくい
・学ぶメリットが感じられない
中学生にとって、理科に興味がわかない理由は山ほどあります。
そんな中、彼ら・彼女らに、
ユーモアをもって興味を誘いつつ、世の中と理科を結びつけ、
科学がいかに人々に貢献しているかを伝えながら
成績上の結果を出させていく
…という命題を、
講師は 常に抱えているわけです。
■書店でビビる
前置きはここまでにして・・・
今日も 何かの手がかりやヒントを求めて、
有隣堂書店の参考書コーナーに出向いてみました。
なんか参考書コーナーが大変なことになってる…!
AKBだらけじゃないっすか
■中身は普通の参考書以下だけど
理科、立ち読み。 とりあえずAKBメンバーの写真を組み合わせて、
漫画風に 薄~く理科を解説したという内容です。
参考書としての機能性でいうと、
「あらためて買うほどのものではない」
と思いました。
■参考になる点
たとえば
「光の性質」などについての解説。
最初にAKBの子が
「そういえば、舞台で浴びるスポットライトってまぶしいよね」
↓
「じゃぁ、光の性質を勉強してみよう!」
みたいな流れ(笑)。
一見ばかばかしいですが、ここにはヒントが隠されています。
■興味を持ってもらわなければ何も始まらない
たとえば単純に、
「光って何だろう?」と漠然と問いかけるよりも、
「AKBの浴びるスポットライトの照度は何ルクス?」
と問いかけた方が、
最初のとっかかりとして、光の話題に入っていきやすい。
そうでなければ、いきなり「光」という、
漠然とした壮大で非日常的な話題から、無理矢理ねじ込んでいかなければならない。
テーマは何でも良いんですが、
まず最初に、相手が興味を持ってくれるための切り口が必要です。
たとえば僕だったら、
・元素の話をする時には マンガ「鋼の錬金術師」の話から入る。
・進化論の話をする時には「ポケモン」の話から入る。
と、ネタを決めています。
しかもそれは、
僕にとって興味が持てる話ではなく、
受け手(中学生)にとって興味の持てる話でなければいけない。
たとえば中学生相手に
「レアメタルが世界経済に与える影響」
と言っても、全く中学生には響かない可能性が高いです。
そういう面では、
AKBという受け入れられ易いキーワードを、
切り口として賢く使っていくのも ひとつの手段です。
(もちろん、そこから先は、しっかりと科学的な説明をしなければ話になりません)
■結論
・この参考書は買わない(笑)
・しかし、「受け入れられやすい切り口を探す」という視点については同意。
「教育をナメんな!」と 怒る人もいるかもしれません(笑)
「どんなに参考にならなそうな参考書からも、
参考になる所を見つけ出す」
という信条で、解説していきます。
中学生に理科を教える場合、
もっとも大きな障害になってくるのは
「みんな、理科に興味が持てない」
ということです。
・実用性が感じられない
・教師の説明がわかりにくい
・学ぶメリットが感じられない
ユーモアをもって興味を誘いつつ、世の中と理科を結びつけ、
科学がいかに人々に貢献しているかを伝えながら
成績上の結果を出させていく
講師は 常に抱えているわけです。
■書店でビビる
前置きはここまでにして・・・
有隣堂書店の参考書コーナーに出向いてみました。
なんか参考書コーナーが大変なことになってる…!
AKBだらけじゃないっすか
理科、立ち読み。 とりあえずAKBメンバーの写真を組み合わせて、
漫画風に 薄~く理科を解説したという内容です。
「あらためて買うほどのものではない」
と思いました。
「光の性質」などについての解説。
「そういえば、舞台で浴びるスポットライトってまぶしいよね」
↓
「じゃぁ、光の性質を勉強してみよう!」
■興味を持ってもらわなければ何も始まらない
「光って何だろう?」と漠然と問いかけるよりも、
「AKBの浴びるスポットライトの照度は何ルクス?」
と問いかけた方が、
最初のとっかかりとして、光の話題に入っていきやすい。
漠然とした壮大で非日常的な話題から、無理矢理ねじ込んでいかなければならない。
まず最初に、相手が興味を持ってくれるための切り口が必要です。
・元素の話をする時には マンガ「鋼の錬金術師」の話から入る。
・進化論の話をする時には「ポケモン」の話から入る。
と、ネタを決めています。
僕にとって興味が持てる話ではなく、
受け手(中学生)にとって興味の持てる話でなければいけない。
「レアメタルが世界経済に与える影響」
と言っても、全く中学生には響かない可能性が高いです。
AKBという受け入れられ易いキーワードを、
切り口として賢く使っていくのも ひとつの手段です。
・この参考書は買わない(笑)
・しかし、「受け入れられやすい切り口を探す」という視点については同意。