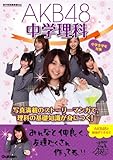「教育をナメんな!」と 怒る人もいるかもしれません(笑)
「どんなに参考にならなそうな参考書からも、
参考になる所を見つけ出す」
という信条で、解説していきます。
中学生に理科を教える場合、
もっとも大きな障害になってくるのは
「みんな、理科に興味が持てない」
ということです。
・実用性が感じられない
・教師の説明がわかりにくい
・学ぶメリットが感じられない
ユーモアをもって興味を誘いつつ、世の中と理科を結びつけ、
科学がいかに人々に貢献しているかを伝えながら
成績上の結果を出させていく
講師は 常に抱えているわけです。
■書店でビビる
前置きはここまでにして・・・
有隣堂書店の参考書コーナーに出向いてみました。
なんか参考書コーナーが大変なことになってる…!
AKBだらけじゃないっすか
理科、立ち読み。 とりあえずAKBメンバーの写真を組み合わせて、
漫画風に 薄~く理科を解説したという内容です。
「あらためて買うほどのものではない」
と思いました。
「光の性質」などについての解説。
「そういえば、舞台で浴びるスポットライトってまぶしいよね」
↓
「じゃぁ、光の性質を勉強してみよう!」
■興味を持ってもらわなければ何も始まらない
「光って何だろう?」と漠然と問いかけるよりも、
「AKBの浴びるスポットライトの照度は何ルクス?」
と問いかけた方が、
最初のとっかかりとして、光の話題に入っていきやすい。
漠然とした壮大で非日常的な話題から、無理矢理ねじ込んでいかなければならない。
まず最初に、相手が興味を持ってくれるための切り口が必要です。
・元素の話をする時には マンガ「鋼の錬金術師」の話から入る。
・進化論の話をする時には「ポケモン」の話から入る。
と、ネタを決めています。
僕にとって興味が持てる話ではなく、
受け手(中学生)にとって興味の持てる話でなければいけない。
「レアメタルが世界経済に与える影響」
と言っても、全く中学生には響かない可能性が高いです。
AKBという受け入れられ易いキーワードを、
切り口として賢く使っていくのも ひとつの手段です。
・この参考書は買わない(笑)
・しかし、「受け入れられやすい切り口を探す」という視点については同意。