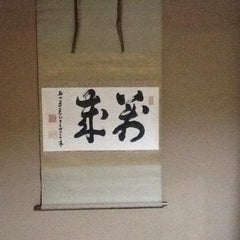昨日の朝は、亥の子餅で、濃茶を一服しました。
いつも甘納豆程度の駄菓子で一服するのですが、炉開きの月ではあり、たまには贅沢をと、ちゃんとした主菓子で一服した次第。それにしても昨日は寒かった。冷たい雨が降りしきり、この間までの夏日が嘘のよう。十分に秋を感じない前に冬が来たとどなたもお思いでしょう。十一月というと、顔を出す亥の子餅、元々は中国の民間の俗信だったようで、旧暦十月の最初の亥の日に、餅を食べれば、健康長寿を保てるということから始まったようです。我が国では、平安時代から宮中行事となり、餅が進献される日として、その内に誰かユーモアのある人が考案したのか、餅を猪の形にしたらしい。これが武家社会や民間にも広まって、江戸時代には定着した行事となった。薄茶色、小豆色、黄茶色などで、体形だけのもの、耳や牙らしいものがチョコっと描かれているものと、多少は種類があるようですが、基本「あ、亥の子餅」とまとまった印象になっている菓子です。ものの本によれば、武家においては、この十月最初の亥の日に、炉開きをする習慣があり、餅の日と重なるので、自然、茶の湯の菓子に亥の子餅を用いるようになった、炉開き月の菓子といえばこれとなったのだというのですね。ところで、今や暦の上では、干支いの習慣が残っているのは、年だけで、これだけは今でも、「卯年生まれです」とか「来年は辰年だ」とか、市民権を得ていますが、月日の干支は絶滅状態です。昔の旧暦は曜日がありませんから、「月曜と金曜に出勤」なんて言わずに「寅の日と申の日に登城」「毎月の午の日が稽古日」というふうに、大切な暦日だったわけです。ところで、今年の旧暦による十月一日、炉開きの月の始まりはいつだったのか、今、旧暦を併記してあるカレンダーはほとんどありませんが、調べてみたら、十一月十三日、今週の月曜がそうだったのですね。更に、最初の亥の日はいつだったかと調べてみたら、なんと、今年は旧暦十月一日がズバリ乙亥の日でした。しかも十月は癸亥の月という、亥の月と最初の亥の日と一日が重なるという特別な年だったのですね。太陽暦に慣れた我々は、気もつかずなんの感動もなかったわけです。
炉開きの頃の茶の湯の菓子で代表的なものは、他には織部饅頭と、銀杏餅でしょう。銀杏餅は手間や原料などの関係か、最近は昔ほど顔を見せなくなったような気もしますが、皮に緑色がちょっぴりついた織部饅頭は、相変わらず、普通の和菓子屋(めっきり減りましたが)でも店先に並ぶようです。中の餡は、粒餡、漉し餡様々ですが、裏千家では、紅餡を用いる決まりだそうですが、家元に遠い巷の茶家の我が家では、紅餡の織部饅頭は賞味した覚えはないようです。それにしても、炉開きの月には、織部関係の道具を何か用いるという慣習、あるいは都市伝説は、何故、いつ頃から行われているのでしょう?手っ取り早いので、菓子で表現するという茶家も多いようですが。
萍亭主