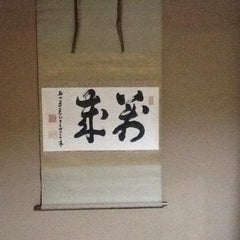茶筅の素材は竹ですが、種類は、ほとんど淡竹(はちく)が使われ、紫竹、黒竹というのも使われるそうです。
伐ったあと、煮沸して油を抜き、天日干しにしたあと、長い間寝かせてから作るそうで、これが白竹茶筅です。白竹をよく燻したものが煤竹で、これが茶黒色の煤竹茶筅。このどちらを使うかは、流儀によります。大所で言えば、白竹は裏千家、藪内流、遠州流、江戸千家、大日本茶道学会、石州流などで、煤竹は表千家、宗徧流不審庵などで使われ、武者小路千家は、紫竹が本来だそうです。一体、何時ごろから、こういうふうになったのでしょう?よくある、流儀の成立と差別化による現象でしょうが、一体、それは何時ごろから始まったものやら、大体、同じ千家で、これだけ分かれた理由と時代を知りたいものです。表千家系である江戸千家が、何故、表千家と違う茶筅を使うのか、これから類推すると、案外近代の決まりのような気もしますが。大昔、紹鴎、利休の時代は、どの茶筅が主流だったのか、疑問は尽きませんが、まあ広い世の中、きっと誰か研究している若手茶の湯学者がいて、いずれ、教えてくれるかも知れません。
話は違いますが、煤竹は、最近、いいものが手に入りにくいと、竹芸家の先生から聞いたことがあります。昔は、農家などをはじめ、囲炉裏生活で、その煙で燻された天井、屋根裏などの良い風合いの竹材が、補修、建替えなどで、ふんだんに出たものが、近年はめっきり減ったというのですね。これらは、茶杓、花入、籠などの素材になるもので、茶筅の素材は、多分、昔からもっと人工的に作られたのだろうと思いますが、それにしても、白竹よりは、もう一手間かかるだけに、価格も白竹より高めのようで、表千家の人は、裏千家より出費が嵩むのでは、と余計なことを考えます。裏千家も、貴人清次という点前の時だけ、お供の茶碗用に煤竹茶筅を使うのですが、たまに買い替えるたびに、妻が「高い」と、ぼやいていたように記憶します。少数派の紫竹を使う武者小路千家は、普通の茶道具店では販売しておらず、家元の道場で手に入れると聞いたことがあります。煤竹でも、小形で華奢なる感じの宗徧流不審庵の茶筅も、普通の店では手に入らず、流儀出入りの店のルートを使うとか、少数派は、やはりご苦労があるようです。少数派と言えば、文献には、正月にのみ使うとして、青竹茶筅というのがありますが、私は使ったこともなく、使われた席に入ったこともありません。実際には、ヘナヘナして点て難いものと聞いた覚えはあります。かがりの糸を赤にした祝い(還暦や古希の)の席に使うという茶筅は、見たことがあります。裏千家では、これを玄々斎好みと称するようです。柄に節が中にあるのと上にあるのと、全くないのと、というふうな違いもあるようですが、正直、気にしたことがありませんでした。点茶道具は、何でも代用品でやれますが、茶筅だけは代用が効かない大切な品なのに、今まで、あんまり真剣に考えたこともないのは、恥ずかしい事ではあります。
明日はブログを休みます。
萍亭主