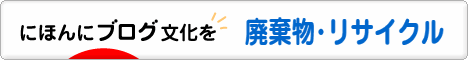小型家電リサイクル法(背景や目的など)【株式会社船井総合研究所:環境&廃棄物コンサルタントコラム】東新一
小型家電リサイクル法(背景や目的など)
数回前のコラムから『資源有効利用促進法』の流れをくむ、個別物品の特性に応じた規制の背景や目的などをご紹介してきました。今回は『小型家電リサイクル法』、正式名称は『使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律』です。この法令は容器包装リサイクル法(1995年制定)、家電リサイクル法(1998年制定)、建設リサイクル法(2000年制定)、食品リサイクル法(2001年制定)、自動車リサイクル法(2002年制定)の後、小型家電リサイクル法として2012年に制定され、2013年に施行されました。
<小型家電リサイクル法>
小型家電リサイクル法とは、パソコンや携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機器等の使用済小型電子機器等の再資源化を促進するため、主務大臣による基本方針の策定及び再資源化事業計画の認定、当該認定を受けた再資源化事業計画に従って行う事業についての廃棄物処理業の許可等に関する特例等について定めた法律です。
なお、小型家電リサイクル法の目的は第一条には次のように示されています。
『この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする』
第一条に記載されている『、、、金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況、、、』とは具体的に何か?以下にて、小型家電リサイクル法の制定の背景と共にご紹介します。
①まず、国民の生活の利便性や豊かさの向上、そして技術革新/発展などにより1990年代からパソコンや携帯電話、デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーやゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速に普及してきました。
②普及が進む使用済小型家電製品の中には、有用金属(レアメタル・レアアース)が多く含まれており、都市鉱山とも言われるようになりました。
③急速な普及は大量生産につながり、また、ブームや競争激化などによる機種更新頻度は増え、結果、大量廃棄されるようになりました。
④廃棄物として市町村が処理する使用済小型電子機器等からは十分な資源回収が出来ない状況で、当時リサイクルが積極的に進められていた「大型家電、自動車、パソコン、蓄電池、コピー機」等の再資源化率は7~9割と高水準であったが、それら以外のものは、鉄やアルミニウムなど一部の金属を除き、殆どが埋立処分されていました。
⑤つまり、小型家庭用電子機器に含まれる希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適正処理、及び違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止など解決するために制定されたのです。
続いて、小型家電リサイクル法の基本方針の概要(①促進の基本的方向、②量に関する目標)と各主体責務、回収量実績(環境省:中央環境審議会)をご紹介します。
①促進の基本的方向
・広域的かつ効率的な回収により、採算性を確保しつつ再資源化することが可能であり、関係者が工夫しながらそれぞれの実情に合わせリサイクルを実施。
・消費者や国、地方公共団体、リサイクル事業者など関係者の適切な役割分担の下それぞれが積極的に参加することが必要。
なお、各主体に以下のような責務などがあります。
〇製造業者(メーカー)の責務:設計/部品/原材料の工夫により再資源化費用低減、再資源化により得られた物の利用
〇小売業者の責務:消費者の適正な排出を確保するために協力
〇国の責務:必要な資金の確保、情報収集/研究開発推進、教育/広報活動
〇消費者の責務:分別して排出
〇市町村の責務:分別して収集、認定事業者その他再資源化を適正に実施し得る者に引渡し
〇排出事業者の責務:分別して排出、認定事業者その他再資源化を適正に実施し得る者に引渡し
②量に関する目標
・市町村又は認定事業者等により回収され再資源化を実施する量の目標(2015年度までに14万t/年、1人当たり1㎏/年)(収率約20%)
以下のグラフは環境省中央環境審議会出典によるもので、年々回収量は増加しているものの、14万tの回収目標には至っていない状況がわかります。
続いて、小型家電リサイクル法の対象品目の概要と具体的な品目をご紹介します。概要は『一般的な消費者が通常生活の用に供する電子機器及びその他の電気機械器具のうち、効率的な収集運搬が可能であり、且つ再資源化が特に必要なものとして、政令において指定されたもの。「家電リサイクル法」の対象となる家電4品目を除く、28類型の品目が指定』です。
<小型家電リサイクル法対象の28類型品目>
・電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
・携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(家電リサイクル法対象を除く。)
・デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用機械器具
・デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
・パソコン(パソコンリサイクル法の適用対象)
・磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
・プリンターその他の印刷装置
・ディスプレイ(パソコンリサイクル法の適用対象)その他表示装置
・電子書籍端末
・電動ミシン
・電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
・電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
・ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
・電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
・フィルムカメラ
・ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(家電リサイクル法対象の冷蔵庫/冷凍庫などを除く)
・扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(家電リサイクル法対象のエアコンなどを除く)
・電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(家電リサイクル法対象の洗濯機/衣類乾燥機などを除く)
・電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
・ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
・電気マッサージ器
・ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
・電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
・蛍光灯器具その他の電気照明器具
・電子時計及び電気時計
・電子楽器及び電気楽器
・ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
なお、上記の附属品(ACアダプターや充電器など)も含むとされています。また、上記のように家電製品全般にわたるように法律上では指定されてますが、小型家電リサイクル法の対象品目は各自治体が独自に決定しており、必ずしも全種類の製品が対象となるわけではないという面もあります。
最後に、小型家電リサイクルの現状課題と目指すべき方向は以下のとおりです。
<現状課題>
・制度開始以降、参加市町村・協力小売店・小型家電の回収量及び再資源化量は年々増加しており、一定の成果は得られていますが、制度設定時に目標としていました回収量(14万t/年)は未達です
・産業廃棄物処理料金の増加、金属価格の変動等状況変化がある中、金属回収量増加、効率化を図っていく必要がある
・制度設定当初に想定していなかった、リチウムイオン電池による発火のおそれなどに対応する必要がある。
<目指すべき方向>
・有用資源の回収/最終処分量の削減/有害物質の管理のため、出来るだけ多くの小型家電を回収し、多くの有用金属などが回収されることを目指す。
・そのためには、各主体による意識向上と回収量増加、認定事業者の効率的なリサイクル推進、新たな課題への対応を進めていく。
以上、小型家電リサイクル法の目的や背景などでした。以下の品目は制度設定時には無かった品ですが、ごみ収集車輛の発火や処分場での発火問題などを考慮しますと、このような品目対応も早急に解決していきたいですね
・加熱式たばこ ・ワイヤレスイヤホン ・プリンター ・食洗器(ブルトイン式) ・オーブンレンジ(ビルトイン式) ・電動ゆりかご ・井戸水ポンプ など
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
☆容器包装リサイクル法(背景や目的など)
☆家電リサイクル法(背景や目的など)
☆建設リサイクル法(背景や目的など)
☆食品リサイクル法(背景や目的など、そして、食品ロス)
☆自動車リサイクル法(背景や目的など)
☆【無料経営相談:お問合せ先】