トニー・レオンと周迅が主演、イー・トンシンが監督だったので、映画「大魔術師」を観ました。
主演の二人、いまだ男盛り&女盛り。

映画の印象は「タンタン」の大人版といったところで、子供が見ても楽しめる内容。現に子供が結構観に来ていて、みんな笑っていました。その割には130分と長編なのですが…。
『大魔術師』ポスター。

一番感銘を受けたのは、戦前(1920年代後半?)の北京の街の描き方。といっても俯瞰的に描かれるのではなく、庶民の娯楽文化にスポットを当てています。
戦前の北京と言えば、『シュリーマン旅行記』で酷評されていたり、老舎『茶館』での悲劇に終わるストーリーなど、あまりいい印象が残っていなかったのですが、もし実際の北京が『大魔術師』に描かれている都市だったならば、タイムスリップして行きたくなりました。
この映画で描かれた北京が本物に近いものであれ、遠いものであれ、もし現在の中国が中国文明の復興を求めるならば、この映画のような世界を目指すのが妥当だなと思わせました。
『つきせぬ想い』(1993)で香港に根付く大衆民芸を活写したイー・トンシン監督ですが、ここでもそのスピリッツが息づいているようです。
つきせぬ想い【字幕版】 [VHS]/アニタ・ユン,ラウ・チンワン,カリーナ・ラウ
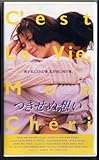
¥3,129
Amazon.co.jp
主演の二人、いまだ男盛り&女盛り。

映画の印象は「タンタン」の大人版といったところで、子供が見ても楽しめる内容。現に子供が結構観に来ていて、みんな笑っていました。その割には130分と長編なのですが…。
『大魔術師』ポスター。

一番感銘を受けたのは、戦前(1920年代後半?)の北京の街の描き方。といっても俯瞰的に描かれるのではなく、庶民の娯楽文化にスポットを当てています。
戦前の北京と言えば、『シュリーマン旅行記』で酷評されていたり、老舎『茶館』での悲劇に終わるストーリーなど、あまりいい印象が残っていなかったのですが、もし実際の北京が『大魔術師』に描かれている都市だったならば、タイムスリップして行きたくなりました。
この映画で描かれた北京が本物に近いものであれ、遠いものであれ、もし現在の中国が中国文明の復興を求めるならば、この映画のような世界を目指すのが妥当だなと思わせました。
『つきせぬ想い』(1993)で香港に根付く大衆民芸を活写したイー・トンシン監督ですが、ここでもそのスピリッツが息づいているようです。
つきせぬ想い【字幕版】 [VHS]/アニタ・ユン,ラウ・チンワン,カリーナ・ラウ
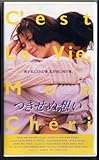
¥3,129
Amazon.co.jp
橋本健二氏による著書『階級都市』(ちくま新書)を読んだのですが、とても面白かったです。
近代以降の東京の下町と山の手の格差について、過去の文士たちがどう描いてきたかを鮮やかにプロットした第三章「異国の風景」を読むだけでも価値があります。
またいくつかの街を実際に歩いてみる第五章「階級都市を歩く」は、常にその町のおすすめ居酒屋を紹介するなど、ややゆるい雰囲気。ちょっと「モヤモヤさま~ず」みたいで面白かったです。
でも一番参考になったのが、サッセンとカステルが主張する都市の「ジェントリフィケーション」が、東京の下町で今まさに起こっているという見解です。
昔町工場だったり、労働者のすみかだったりした場所が、グローバル化で用無しになります。しかし立地的には都市の中心部に近いため、再開発で豪華高層マンションを作れば、エリートたちのすみかに様変わりできます。このような、洗練化したエリアに様変わりすることをジェントリフィケーションといいます。
昔下町だということで金持ちが住みたがらなかったエリアでも、ジェントリフィケーションによって住み出し、山の手っぽい雰囲気になる。そんな状況です。
以前上海の街について勉強していたとき、歴史的背景から蘇州河の北側や旧フランス租界の南側は発展しないと思っていましたが、今やすっかり発展しています。これはジェントリフィケーションという言葉ですっかり説明できるというわけです。
さらにおもしろかったのが、今から140年前の1872年にエンゲルスが同様のことを『住宅問題』という著書で書いていたことでした。以下、孫引き。
現代の大都市の成長は、その若干の地域、とくに都心地域の土地に人為的な価値をあたえ、それはしばしば法外に騰貴していく。この土地の上に建てられている建物は、土地の価値を高めずに、むしろ引き下げる。これらの建物は、変化した状況にもはや適合しなくなったからである。人々はそれを取り壊して、かわりに別の建物を建てる。とりわけ、都心にある労働者住宅について、こういうことが起こる。労働者住宅の家賃は、どんなに人口が過密になっても、けっして一定の最高限をこえて上昇することはできない。あるいは、こえるとしても、ごく緩慢にしかこえることができない。そこで、これらの労働者住宅をとりこわして、そのあとに店舗や商品倉庫や、公共建物を建てるのである。(中略)その結果、労働者階級は都心から郊外におしだされ、労働者住宅や、一般に小住宅は少なくなり、高価になり、しばしばまったくみつからなくなってしまう。なぜなら、こうした事情のもとでは、高価な住宅のほうが投機の場としてずっとうまみがあるので、建築業者が労働者住宅を建てるようなことは、まったくの例外になるのである。
東京のみならず中国の都市でいま起こっていることを、こんな昔にきちんと説明していたとは、まったくの驚きでした。
階級都市: 格差が街を侵食する (ちくま新書)/橋本 健二

¥882
Amazon.co.jp
近代以降の東京の下町と山の手の格差について、過去の文士たちがどう描いてきたかを鮮やかにプロットした第三章「異国の風景」を読むだけでも価値があります。
またいくつかの街を実際に歩いてみる第五章「階級都市を歩く」は、常にその町のおすすめ居酒屋を紹介するなど、ややゆるい雰囲気。ちょっと「モヤモヤさま~ず」みたいで面白かったです。
でも一番参考になったのが、サッセンとカステルが主張する都市の「ジェントリフィケーション」が、東京の下町で今まさに起こっているという見解です。
昔町工場だったり、労働者のすみかだったりした場所が、グローバル化で用無しになります。しかし立地的には都市の中心部に近いため、再開発で豪華高層マンションを作れば、エリートたちのすみかに様変わりできます。このような、洗練化したエリアに様変わりすることをジェントリフィケーションといいます。
昔下町だということで金持ちが住みたがらなかったエリアでも、ジェントリフィケーションによって住み出し、山の手っぽい雰囲気になる。そんな状況です。
以前上海の街について勉強していたとき、歴史的背景から蘇州河の北側や旧フランス租界の南側は発展しないと思っていましたが、今やすっかり発展しています。これはジェントリフィケーションという言葉ですっかり説明できるというわけです。
さらにおもしろかったのが、今から140年前の1872年にエンゲルスが同様のことを『住宅問題』という著書で書いていたことでした。以下、孫引き。
現代の大都市の成長は、その若干の地域、とくに都心地域の土地に人為的な価値をあたえ、それはしばしば法外に騰貴していく。この土地の上に建てられている建物は、土地の価値を高めずに、むしろ引き下げる。これらの建物は、変化した状況にもはや適合しなくなったからである。人々はそれを取り壊して、かわりに別の建物を建てる。とりわけ、都心にある労働者住宅について、こういうことが起こる。労働者住宅の家賃は、どんなに人口が過密になっても、けっして一定の最高限をこえて上昇することはできない。あるいは、こえるとしても、ごく緩慢にしかこえることができない。そこで、これらの労働者住宅をとりこわして、そのあとに店舗や商品倉庫や、公共建物を建てるのである。(中略)その結果、労働者階級は都心から郊外におしだされ、労働者住宅や、一般に小住宅は少なくなり、高価になり、しばしばまったくみつからなくなってしまう。なぜなら、こうした事情のもとでは、高価な住宅のほうが投機の場としてずっとうまみがあるので、建築業者が労働者住宅を建てるようなことは、まったくの例外になるのである。
東京のみならず中国の都市でいま起こっていることを、こんな昔にきちんと説明していたとは、まったくの驚きでした。
階級都市: 格差が街を侵食する (ちくま新書)/橋本 健二

¥882
Amazon.co.jp
先週、上海に3泊しました。
最初の2泊は、
River View On The Bundというホテルに泊まりました。
ここを選んだ理由は、5星級ホテルなのに安かったから。
たしか5千円くらいかな?
また、外灘の夜景がきれいそうだったからです。
River View On The Bundの客室

たしかに客室も広いし、ハード面は良いのですが、サービスがハードに追いついていない印象でした。
夜に到着したのですが、フロントの人がいかにもめんどくさそうな態度。
その時点でこのホテルに対する不安感が高まりました。
実際、多くを期待してはいけないホテルでした。
残りの1泊は、
上海嘉廷虹梅ホテルに泊まりました。
ここを選んだ理由は、翌朝に虹橋空港へ行く必要があったことと、安かったからです。
たしか4千円弱かと思います。
上海嘉廷虹梅ホテルの客室

午前中にチェックインしたので「大丈夫ですか?」と問うと、フロントの人が笑顔で「全然問題ないですよ」と言ってくれて、とても安心感が持てました。
こちらは客室が狭いのですが、浴室にはちゃんと猫足のバスタブがあり、デスクも狭いながらも使いやすいなど、意外に心地よい空間です。
デスクにあったホテルの説明書を見ると、「枕に関して問題があればフロントに電話してください」とありました。柔らかい枕、硬い枕など数種類取り揃えているのでしょう。
このとき、よいホテルとは「客に安心感を与えるホテル」なんだと思いました。
「何か問題が起きても、相談すればきっと解決してくれるだろう」
顧客にそう思わせるホテルこそ、よいホテルなのではないでしょうか。
最初の2泊は、
River View On The Bundというホテルに泊まりました。
ここを選んだ理由は、5星級ホテルなのに安かったから。
たしか5千円くらいかな?
また、外灘の夜景がきれいそうだったからです。
River View On The Bundの客室

たしかに客室も広いし、ハード面は良いのですが、サービスがハードに追いついていない印象でした。
夜に到着したのですが、フロントの人がいかにもめんどくさそうな態度。
その時点でこのホテルに対する不安感が高まりました。
実際、多くを期待してはいけないホテルでした。
残りの1泊は、
上海嘉廷虹梅ホテルに泊まりました。
ここを選んだ理由は、翌朝に虹橋空港へ行く必要があったことと、安かったからです。
たしか4千円弱かと思います。
上海嘉廷虹梅ホテルの客室

午前中にチェックインしたので「大丈夫ですか?」と問うと、フロントの人が笑顔で「全然問題ないですよ」と言ってくれて、とても安心感が持てました。
こちらは客室が狭いのですが、浴室にはちゃんと猫足のバスタブがあり、デスクも狭いながらも使いやすいなど、意外に心地よい空間です。
デスクにあったホテルの説明書を見ると、「枕に関して問題があればフロントに電話してください」とありました。柔らかい枕、硬い枕など数種類取り揃えているのでしょう。
このとき、よいホテルとは「客に安心感を与えるホテル」なんだと思いました。
「何か問題が起きても、相談すればきっと解決してくれるだろう」
顧客にそう思わせるホテルこそ、よいホテルなのではないでしょうか。


