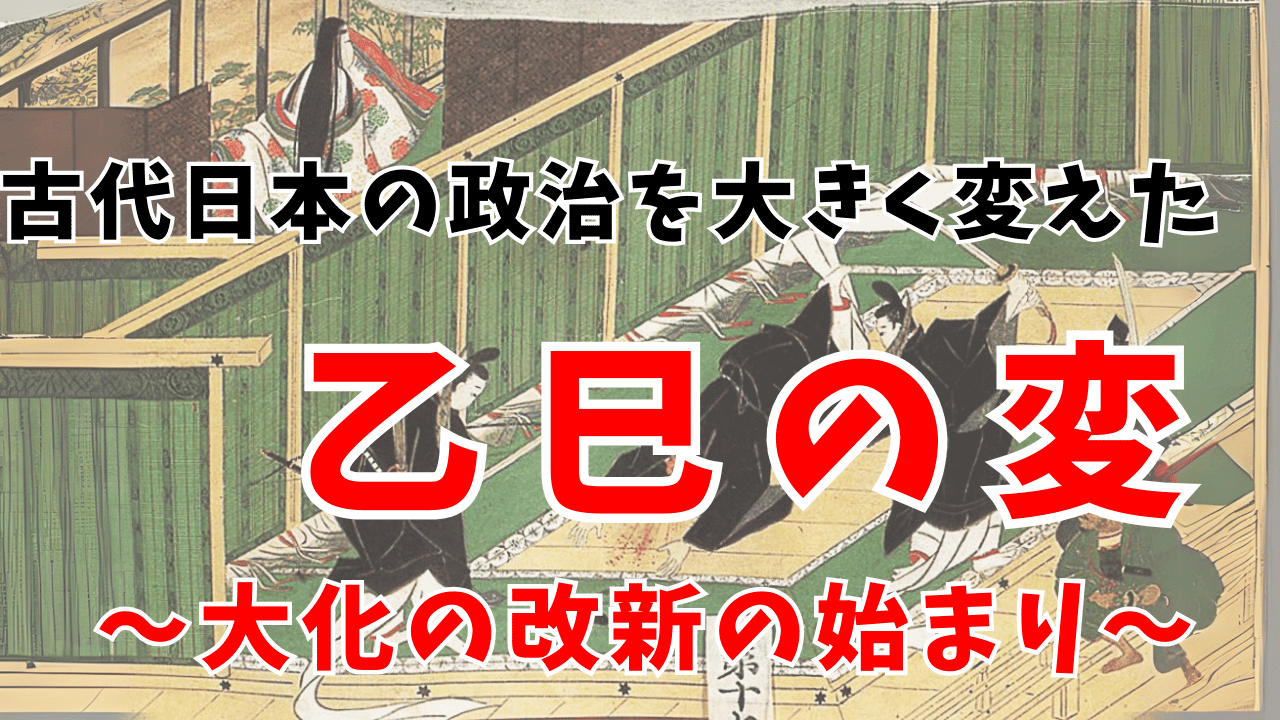半径5メートル、向う三軒両隣りに限って言えば、まあまあ、穏やかに明けた令和7年。このまま“世は事もなし”を願いたいところですけれども、そうは首相(と市長)が許さない・・・
遅ればせながら、明けましてお目出度うございます。
我が家から車で10分程、浜名湖の、その向こうの遠州灘(太平洋)に昇る太陽。
初日の出です。
●祈、再生
さて、今年の干支は乙巳(きのとみ)。
2025年、令和7年は「巳年(みどし)」にあたります。干支は古代中国から伝わるもので、十干(じっかん)と十二支(じゅうにし)を組み合わせた60通りの年号を形成しています。来年の干支は「乙巳(きのとみ)」と呼ばれ、特に再生や変化を象徴する年とされています。
なのだそうです。
再生と変化は表裏一体。
望む者があれば、抗う者もいるでしょう。
遥か昔、と言っても、きちんと記録が残り、その記録を今でも読める、のが我が国のすごいところなのですが・・・
それはともかく「乙巳の変」と呼ばれる出来事がありました。
乙巳の変は、長年にわたって政治の実権を握っていた蘇我入鹿・蝦夷 を、皇族の中大兄皇子が暗殺したクーデター事件のことを言います。飛鳥時代の645年に起こりました。
飛鳥時代の日本は、大国の隋 (618年以降は唐)を参考にしながら天皇中心の国家を目指しているところでした。そんな中起きた乙巳の変は、豪族の蘇我氏から政治の実権を奪い取り、日本が天皇中心の国へと変貌するきっかけとなった歴史的にも重要な事件でした。
●願・変化
グローバリスト・・・
「多様性」を謳いながらその一方で「分断」を嘆くの体で世界を均一化、モノや情報が売れやすい環境を求めている。
「統合」を謳いつつ返す刀で「境界」を拒み「国」や「家」を破壊、人間の弱さ⎯⎯孤独や嫉妬や羨望⎯⎯に付け込んでその支配を目論む。
・・・の存在は、余程鈍感でない限り、認めざるを得ないでしょう。
特定の個人、集団、組織を思い描くかどうかは別としても。
乙巳の変のような歴史的事件を、単なる権力闘争に矮小化してしまう「学者」や「知識人」も多くいて、何やら情けなくなってしまう昨今。
そういう個人的動機が無かったとは言わないけれど、同時に、そこに至る危機感やその先の展望も、間違いなく在ったはずで。
翌年646年、改新の詔と呼ばれる朝廷の改革方針が示されました。
改新の詔の内容は、簡単に言えば「公地公民制を目指す!」というものでした。
公地公民制というのは、「日本の土地・民は天皇のもの」という制度のことです。
公地公民制により天皇に強大な権力を与え、豪族たちの協力による成立していた国家体制を終わらせよう・・・と考えたのでした。
この一連の改革のことを歴史用語で大化の改新と言います。
蘇我氏の台頭により停滞していた「唐を参考にした天皇中心の国造り」は、乙巳の変により大きく前進することとなりました。
大化の改新を経て、飛鳥時代末期の天武天皇の時代(673年〜686年)になると、ついに日本は天皇中心の国へと変貌を遂げることになります。
●化けるか、消えるか
石破氏の頭ン中に、日本国首相として「やりたいこと」が本当に在るのか無いのか。
氏の変幻自在過ぎる言動からして、ぶっちゃけ皆無だろうと思われるのだけれども。
逆に、ヒシヒシと伝わってくるのは「一日でも長く、首相でいたい、そのためになら悪魔(≒立憲民主党とか、れいわ新選組とか、日本共産党とか)とだって手を組むよ」という邪な願望だけ。
おっと、新年早々、悪口が過ぎました。
ひょっとして「立場が人を創る」ということも無いではないし、曲がりなりにも我が国の・・・いや、やっぱり、心にもないキレイゴトは止しましょう。
気になるのは、石破氏にとって師と呼べる人が、かつて、いたのかいなかったのか、今、いるのかいないのか、といった辺り。
●「かのように」
南淵請安は、渡来系氏族の学問僧。推古天皇16年(608年)、遣隋使・小野妹子に従い、8人の学問僧の1人として派遣された。隋から唐へと時代が移り変わるなか、儒学など大陸の先進の学問を学び、32年の歳月を経て、舒明天皇12年(640年)に帰国。
『日本書紀』によると、帰国後、「周孔の学」(儒教)を教えていた請安のもとに、法興寺の槻の木の下で近づいた中大兄皇子と中臣鎌足が、ともに書物を持って通ったと記されている。二人はその道中、蘇我氏打倒の計画をひそかに練り、その考えはことごとく一致したとある。
645年の「乙巳の変」の後、請安とともに隋・唐へ留学していた高向玄理(たかむこのくろまろ)や僧・旻(みん)は新政権にて国博士(政治顧問としての官名)となるが、請安が関わった形跡はなく、その直前に没したという説もある。
寛文2年(1662年)建立の南淵請安の墓は、明日香村稲渕の高台にひっそりとたたずむ。
明日死ぬかのように生きろ。永遠に生きるかのように学べ。
“インド独立の父”、マハトマ・ガンジーが言ったとか。
年頭ですし、今年の抱負のようなものとして、心に留め置いておきます。
(暴力を伴うような)「クーデター」を望んでいるわけではないけれど・・・
政策の良し悪しとは別の力学で誕生した日本国首相もさることながら・・・
「保守」分断、漁夫の利で当選した長坂氏(現豊橋市長)も、ぶっちゃけ、まあ、困ったお人です。年末年始を挟んでも、滾る想い冷めやらず・・・
以下、お時間あれば、お付き合いください。
中日新聞も長坂氏も、「嘘は(一応)ついてないよ。隠していることはあるけどね」の世界で生きています。東海テレビ、CBC、中京テレビなんかも、概ね同じです。決して、それだけをそのまま信じたりしないように。
世の中、いわゆる体制べったりの“御用学者”がたまにいます。同じように、マスメディアにとって便利な“迎合学者”もちょくちょくいるもので。
「地方自治法の趣旨に即していない可能性もある。分からない点が多く、法的精査が必要」⎯⎯例の条例改正案が可決したことを受け、長坂氏はそう宣った由。「理屈と膏薬はどこへでもつく」とか言いますが、さて・・・