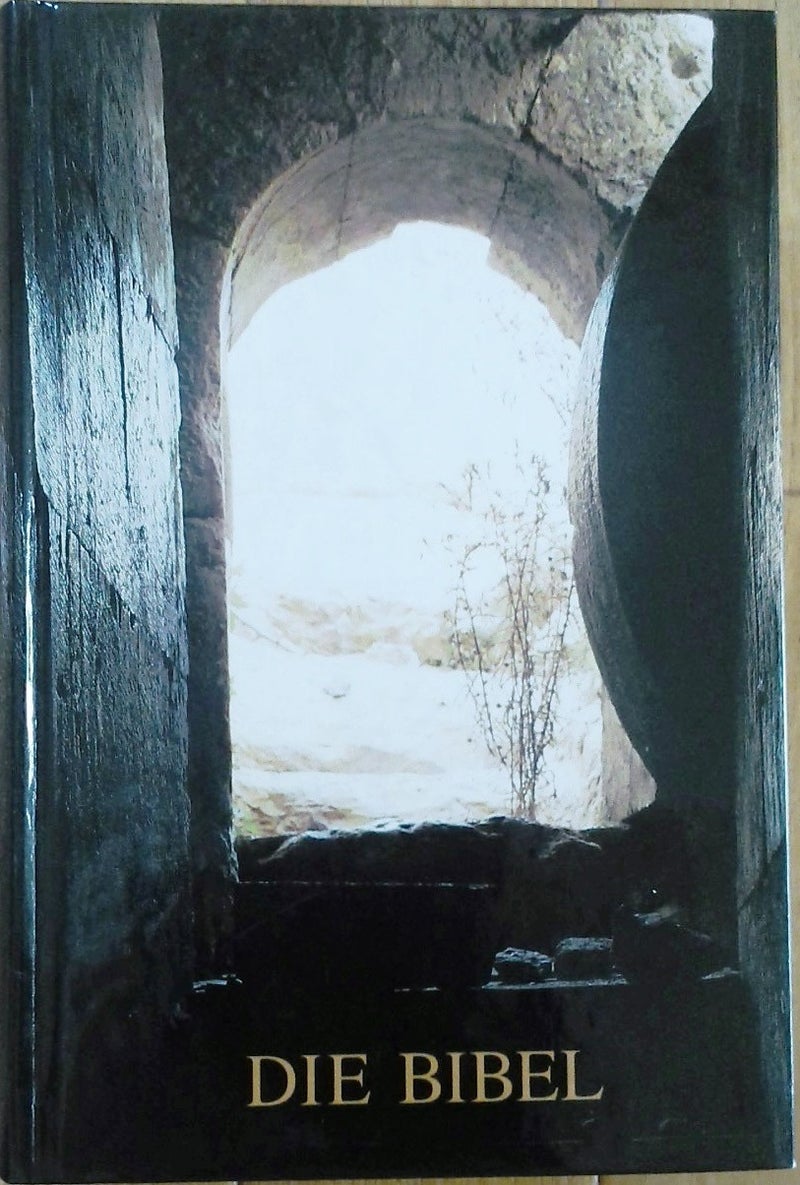マタイ福音書の2章後半。
イエス・キリストの出身地が、
ガリラヤ地方のナザレになった経緯が書かれています。
幼子イエスを殺そうとするヘロデ王から逃れるため、
父ヨセフ、母マリアは、イエスを抱えてエジプトで難民生活をし、
ヘロデ王の死後、再びイスラエルに戻る。
2章の最後はこう締められてます。
そこで、ヨセフは起きて、
幼子とその母を連れて、イスラエルの地へ帰って来た。
しかし、アルケラオが父ヘロデの跡を継いで
ユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。
ところが、夢でお告げがあったので、
ガリラヤ地方に引きこもり、
ナザレという町に行って住んだ。
「彼はナザレの人と呼ばれる」と、
預言者たちを通して言われていたことが実現するためであった。
――新約聖書 『マタイによる福音書』 2章21-23節
アラビア語聖書では、
「ナザレ」という地名は「ناصرة ナースィラ」。
「勝利」という意味です。
だから、預言者たちがメシアについて言った
「ナザレの人」は、「勝利の人」って意味になりますね。
私は聖書辞典の類はもっていませんから、
原語のヘブライ語でも、
「ナザレ= 勝利」かどうかは存じませんが……
少なくとも、アラビア語聖書の読者には、
新約聖書の序盤で、
イエスが「ナザレ人/勝利者」であることが分かります。
その方が、聖書を読み進める上では都合がいいと思います。
聖書がいう「勝利」は、この世の生存競争に勝つとかじゃなくて、
「死を滅ぼす勝利」、「命の勝利」のことだから。
イエスが十字架刑で死に、3日目に復活する。
「罪の結果である死」を、イエスが引き受けてくれたことで、
私たちすべての人は、復活の主イエスの命を生きられる。
福音書序盤で「ナザレ/勝利」のイエスと意識しておけば、
終盤の十字架刑~イエス復活の流れが、
よりスムーズに受けとりやすくなると思いました。
アラビア語聖書の翻訳者は、
わざわざ町の名前を「ナースィラ/勝利」と括弧でくくってます。
しかも文末にはびっくりマーク!をつけてる。
聖書読者に、「勝利」という地名を意識してほしいのでしょうね。
(※ アラビア語は右から左に読む)
ナザレ = 勝利
これを前提に、新約聖書を読むと、
なるほどと納得できる箇所が増えておもしろいです。
たとえば、マルコ福音書1章。
イエスに追い出された悪霊のセリフに注目。
そのとき、この会堂に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。
「ナザレのイエス、かまわないでくれ。
我々を滅ぼしに来たのか。
正体は分かっている。
神の聖者だ。」
イエスが、「黙れ。この人から出て行け」とお叱りになると、
汚れた霊はその人にけいれんを起こさせ、大声をあげて出て行った。
――新約聖書 『マルコによる福音書』 1章23-26節
雑魚レベルの悪霊ですら、
イエス・キリストの正体をよく知ってるんだなあと、
いつ読んでも感心してしまいます。
「ナザレのイエス、かまわないでくれ。」
悪霊は、イエスの出身地の話をしてるんじゃない。
イエスが「勝利のイエス」だと言ってるんですね。
イエスは神の聖者にして、勝利のイエスだから、
悪霊はイエスに滅ぼされるしかない。
イエスが十字架刑になった際、
ローマ総督ポンテオ・ピラトは、
十字架にこんな銘板を付けさせましたね。
「ナザレのイエス ユダヤ人の王」
ポンテオ・ピラトは、ユダヤ宗教エリートへのあてつけとして、
そういう銘板をつけたつもりでしょうが。
結果として、「イエスは十字架刑の死に勝利するユダヤ人の王」
という預言板になってしまいました。
(関連記事)
『使徒言行録/使徒行伝』の3章、ペテロの言葉も、
「ナザレ = 勝利」と読めば、合点がいきます。
イエスの直弟子だったペテロとヨハネが、
足の不自由な物乞いにかけた言葉です。
ペトロは言った。
「わたしには金や銀はないが、
持っているものをあげよう。
ナザレの人イエス・キリストの名によって
立ち上がり、歩きなさい。」
そして、右手を取って彼を立ち上がらせた。
すると、たちまち、その男は足やくるぶしがしっかりして、
躍り上がって立ち、歩きだした。
そして、歩き回ったり躍ったりして神を賛美し、
二人と一緒に境内に入って行った。
――新約聖書 『使徒言行録』 3章6-8節
私はいつもペテロの言葉にひっかかってました。
どうしてイエス・キリストに、
「ナザレの人」という出身地名をつけるのかなって。
イエスという男性名がけっこうありふれてるから、
他のイエスさんと混同しないために、
「ナザレ村出身のイエス」と言ってるのかな?
と思ってました。
しかし、「ナザレ = 勝利」ならば。
「勝利の人イエス・キリストの名によって
立ち上がり、歩きなさい。」
ああ、それならスッキリわかる。
すべての人の罪をひきうけ、
死に勝利したイエス・キリストの名で命じるからこそ、
足が不自由な人を癒せたわけですね。
この当時は、イエスの復活・昇天から、
まだそんなに月日が経ってない時期でした。
だから「イエス・キリスト」というだけでなく、
「ナザレの人/勝利の人」という説明も添えたのかなと思いました。
とにかく、聖書に「ナザレのイエス」と出てきたら、
単に出身地の話をしてると思わず、
「勝利の人」という意味も加味して読むのがお勧めです☆
キリスト教会の、毎週日曜日の礼拝と、
春のイースター/復活祭は、
復活の主イエス・キリストを記念していますね。
死に勝利したイエスです。
今年は4月4日ですね。
異端・カルトと呼ばれる宗教は、
イエスの復活を認めないか、
イエスはたしかに復活したけどまだ不完全などと言うようです。
たとえばエホバの証人は、
イエスの死と復活は認めるが、
イースターを祝うのは認めないと公言してます。
理由は、イースターの元は異教の春分祭りだから……らしい。
イースターの趣旨を勘違いしてるから、
そういう発想になるんですよね。
クリスマスもイースターも、
イエス・キリストと私たちの絆を深めるための祝祭です。
× 日付を記念する
◎ 出来事を記念する
日付はどうでもいいのです。
クリスマスは、イエスの誕生日に注目するんじゃなくて、
イエスが人間の世界に来て、私たちと出会ったという事実に注目する。
イースターは、イエスが復活した日付に注目するんじゃなくて、
イエスが死から復活して今生きておられる事実に注目する。
イエス・キリストを生ける神と信じて従う者には、
毎日がクリスマスで、毎日がイースターです。
毎日イエスと出会い、毎日イエスの命をいただいているから。
ただ、キリストを信じる者どうしがあつまって、
合同でクリスマスやイースターなどを記念したい場合は、
参加者にわかりやすい日付を設定しておくのが便利です。
クリスマスは冬至の後。
イースターは春分の後。
普段の礼拝は日曜日。
節目としてわかりやすいし便利だから、それでいいと思います。
永遠の命であるイエス・キリストを前に、
祝祭の日付を論じるのは無意味ですね。
復活の主イエス・キリストは、
昨日も、今日も、永遠に変わらず、
私たちと共にいてくださる、命の主です。
イエスにまつわる日付ではなく、
ナザレ/勝利のイエスご本人を見つめて、
今日も明日も歩んでいきたいですね。
***************************
※このブログのコメントは承認制です。
ブログチェックのタイミングにより、
コメントの反映・返信が2,3日後になる場合もあります。
***************************
■ ルーン魔女KAZのホームページ/著書一覧は こちら
■ 無料WEBコミック雑誌てんてる …… KAZの著書の版元さんが運営しています☆
![]()