さぁ~
第二部の始まりですよぉ~ ヽ(^◇^*)/
高価なカメラとお手軽な価格の
カメラの性能差は無いのかって言うと
はっきり言って
ほとんどありません (`・ω・´)
じゃぁ
価格の違いは何なのかって言うと
機能の違いです α(・_・)
基本性能以外の機能と言うことなんですけど
例えば
高速連写(秒間10コマ以上)・高速AF・全画面AFポイント・超々高感度センサー・
超高性能本体内手ブレ補正・超高画質センサーなんて言うのがありますね
高速連写は秒間3~5コマあれば充分で
それ以上になると画像データをメモリーに書き込む速度が追いつかなくて
本体メモリーにバッファするため
息をつき始めるんですね
つまり
はじめは『カシャッカシャッカシャッ』と連写していますけど
徐々に『カッシャン、カッシャン、カシャ・・・ カシャ』ってなってきます (;^_^A
高速AFもそうで
時速300km/hで疾走するF1の写真とかでなければオーバースペックです
全画面AFポイントなんかも
便利と言えば便利なんですけど・・・
弊害もあるんですね (;^_^A
AFポイントって言うのは
オートフォーカスのピントを合わせる点になりますけど
一般には中央に合わせたり、広いエリアに合わせるようにしたりなんですけど
中央に合わせる点を
全画面の任意の位置に設定できる機能ですね
第三部でお話ししますけど
”三分割法” と言う構図の取り方があるんですけど
被写体が画面の中央にない場合に
任意の位置にフォーカスポイントを動かすことができる機能です
最近のデジイチはタッチパネルになっているものが多いんですけど
うっかりタッチパネルに触れたり
触れないまでも接近しすぎてポイントがどこに移動したか
わからなくなっちゃう事もあるんですね (;^_^A
例えで書いた機能が不要とは言いませんけど
高速連写や高速AFなんて
飛んでいる鳥を撮りたいとかレースシーンを撮したい
なんて言う方には必要になってきますし
超々高感度センサーや超高画質センサーなんて言うのは
星景写真とかを撮したい人に必要になってくる機能で
必要ない方が持っても
より大容量で高速書き込みできるメモリーが必要ですし
編集するPCも高性能なものが必要になりますし
データの保存には大容量なHDDや読み書きの速いSSDが必要になってきますから
カメラ以外の機材の出費も多くなっちゃうんですね (´・ω・`)
第一部を読んでいただいた方は
カメラの差はほとんどないと思い始めてきたんじゃないかと思います
実際に同じカメラ(α6000)でレンズを替えて
比較写真を撮ってみましたけど
そろそろ
重箱の隅をつついてみましょうか (;´∀`)
α6000 + TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD(α7S-Ⅱで使ったレンズ)

とっても画質の良かった
α7S-Ⅱの組み合わせに使ったレンズですけど
カメラがα6000になっても
良い写りですよね
フルサイズ対応ですので
ワイ端の28mmで写しています
α6000 + SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM(α77-Ⅱで使ったレンズ)

α77-Ⅱで使ったレンズですけど
拡大すると高倍率ゆえの甘さが出ていますね (;^_^A
ワイ端ではなく画角を合わせるため
28mmにズームしていますよ
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSS(元々のα6000のレンズ)

元々α6000で使っていたキットレンズですけど
ん~
やっぱりあなどれないですね (;´∀`)
今度はパープルフリンジの出やすそうな
上部の木の枝を拡大してみましょうか
α6000 + TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD(α7S-Ⅱで使ったレンズ)

α7S-Ⅱの組み合わせに使ったレンズで、若干のパープルフリンジが出ていますけど
忍城の木の葉と同様で
なんとなく見える程度で
拡大しなければほぼわかりませんね
α6000 + SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM(α77-Ⅱで使ったレンズ)

α77-Ⅱで使ったレンズで
やはりパープルフリンジが出ているのがわかりますね (;^_^A
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSS(元々のα6000のレンズ)

元々のα6000で使っていたレンズですけど
描写が甘い感はありますけど
パープルフリンジはほとんど見られませんね
画像の右端に
細い木の枝が写っていましたので拡大してみましょうか
α6000 + TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD(α7S-Ⅱで使ったレンズ)

α7S-Ⅱで使ったレンズですけど
駅構内に貼られている大きなサイズのポスターから
ハガキ大の一部分を見ている感じですよ
手持ちの一眼で
もっとも チープな お手軽価格なα6000でこの写りですから・・・
ものすごく詳細な画質で
これは神レンズの粋と言えるんじゃないですかね ヽ((◎д◎ ))ゝ
α6000 + SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM(α77-Ⅱで使ったレンズ)

α77-Ⅱで使った高倍率ズームレンズですけど・・・
うん、画面の端は特に画質が落ちる部分ですから
まぁ~
こんなもんでしょうかね (;^_^A
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSS(元々のα6000のレンズ)

元々のα6000で使っていたレンズとの組み合わせですけど
いやぁ~
もっともチープな組み合わせでこれですよ
実力はなかなかのもので
あなどれないレンズと言ったわけがわかっていただけましたかね α(・_・)
第一部の最初の忍城の
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSSでの比較写真を
A4くらいにサイズダウンして
1/4の部分がこのくらいですから

カメラの差はほとんどない
と、言うことがわかっていただけましたかね
決して極端な言い方ではないと思っていますけど
初心者の方が
初めてデジタル一眼を選ぶなら
数値などほとんど考えずに
デザインと価格で決めても
まったく問題ないと思っています
レンズに関しても
そのカメラのズームセット(またはダブルズームセット)で
充分と思います
むしろ
気に入ったデザインで手軽なサイズと言うのが重要で
価格も
気にしないで気楽に持ち歩けることが重要と思います
デザイン重視と言うわけではないんですけど
例えば
仔犬や仔猫を飼うとして
ブサイクで愛想のない仔を
飼いますか?
親バカになって
ブチャいけど可愛いとか
いつも一緒に居たいとか
そんな魅力がなければ
求めませんよね
全く同じ機能と性能なら
絶対的に気に入ったデザインを使うでしょう?
そして、最初の段階で楽しさが見つからなければ
続きませんし
カメラの楽しさって色々あって
私の場合は、テーマ: ”花鳥風月” を書いたりしてる通りで
自然や季節を切り取るのが楽しいんですね
私はあまりやらないのですけど
トリッキーな写真なんて言うのも面白いものですよ
ズームレンズさえあれば
こんな写真も写せます

これは以前ご紹介しました
”露光間ズーム” と言うテクニックで写したんですね
カメラ 絞りとシャッター速度とISO感度 2017-05-20 (別窓で開きます)
飯能市にある ”トーベ・ヤンソン あけぼの子どもの森公園” で
別のトリッキーな写真を撮ろうとして
うまくいかなかったので
茶を濁すために写してきた写真で
写真の ”きのこの家” と言う建物を
露光間ズームで巨大化しているように写して
きのこの家は
実は、森のきのこが巨大化したもの・・・
なんてことにしたんですね
ところが
トリッキーな写真ってもっと簡単で
ちょっとした工夫や
発想をちょっと変えるだけで面白いのもができるんですよね
例えば
この写真

えぇぇぇぇ~ ∑ヾ( ̄0 ̄;ノ
って、思っちゃいますけど
こうやって写した写真なんですね

他にも
こんな写真も

実は、こうやって道路で寝転がって写しているんですね
あ! 普通に歩いている人の足も写ってます ( ̄ー ̄;

この写真も凝ってますよ

この写真も
やっぱりこうやって・・・
角度が絶妙で
ただ横にしただけじゃないんですね ヾ(≧▽≦) ノ

さて、ちょっと数値的なお話しもしましょうか
デジタル一眼カメラの撮像素子(画素、ピクセル)数は
1,200万画素から5,000万画素がほとんど
中には100,200万画素
なんて言うとんでもないモデルもありますけど
これはフルサイズより大きなセンサーを搭載している
”中判サイズ” と呼ばれるものですので別扱いですね (;^_^A
現在、主流になっているセンサーは
マイクロフォーサーズ、APS-C、フルサイズになりますけど
センサーの大きさは
こんな感じで違うんですね

これだけ面積の違うセンサーに
1,200万個から5,000万個もの撮像素子が並んでいるわけですから
撮像素子の大きさや密度が違ってきます
一時期は画素数の多さを競っていた感がありますけど
実際には撮像素子の大きさが重要なんですね α(・_・)
どう言う事かって言うと・・・
撮像素子が多い(画素数が高い)って言うことは
たしかに解像度は高くなります
ところが、
撮像素子が多いって言うことは撮像素子自体は小さくなるんですね
このため、画素数が多くなると
”暗所性能” が落ちると言われます (;^_^A ちとムズい
分かりやすい例では
レースのカーテンとカーテンの違いですかね
レースのカーテンは糸が細く隙間が大きいので
部屋の中に光がたくさん入るので明るいですよね
カーテンの場合は編み目がぎっしりと詰まっていて
隙間がほとんどありませんから光を通しにくくなっていますね
この編み目の隙間の数が
撮像素子の数、画素数と考えると理解できますかね
編み目の隙間の数が
10cm四方に1,000個あるのが1,000万画素とすれば
10cm四方に5,000個あるのが5,000万画素で
どちらが明るいでしょうかね (;^_^A
撮像素子の多い高画質カメラは
どう言う使い方に向いているかって言うと
かわいいお子さんの写真を
ビルの屋上にある大型看板サイズにして家の外に飾りたい
なんて言う場合には
画素数が多いカメラが絶対に必要になりますね ( ̄ー ̄; そんな奴いるか?
まぁ~
実際には
夜空を望遠レンズで写して
天の川の雲のように見える部分を拡大すると
ひとつひとつの光の粒が天体で在ることがわかりますし
お隣の銀河系のアンドロメダ銀河の渦巻も確認できます
こう言った写真を写したい場合には
高画質なカメラが必要になってきますね
しかし
カメラってものすごく複雑なもので
どれかを伸ばすと
必ずマイナス面が出てくるんですね
一概に画素数が多ければ良い
って言うわけにはいかないんですね
一般的には
センサーサイズはマイクロフォーサーズ、APS-C、フルサイズのいずれでも
1,000万画素あれば
充分にキレイな写真が撮れます
σ(・_・) 3台あるデジイチでもっともこだわったのが
α7S-Ⅱなんですけど
暗所に強いカメラが欲しくて選んだんですね
α7S-Ⅱが発売されてしばらくして
PENTAXからものすごい高感度なカメラが発売されたんです
”PENTAX KP” って言いますけど
APS-Cセンサーで画素数は2,496万画素ですからα77-Ⅱやα6000と同等
しかしISO感度がすごいんです
ISO100~819,200
α7S-Ⅱがフルサイズで1,240万画素で
半分近いですけど、センサーの面積も違いますから
単位面積を同じにすると画素は1/5程度の低画質になりますね
ISO感度は
常用ISO100~102,400
(拡張ISO50~80、128,000~409,600)ですから
なんと
最大ISO感度が819,200対409,600ですから倍ですね
ところが
高画質超高感度なKPと低画質高感度なα7S-Ⅱの比較撮影では
KPの方が画質が悪かったので
α7S-Ⅱに決めたんですね (;^_^A マウントもSONYで統一できるし
なんでこうなったのかって言うと
SONYではセンサーの感度をよくした上で
画素数をあえて落として
高感度のセンサーを贅沢に使おう
と言う狙いのスペックとのことなんですね
ISO感度は
フィルムでは数値が大きくなると粒子の大きさが大きくなるんです
ISO100よりもISO400では4倍明るく写るんですね
なので、拡大すると
粒子が見えてきてしまうんですね
わかりやすい例では
最近は、信号機もLEDのものが増えましたけど
それ以前は直径25cmか30cmのランプなんですね
100m離れてみると
LEDでもひとつのランプの信号に見えますけど
50mまで近づくと
なんか粒粒っぽく見えてきますね (;^_^A 目が良いとね
さらに25mまで近づくと
粒粒らしく見えますね
10mくらい(25mの半分の12.5m)になると
完全に粒粒が見えます
これがISO100とすれば
倍のISO200では100mで粒粒っぽく見え、50mで粒粒らしく見えますね
25m完全に粒粒が見えてしまうんです
逆に半分のISO50なら
25mまで近づいてやっと粒粒っぽく見え、10mくらいで粒粒らしく見えて来るわけです
これが粒子の大きさと言うことですけど
デジカメのISOは
フィルムのISOに相当する明るさなんですね
デジカメのISOは光を受けた信号を増幅しているんです
かんたんに言えば
スマフォのスピーカーで音楽を聞いていると
音質が良い位だと音が小さくて聞きにくいですよね
ボリュームを上げると
聞き取りやすいですけど、音が割れて音質が下がってきます
これは音楽の信号を
増幅して大きな電流にしてスピーカーに送っているからなんですね
そのため、音は大きくなりますけど
質が下がってしまう
これがISO感度を上げると
画質にノイズが出ると言う現象で
フィルムの粒子の粗さと
同じようにとらえる事ができるんですね
カメラを売る側からすれば
数字になりにくい性能は伝えにくいですし
数字で比較できると言うことは売り込みやすいんですね
それで
画素数やISO感度が売りになってくるわけです α(・_・)
機能の違いと言う面では
オートフォーカスの早さとか
手ブレ補正の性能なんかが
あげられますけど
昔のフィルムカメラと大きな違いは
動画が撮れることなんですね
4K動画が撮れるとか
同じ4K動画でも 8bit か 10bit が可能か
他にも Wi-Fi の性能だとか
GPS機能だとか、防水性能だとか
基本性能とは
あまり関係のない機能だったりします
プロカメラマンの中には
手軽なカメラではなくて
フラッグシップ機こそ
初心者が持つべきカメラだと言う方もいらっしゃいます
私は余計な機能のように言っていますけど
そのプロカメラマンに言わせると
使える武器は多い方が良い
ただし、その武器がどこに有るのかを知る必要がある
と、言うんですね
一理あるので否定する気はありませんけど
私の場合は、気軽に
楽しさを覚えながらステップアップした方が良いと考えているんですね
実際に今回使ったカメラの基本的な性能の違いは
α7S-Ⅱはフルサイズセンサーで1240万画素
α77-Ⅱとα6000はAPS-Cで2470万画素
レンズの画角ではフルサイズとAPS-Cでは
1.5倍(0.67倍)の違いが有るって言いましたけど
面積では、フルサイズ = 24x36mm = 864㎟
APS-C = 23.6×15.6mm = 368.16㎟
なので、864㎟ ÷ 368.16㎟ = 2.36倍
(368.16㎟ ÷ 864㎟ = 0.426倍)になりますから
フルサイズで1240万画素のα7S-Ⅱは
APS-Cサイズなら528万画素になるんですね
で、APS-Cで約2470万画素のα77-Ⅱとα6000は
フルサイズなら5829万画素になりますから
なんと
α7S-Ⅱの4.7倍(0.21倍)の画素数の高画質になるんですね ( ̄□ ̄;)!!
この画素数がどのくらいすごいかって言うと
α7シリーズのベーシックモデルの
α7とα7-Ⅱの総画素数は2470万画素の2.35倍の画素数に相当し
超高画質機のα7R-Ⅱ、Ⅲが
4360万画素ですから1.3倍の画素数に相当しますし
最新の超高画質機のα7R-Ⅳの
6250万画素に迫る高画質って言うことになります ヽ((◎д◎ ))ゝ
最近、SONYから
フルサイズセンサーのコンパクトカメラも発売されましたね
α7-C

α6000系のボディにフルサイズセンサーを
搭載したようなモデルなんですけど ( ̄ー ̄; 若干大きいそうです
センサーサイズが変わると、何が変わるの?
って、言うと
①画角が変わりますね
50mmの標準レンズは
フルサイズでは50mmのままですけど
APS-Cでは1.5倍の75mmの中望遠になりますね
300mmと言う望遠レンズなら
APS-Cでは450mmになりますし
500mmの超望遠なら
なんと750mmになっちゃうんですね ヽ((◎д◎ ))ゝ
言い換えると
フルサイズはワイドに強くてAPS-Cは望遠に強いセンサーと言えます
②ボケる量が変わる。
同じ範囲を撮影する場合は
フルサイズはAPS-Cに比べてボケ量が多くなる
と言う特徴があります
短焦点レンズを使ったポートレート撮影時などは
APS-Cではなくフルサイズをセレクトすることで
より綺麗な玉ボケなどを実現することが可能なんですね o(^▽^)o
③諧調が変わる
諧調って言うのは
いわゆる色のグラデーションのこと
イメージセンサーの大きいフルサイズは
APS-Cに比べて1画素あたりの受光面積が大きいため
白とびや黒つぶれを抑えることが可能です
暗い場所で撮影する方や、撮影後にRAW現像などで
明るさや色味を調整する方であれば、APS-Cよりフルサイズ機が有利なんですね
④暗所性能が変わる
暗所性能って言うのは
暗い場所で撮影する際の性能を指すんですね
フルサイズは、APS-Cに比べてイメージセンサーが大きいため
より多くの光を取り込むことが可能なんですね
その結果、暗い場所でISOを高くして撮影した場合でも
ノイズを抑えた、ディティールの細かい写真を撮影が可能なんですね
⑤カメラの大きさが変わる
デジタルカメラは
センサーサイズの大きさに合わせて設計・製造されています
つまり、フルサイズはイメージセンサーが大きいため
APS-Cに比べてカメラ本体が大きかったり、重かったりする場合が一般的です
⑥使用できるレンズが変わる
APS-Cとフルサイズでは
それぞれ装着できるレンズが異なります
カメラ本体同様、交換レンズもセンサーサイズの大きさに合わせて
設計・製造されているため、APS-C対応レンズより
フルサイズ対応レンズの方が大きく・重くなりがちです
中にはAPS-Cとフルサイズのどちらにも対応したレンズも存在しますが
カメラをAPS-Cからフルサイズに変更したことにより
これまで愛用していたレンズが使えない…
なんて事態が発生しないようにご注意くださいね
で、お手軽なミラーレスをオススメする理由のひとつに
フルサイズ対応のレンズが
まだ少ないのと
出始めなので
少々お高くなってしまいます
なので
お手軽なミラーレスとしては
APS-Cセンサーの方が
価格もお手軽になるとも言えますね
あるいは、SONY のαシリーズならば
Eマウントに力を入れていますから
フルサイズ対応のレンズとAPS-C機を購入しても
後々フルサイズ機に買い替えても
レンズはそのまま使えますし
SONYの古くからのAマウント用レンズを
アダプターで使うのも手で
ミノルタ時代のフィルム機の頃のレンズなら
EF-Sレンズというのも存在しますが、
こちらはAPS-C専用のレンズの区分であって
EFマウントを採用したAPS-Cセンサー搭載モデルには使用することができます。
(フルサイズセンサーモデルには非対応)
さて
最後になりますけど
3機種で夜景を写してみました
自宅近くの埼玉スタジアム2002です
α7S II + TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD(Model A071)

α77 II + SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM

α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSS

細部を比べてみましょうか
α7S-Ⅱ
(F値は2.8、シャッター速度1/4秒、ISO感度は12800)

α77-Ⅱ
(F値は3.5、シャッター速度1/4秒、ISO感度は3200)

α6000
(F値は3.5、シャッター速度1/5秒、ISO感度は3200)

細部を比べるとレンズ差は出ていますけど
このくらいの暗さならカメラの差はほとんど無いと言えますね
こうなると
デザインや価格を中心に選んでも問題ないと言えますね
ネットで比較して使いたいカメラを選べば良いですし
プラスαな機能は ”瞳AI” とかの便利機能で選べば良いでしょうね
価格.comなんて
売れ筋を確認できますし
実際に使った方のレビューなんかも
確認することができますよ
ミラーレス一眼 売れ筋順 / 価格.com (別窓で開きます)
カメラは持ち出して、撮してなんぼのものですから
愛着を持って、気軽に、手軽に使えることが重要かと思いますよ
私自身、今日は○○を撮るぞ!
と、気合を入れた時はα7S-IIやα77-IIを用意しますけど
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSSを
メットインやバッグに入れて動き回ることの方が多いですし
ちょっと散歩、という時に
α6000にオールドレンズを付けて
見つけた被写体に
構図やら何やらを思案して楽しんでいます
こうしてみると
コンパクトで持ち出しやすい事が重要な機能のように思えます
そう考えると
フルサイズセンサーよりも
コンパクトに作られるAPS-Cなんてとても機能的ですし
もっとコンパクトなフォーサーズセンサーのカメラなんて
レンズもコンパクトですから
レンズも数本持ち歩けて
とても魅力的です
さて、第三部の予告になりますけど
先の夜景は、いずれも美しい夜景と思うんですけど
ちょっと設定を変えて
”色温度(しきおんど、色温度)” を変えてみると
もっと夜らしい寒々しさと透き通ったような写真になるんですね
色温度って言うのは
物質が熱を持つと発光するんですねど
真っ赤に焼けた鉄だとか
炭火が赤々と燃えている
って言うのがそれで
赤く光るのは
700℃から1000℃くらいなんですね
日中の太陽光は5,500~6,000度って言われていますけど
これは熱力学温度(絶対温度)で表していますから
単位は ”ケルビン” と言い
記号は ”K” を使い、5,500K~6,000Kとなります
日が昇ってまもなくや夕方近くなると4,000Kくらいに低くなって
少し黄色がかった色になってきますけど
カメラ側で少し黄色い4,000Kを
白く写すように設定すると、黄色がかった光が白く写るんですね
逆に
真夏の海辺など紫外線の影響もあって青みがかった色に写るんですけど
6,000Kとか6,500Kに設定すると
青みが消えて白く写るんですね
言ってみればカラーフィルターとして
使うことができるんですけど
同じ構図で数分後に
α6000 + SONY E18-55mm F3.5-5.6 OSSを4,000Kで撮影してみました

どうです
ぼんやりした暖色系が消え
寒々とした夜らしく
引き締まったでしょう
並べると
こんな感じに違いますよ
(上がフルオート、下がホワイトバランス調整)

このカラーフィルターを逆に
7,000K~8,000Kくらいにすると
朝焼けや夕焼けが
燃えるような赤に写すこともできるんですよね o(^▽^)o
お手軽なミラーレスのα6000でも
基本撮影能力は充分な性能ですけど
ちょっとした設定や構図で
プロっぽい写真が写せるんですね
次回は、そんなテクニックをちょっとご紹介したいと思います
★アメブロのメッセージは停止しています
携帯・スマフォなどからの
メッセージは ↓ こちらをご利用ください

*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*



風評被害をなくしましょう 地震速報
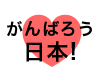 |
 |
*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*
にほんブログ村参加カテゴリー/膵炎、ランキング
にほんブログ村参加カテゴリー/食事制限ダイエット、ランキング
人気ブログランキング参加カテゴリーへ/健康と医療⇒病気・病状⇒肝臓・胆嚢・すい臓
レシピブログのランキングに参加中♪ よろしければクリックしてくださいね♪