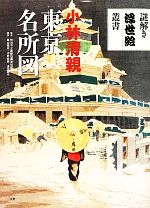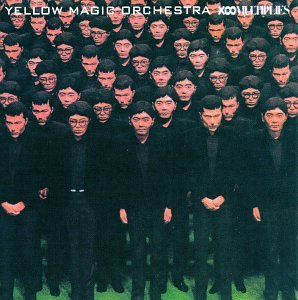生誕100年の芥川也寸志
このところNHKの「らじるらじる」を聴いていると芥川也寸志が頻繁に登場しています。まあ、NHKの「らじるらじる」はリアルタイムで聴くことはなく、いつも聴き逃ししか聞きません。ただ、この聴き逃し週によって配信されるか配信されないか番組みをクリックしないと分かりません。今週はたまたま音楽評論家の片山杜秀氏が、パーソナリティを務めている「クラシックの迷宮」が聴き逃し配信されているではありませんか。普段はリアルタイムで聴くしか方法がないのですが、ラッキーということで聞き入ってしまいました。今年はラヴェルやショスタコーヴィチの記念イヤーですが、この芥川也寸志も生誕100年なんですなぁ。管弦楽曲から合唱曲、映画音楽、さらには学校や団体の効果まで後半な分野に多大なる足跡を残した芥川康ですが、既に亡くなってから36年が経過して忘れられている側面もあるのではないでしょうか。
そんなことで、先週と今週の2週にわたり「クラシックの迷宮」ではこの芥川也寸志が特集されていました。第1集は彼の作曲したオーケストラ作品が取り上げられていましたが、第2集では映画音楽作家としての芥川也寸志にスポットを当てての放送となっていました。この第2回分は7月19日の午後9時まで配信されています。
第1集のプログラムは以下のようになっていました。
「トリプティーク」から第3楽章モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団(管弦楽) 、キリル・コンドラシン(指揮) 作曲: 芥川也寸志(2分53秒) <Altus ALT-020>
「交響三章」から第3楽章東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(6分4秒) <東芝EMI CZ30-9008>
「交響管弦楽のための音楽」から第2楽章東京交響楽団(管弦楽) 、森正(指揮) 作曲: 芥川也寸志(4分41秒) <東芝EMI TOCE-9426>
エルベ河渡辺一利(独唱) 、中央合唱団(合唱) 、センターオーケストラ(演奏) 、井上頼豊(指揮) 作曲: ショスタコーヴィチ(2分48秒) <音楽センター UCD-404>
心さわぐ青春の歌高橋修一(独唱) 、中央合唱団(合唱) 、センターオーケストラ(演奏) 、井上頼豊(指揮) 作詞: オシャーニン作曲: パフムートワ(3分42秒) <音楽センター UCD-404>
カチューシャ中央合唱団(合唱) 、センターオーケストラ(演奏) 、井上頼豊(指揮) 作詞: イサコフスキー作曲: ブランテル(2分10秒) <音楽センター UCD-402>
灯中央合唱団(合唱) 、センターオーケストラ(演奏) 、井上頼豊(指揮) 作詞: イサコフスキー作曲: ロシア民謡(3分58秒) <音楽センター UCD-402>
国民大行進曲「祖国の山河に」中央合唱団(合唱) 、30周年記念レコーディングオーケストラ(演奏) 、守屋博之(指揮) 作詞: 紺谷邦子作曲: 芥川也寸志編曲: 助川敏弥(3分30秒) <音楽センター UCD-402>
交響曲第1番 から 第4楽章東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(8分15秒) <東芝EMI CZ30-9008>
交響曲第1番 から 第2楽章東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(2分58秒) <東芝EMI CZ30-9008>
合唱組曲「砂川」グルーポ・ヴォーカル・デ・トキオ(合唱) 、斎木ユリ(ピアノ) 、栗山文昭(指揮) 作詞: 坂本万里作曲: 芥川也寸志(16分14秒) <「日本の作曲・21世紀へのあゆみ」実行委員会 ECJC-009>
剣の舞今井登茂子(語り手) 、東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: ハチャトゥリヤン(2分50秒) <東京こどもクラブ TKCB-3-1>
歌劇「ヒロシマのオルフェ」から最後の部分黒田博(青年) 、腰越満美(若い娘、のちに看護師) 、吉田伸昭(死の国の運転手、のちに医師) 、オルフェ合唱団(合唱) 、オーケストラ・ニッポニカ(管弦楽) 、本名徹次(指揮) 作曲: 芥川也寸志(5分37秒) <EXTON OVCL-00444>
いゃあ、内容が濃いですねぇ。
そして、この第2回では、
芥川也寸志と映画音楽 〜芥川也寸志生誕100年(2)〜
楽曲一覧
えり子の歌二葉あき子(歌) 、東京放送合唱団(歌) 、シャンブル・ノネット(演奏) 作詞: 野上彰作曲: 芥川也寸志(3分13秒) <コロムビア COCA-13731>
初恋の歌二葉あき子(歌) 、東京放送合唱団(歌) 、シャンブル・ノネット(演奏) 作詞: 野上彰作曲: 芥川也寸志(2分53秒) <コロムビア COCA-13731>
映画音楽「煙突の見える場所」テーマ曲オリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(1分53秒) <SLC SLCS5085>
挽歌越路吹雪(歌) 作詞: 藤浦洸作曲: 芥川也寸志(3分31秒) <コロムビア COCA-14207>
みみずく座の唄若山彰(歌) 、コロムビア合唱団(歌) 作詞: 藤浦洸作曲: 芥川也寸志(3分19秒) <コロムビア COCA-14207>
映画音楽「野火」テーマ曲オリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(1分50秒) <SLC SLCS5085>
映画音楽「ゼロの焦点」からオリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(3分34秒) <SLC SLCS5085>
映画音楽「五瓣の椿」テーマ曲と予告編用音楽オリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(4分53秒) <SLC SLCS5085>
映画音楽「地獄変」東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(11分13秒) <SLC SLCS5085>
映画音楽「影の車」オリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(5分59秒) <SLC SLCS5085>
春には花の下で五堂新太郎(歌) 作詞: 山川啓介作曲: 芥川也寸志編曲: 若草恵(3分50秒) <CINEMA-KAN CINK-78-79>
大いなる旅五堂新太郎(歌) 作詞: 山川啓介作曲: 芥川也寸志編曲: 若草恵(1分40秒) <CINEMA-KAN CINK-78-79>
映画音楽「八甲田山」テーマ曲とエンディング東京交響楽団(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(5分26秒) <CINEMA-KAN CINK-78-79>
映画音楽「八つ墓村」から「メイン・タイトル」「惨劇・32人殺し」「道行のテーマ」「落武者のテーマ」新室内楽協会(管弦楽) 、芥川也寸志(指揮) 作曲: 芥川也寸志(13分) <松竹レコード SOST3017>
映画音楽「鬼畜」メイン・タイトルオリジナル・サウンドトラック 作曲: 芥川也寸志(2分13秒) <松竹レコード SOST3022>
今回は映画音楽ということでの括りでしたが、小生が芥川也寸志を初めて意識したのはNHKの大河ドラマ「赤穂浪士」のテーマでした。その頃は全く意識しませんでしたがミニマル音楽としてのこのテーマは非常に斬新に聴こえました。
それにしても今回の放送で「ゼロの焦点」や「五辯の椿」、さらに「八甲田山」や「八つ墓村」(渥美清主演)の音楽までもが芥川也寸志とは知りませんでした。特に「ゼロの焦点」などはのちのサスペンスドラマの原点となる海辺の崖っぷちで大団円を迎えるという演出の走りとなった作品ということで、アコーディオンを使った斬新なサウンドは中々です。
さてNHKでは時を同じくして、奥田佳道氏が解説を務める「音楽の泉」でも芥川也寸志の「交響三章」が取り上げられています。こちらはNHKラジオ第1とFMで放送されていて、FM放送が一周遅れている関係で聴き逃しは19日の午前5時50分までの配信となっています。取り上げられた演奏は、
交響三章(トリニタ・シンフォニカ)ニュージーランド交響楽団(管弦楽) 、湯浅卓雄(指揮) 作曲: 芥川也寸志(21分26秒) <ナクソス 8.555975J>
交響管弦楽のための音楽東京都交響楽団(管弦楽) 、沼尻竜典(指揮) 作曲: 芥川也寸志(9分36秒) <ナクソス 8.555071J>
ノールショピング交響楽団のためのプレリュードノールショピング交響楽団(管弦楽) 、広上淳一(指揮) 作曲: 外山雄三(9分11秒) <ファンハウス FHCE2020>
ということで、ナクソスの音源が使われています。このナクソスの音源は愛知県図書館の貸し出しカードを登録するともれなく「ナクソス・ミュージックライブラリー」の配信が付いてきます。これはおすすめです。ただし、下に貼り付けたのは芥川自身の指揮する東京交響楽団の演奏です。芥川也寸志の生涯の師となるのは伊福部昭である事はよく知られていますが、この作品でも主題を必要に繰り返す伊福部のミニマム音楽の特徴を聴き取ることができます。
ついでに、この芥川也寸志の生誕100年を記念したコンサートが8月30日にサントリーホールで開かれます。ここでは芥川の「公共管弦楽のための音楽」が演奏されることになってますが、コンサートのタイトルは「第35回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会」となっていて、サントリーホールと芥川也寸志の結びつきの強さを感じさせます。なんとなれば、1986年に開業した時には彼の「オルガンとオーケストラのための響」という作品が初演されています。
芥川也寸志の名言として、よく「音楽はみんなのもの」と言う言葉が挙げられます。これは、
「音楽と言うものは、生活の中に取り入れるものではなく、生活の中から引き出すものであると考えております」(芥川康志「私の音楽、談義」(ちくま文庫)よに記されています。
團伊玖磨、黛敏郎とともに三人の会を結成し、精力的にマスコミにも登場していました。N饗コンサートホールという番組でも、分かりやすい解説をしていたのは懐かしい記憶です。