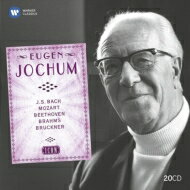ヨッフム/ロンドン響
ベートーヴェン交響曲第7番イ長調Op.92
1. Poco Sostenuto - Vivace 15:05
2. Alllegretto 9:17
3.Presto - Assai Meno Presto 10:47
4. Allegro Con Brio 9:30
指揮/オイゲン・ヨッフム
演奏/ロンドン交響楽団
録音:1977/09/30-10/01 キングスウェイ・ホール
P:クリストファー・ビショップ
E:クリストファー・パーカー
東芝EMI EAC60161
このレコードは実はベートーヴェンの交響曲全集の中の一枚です。この春先に手に入れていたセットですが、ようやく聴くことができました。そして、この写真はボックスのデザインではなく、個々のレコードのインナースリーヴのデザインです。ヨッフムのベートーヴェンの「第7番」の音源はセッション、ライヴを含めて多数存在します。ベルリンPO.(1952年セッション)、フィラデルフィアO.(1966年ライヴ ※EVE-017-S)、コンセルトヘボウO.(1968年セッション)、ロンドンSO.(1977年セッション)、バンベルクSO.(1982年ライヴ)等々でこれ以外にも海賊版もあります。人気なんでしょうなぁ。実はヨッフムの7番はじっくり聴いたことがありませんでした。以前は「田園」ばかり聴いていたからです。
ヨッフムのベートーヴェンはドイツ的な堅牢さと現代的な表現の見事な融合ということができます。ロンドン響の性格もありますが、いわゆるドイツ風の重厚さ素朴さといった部分から離れていて、同じ方向のアプローチでありながら、同時代のケンペ/ミュンヘンフィルの演奏とは大きく印象が異なります。そして、あまり大きくはアピールされていませんが、繰り返しは全て励行しています。ベートーヴェンが書いた音符は全て音にするという姿勢のようです。ただ、楽譜に忠実ということもないようで第四楽章の主題のホルンは、木管楽器と同じ動きに改変しています。道理で他の演奏とイメージが違うと思ったところです。そして、もう一つの大きな違いはこの演奏はCDでも所有していますが、音の印象が全く違うということです。
何故だろうとマトリックス番号を確認すると意外な発見がありました。このヨッフムのの交響曲全集はEMIらしい手抜きをしています。全集のほとんどが4ch用のマスターをそのまま使っているのです。当時は欧米ではこのよっふむのレコードは4ch盤として発売されていました。しかし、日本では4chで発売された記憶はありません。1977年当時は既にピークは過ぎていてほぼ壊滅状態でした。ただ、イギリスは保守的でしたからこの時代でも4ch録音していたのでしょうな。ところがイギリス本国から送られてきたのは4chのマスターだったのでしょう。そんなことで、ほぼ4chマスターでプレスされています。ところがこの7番だけA面とB面でマスターが違うのです。下はその写真です。
ところがB面は国内マスターの2YJ-2714が使われています。こちらのスタンパー番号は1Sです。ちなみに単発で発売されたイギリスの原盤ではQ2EA 6632が使われていて、やはりB面にコリオラン序曲が収録されています。
ヨーロッパでの発売盤にはSQ方式の4chであることが表示されています。さらにこの7番は単品で発売されていた時はコリオラン序曲がカップリングされていましたが、レコードの全集ではこれ1曲のみの収録ということで日本盤マスターが制作された節があります。
さて、このベートーヴェンの交響曲第7番は「のだめ」前と「のだめ」後では曲の扱いが全く違います。当然ヨッフムの録音は「のだめ」以前ですから古いスタイルで演奏されていると考えるのは当然でしょう。曲自体も序奏部が最初にある古いスタイルをとっています。現代の演奏ではこの序奏部は遅く、主部に入るとテンポを上げるというスタイルが一般的ですが、ヨッフムは第一楽章冒頭からさわやかで軽い響きで始めます。ただ、テンポは遅く、これが主部になってもテンポは思いのほか上がりません。全体はリピートを全て入れていますから巨大で重量感があります。小節1拍めの4分音符の柔らかな着地が印象的。ヴィヴァーチェの手前の61,62小節で微妙に速め、276小節再現部
第二楽章ではロンドン響から重い響きを引き出している悲しみのアレグレットです。遅いテンポで切々と歌い込んでいます。ヴァイオリン軍の主旋律を支える低音部のチェロやコントラバスの表情は濃厚で対比が見事です。ここではアレグレットということで全体は早めの店舗で演奏しています。これがこの時代の表現だったのでしょうなぁ。
ヨッフムのこの時の演奏の特徴手もありますが、第三楽章も繰り返しを全て実施していて、行けるツォとしては規模の大きな演奏になっています。長い曲となりました。ヴァイオリンはアクセントを強調させてメリハリの効いた響きを作り出していますし、ティンパニの打ち込みはやや大きめに捉えられていてパンチがあります。木管とのバランスも実に良く、充実した演奏になっています。この面は国内マスターを使用していることと、ステレオ収録ということで音がよりくっきりと聴こえます。カッティングレベルも幾分高く聞き応えがアップしています。
本来第四楽章へは切れ目なしに突入するようになっていないのですが、レコードではアタッカ気味に収録されていて、タイミングも一括の20:06と表記されています。それだけヨッフムは一気呵成に演奏したかったのでしょう。それもあって、単調になりがちなこのフィナーレも、リピートを全て励行しながらもダレずに緊張感が崩れないのが見事です。小生はここで身を乗り出しさらにアンプのボリュームを上げて音の洪水の中に身を置きました。普通はこんなことはしないで音楽に身を委ねるのですが、ここでは熱い盛り上がりで思わずフェスのようなノリで聴き入った次第です。面白いことに主題のホルンの後半は木管楽器と同じように旋律化させて演奏していますし、聴きどころ満載です。ヨッフムのEMI録音はボックスてCDも所有しているのですが、以前CDで聴いた時はこんなことはありませんでした。レコードマジックなんでしょうかねぇ。後半の金管の咆哮も今の若い指揮者では真似のできない演出で面白いです。この頃はプレヴィンが主席指揮者でしたが多分彼ではこういうベートーヴェンは録音できなかったでしょう。ここでロンドン響とヨッフムを組み合わせたのはEMIスタッフの英断と言って良いでしょう。
このB面が国内マスターになっているのは小生の手持ちのセットだけかもしれませんが、そこから新しい響きを聴き取ることができヨッフム爺さんはただの旧式規範的な演奏ではないぞという思いを感じることができました。下はデジタル化されたものを貼り付けていますが、これは是非ともレコードで聴いてほしい演奏です。