町人の大名への貸付、大名貸はしばしば、窮乏化しつつある大名が富裕化しつつある商人に消費貸借を要求したものと考えられることが多い。しかし、このような考えは必ずしも正しくない。たしかに大名財政の窮乏化はあったし、それによって大名貸の焦げ付き、踏み倒しは初期から存在した。
しかし、もし大名財政の窮乏化が長期的な傾向を表すもので、しかもそのことを商人が看破していたなら、商人が合理性を持ち合わせている限り、そのような「不良企業」への貸付を連続的に行うようなことはなかったろうし、まして、それを専業とするような両替商は成立しなかったであろう。
(中略)
幕藩領主が、当地における至上の富の源泉である土地を支配し、かつ最大の消費物資である米を掌握している限り、揺ぎ無い経済的基礎をもっているという認識があったといえよう。このような意味で、鴻池家が行ったような大名貸は単なる消費貸借と考えられるべきではない。それは米という近世最大の商品の流通を担当する大名=大坂蔵屋敷という一種の商館に対する商業金融の性格をもつものであった。
つまり、右に述べた本来的な意味の大名貸は、実物の財の流通状況に依存して供与される信用であったといえる。それがゆえに、大名の大坂登米量が増加しつつあった寛文~元禄期に鴻池の大名貸の増加、専業化がおこったのである。右に見たように鴻池家の大名貸は、蔵物流通と結びついた貸付であり、そしてこの点に鴻池の大名貸の革新性があった。
宮本又郎「日本企業経営史研究 人と制度と戦略と」
2009-09-10
は「パブリックエネミーナンバーワン」、別に霧間誠一じゃないよと(こちらももう分かる人のほうが少ないネタですかorz)。あとは千葉法相下で1ミクロも進展しなかった可視化法案、そして今年は25%に悪化した新司法試験合格率と。
2009-09-11 は保坂展人選挙報告会(今回参院選で病とはいえ、ボランティアに参加できなかったことは痛切の極み)
国際競争力で米国が4位に後退、日本は6位に浮上
>世界経済フォーラム(WEF)が9日発表した2010/11年版「世界競争力リポート」で、米国は2位から4位に順位を落とした。一方、日本は8位から6位に順位を2つ上げた。今年もスイスがトップの座を維持し、2位はスウェーデン、3位はシンガポールとなっている。昨年は、3位がシンガポール、4位がスウェーデンだった。今回は新たにトップ10入りした国はないが、ドイツが7位から5位に順位を上げた。前回29位だった中国は27位に上昇。(NewsWeek 2010年09月09日(木)16時27分)
日本のランクが上がっているんだけど、これまた綺麗にTVを中心にマスゴミは黙殺ですか?昔、GNPランキングが上がるごとに国家を挙げて大騒ぎしていた時代は今何処。どうして暗~いニュースばかりやるんでしょうね。そんなんで景「気」がよくなるわけないじゃん。あといいかげん、シンガポールのような小国は都市国家として別のランキングにしてほしい。
4 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 14:21:45 ID:9ugJW9uL
国家の国際競争力なんて存在しない。なんつーか世界中馬鹿なんだろな。
経済競争ってどっかが勝てばどっかが負けるようなものではないよ。
5 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 14:27:04 ID:MaJMqkOG
>>4
そういって競争を否定し、世界に背を向ける脳内お花畑
7 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 14:29:00 ID:9ugJW9uL
>>5
競争を否定なんかぜんぜんしていないけど、国と国は経済戦争争していないってこと。
ミクロ主体同士が競争してるのよ。サムソンと松下は競争してるけど韓国と日本は競争してないってこと。
名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 14:37:40 ID:yq+62p9U
>>4,7
世界中がバカで国家の国際競争力を認識しているのなら、もちろんそれを前提として世界が動いてるわけで、
結果的に国家の国際競争力というものは、あるといっていいと思うんだけどどうかな?
ここから有意義な講義が始まります。
12 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 14:39:32 ID:9ugJW9uL
>>11
それは違うなぁ。ミクロ単位がそう思って行動しても結果的にはマクロでは存在しないから。
大事なことは生産性を上げることなんだよ。国際競争力なんておもいっきりぶった切れば為替と物価のこと。
13 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 14:42:04 ID:9ugJW9uL
例えば、日本は農林業をやめて工業やサービス業へ戦後シフトして食糧は輸入に頼るようになったわけだけど
このとき農家が国際競争に負けて殲滅させられたなんて言うのかい?
17 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 15:26:08 ID:yq+62p9U
>>12
ミクロが国家の国際競争力を認識してマクロを構成しているのなら、
マクロにも表れると思うんだけども。どうして結果的にマクロで表れないんだろうか?
為替と物価が国家競争力であるというなら、その影響はミクロにも及ぶのでは?
現に一輸出企業は為替一つで業績が大きく変動するよね。遅くてすまんが教えてもらえるとうれしいです。
結局はミクロ主体同士が争っているに過ぎないというのが説得力あってな。
18 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 15:34:16 ID:9ugJW9uL
>>17
例えばミクロで競争力があるって考えてそれを上げるために必死で努力しても
その結果起こる経済成長で、あらゆる外的要因により比較劣位になる産業は淘汰されざるを得ない。
いくらがんばっても繊維産業の多くは日本では食えないってことだよ。農林業もそうだよね。
為替と物価の影響は当然ミクロに及ぶよ。だから国際競争力があるとすれば通貨の切り下げによる
内外価格差の是正だってこと。生産コストが途上国に近づけば既存産業が活気付くのは当然。
逆に言えば途上国が日本を抜かすには日本より高い生産コストでも競争力を維持しなければならないってこと。
だから通貨安自体に景気浮揚効果がある。
これはクルーグマンのマサチューセッツアベニューモデルで明らかにされている。日本に無いのは政府の競争力だよ。ほかの国がやっている当たり前のことをしないからデフレとそれが招く通貨高で経済が衰退してる。
20 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 15:53:59 ID:yq+62p9U
>>18
レスありがとう。
言ってることのニュアンスはつかめたつもりだけど、半分も理解できてないかな。
18の内容はむしろ国家間の競争力を認める内容な気がするが。経済はまともに勉強したことないのでな。
理解するのにまだ時間かかりそうだ。よく咀嚼してみるよ。
21 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 15:54:26 ID:9ugJW9uL
>>19
結局極端な通貨切り下げとGDP比で膨大な貿易黒字とかはよくないんだよ。
それは国民を他国の奴隷にしているのと同じだからね。
産業構造が自然に変化していくのはまず需要が無いと無理だからデフレでは期待できないでしょっと
22 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 15:56:39 ID:9ugJW9uL
>>20
いやだから、為替と物価に関してあるって言ってるだけだよ。
それでも大事なことは結局生産性を上げたほうがより国民が豊かになるということ。
海外に物を売るから豊かになるのでは無くて、他国民がほしいと思うようなものを
沢山作れるから豊かであるというほうが正しい。みながほしいと思うというのはそれだけ付加価値が高いということだよね。そしてそれが工業製品である必要は必ずしも無いわけだ。
23 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 16:07:08 ID:yq+62p9U
>>22
ふーむ。繊維産業やら農林業やらは経済成長済みの国では衰退するといったあたりもね、
国家間の競争力の話なのではと思ったんだよ。
上げるべき生産性というのは何だろう?対時間?省賃金?
24 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 16:15:39 ID:9ugJW9uL
>>23
国家間じゃなくて国内でなんだよね、本来比較優位って。もちろん国際的にも成り立つから国際分業が発展したんだけど、フリードマンが面白いことを言ったんだけれど、日本は明治時代関税自主権が無かったから発展したんだと。生産性の低い産業は輸入品位木端微塵にされ新たな産業が起こったってこと。
だから例えば国際競争を経常収支や貿易収支と定義して既存の産業に補助金をばら撒いたり輸入品に関税をかけたりすることが国家の経済厚生に寄与することは基本的に無いんだよ。むしろ高い値段で悪いものを買わされる消費者の不利益になり国家が産業に介入することにより市場メカニズムが働かなくなってしまう恐れもある。その国でできない商売(比較劣位)はできないでよくてさっさとアウトソースすればいいって話。
これは機会費用という概念に支えられている。まぁググってよ。んでこれから何をするかだけど、それはわからないなぁ。儲かる産業は市場とプレイヤーが決めること。ただ日本政府がすることは適切なマクロ政策。金融政策で景気の変動をできるだけ抑えたり、公共事業で外部性のある箇所に投資したりすること。こういうことで商売がしやすい国は国際競争力があると定義することはできるのかもしれない。
ただ、世間の多くが想像しているような国際競争力は存在しない。
このくだりは素直に肯んぜない。北米の工業が発展したのは南北戦争以降、保護貿易してからですねぇ。以前も紹介した けれど、ハジュン チャン「はしごを外せ―蹴落とされる発展途上国」のような経済(学)史の方が厳然たる歴史的事実としてリアリティを私は感じます。
26 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/09/09(木) 16:35:08 ID:yq+62p9U
>>24
今まででいちばんすっと入った文章だった。実は理系だけど少し地域経済について習ったんだ。
機会費用とか外部経済とか思いだしてきた。詳しくはグーグル先生に聞くよ。
比較優位、比較劣位、機会費用あたりがキーワードかな。
政府は競争主体が活動しやすいように環境を整えるまでをすべきであって、
比較劣位な産業を守るために対症療法的な政策をすべきでない。
適材適所な競争を促すことが合理的で求めるべき姿ってことかな。
そういう考えの一派に名前ついてそうだね。合理性を追求したら結果全体の幸福も最適化されるみたいな。ここへきて、世間の多くが想像しているような国際競争力が存在しないってことが理解(ふんわりとだけど)できた気がする。競争主体があくまでも企業単位なのだから、国家の国際競争力というものにとらわれると実情を見誤りやすいのだね。
丁寧にレスくれてありがとう。さすがに仕事せねば><
ひどい誤解をしてる時だけ指摘ください。
27 名前:名刺は切らしておりまして[sage] 投稿日:2010/09/09(木) 16:44:14 ID:9ugJW9uL
>>26
名前は新古典派っていうのかな。古典派でもいいけどこれらはもう世界的に常識中の常識なんだ。
なんたってかの有名なアダムスミスの国富論は世論の重商主義を激しく批判したものであり、リカード、スチュアートミルなども彼と同じで重商主義を批判している。
政府による成長産業の選択と投資もなんて経済学的にはかなり間違っているんだね。でも80年代後半に比較優位は諸条件を満たせば人為的に作り出せること自体はクルーグマンを中心に発見された。でもそれは多くの場合には不可能で、実務的にも無理だから政府はそんなことを考えなくてもいいって本人が言ってしまってるんだよね。
日本人は産業政策が大好きだし、これから何で食べていくのかと考えてしまうけど、本来別に食えればなんだっていいんだよ。AKB商法だってあくどいけどあれはあれで無から有を作っている。性欲にコミットしてねw
経済学と経済学史の境界は徐々に狭まっていくのではないでしょうか(まさにリフレ派が高橋是清を持ち上げているように)。ちょうど記事になっていた「猫も王の姿を見ることは許される」 というやつみたいに。
日印EPA締結で実質合意 関税94%撤廃へ
>関税撤廃が実現すれば、協定発効から10年間で、日本への輸入品については97%、インドへの輸出品については90%がそれぞれ無税になる。これまで13回にわたる協議で日本側は、主要な輸出品である自動車部品の関税引き下げを要請。インド側は後発医薬品(ジェネリック医薬品)認可手続きの簡素化や、インド人が日本国内で介護士や看護師として就労できる機会の拡大を求めていた。(2010/09/09 19:59 【共同通信】)
久方ぶりのEPA締結なんですが、これだけ円独歩高状態では、アマテラス製薬のようにインドの医薬品企業を買収するというのでもない限り、純然たる輸出入の関係ではどちらにとって旨味があるかは…ねぇ。
オバマ大統領 3500億ドルの追加経済対策を発表
>このうち2000億ドルは法人税の免除に充てられる。企業が2011年末までに新たな設備投資や新規投資を償却できる。また、研究開発減税の恒久化に1000億ドル、インフラ投資に500億ドルを充てる。
法人税減税というよりは、投資減税の拡充をと菅総理が経団連パックの法人税率軽減+消費税増税という提言に載ったかの如き発言をした際にブーイングを記したとおり。宗主国ですらこうなのに…。
>一方、ブッシュ前政権時に導入された家計向け減税の期間延長については、年収25万ドル超の富裕層に対しては延長せず、25万ドル以下の層に限り延長する方針を示した。
25万ドルという基準は高過ぎるように思いますが、富裕層減税というもはや竹中の妄言だったことが明らかになったトリクルダウン効果に期待する方向とはそっぽ。
>追加経済対策を発表するうえでオバマ大統領は、「刺激策」という言葉の使用を避けた。昨年承認された8620億ドルの景気刺激策に対して、赤字を増大させただけで効果が出ていないとの批判が共和党から噴出していた。(2010.09.09 Thu posted at: 09:48 JST)
温暖化でもメモしましたが、選挙モードですと。共和党の主張はまさに小渕・森政権に対する小泉かつ民主党の批判とダブります。
ゴーン氏に米GM再建要請=オバマ政権が09年-暴露本で判明
>オバマ米政権が2009年、経営危機に直面していた自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)のワゴナー会長兼最高経営責任者(CEO)を3月末に事実上解任した後、日産自動車のカルロス・ゴーン社長(仏自動車大手ルノー会長)にGMの経営再建を要請していたことが3日、米紙デトロイト・ニューズなど複数のメディア報道で明らかになった。(時事通信 2010/09/04-11:45)
再上場が視野に入っても経営者がコロコロ代わるGMを見ると、短期間でいかにリストラして利益を出すかという点でゴーン氏はうってつけだったでしょう。だからこそ、買収、提携などで日産ルノーの名が最後まで上がっていたわけです。納得、納得。
エコカー補助金、残1000億円切る…1日最高26億円
>補助金総額約5837億円のおよそ8割を消化した。直近5営業日の1日あたりの申請状況での最高額は8月5日の約26億円(申請受理台数:約2万1000台)。日付別では、7月30日・18億円、2日・18億円、3日・20億円、4日・23億円、5日・26億円、で、5日間を平均すると1日あたり約21億円を消化している状況だ。(レスポンス自動車ニュース 2010年8月7日)
メデタク、補助金を使い果たしたというニュースが流れたので掘り起こしてメモ。共産党がよく言うところの「財布を温める(=減税)」よりも、「財布を開かせる(=補助金)」施策の有効性が今回の一連の景気対策で確認されたように思うのですが。
127 名前:名刺は切らしておりまして[] 投稿日:2010/08/13(金) 09:05:47 ID:KetZrPqy
http://www.cev-pc.or.jp/NGVPC/subsidy/eco/eco_PDF/shintyoku.pdf
ここで補助金があとどれくらい残ってるか毎日更新してるけど
この調子であれば9月第2週で終わってしまいそうだ
なんとか9月末日までの受付分までにしてほしい
大正解!
家電エコポイント:「五つ星」機種に限定 来年以降の対象
>直嶋正行経済産業相は7日の閣議後会見で、追加経済対策に盛り込んだ来年3月末までの家電エコポイント制度の延長について、来年以降の対象商品は省エネ性能を5段階で示す「統一省エネラベル」で最も高性能の「五つ星」の機種に限定する方針を示した。
白かろうが黒かろうが鼠がとれれば良いので、自民党政権下でも良かった政策はそのまま踏襲すればよろし。ただ時限だからこそ心理的に需要掘り起こし効果があるのでしょうから、さまざまなもので消費を促していくぐらいの工夫は欲しいけれど。
>五つ星への絞り込みで、対象商品の数は、薄型テレビの場合、現在の6割程度になるという。10日の閣議で正式決定する。昨年5月に始まった家電エコポイント制度は今年12月末の購入分で打ち切る予定だった。しかし、景気の先行き不透明感が強まったため、政府は来年3月末まで3カ月延長する方針を決めた。(毎日新聞 2010年9月7日)
なんで対象品を変更しないんだろう…GOPANを筆頭に炊飯器もエコという理屈はいくらでも付与できるし、掃除機や食洗機とかオーブンとかあるじゃん。
<アニメ感想>
火曜
世紀末オカルト学院 第10話
若干、失速してきたかなぁと。ヒーローと見せかけて全くヒーローに相応しくなく単なるお笑い役と化していたヒーローと、ヒロインそして仲間たちの怪奇話に正面から立向うギャップが良かったのに。ヒーローに真面目にヒロインに向かいあわれると残念。
ぬらりひょんの孫 第10話
雲外鏡の恐怖が足りない(ぬらりひょんが強すぎ)。この点はぬーべーとか、学校の怪談とか似た様な話はあっただけに参考にして欲しいとも思ったけれど、そもそも妖怪モノというより妖怪バトルモノであってジャンルが異なるからいいんでしょうな。
水曜
オオカミさんと七人の仲間たち 第10話
早送り視聴。
学園黙示録 第10話
高城夫妻@中田譲治&榊原良子さまがカッコ良すぎて震えた。今回は息抜き回(少なくともセックス&バイオレンスという点では)かと思わせておいて、大人と子供の関係性を守るものと、守られるものというより権力関係で突きつけるテーマは面白かった。ただ、主人公は言葉より次第に腕力で有無をいわせず納得させているところは、高城氏とそっくりなような気もするけれど。
あと、前々回のおっぱい台座ネタが継続されているのは笑った。
「市場機能拡張的見解」は「歴史制度分析」のA・グライフのアプローチと通じている。グライフは、所有権と契約の履行に対する公権力の保証に限界があった中世地中海交易においては、交易商人は在外代理人の不正行為を受ける危険に晒されていたが、マグリビと呼ばれるユダヤ人商人集団は、不正を働いた在外代理人に対して結託して集団的制裁を加えるという「多角的懲罰戦略」を採用し、このことによって継続的交易を実現することができたと指摘した。
宮本又郎「日本企業経営史研究 人と制度と戦略と」
- 日本企業経営史研究 -- 人と制度と戦略と/宮本 又郎

- ¥6,825
- Amazon.co.jp
- ▲タイトルからイメージしたものとは裏腹に、近代ではなく近世の企業経営(例が鴻池家など)興味深かった。江戸と明治の狭間で豪商、どう波に乗り、どう没落したかなどを家訓や財務状況などから丹念に掘り起こしています。…ただ、学術書の多分にもれず高いねぇ。
- はしごを外せ―蹴落とされる発展途上国/ハジュン チャン
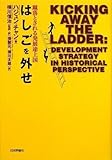
- ¥2,520
- Amazon.co.jp
- ▲こちらはAmazonレビューにも記した通り、私はしっくり腑に落ちました。