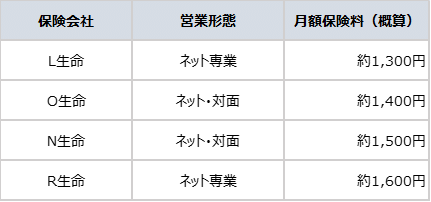生命保険に加入するベストな時期は、「経済的責任を負う相手ができたとき」と言えるでしょう。
多くの場合、それは結婚や子どもの誕生のタイミングですが、就職後すぐに備えるのもコスト面で有利な選択肢とも言えますが、独身である以上大きな保障は不要と言えます。
今回は、ライフイベントごとに考える生命保険の加入タイミングについて説明して行きます。
生命保険に加入する理由
生命保険の主な役割は、万が一の際に残された家族の生活を守ることです。独身の間は、両親などに経済的責任を負っていなければ必要性は低い場合もあります。しかし、結婚や出産を機に扶養家族ができると、その責任が生まれます。
また、保険は若く健康なうちに加入すると保険料が安く、万一のリスクも保障されるため、早期加入には一定のメリットがあります。
生命保険に加入する時期の例
就職時に加入するケース
大学を卒業して就職する多くの人が23歳~24歳くらいでしょう。
この時期に生命保険に加入すると、保険料が安く済むことが最大のメリットとなります。
ただし、独身で両親以外に家族がいない場合には、無理に生命保険に加入する必要ないでしょう。加入するにしても必要最低限の保障で抑えておき、将来結婚したり、子どもができた時期に見直していくという作業をするのが合理的と言えます。
結婚時に加入するケース
結婚は、被扶養者が生まれたる瞬間でもあり、死亡保障の必要性が一気に高まる代表例です。
会社員の人が結婚した場合、配偶者が働いている人か、専業主婦なのかでも必要保障額は大きく変わります。
共働きの場合にはお互いに収入があるため、配偶者に万が一のことがあったとしても、一人の生命保険で当面の生活費等を賄うような保険設計は合理的ではありません。
きちんとしたライフプランをもとに、保険設計をするのが望ましいと言えます。
子どもが生まれた時に加入するケース
子どもが生まれた時は、生命保険の必要性が一気に高まります。
子育ては時間とともにお金がかかります。そんな時に自分自身に万が一のことが起きた場合、経済的な安心感を与えてくれるのが生命保険です。
近年、大学全入時代とも言われ、多くの人が大学に通う時代になっています。
これにより、教育費のピークは子育て後半に来ることが多くなっていますが、各家庭での子育ての方針・教育方針もふまえて、ライフプランに合わせて必要保障額をシミュレーションすることは必須の作業と言えます。
まとめ
生命保険は「年齢」よりも「誰の生活を支えているか」で必要性が決まります。
つまり、結婚や出産などで「守るべき存在ができたタイミング」が加入の目安と言えるでしょう。
当初、綿密なライフプランを立てて保険設計をしたとしても、子どもが増えたり、子どもの進路や親の仕事に変化があった際には、プライフプランの修正とともに保険の見直しも必要になります。
自分と大切な人の未来を守るために、「いつ入るべきか?」
そして、「いつ見直すべきか?」を今こそ考えてみませんか?
FPドットコムでは、ライフプランの作成から保険設計まで対応してくれるFPをご紹介しています。
一人で考えるよりも、保険設計のプロに直接相談して解決策を探ってみてください。
ご相談はこちらから👇