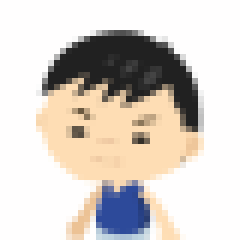村上春樹『街とその不確かな壁』を読んだ。おそらく何年も後になって、村上の最高傑作と呼ばれる事になるだろう。
何十年も前に私は『風の歌を聴け』から『ダンス・ダンス・ダンス』を読んだだけでとても熱心な読者とは言えない。
軽い文体でひたすら寓話を紡ぐ作家。当時の大量消費社会を批評する感受性豊かなノンポリ作家としか思えなかった。『ノルウェイの森』よりは『ダンス・ダンス・ダンス』の方が断然、文学的な価値があるとは思った。
ところが、今作、『街とその不確かな壁』は円熟した眼差しで二つの世界に横たわる壁をぶち壊してみせる。まるで二項図式の「不確かな壁」という言わば<神話>を脱構築することに傾注している。疫病と戦争の時代だからこそ、村上は矛盾に満ちた現実を生き抜くことを選択する。それを証左に今作で村上は寓話に逃げない。それこそが村上にとって自己と他者を繋ぐ継承としての意義をもつのだろう。
過去の焼き直し、使い古されたテーマ、と論じる「批評屋」も多い。だが、円熟した境地に達した村上とは裏腹に、これらの論者はまるで村上春樹の文学をスリルとサスペンスのエンターテインメントおよびファンタジーとして読み、<物足りない>と論じているに過ぎない。己の弱さを知れ!とはまさにこのことだ。
村上が『街と、その不確かな壁』をリライトし、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』ののりこえをめざした本作『街とその不確かな壁』には、未熟さも現実逃避に過ぎない寓話性も読者に迎合するエンターテインメント性も、ましてや軽薄さも、これら一片の雑念も入り込む余地はない。
大江健三郎が当時の最高傑作『万延元年のフットボール』を起点に、『同時代ゲーム』を『M/Tと森のフシギの物語』としてリライトし、『懐かしい年への手紙』へと結実させた仕事と、(村上にとって)同様の意義をもつ。それはまた村上春樹にとって、ガブリエル・ガルシア=マルケスが構築した<マジック・リアリズム>を改めて問い直す作業としても結実化されている。
かくして、村上は作家としての己自身の《街とその不確かな壁》の境界線をぶち壊すとともに、今このあるがままの否定的な現実と向き合い生きる事を呈示する。おそらくこのことが村上が今作を発表した内的必然性に他ならぬだろう。あらためて言おう、『街とその不確かな壁』は10年後、村上春樹の最高傑作と称される事になるだろう。
今作で村上春樹はついにかつて氏が翻訳したレイモンド・カーヴァーの境地に達した。一見寓話的にみえる二項図式だが、三世代を繋ぐこの<語りとしての物語>には、すべて2020年代を生きるささやかな生命の発露と不安とそこはかとない希望が想像力豊かに描かれているのだ。
.
.