ヒカルの碁/ヒカル佐為と出会う-小学生編-
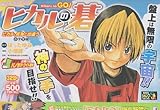
Amazon.co.jp
囲碁棋士の方も読んでいる方が多いようです。これまでずっと気になっていましたので、これを機会に買って読み始めました。
いやー、ジャンプの王道ですね。少年の挑戦、成長、ライバル、友情。主人公が特殊な能力を持っているところもジャンプらしい(幽霊がとりついているのですが)。
囲碁がテーマですが、盤面が大きく取り上げられるわけではなく、人間ドラマとのバランスが秀逸です。
週刊誌連載時には、みんな次号が待ち遠しかっただろうなあと思います。
4歳の子供に「囲碁の本なんだよ」と言って見せたら、ぱらっとみて「囲碁全然出てないじゃん」と言われました。まあ詰碁の本ではないからね…