鎌倉大仏 阿弥陀如来坐像 ~ 高徳院 鎌倉 【東京・横浜探訪】
しばし、鎌倉探訪を楽しんでします。
o(〃^▽^〃)o
由比ヶ浜から山側へあがると、観光客がどっと増えます。
観光バスがひっきりなしにおとずれるそこは、高徳院。
そうです鎌倉大佛の名で親しまれている巨大な阿弥陀如来坐像がおわします。
大きいですねー。
ヾ(@°▽°@)ノ
台座を含め総高、約13.4メートル。
重量は約121トン。
建長4年(1252)から10年の歳月を費やしたと伝えられています。
創建に関わる事情の多くは謎につつまれています。
製作には浄光が勧進した浄財があてられたとのこと。
鋳工として丹治久友、大野五郎右衛門の名を記す史料があるが、
原型制作者など不明となっています。
うぉっ
背中があいてる
∑ヾ( ̄0 ̄;ノ
大仏といえばこちら。
【総集編】世界初の夫婦物語~平城遷都から大仏開眼まで。
【鎌倉探訪】
>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
>1.女が築いた時代 鶴岡八幡宮
>2.女が築いた時代 由比ヶ浜
でっかいな、大仏・・・
しかし、日本では2番だ。
(°∀°)b
↓↓↓↓↓

奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
o(〃^▽^〃)o
由比ヶ浜から山側へあがると、観光客がどっと増えます。
観光バスがひっきりなしにおとずれるそこは、高徳院。
そうです鎌倉大佛の名で親しまれている巨大な阿弥陀如来坐像がおわします。
大きいですねー。
ヾ(@°▽°@)ノ
台座を含め総高、約13.4メートル。
重量は約121トン。
建長4年(1252)から10年の歳月を費やしたと伝えられています。
創建に関わる事情の多くは謎につつまれています。
製作には浄光が勧進した浄財があてられたとのこと。
鋳工として丹治久友、大野五郎右衛門の名を記す史料があるが、
原型制作者など不明となっています。
うぉっ

背中があいてる

∑ヾ( ̄0 ̄;ノ
大仏といえばこちら。
【総集編】世界初の夫婦物語~平城遷都から大仏開眼まで。
【鎌倉探訪】
>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
>1.女が築いた時代 鶴岡八幡宮
>2.女が築いた時代 由比ヶ浜
でっかいな、大仏・・・
しかし、日本では2番だ。
(°∀°)b
↓↓↓↓↓
奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
- 白拍子 静御前/森本 繁
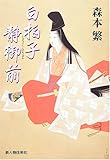
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
女が築いた時代(2) 源頼朝と静御前 ~ 由比ヶ浜 鎌倉 【東京・横浜探訪】
文治元年(1185)11月。
雪深い吉野の山。
「・・・私はあなたの子を身籠っています。」
吹きすさぶ風雪にかきけされんと静は、源義経に叫んだ。
義経と別れ、静御前は鎌倉の探索方に捕まり、鎌倉へと送られました。
義経捜索のためでしたが、義経の行方はようとしれず、静は都へ還されることとなります。
しかし身重であることが知られ、大事をとって鎌倉にとどまることとなったのでした。
やがて鎌倉に春がきます。
静は請われて、鶴岡八幡宮で舞を披露することとなります。
舞の奉納には北条政子の計らいもあったそうです。
文治2年(1186)4月。
満開の桜の鶴岡八幡宮で頼朝と北条政子の前で、舞うのでした。
しかし、所作ひとつひとつ、空を切るばかりで、手ごたえない。
床に手をつき、考える。
やがて、脳裏にあの日の吹雪の音がまきあがります。
どくん・・・全身に力がみなぎります。
再び、静は舞った。
吉野山
峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき
しづやしづ
しづのをだまき くり返し
昔を今に なすよしもがな
会場は静まり返ります。
しかし、一人黒い炎をもやし静を見下ろす者がいました。
義経の兄・頼朝でした。
やがて近侍のものたちも色めき立っている。
今にも太刀をぬきかからんとする勢いです。
男たちの怒りを、掻き消したのは政子の一喝でした。
「わたしには、彼女の気持ちがよくわかります。」
良人を前に、政子は流人であった頼朝との辛い馴れ初めと、挙兵のときの不安の日々を語ります。
「私のあの時の愁いは今の静の心と同じです。
義経の多年の愛を忘れて、恋慕しなければ貞女ではありません」
ふぅと頼朝は息をついた。
「政子にはかなわん。誰ぞ、あのものに褒美をとらせよ。」
と頼朝は破顔一笑した。
坐をたち、立ち去る間際、
「子を身籠っていると・・・」
ギクリと政子の顔が蒼ざめる。
「男子であれば、後の憂いとなりうるだろう。
そのことは、己がいちばんよく知っておるからな。
生まれてくる子が男であれば、覚悟せよ。」
由比ヶ浜。
鎌倉時代、由比ヶ浜は、鶴岡八幡宮の前の浜という意味から「前浜」と呼ばれていました。
同年7月29日。
静は、出産します。男子でした。
その報せが頼朝の耳に届くや、頼朝の命を受け安達清常が、母子のもとにやってきました。
磯禅師が催促するが、静は生まれたばかりの子を衣にまといはなしません。
数刻に及び泣き叫んで抵抗しました。
しかし子は取り上げられます。
母子はわずかな対面のみで、今生の別れとなります。
・・・
由比ヶ浜を漕ぎだす舟に、母恋しと子の泣き叫ぶ声が響きます。
そしてその声は、沖へとつづきます。
やがて、どぷん・・・と途絶えました。
それから2ヶ月後。
静は、北条政子をはじめとする女たちから大事にされ都へと旅立ったとあります。
その後、静の消息は諸説ありますが、定かではありません。
>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
>1.女が築いた時代 源頼朝と池禅尼、北条政子、静御前
静御前、その後の行方は・・・
↓↓↓↓↓

奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
雪深い吉野の山。
「・・・私はあなたの子を身籠っています。」
吹きすさぶ風雪にかきけされんと静は、源義経に叫んだ。
義経と別れ、静御前は鎌倉の探索方に捕まり、鎌倉へと送られました。
義経捜索のためでしたが、義経の行方はようとしれず、静は都へ還されることとなります。
しかし身重であることが知られ、大事をとって鎌倉にとどまることとなったのでした。
やがて鎌倉に春がきます。
静は請われて、鶴岡八幡宮で舞を披露することとなります。
舞の奉納には北条政子の計らいもあったそうです。
文治2年(1186)4月。
満開の桜の鶴岡八幡宮で頼朝と北条政子の前で、舞うのでした。
しかし、所作ひとつひとつ、空を切るばかりで、手ごたえない。
床に手をつき、考える。
やがて、脳裏にあの日の吹雪の音がまきあがります。
どくん・・・全身に力がみなぎります。
再び、静は舞った。
吉野山
峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき
しづやしづ
しづのをだまき くり返し
昔を今に なすよしもがな
会場は静まり返ります。
しかし、一人黒い炎をもやし静を見下ろす者がいました。
義経の兄・頼朝でした。
やがて近侍のものたちも色めき立っている。
今にも太刀をぬきかからんとする勢いです。
男たちの怒りを、掻き消したのは政子の一喝でした。
「わたしには、彼女の気持ちがよくわかります。」
良人を前に、政子は流人であった頼朝との辛い馴れ初めと、挙兵のときの不安の日々を語ります。
「私のあの時の愁いは今の静の心と同じです。
義経の多年の愛を忘れて、恋慕しなければ貞女ではありません」
ふぅと頼朝は息をついた。
「政子にはかなわん。誰ぞ、あのものに褒美をとらせよ。」
と頼朝は破顔一笑した。
坐をたち、立ち去る間際、
「子を身籠っていると・・・」
ギクリと政子の顔が蒼ざめる。
「男子であれば、後の憂いとなりうるだろう。
そのことは、己がいちばんよく知っておるからな。
生まれてくる子が男であれば、覚悟せよ。」
由比ヶ浜。
鎌倉時代、由比ヶ浜は、鶴岡八幡宮の前の浜という意味から「前浜」と呼ばれていました。
同年7月29日。
静は、出産します。男子でした。
その報せが頼朝の耳に届くや、頼朝の命を受け安達清常が、母子のもとにやってきました。
磯禅師が催促するが、静は生まれたばかりの子を衣にまといはなしません。
数刻に及び泣き叫んで抵抗しました。
しかし子は取り上げられます。
母子はわずかな対面のみで、今生の別れとなります。
・・・
由比ヶ浜を漕ぎだす舟に、母恋しと子の泣き叫ぶ声が響きます。
そしてその声は、沖へとつづきます。
やがて、どぷん・・・と途絶えました。
それから2ヶ月後。
静は、北条政子をはじめとする女たちから大事にされ都へと旅立ったとあります。
その後、静の消息は諸説ありますが、定かではありません。
>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
>1.女が築いた時代 源頼朝と池禅尼、北条政子、静御前
静御前、その後の行方は・・・
↓↓↓↓↓
奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
- 白拍子 静御前/森本 繁
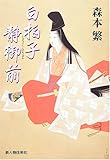
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
女が築いた時代(1) 源頼朝と池禅尼、北条政子、静御前 ~ 鶴岡八幡宮 鎌倉 【東京・横浜探訪】
父と、兄が死んだ。
自身は平氏に捕縛された。
処刑されるのは必至だった。
死を目前としたとき、不思議なことに恐怖がなくなった。
恐怖どころか感情が消えた。
平氏一党の前にだされても何も感じていない。
まるで鳥になったかのように、頭の上を漂い見下ろしているようだ。
「おまちください。」
池禅尼。
平清盛の継母である。
この女は、私の助命を訴えかけているではないか。
助かったというよりも、この女の情(なさけ)がむせかえるようだ。
助けられた命は、伊豆国へ流される。平氏が助けた命によって、平氏は滅んだ。
源頼朝(みなもとのよりとも)。
久安3年(1147)4月。
河内源氏・源義朝の三男として生まれる。
平治元年(1160)12月9日。
院近臣らの対立により発生した政変・平治の乱により、父・兄が敗れ命を落とす。
頼朝は、池禅尼の嘆願により伊豆国へ流される。
治承4年(1180)。
長く沈黙を守っていた頼朝は、以仁王の令旨により平氏打倒の兵を挙げる。
関東を平定し鎌倉を本拠とし弟たちとともに、みごと平氏を滅ぼす。
しかし運命のいたずらか、平氏討伐の戦功高い末弟・源義経と対立、そして追うこととなる。
文治元年(1185)11月。
雪深い吉野の山。
身をも削るような寒さと、吹きすさぶ風の中を進む一行がいました。
源義経とその家来たちでした。兄・頼朝の追跡より逃れるところでした。
そこに、ひとり異彩をはなつ女がいた。
かつて都で、神に声がとどく唯一のものと名を馳せた白拍子・静御前。
今は武具をまとい、源義経と行動をともにしていました。
はたと義経は一行の足をとめた。
雪をふみしめ、静のそばによる足音は、まるで最期の時をきざむかのように届いた。
義経は、静にいった。
「おまえはここから都へ帰るのだ。」
「なにをおっしゃいますか。
別れるのなら、いっそ殺して下さい!」
激しい言葉を吐く、その心の奥では、ここが今生の別れであるという、冷え切った自分がいた。
「・・・私はあなたの子を身籠っています。」
・・・
果して、ふたりは別れます。
静は鎌倉の探査方に捕まり、鎌倉へ送られます。
文治2年(1186)4月。
満開の桜の鶴岡八幡宮 へ頼朝と妻の北条政子が参拝します。
吉野の山奥よりこの鎌倉へ護送された女がいると聞いた。
弟・義経の妾で、京で名高い白拍子であったと聞く。
誰の計らいか、この場に呼び寄せているというではないか。
女が来てからか、この鎌倉までがわきたっていた。
稀代の舞の手だという。
それにしてもこの女の妖気はどうだろう。
まるで太刀をのんでいるかのようではないか。

満開の桜の中、女が舞った。
近侍のものや、女房たちがほぉと見とれていた。
隣の政子もすこぶる機嫌がよい。
しかしこんなものであろうか。噂ほどでもない?
そう思っていたのは女も同じであったようだ。
舞おわり、床に手をつき女は動かなくなった。
あたりは水を打ったように、シンと静まりかえった。
再び、女は舞った。
吉野山
峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき
しづやしづ
しづのをだまき くり返し
昔を今に なすよしもがな
なんと、こともあろうにも女は弟・義経を慕う唄を詠んだ。
またみごとな舞だけに、心うばわれ、正気にもどったときには、怒りと笑いがないまぜに、こみあげた。
平静をふるまっていたつもりだっが、近侍のものたちが過剰に反応してしまった。
虜囚の身でありながら、鎌倉を讃えるどころか、逆賊・義経のことを慕う唄をうたう。
太刀に手をやるものもあらわれた。
「・・・」
さてと大将としての処断がなければ、この場はおさまらないだろうな。
腰をあげようとしたとき、バッと行く手を遮ったのは、妻・政子だった。
「おまちください!」
・・・
あの、むせかえるような臭いがした。
かつて池禅尼から感じたそれだ。
「わたしには、彼女の気持ちがよくわかります。」
女が・・・!
真に怒りがこみ上げた。
この頼朝の命をすくったのが池禅尼も、女。
伊豆国で、平氏討伐に奮い立たせた政子も、女。
義経の妾、静御前、そして、今ここで女が・・・
政子は流人であった頼朝との辛い馴れ初めと、挙兵のときの不安の日々を語ります。
「私のあの時の愁いは今の静の心と同じです。
義経の多年の愛を忘れて、恋慕しなければ貞女ではありません」
・・・
すでに頼朝には政子の言葉はとどいていません。
ただただ、時代の節目に顕れる女たちの僥倖に、思いを巡らせていました。
頼朝は、勇猛果敢な男たちをまとめあげ、平氏による一時代に幕をおろした。
そして、今、清和源氏の一時代を築こうとしている。
この世に神というものがいるのなら、世界をあるべき姿へと導こうとし、その導き手に女が選ばれているようだ。
これではまるで女が時代を築いているようではないか。
そう考えていると、己がひどくちっぽけな存在に思える。
(この物語は、次回、「女が築いた時代(2) 源頼朝と静御前 」につづきます。)
鶴岡八幡宮
康平6年(1063)。
奥州平定の出陣に際し源頼義が、ご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を、鎌倉の由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。
治承4年(1180)。
源氏再興の旗上げをした源頼朝が、鎌倉・由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、鎌倉の町づくりの中心としました。
以降、武家の精神のよりどころとなり、関東の総鎮守として崇敬を寄せたました。
更には国家鎮護の神としての信仰が全国に広まりました。
文治2年(1186)4月8日。
白拍子・静御前が、八幡宮の神前に舞を奉納したことは、今でも語り継がれています。

>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
頼朝と、静御前のお話、次回につづきます。
φ(.. )
↓↓↓↓↓

奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
自身は平氏に捕縛された。
処刑されるのは必至だった。
死を目前としたとき、不思議なことに恐怖がなくなった。
恐怖どころか感情が消えた。
平氏一党の前にだされても何も感じていない。
まるで鳥になったかのように、頭の上を漂い見下ろしているようだ。
「おまちください。」
池禅尼。
平清盛の継母である。
この女は、私の助命を訴えかけているではないか。
助かったというよりも、この女の情(なさけ)がむせかえるようだ。
助けられた命は、伊豆国へ流される。平氏が助けた命によって、平氏は滅んだ。
源頼朝(みなもとのよりとも)。
久安3年(1147)4月。
河内源氏・源義朝の三男として生まれる。
平治元年(1160)12月9日。
院近臣らの対立により発生した政変・平治の乱により、父・兄が敗れ命を落とす。
頼朝は、池禅尼の嘆願により伊豆国へ流される。
治承4年(1180)。
長く沈黙を守っていた頼朝は、以仁王の令旨により平氏打倒の兵を挙げる。
関東を平定し鎌倉を本拠とし弟たちとともに、みごと平氏を滅ぼす。
しかし運命のいたずらか、平氏討伐の戦功高い末弟・源義経と対立、そして追うこととなる。
文治元年(1185)11月。
雪深い吉野の山。
身をも削るような寒さと、吹きすさぶ風の中を進む一行がいました。
源義経とその家来たちでした。兄・頼朝の追跡より逃れるところでした。
そこに、ひとり異彩をはなつ女がいた。
かつて都で、神に声がとどく唯一のものと名を馳せた白拍子・静御前。
今は武具をまとい、源義経と行動をともにしていました。
はたと義経は一行の足をとめた。
雪をふみしめ、静のそばによる足音は、まるで最期の時をきざむかのように届いた。
義経は、静にいった。
「おまえはここから都へ帰るのだ。」
「なにをおっしゃいますか。
別れるのなら、いっそ殺して下さい!」
激しい言葉を吐く、その心の奥では、ここが今生の別れであるという、冷え切った自分がいた。
「・・・私はあなたの子を身籠っています。」
・・・
果して、ふたりは別れます。
静は鎌倉の探査方に捕まり、鎌倉へ送られます。
文治2年(1186)4月。
満開の桜の鶴岡八幡宮 へ頼朝と妻の北条政子が参拝します。
吉野の山奥よりこの鎌倉へ護送された女がいると聞いた。
弟・義経の妾で、京で名高い白拍子であったと聞く。
誰の計らいか、この場に呼び寄せているというではないか。
女が来てからか、この鎌倉までがわきたっていた。
稀代の舞の手だという。
それにしてもこの女の妖気はどうだろう。
まるで太刀をのんでいるかのようではないか。

満開の桜の中、女が舞った。
近侍のものや、女房たちがほぉと見とれていた。
隣の政子もすこぶる機嫌がよい。
しかしこんなものであろうか。噂ほどでもない?
そう思っていたのは女も同じであったようだ。
舞おわり、床に手をつき女は動かなくなった。
あたりは水を打ったように、シンと静まりかえった。
再び、女は舞った。
吉野山
峰の白雪 ふみわけて 入りにし人の 跡ぞ恋しき
しづやしづ
しづのをだまき くり返し
昔を今に なすよしもがな
なんと、こともあろうにも女は弟・義経を慕う唄を詠んだ。
またみごとな舞だけに、心うばわれ、正気にもどったときには、怒りと笑いがないまぜに、こみあげた。
平静をふるまっていたつもりだっが、近侍のものたちが過剰に反応してしまった。
虜囚の身でありながら、鎌倉を讃えるどころか、逆賊・義経のことを慕う唄をうたう。
太刀に手をやるものもあらわれた。
「・・・」
さてと大将としての処断がなければ、この場はおさまらないだろうな。
腰をあげようとしたとき、バッと行く手を遮ったのは、妻・政子だった。
「おまちください!」
・・・
あの、むせかえるような臭いがした。
かつて池禅尼から感じたそれだ。
「わたしには、彼女の気持ちがよくわかります。」
女が・・・!
真に怒りがこみ上げた。
この頼朝の命をすくったのが池禅尼も、女。
伊豆国で、平氏討伐に奮い立たせた政子も、女。
義経の妾、静御前、そして、今ここで女が・・・
政子は流人であった頼朝との辛い馴れ初めと、挙兵のときの不安の日々を語ります。
「私のあの時の愁いは今の静の心と同じです。
義経の多年の愛を忘れて、恋慕しなければ貞女ではありません」
・・・
すでに頼朝には政子の言葉はとどいていません。
ただただ、時代の節目に顕れる女たちの僥倖に、思いを巡らせていました。
頼朝は、勇猛果敢な男たちをまとめあげ、平氏による一時代に幕をおろした。
そして、今、清和源氏の一時代を築こうとしている。
この世に神というものがいるのなら、世界をあるべき姿へと導こうとし、その導き手に女が選ばれているようだ。
これではまるで女が時代を築いているようではないか。
そう考えていると、己がひどくちっぽけな存在に思える。
(この物語は、次回、「女が築いた時代(2) 源頼朝と静御前 」につづきます。)
鶴岡八幡宮
康平6年(1063)。
奥州平定の出陣に際し源頼義が、ご加護を祈願した京都の石清水八幡宮を、鎌倉の由比ヶ浜辺にお祀りしたのが始まりです。
治承4年(1180)。
源氏再興の旗上げをした源頼朝が、鎌倉・由比ヶ浜辺の八幡宮を現在の地にお遷しし、鎌倉の町づくりの中心としました。
以降、武家の精神のよりどころとなり、関東の総鎮守として崇敬を寄せたました。
更には国家鎮護の神としての信仰が全国に広まりました。
文治2年(1186)4月8日。
白拍子・静御前が、八幡宮の神前に舞を奉納したことは、今でも語り継がれています。

>ウキウキ!にぎやかな鶴岡八幡宮の秋祭り
頼朝と、静御前のお話、次回につづきます。
φ(.. )
↓↓↓↓↓
奈良歴史ミステリーハンターの電子書籍です。
東北地方太平洋沖地震 チャリティ作品
奈良妖怪大戦争「少年・聖徳太子物語 」
大和郡山 洞泉寺町 源九郎稲荷神社 社伝
「神仏おそれぬ羽柴秀長、 白狐源九郎に折伏される 」
- 白拍子 静御前/森本 繁
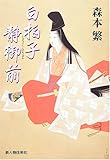
- ¥1,890
- Amazon.co.jp










