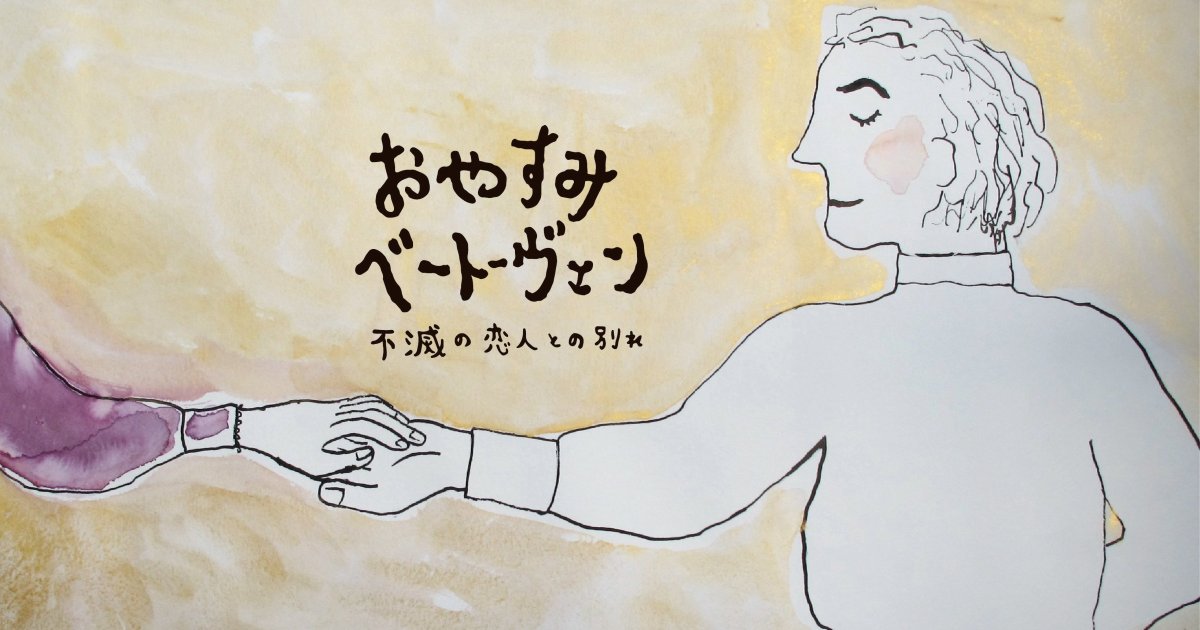ピアノの偉大なマエストロ、アルフレート(アルフレッド)・ブレンデル(1931-)の、「若かりし頃」の演奏映像です。
1970年2月28日、パリにて収録されたこの映像には、「ハンマークラヴィーア・ソナタ」(44分40秒)に引き続いて、op(作品).126「6つのバガテル(小品)」(1824)より、「第2番 ト短調」「第3番 変ホ長調」の2曲が弾かれています。
「N響音楽監督/桂冠指揮者」として、日本でもおなじみのマエストロ、ウラディーミル・アシュケナージ(1937-)の、やはり「若かりし頃」の名演奏をどうぞ(1980年)。
「リンク」のため、「別ウィンドウ」が開きます。
「べートーヴェン直系の弟子」でもあるヴィルヘルム・バックハウス(1884-1969)は、「2度目」となる「ピアノソナタ全集」の録音に取り組んでいましたが、この曲のみが「未録音」に終わったため、現在発売されている「全集盤」でも、こちらの「旧録音」(1952年4月)が、そのまま「採用」されています。
「20世紀最高のベートーヴェン弾き」として「その名」を残した、南米チリ出身で、今年「生誕120周年」を迎えた偉大なマエストロ、クラウディオ・アラウ(1903-91)の名演奏もどうぞ。
「晩年」(1984-89)に録音された「ピアノソナタ全集」は、「月光ソナタ」(第14番)とともに、やはりこの曲が「未録音」だったため、ついに、「未完成」に終わってしまいました。
こちらは、「旧全集」からの音源で、1963年の録音となります。
こちらもやはり、アラウによる同年の録音からですが、べ―ト―ヴェン自身により、「この曲」にのみ入れられている、「メトロノーム記号」(![]() =138)を「順守」した演奏となっています(「第1楽章」のみ)。
=138)を「順守」した演奏となっています(「第1楽章」のみ)。
ブレンデルの「師匠」でもあった名ピアニスト、エドヴィン・フィッシャー(1886-1960)は、「(速すぎる)この指定は間違っている」と断じていますが、「ピアニスト仲間」でもあったヴァルター・ギ—ゼキング(1895-1956)は、「この速さ」で弾いていたということです。
「参考」までに、やはり「譜面付き」の演奏をどうぞ。
テーマが「ベートーヴェン」のこれまでの記事。
「記念サイト」もまだあります...。
さて...
日本では「楽聖」とも呼ばれているべートーヴェン(1770-1827)ですが、「12月16日頃」が「誕生日」だということで(「洗礼」を受けたのが「12月17日」とのことから)、やはり、「1年の終わり」に、その「名曲」を紹介してみたいと思います。
今回のこの曲、「ピアノソナタ第29番 変ロ長調 op.106 "ハンマークラヴィーア"」(1817-19)は、すでに「後期」の様式で書かれている作品ながら、「中期」の「爆発的な力」すら感じさせる、大変「精力的」な曲でもあり、べ―ト―ヴェン自身の「ピアノソナタ」の中でも、「最大規模」を誇っているとも言うことが出来るものです。
その「原因」のひとつとして、いわゆる「不滅の恋人」との恋が実らず、結婚を「断念」したであろうことも関係しているのではないかと言われていますが、そのため、その影響は、1815年においてもなお、続くことになりました。
(参考)「交響曲第8番」についての記事
病床にあった弟カ―ルの「援助」のため、出版社からお金を借りていたべ―ト―ヴェンは、その「返済」の代わりに、「新作」である「ピアノソナタ第27番 ホ短調 op.90」(1814)その他を、「無償譲渡」することになりましたが、そのカ―ルも、11月に亡くなったため、今度は、「甥」であるカールの、「後見問題」に悩まされることになってしまいました。
べ―ト―ヴェンと関わりの深い、ラズモフスキー伯爵(1752-1836)の邸宅が火災に遭ったこともあり(1814年12月31日)、1816年2月には、その「四重奏団」も「解散」となってしまいますが、そのメンバーのひとりで、「親友」でもあったチェリスト、ヨ―ゼフ・リンケ(1783-1837, 「命日」は、べ―ト―ヴェンと同じ「3月26日」)のために、「チェロソナタ第4番 ハ長調 op.102-1」「同第5番 ニ長調 op.102-2」(1815)の2曲が書かれることになりました。
そして、これらの曲あたりが、いわゆる、「後期の入口」と呼ばれているものです。
「第4番」(上「約15分」)、「第5番」(下「約20分」)とも、「旧ソ連」の偉大なマエストロ、ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(1927-2007)のチェロ、スヴャトスラフ・リヒテル(1915-97)のピアノという、「歴史的名演奏」でどうぞ。
また、1816年には、当時「医学生」であった、アロイス・ヤイテレス(1794-1858)によって書かれた詩による「連作歌曲」、「はるかなる恋人に寄す op.98」、そして、「ピアノソナタ第28番 イ長調 op.101」が書かれたことで、ここでようやく、「スランプ」からの「脱却」を果たしたようでもあります。
(参考)歌曲集「はるかなる恋人に寄す」についての記事
そんな折、べ―ト―ヴェンは、「出版社」に対し、ある「提案(依頼)」をしています。
それは...
「第28番以降のソナタには、(イタリア語の) "ピアノ(フォルテ)"ではなく、ドイツ語表記の "ハンマークラヴィーア" をタイトルに使ってもらいたい」
というものでした(1817年1月23日)。
しかし、これが誤って受け止められたのか、「ハンマークラヴィーア」は「副題」として(「ハンマークラヴィーアのためのソナタ」ではなくて)、その次のソナタにのみ使われることになってしまいました。
これが、今回の曲のタイトル、「ハンマークラヴィーア」の「由来」なのです...。
べ―ト―ヴェンが、この曲の作曲に取りかかったのは、1817年11月のこと。
体調は相変わらず悪く、6月には、1817年冬のシ―ズンにロンドンへ招聘するため、「交響曲」を2曲(=後の「交響曲第9番」)書いてもらいたいという、「依頼」も受け取っていたところでしたが、その代わりに書き始めたのが、この「ピアノソナタ第29番 変ロ長調 op.106 "ハンマークラヴィーア"」だったのです。
結局、ロンドンへは行くことが出来ませんでしたが、あのメルツェルが、今度は、「新発明」した「メトロノーム」を持って現われ、先の「ウェリントンの勝利」についての裁判の費用を「折半する」ということで、「和解」に至りました。
べ―ト―ヴェンは、この「メトロノーム」を「絶賛」し、さっそく、「第8番」までの「交響曲」の「速度表」なるものを発表し、新聞には、「推薦文」も載せているくらいなのですが...。
1818年5月には、「問題」の甥、カールを連れて、郊外のメ―トリンクに滞在することになりますが(「ハフナーハウス」)、そこに贈られて来たのが、「英ブロードウッド社の最新型ピアノ」でした。
当時、すでに「第2楽章」までは「完成」し、「第3楽章」を「作曲中」という「ハンマークラヴィーア・ソナタ」でしたが、それまでべ―ト―ヴェンが使っていた「シュトライヒャー」のピアノは「高音域」に強く、逆に、「ブロ―ドウッド」は、「低音域」に強いピアノでした。
「第3楽章」までは、従来使用していた「シュトライヒャ―」で完成させたとする見方が「有力」ですが、「第4楽章」には、その「ブロ―ドウッド」でしか弾けない、「超低音」が書き込まれているのです。
(「ピアノ独奏曲」の場合、べ―ト―ヴェンは、「演奏不可能な音」は、原則、楽譜に書き込んではいません)
しかし当時は、楽器の「改良」、「発展」が盛んでもあったため、「そのうち、1台で弾くことが出来るピアノも登場するだろう」という「思惑」があったものとも考えられています。
そして、極めて「演奏困難」であることもまた「事実」で、べート―ヴェン自身も、
「私の死後50年を経ても、演奏は至難であろう」
と、語っていたほどだということです。
こうして、1819年3月頃、ようやく「完成」となったこのソナタですが、
「ほとんどパンのために書くことはつらいことだった...」
とも述べており、当時の、「切羽詰まった」状況がうかがえるというものです。
(参考記事)「詳しく」はこちらを...。
毎度おなじみ、「おやすみベートーヴェン」からもどうぞ。
この後、いよいよ「ミサ・ソレムニス ニ長調 op.123」(1823年完成)や、「交響曲第9番 ニ短調 op.125 "合唱付き"」(1824年完成)へと、歩みを進めることになるのですが、まだまだ「前途は多難」で...。
当時、「枢機卿」への「昇進」(1819年4月24日)や、「オルミュッツ大司教」への「就任」(1820年3月)も控えていたルドルフ大公に献呈すべく、「ミサ・ソレムニス」の作曲を急いでいたべートーヴェンではありましたが、結局間に合うことはなく、「大幅」に、「遅れる」ことになってしまいました...。
今回の曲、「ハンマークラヴィーア・ソナタ」もまた、ベートーヴェン最大の「パトロン」であり、「弟子」であり、「友人」でもあった、その「ルドルフ大公」(1788-1831)に捧げられた作品なのです。
「後期」に入ったべート―ヴェンは、J.S.バッハ(1685-1750)の「遺産」でもある「対位法」を研究し、それを曲の中に採り入れることによって、「スランプ」を乗り切りました。
「第9交響曲」の「歓喜の歌」もその一例ですが、もちろん、この「ハンマークラヴィーア・ソナタ」にも活かされ、「両端楽章」、特に、「最終(第4)楽章」の「フーガ」は、規模も大きく、「入念」に作り込まれていることから、演奏は、「技術的」に極めて難しく、しかも、「崇高さ」すら求められています。
「フ―ガ」と言えば、この曲もそうですね。
「ディアベリのワルツによる33の変奏曲 (ディアベッリ変奏曲) op.120」(1823)。
1990年頃のブレンデルによる名演奏で、「東京」での収録ですが、これも「きっかけ」のひとつとなって、1992年1月29日の「大阪公演」(「ザ・シンフォニーホール」)には、私自身、足を運んでもいます。
まさにこの曲の「ハイライト」とも言える、ヘンデル(1685-1759)風に始まる壮大な「二重フーガ」、「第32変奏」を、内田光子さん(1948-)のピアノでもどうぞ。
(参考)この曲についての記事
そして最後に、「もはや現代音楽」とまで評されている「前衛的」な作品、「大フーガ 変ロ長調 op.133」(1825-26)もあわせてどうぞ。
もともとは、「弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 op.130」(1825)の「最終楽章」でしたが、当時の「理解」をはるかに超える作品であったため、「外された」ものです。
「理解」が進んだのは、やはり「20世紀初頭」...。
つまり、「現代音楽」の時代になってからだということです。
...というわけで、大変長くなりました。
「ピアノの交響曲」と呼ぶ人もいるという、この「ピアノソナタ第29番 変ロ長調 op.106 "ハンマークラヴィーア"」。
ぜひ一度、聴いてみてください。
ありがとうございました。
それではまた...。
(daniel-b=フランス専門)