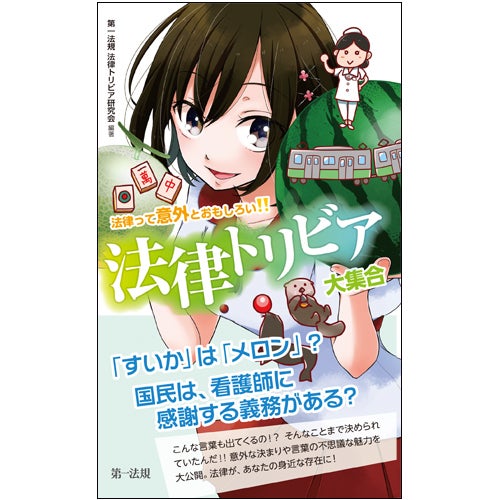こんにちは、第一法規「法律トリビア」ブログ編集担当です![]()
大昔、お金というものが無かった時代は、
例えば山で狩猟した人と、海で魚を獲った人とが、肉を魚とを交換して、
色々な物を手に入れていました。
今は、欲しい物があるときは、お金を出して買いますね。
ですが、最近、インターネットでは物々交換のサイトも登場しています。
インターネットという新しいコミュニケーションの手段を使って、
昔ながらの物々交換が行われているのは、面白いですね。
さて、お金を介して物が売り買いされるためには、そのルールが必要になります。
民法には、売主が物や権利を渡し、買主は代金を支払うという、
売買のルールが書かれています。
★民法(明治29年法律第89号)
(売買)
第555条
そして、それに続き、手付金に関する決まりや、
買ったものが実は故障していたことが判明したらどうするか、
といったことについての決まりが書かれています。
売買は、消しゴム一つ手に入れるにも必要な行為なので、
365日、日本中で行われていますから、
売買についてのルールが細かく決められているのは当然のことでしょう。
それでは、物々交換についてはどうでしょうか。
お互いの持ち物を取り換えるだけですから、
わざわざ法律で決めなければならないようなルールはないように思いますね。
しかし、実は「民法」には、物々交換に関する決まりが書かれているのです。
一体何が書かれているのでしょうか。条文を見てみましょう。
まず、民法によると、「交換」とは、
お互いに金銭以外のものを相手にあげる約束をすることをいいます。
★民法(明治29年法律第89号)
第586条第1項
ただし、「交換」の約束をした人同士の間で、どのようなルールがあるか、
具体的には書かれていません。
実は、「民法」を見ると、物と物を交換する約束をした人には、
物の売買に関するルールが使われるという規定があります。
★民法
(有償契約への準用)
第559条
例えば、買った物に欠陥があって使えない場合、買主は売買契約を解除することができます。
これは、「瑕疵担保責任」と呼ばれています。
売買に関するこのようなルールを、物々交換の場合に当てはめると、
例えば、Aさんはヘリコプターのラジコンを、Bさんは車のラジコンを持っていて、
それを交換した場合に、車のラジコンの部品に欠陥があり、
真っすぐしか走れないことが判明したとしましょう。
車のラジコンをもらったAさんとしては、
カーブを曲がることができないのでは全然楽しくないので、持っている意味がないでしょう。
この場合、売買と同じルールを使えば、
Aさんは、Bさんとの物々交換の契約を解除し、
ヘリコプターのラジコンを返すよう求めることができる、ということになるでしょう。
ですので、物々交換といっても、いい加減な気持ちで臨んではいけませんね。
(この記事は、2019年1月29日時点の情報に基づいています)
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
いかがでしたでしょうか。
ブログ本『法律って意外とおもしろい 法律トリビア大集合』もぜひご覧ください!
是非、次回もお楽しみに![]()
![]()
by 第一法規 法律トリビア編集担当