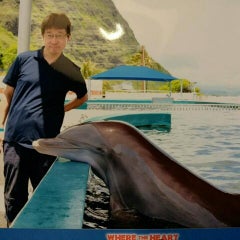今回は予告していた通り、「竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)」を取り上げます。
今回の投稿で膀胱炎等に用いられる一般用漢方薬で「八味地黄丸(はちみじおうがん)」、「清心蓮子飲(せいしんれんしいん)」、「五淋散ごりんさん」、「猪苓湯(ちょらいとう)」そして「竜胆瀉肝湯」の使い分けがわかるようになると思います。
では、さっそく「竜胆瀉肝湯」の構成生薬と配合量をみてみます。
「地黄(じおう)」5.0「当帰(とうき)」5.0「木通(もくつう)」5.0「黄芩
(おうごん)」3.0「車前子(しゃぜんし)」3.0「沢瀉(たくしゃ)」3.0「甘草(かんぞう)」1.0「山梔子(さんしし)」1.0「竜胆(りゅうたん)」1.0 出展は「薜氏十六種(へきしじゅうろくしゅ)」です1)。
パッと見た感じは、生薬構成が「五淋散(ごりんさん)」に似ていると思いました。
「竜胆瀉肝湯」と「五淋散」の共通生薬は、「地黄」「当帰」「木通」「黄芩」「車前子」「沢瀉」「甘草」「山梔子」で異なるところは「竜胆瀉肝湯」は「竜胆」を「五淋散」は「芍薬」「茯苓」「滑石」を含むところです。
ということは、「竜胆瀉肝湯」と「五淋散」の違いは共通する生薬の配合量は別として「竜胆」vs「芍薬・茯苓・滑石」の役割の違いになるのでしょうか。「竜胆」の性質が気になりますね。
「竜胆瀉肝湯」の君薬*1の「竜胆」は、「大苦大寒。肝胆の実火を瀉す。下焦の湿熱を除く。(➡️瀉火*2)」とされます1)。
*1君薬:一方中の主薬で、疾病の主証に対して主な治療効果を発揮する薬剤をいいます。
*2瀉火:肝や胆の強い熱と気の逆上を抑え、下します。熱が身体の上部に上った場合と、体内の水毒が結合して湿熱として内蔵に滞った場合の双方に効果があります。具体的には怒りや苛立ちなどの精神症状や眼・耳の炎症、口内炎などのような頭部の炎症、頭痛を治療すると同時に、陰部の炎症やこしけなど下半身の炎症も治療します2)
つまり、肝の実熱を清熱する目的がメインの方剤で肝実ということは、肝胆の実熱が腎膀胱に影響を与えて(五臓の親子関係では肝が親で腎が子になり、親の影響を子が受けてしまいます)膀胱に湿熱がある病態と考えればよいと思われます。
最後に一般用漢方薬で、効能に膀胱炎等を標榜している漢方薬の使い分け(鑑別)を載せて終わりにしたいと思います1)。
「八味地黄丸」:口渇、軽度の排尿痛のほか、全身倦怠感、足腰の冷えや痛みを訴え、下腹部が上腹部に比し緊張が弱い場合(小腹不仁の腹証)に用いる。(腎陰陽両虚)
「清心蓮子飲」:比較的体力が低下した人で、胃腸虚弱、冷え性、神経過敏の傾向がある場合に用いる。(気陰両虚と心火旺)
「五淋散」:体力中等度の人で、やや体質が虚弱で、冷え性の傾向があり、症状が慢性に経過する場合に用いる(表寒蓄水の証)。(腎気不足で熱淋)
「猪苓湯」:体力中等度の人で、冷え性の傾向がなく、排尿困難、排尿痛、残尿感などを訴える場合に用いる。(下焦水熱互結)
「竜胆瀉肝湯」:比較的体力のある人で、排尿困難、排尿痛、残尿感を訴えるとともに、帯下陰部掻痒感なと生殖器症状を伴う場合に用いる。(下焦湿熱)
あとは実際にお客さまにお使いいただき、使いどころを体得するだけですね。
引用・参考文献
1)「腹証図解漢方常用処方解説」髙山宏世先生編著
2)『よくわかる漢方処方の服薬指導』雨谷栄先生および糸数七重先生共著
AD