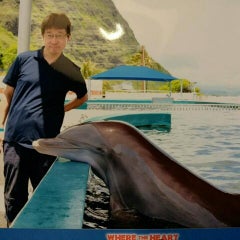漢方薬コーナーである漢方薬を手に取って吟味しているお客さまを発見しました。
『いらっしゃいませ。何かご説明しましょうか。』
「いえ、今はいいです。」
『かしこまりました。失礼しました。』
レジに戻って別のお客さまの会計をしたのちに、先ほどのお客さまがこちらを振り向きました。『これはAIDMA(アイドマ)の最後の「A」の段階、つまりActionです。』
私はすぐにお客さまのもとに行きました。
「これ(命の母®ホワイト)とこれ(クラシエ薬品の当帰芍薬散)はどう違うのでしょうか?」

↑命の母®ホワイト

↑クラシエ当帰芍薬散
『「命の母®ホワイト」は生薬製剤で「当帰芍薬散」は漢方薬という違いがあります。婦人向けの三大漢方薬というのがあってそれは、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」、「桃核承気湯(とうかくじょうきとう)」といわれていますが、「命の母®ホワイト」はその「当帰芍薬散」と「桂枝茯苓丸」を合わせたような内容になっています。』
「良いとこ取りということですか。」
『簡単に言うとそうです。また、網を広げてかするようにしていると思われます。また配合生薬量が少ないことと相まって効果を実感しにくいと思います。「効き目なんてこんなもんだろう。」とか「効いてるか効いてないかわからないけどとりあえず飲んでみる。」という感覚で漫然と飲んでいる方が多い印象です。』
以前、「命の母®ホワイト」の説明をした時より上手く説明できました。(⇒こちら)
「なるほど。わかりました。こちら(当帰芍薬散)はどうですか?」
『「当帰芍薬散」は「四物湯(しもつとう)」と
「五苓散(ごれいさん)」を合わせたような漢方薬で、貧血(血虚)や浮腫(水毒)に起因する種々の症状に奏功します。肩こりの方に勧めて喜ばれたことがあります。』
「わかりました。ではメーカーの違いはありますか?ツムラとクラシエの違いはありますか?」
『はい。実はあります。「当帰芍薬散」は出典が金匱要略でそこでは用いる生薬が[朮(じゅつ)]としか書かれていません。そこで問題が生じます。現在の日本薬局方では[朮]を[蒼朮(そうじゅつ)]と[白朮(びゃくじゅつ)]の二つに厳密に分けています。両方とも利水作用があるのですが[白朮]は脾胃の水分を取り除く作用(補気健脾的な作用)があり、[蒼朮]は体表の水分を汗として取り除きます。』
※以前、「[蒼朮]か[白朮]」というタイトルで投稿しています。よろしければお読みください。(⇒こちら)
「なるほど。それでこれはどうなんですか?」
『クラシエの「当帰芍薬散」は[蒼朮]を使っているようですね。体表の水分を取り除くことを意図していると思います。』
※「当帰芍薬散」はツムラもクラシエも[朮]は[蒼朮]を使っています。
実はクラシエ薬品の「当帰芍薬散」をうちの店は二種類扱っています。そこでお客さまから違いについて質問を受けました。
「これ(漢方セラピーシリーズ)とこれ(青い箱のクラシエ当帰芍薬散)はどう違いますか?」
『どちらも錠剤で配合生薬量も一緒です。しかし漢方セラピーの方は成人の1回量(4錠)が1パックになっていますが、コッコアポの方は瓶にひとまとめに入っています。それの違いです。』
お客さまの最後の質問は「生理不順にはどうですか?」という質問でした。
『[川芎(せんきゅう)]には調経作用があるので効果は期待できると思います。半年生理が来ない方に勧めて奏功したこたがあります。』とお答えしました。
このお客さまは「クラシエ当帰芍薬散」を買って行かれました。
今回はスラスラと説明ができました。良かったです。
『いらっしゃいませ。何かご説明しましょうか。』
「いえ、今はいいです。」
『かしこまりました。失礼しました。』
レジに戻って別のお客さまの会計をしたのちに、先ほどのお客さまがこちらを振り向きました。『これはAIDMA(アイドマ)の最後の「A」の段階、つまりActionです。』
私はすぐにお客さまのもとに行きました。
「これ(命の母®ホワイト)とこれ(クラシエ薬品の当帰芍薬散)はどう違うのでしょうか?」

↑命の母®ホワイト

↑クラシエ当帰芍薬散
『「命の母®ホワイト」は生薬製剤で「当帰芍薬散」は漢方薬という違いがあります。婦人向けの三大漢方薬というのがあってそれは、「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」、「桃核承気湯(とうかくじょうきとう)」といわれていますが、「命の母®ホワイト」はその「当帰芍薬散」と「桂枝茯苓丸」を合わせたような内容になっています。』
「良いとこ取りということですか。」
『簡単に言うとそうです。また、網を広げてかするようにしていると思われます。また配合生薬量が少ないことと相まって効果を実感しにくいと思います。「効き目なんてこんなもんだろう。」とか「効いてるか効いてないかわからないけどとりあえず飲んでみる。」という感覚で漫然と飲んでいる方が多い印象です。』
以前、「命の母®ホワイト」の説明をした時より上手く説明できました。(⇒こちら)
「なるほど。わかりました。こちら(当帰芍薬散)はどうですか?」
『「当帰芍薬散」は「四物湯(しもつとう)」と
「五苓散(ごれいさん)」を合わせたような漢方薬で、貧血(血虚)や浮腫(水毒)に起因する種々の症状に奏功します。肩こりの方に勧めて喜ばれたことがあります。』
「わかりました。ではメーカーの違いはありますか?ツムラとクラシエの違いはありますか?」
『はい。実はあります。「当帰芍薬散」は出典が金匱要略でそこでは用いる生薬が[朮(じゅつ)]としか書かれていません。そこで問題が生じます。現在の日本薬局方では[朮]を[蒼朮(そうじゅつ)]と[白朮(びゃくじゅつ)]の二つに厳密に分けています。両方とも利水作用があるのですが[白朮]は脾胃の水分を取り除く作用(補気健脾的な作用)があり、[蒼朮]は体表の水分を汗として取り除きます。』
※以前、「[蒼朮]か[白朮]」というタイトルで投稿しています。よろしければお読みください。(⇒こちら)
「なるほど。それでこれはどうなんですか?」
『クラシエの「当帰芍薬散」は[蒼朮]を使っているようですね。体表の水分を取り除くことを意図していると思います。』
※「当帰芍薬散」はツムラもクラシエも[朮]は[蒼朮]を使っています。
実はクラシエ薬品の「当帰芍薬散」をうちの店は二種類扱っています。そこでお客さまから違いについて質問を受けました。
「これ(漢方セラピーシリーズ)とこれ(青い箱のクラシエ当帰芍薬散)はどう違いますか?」
『どちらも錠剤で配合生薬量も一緒です。しかし漢方セラピーの方は成人の1回量(4錠)が1パックになっていますが、コッコアポの方は瓶にひとまとめに入っています。それの違いです。』
お客さまの最後の質問は「生理不順にはどうですか?」という質問でした。
『[川芎(せんきゅう)]には調経作用があるので効果は期待できると思います。半年生理が来ない方に勧めて奏功したこたがあります。』とお答えしました。
このお客さまは「クラシエ当帰芍薬散」を買って行かれました。
今回はスラスラと説明ができました。良かったです。