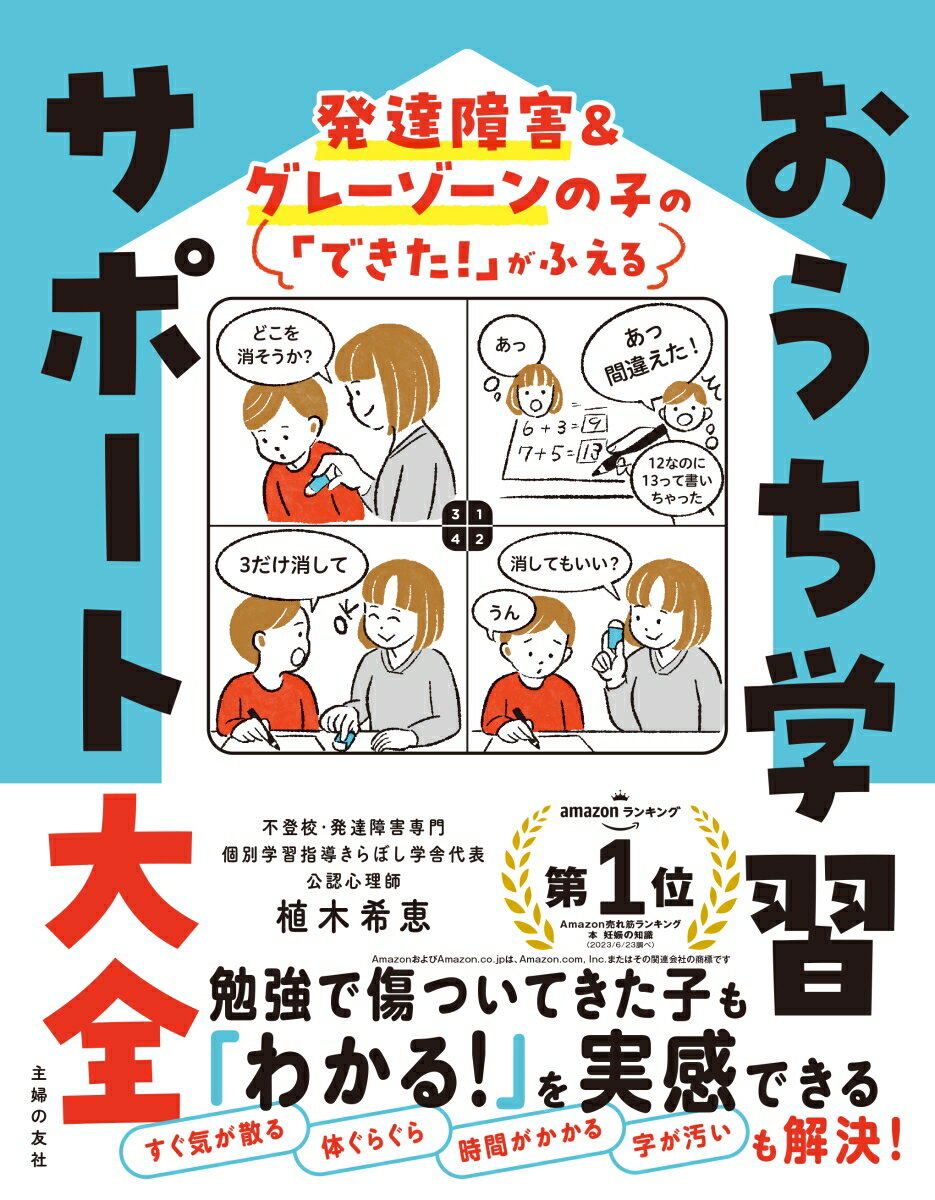こんにちはー!Starfisfです。
いいね!フォローありがとうございます。![]()

どうでもええことかもですが、今回からタイトルに数字を入れることにしました。
何回目よりも月日の方がいいんですかね~?![]()
息子の特性とそれに基づいた塾選びの道のりについて。続編です。
まだ途中経過ではありますが、お話ししたいと思います。
息子は現在小学6年生。
ADHD、学習障害、自閉症の特性を持っています。
これらの特性がどのように彼の学びに影響を与えていていくのか、自分の備忘録も兼ねて残しておきます。
一話目はこちら⬇
三話目はこちら⬇
四話目はこちら⬇

この日は久しぶりに
通級▶塾へ行きました
息子 塾 5回目の様子です
息子は、算数を理解するでまでに、とても時間がかかるタイプの子です。
例えば四角形の面積の問題があったとします。
たてが700m よこが300m
この長方形の面積を求めなさい
普通なら、なんの迷いもなく掛け算をしますよね。
問題文を見つめ、手が動かない息子に声をかけます。
わたし
息子
から始まるのです。

しかも四角形って長方形だけじゃないじゃないですか。平行四辺形や台形などいろいろあって。。
その都度、その図形の特徴を伝えないとならなくて。。多分ちゃんと形が頭の中に入ってないからだとは思うんですが、毎回教えても分からないって、教える意味あるか?って毎回思っちゃいます。![]()
これは果たして、
覚えてないだけ
(脳がそこまで必要と感じていない)
または
覚えられない
(脳の機能的に理解不能)
どっちかわからないから毎回説明してしまうんですよね。。。![]()
親の心配を他所に、本人は算数にすごく不安があるわけではないようですが、分かった時には楽しいと感じられるものの、テストの得点が伸び悩むことがよくあります。
息子
良くても60点台といったことが多く、決して悪くはないけれど、「努力した結果がこの点数か」と思うと、親としても少し複雑な気持ちになります。
これまで通級指導の先生や学校の先生と一緒に繰り返し学び、テストでどこが問われるのかを抑えながら取り組んできましたが、文章から計算や筆記問題へと移行するまでのプロセスが、息子には特に時間のかかる課題のように感じます。
ぜんぶで~ とか残ったのは~ で答えられた低学年の頃に戻りたい
そんな息子が塾に通い始めたのは、私の友達からのおすすめがあったからです。
また、相場よりも費用が安いというのも選んだ理由の一つです。
ただ、これまでのグループ指導に加え、マンツーマン指導に切り替えればもっと効果が出る可能性があります。(過去記事参考)
うーん、1か月だけでも試してみようかなぁと悩んでいるところです。

一方で、国語については塾では重視していません。息子は今のところ文章の読解力について公文でしっかり基礎を身につけられているからです。
そのため、塾ではあえて国語をしなくてもいいのではないかと考えています。とはいえ、公文の国語を続けるべきかどうかは、まだ考え中です。
公文の英語も検討中。
公文だけで22000円かかるんですよ。
塾は週二で12000円くらい
今までのルーティンを変えるのは勇気が要ります

今回の塾の結果
今回は、国語と数学に取り組んだそうです。
簡単なフィードバックをもらいながら、進捗を確認することができました。
- 国語:同音異義語の理解はOK!
まずは国語について。今回は「同音異義語」と「同訓異字」を中心に取り組む。先生からは、「選択問題が正解できていたので、理解できているように思います。国語はいいですね」とのお言葉があり、本人も少し自信がついた様子です。



- 数学:絶対値と正負の数の進捗
絶対値については、家庭で教えた「ゼロからの距離が同じ」という考え方が役立ったようで、先生からも「ちゃんと理解できていますね」と評価をいただきました ![]()


何回繰り返すんやねん!と言うほど繰り返さないとならず定着にはまだ時間がかかるということで、油断は禁物です。⚠️
今日の課題、「正負の数と不等号」のルールがまだ曖昧で 負の数はマイナスが大きくなるほど小さくなるという感覚を掴むには、繰り返し練習が必要そうです。
先生
わたし
> = <
例えば、マイナス7とプラス7を比較するとき、プラス7の方が大きいという理屈は理解できても、実際にプリントで問題に取り組むと戸惑うこともあるようでした。
息子には
と、帰ってから伝えると少し納得してた気がします👈

家庭学習と塾の相乗効果改めて感じたのは、塾だけでなく家庭での学びも重要だということ。
絶対値の基本的な考え方を家庭で教えたことで、塾での学びがより深まったように思います。
とはいえ、新しい内容をすぐに定着させるのは難しいので、焦らず何度も繰り返し学んでいきたいです。
最終的に目指しているのは、公文のようにプリント学習を通じて、息子が自分で問題を読み解き、自分の力で納得しながら問題を解けるようになること。それが、息子にとっての自信に繋がり、将来の学びを支える基盤になると信じています。
骨がなくてしかもウマいっ!(^^)

骨がないし、柔らかくてうまい!
また今年も買おう![]()
![]()
⟡.·*.··············································⟡.·*.
塾や公文、そして家でのサポートを組み合わせながら、息子に合った学びのスタイルを模索する日々。
この試行錯誤が、いつか大きな成果に繋がることを願っています。
自宅学習のヒントに
今後も親子で学習障害に立ち向かう?様子をブログで共有していきますので、ぜひまた読みに来てください。
最後までお読み下さり
ありがとうございました🙏