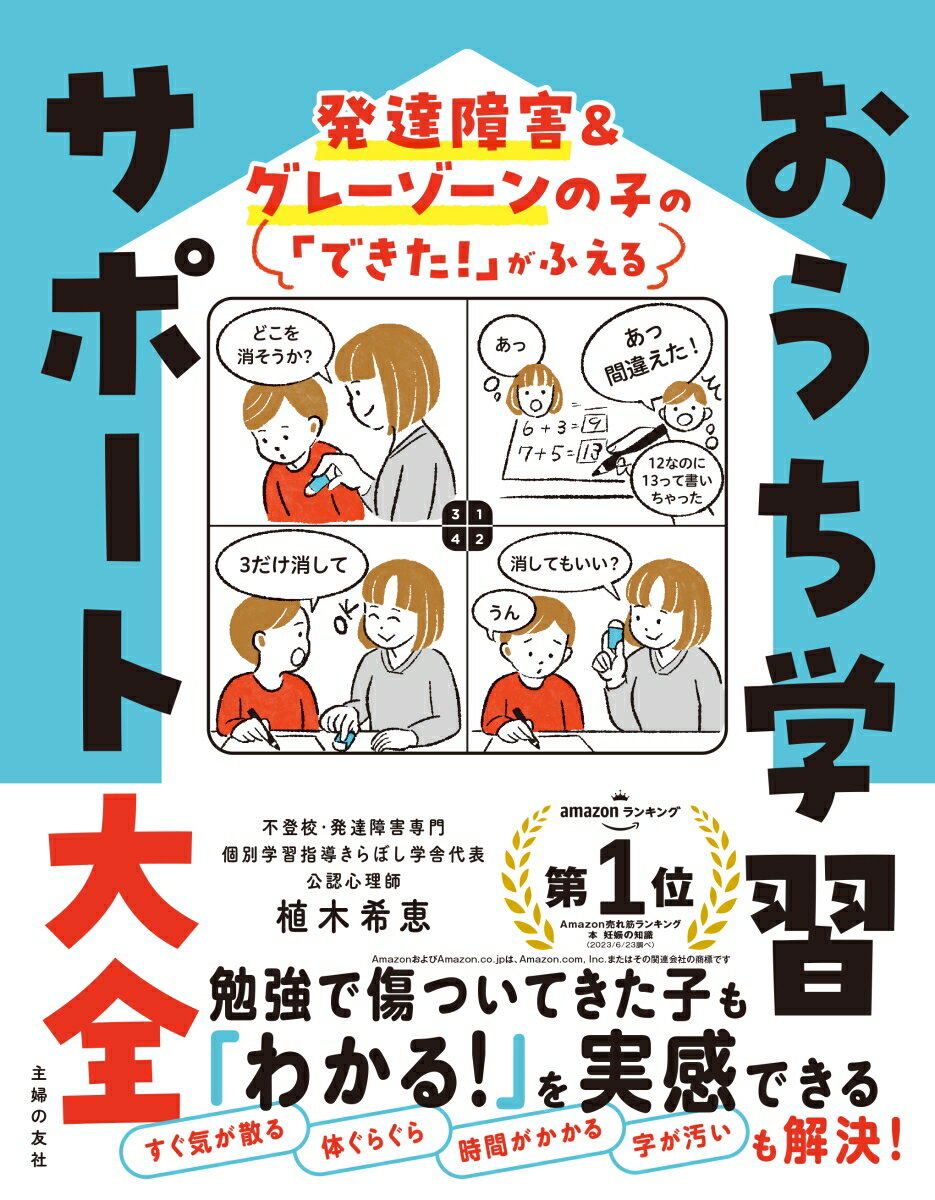こんにちはー!Starfisfです。
いいね!フォローありがとうございます。![]()

息子の特性とそれに基づいた塾選びの道のりについて。続編です。
まだ途中経過ではありますが、お話ししたいと思います。
息子は現在小学6年生。
ADHD、学習障害、自閉症の特性を持っています。
これらの特性がどのように彼の学びに影響を与えていていくのか、自分の備忘録も兼ねて残しておきます。
一話目はこちら⬇
塾 3回目の挑戦
息子が塾に通い始めて3回目の様子です
学校から歩いて帰宅
⬇
リフレッシュのため30分ゲーム
⬇
15分 学校の宿題
⬇
出発
新しいことに取り組むときは、こちらが思った以上に緊張や不安が伴う息子ですが、(昔過ぎて私が忘れてるだけでしょうが ![]() )
)
このルーティンを続けることで、少しでも気持ちを落ち着けてから塾に向かえるよう試行錯誤していきます。
移動中は車内でYouTubeをみるか、スマホでゲームが鉄板
他所もそうですよね?![]()

指導前に内容を依頼
塾の中に入ると担当の先生から
先生
今日もか。。![]()
お試しの時はこんなに満員にならなかったのに
受験シーズンが近いから、クラスが満員になるのは避けられないんだろうなぁ。
それでも息子にとって負担が少なくなるよう、今回は算数の基礎の基礎を重点的にお願いしました。
先生は前回の授業で
「歴史のプリントに集中できていた」
と感じていたらしく、今回プリントを用意してくれていたのですが、息子にとって文字が小さく見えづらいと伝えました。
なので、プリントを刷るときは字のサイズを倍にしてもらうようお願いしました。
そして、前回は数学の文字式の不等式でほぼ全滅だってので、数学の基礎の基礎をする方が良いのではと要望し、わたしは去りました。
50分後 塾へもどる
マンツーマンの提案と家庭の現実
この日の算数の指導では、「絶対値」や「正負の数」 といった基礎のプリントに取り組んだとこのことでしたが、息子にはプリントだけ渡して説明なしでは難しいようでした。
プリントに書かれた箇条書きの説明を見てもその内容は理解できず、何をヒントに考えるべきか さえ分からない状況だったそうです。
これは塾だけの問題ではなく、家庭学習でも同じです。
自宅ではすでにYouTubeなどの動画を見ながら「問題 の特徴」や「解き方のコツ」を具体的に示してから取り組ませています。
ただ、まだ3回目。
続けていけば「慣れる」ことができるのか、 続けても無駄なのか、私 自身もまだ判断がつきません。
自宅学習のヒントに

先生
私自身もマンツーマンが効果的であることは理解していますが、公文との同時進行で出費がかさんでいるため、現時点では厳しいとお伝えしました。

うーん。。塾には既に2か月分の前金を支払っているので、その期間で様子を見ようかなぁ。
家でのサポートと今後の課題
塾での環境にはまだ完全には慣れていないようですが、息子自身は「もう少し頑張ってみる」と前向きに話してくれました。
先生の声が少し大きめでちょっと気になる様子だったので、耳栓を使ってみることを提案しましたが、息子は「慣れるまで頑張る」と努力しようとしている姿勢を見せてくれました。
塾に通うこと自体を嫌がってはいないようで安心しました。![]()
過敏があっても大丈夫、な耳栓発見
それから見え方については少し問題というか課題があります。
息子は0.6程度の弱視で、斜視もありますが、眼鏡をかければ見えやすくなるはずなのですが、「人の目が気になる」と言って人前ではかけたがりません。
また、本人いわく「眼鏡をかけても完全に見えるわけじゃない」という感覚もあるようで、学校やくもんでも眼鏡を持参していません。
この視力の問題がプリントの文字の見えづらさに影響している可能性もあるので、少しずつ眼鏡を外で活用する習慣を促していきたいと考えています。
家ではメガネしてます

まだまだ課題はありますが、塾に対する抵抗感がないことは大きな前進だと感じています。
先生の声の大きさや本人の視力の問題など、サポートが必要な部分も見えてきたので、これらに向き合いながら息子の成長を見守っていきたいです。
今後も試行錯誤の様子をブログで共有していきますので、ぜひまた読みに来てください。