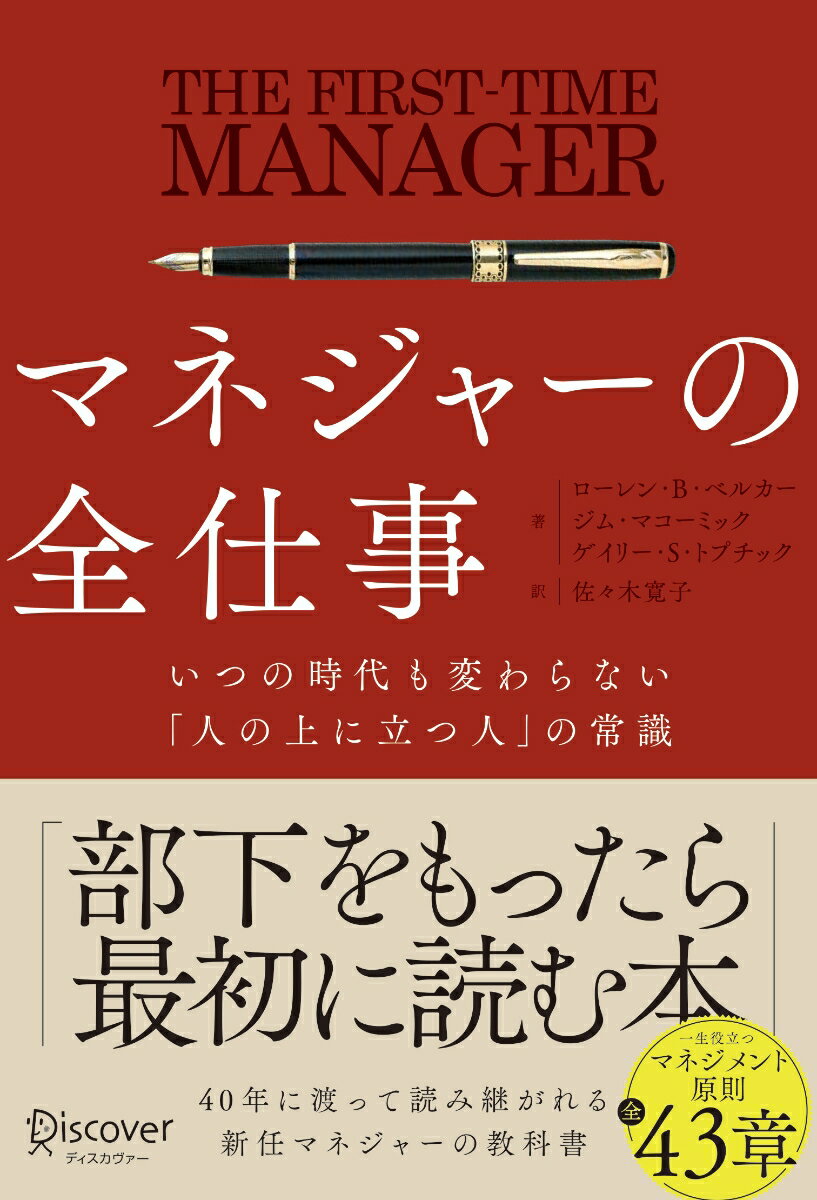カナダの流通大手がセブンイレブン買収ニュース。
成立はしないと個人的には思いますが、成長のために地域拡大は必要な一方で、流通業はその土地土地の商習慣あり、グローバル標準化は難しいように思います。
保険業界のように連邦制が正解なのでは。
昨日は朝から1on1やアライアンスの打ち合わせ。
午後は資料作成や内部の組織関連のミーティング。
夜はパートナーさんとの懇親会。
終わって深夜1時からグローバルコール。
なかなか忙しい。日常に戻ってきた感じ。
GDPが回復基調というニュース。
株価も現時点で37000円台と戻ってきました。
経済格差が広がっているという認識を持った前提で、旅行先に行くと明らかに消費支出は増加傾向にあるのではないかという印象を持ちました。一方で昨晩見たニュースでは貧困家庭では子供が1日二食しか食べれないという心が締め付けられる事柄も。経済の好循環がすべてのそうに行き渡るベーシックサービスのような仕組みの必要性を感じました。
**キーワード**: 国内総生産(GDP)、賃上げ、米中経済リスク
国内の景気が回復しつつある。内閣府発表によると、2023年4~6月期の実質GDPは前期比0.8%増、年率換算で3.1%増となり、2四半期ぶりのプラス成長を記録した。個人消費も5四半期ぶりに増加し、名目GDPは初めて600兆円を超えた。賃上げと投資が成長をけん引している一方、今後は賃上げ効果が消費を支える見通し。リスク要因として、米中経済の減速が挙げられる。中国の不動産業の不振や、米国の景気先行きが日本経済に影響を及ぼす可能性がある。
今日は79回目の終戦記念日。
昨晩テレビで、漫画が好きだった特攻兵の方の特集を見ていた。未来ある青年の人生を狂わす戦争。
今この瞬間も世界では犠牲になっている。平和を祈っていく。
研究もAIによる自動化ができてしまいますね。
**キーワード**: AI自動化、The AI Scientist、科学研究
Sakana AIは8月13日に「The AI Scientist」を発表しました。このシステムは、AIを用いて研究のアイデア出しから実験、論文執筆、査読までを自動化します。特に、大規模言語モデル(LLM)を活用し、テーマに基づくアイデア生成、実験設計、結果の分析、論文の作成を自動的に行い、査読も別のAIが担当します。研究速度と効率の向上が期待される一方で、質的評価や倫理的な課題が残されています。