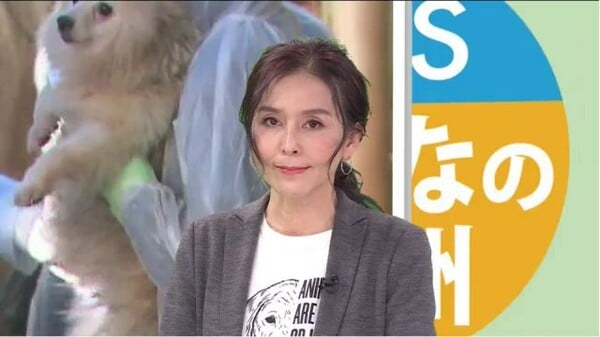特定非営利活動法人C.O.N -17ページ目
麻酔をかけず
帝王切開を行う。
あり得ないことだ。
痛みはどれほどか、
想像を絶する。
そんな恐ろしいことが
長年に渡り放置され、
許されてきた。
何が動物愛護法かと思う。
Evaさんや勇気ある人々が
事件として、
ここまで表面化させてくれて、
やっと、
無麻酔帝王切開が、
追送検された。
私たちがはじめて
無麻酔帝王切開の存在を
耳にしたのは
もう10年以上前。
動物虐待などではない。
殺傷の罪に問われることが
当然だと思う。
これでやっと、
法律が当たり前に
動きだすのか。
動き出してほしい。
当たり前の法律が
当たり前に使われること。
理不尽に命を落とす
犬猫たちが救われること。
願いは
ただそれだけ。

地域ケア個別会議に
参加させていただきました。
今回で4回目になります。
この会議は?
解決が困難な課題のある事例について、
他職種の方々が集まり
情報共有をしつつ対応策を検討します。
福祉関係の部署の方々や
アドバイザーとして専門職種の方々
などがずらっといる中、
私は『高齢者さんとペット』つながりの
立場で発言させてもらうのですが、
皆さん本当に真剣です。

人間のことも大変なのに
犬猫のことなんて、
と言われてきたことが
抜け切れないのか、
なんて熱心に聞いてくれるんだろうと
心の中で感動しています。
とともに、
皆さんの課題解決に
向かおうとする姿勢が
とても新鮮です。

高齢者さんとペットの
見守り案件が
増えてきました。
こういう場合はどうしたらいいんやろ?
法律はどうなってるんやろ?
と考えることが多いのですが、
この会議で
的確なアドバイスをもらえるので
非常にありがたいのです。

福祉のお世話にはなりたくない。
そんな高齢者さんも
意外と多いです。
そうなると、
地域や社会とのつながりがなく
孤立しがちなのですが、
猫つながりなら、
交流ができるケースが
多々あります。
この会議では、
そんなようなことも
理解してもらっています。
まだまだ苦情の的に
されてばかりの
猫たちですが、
猫が高齢者さんを
助けてるやん。
そんな気がする
この頃です。

C.O.Nは、政策提言の団体ですよね。
なのにどうして多頭飼育の現場に
関わっているんですか?
と聞かれたらしい。
うちが現場に関わってないって?
と理事長は、
返す言葉を見失ったそうですが。

現場のボランティアは、
もがき苦しんでいて、
現場の痛みを身に刻み、
そこから対策を見出し、
議会や行政に訴えてきました。
苦しんでいる
多くの人たち、
そして猫。
その助けにならないのなら、
私たちには、
何の意味もありません。
答えは現場にありと
言われますが、
正しい情報も
現場にしかありません。
正しい情報がなければ
本当に必要とされる対策も
生まれないと思います。
やはり、答えは
現場にしかないのです。
尼崎西ロータリークラブさんの例会にて、
動物愛護についてお話しする
機会をいただきました。
ロータリークラブでのお話しは3回目。
今回も顧問が
お話しさせていただきました。
皆さまには、
とても熱心に
聞いていただき、
共感しました、
協力しますよ、
と。
知っていだたくことで、
尼崎西ロータリークラブの皆さま
貴重な機会を
ありがとうございました。
1月18日
都ホテル尼崎
多頭飼育の
相談が続いていますが、
これまでとは
だいぶん様子が違ってきました。
速やかに不妊手術をすれば、
飼い主の生活がなんとか回復し、
猫との生活も維持できるかも…
というレベルです。

多頭飼育問題の取り組みを
始めた頃は、
回復なんて思いもしませんでした。
ここは室内なのか、沼なのか?
そんな所に猫が何十匹もいて、
猫の死骸が埋もれていました。
飼い主のその後の生活を
考えてあげる余裕など
あるはずもなく。
一日で60匹以上の猫を引き取り、
その数日後、飼い主さんは
どこへ行ったか分からなくなった
という事もありました。
ここにきて、
以前より早い段階で
相談が入ってきていることに
気づきました。
なぜなんでしょう?

多頭飼育問題は、
なんといっても未然防止
ですが、
一旦増えてしまったら
出来る限り早く不妊手術をしなければ
なりません。
ですが、
何十匹もの不妊手術費用をどうするか?
まず、それが大きな問題になります。
61匹崩壊の時も『自腹』でした。
ボランティアが
肩代わりするしかない
というのが通常です。
この現状が
議会や協議会に届き、
尼崎市に、
多頭飼育崩壊を防ぐための
助成金ができました。

これまで関わった多頭崩壊の飼い主に
「なぜこうなったの?」
「どうして手術しなかったの?」
と、毎回質問しましたが、
ほぼ全員が『経済的な理由』
をあげました。
お金です。
なので、
飼い主にとっても、
サポートするボランティアにとっても、
この助成金が、
あると無いでは大違いなのです。

2つ目の問題は、
助成金が出るといっても、
手元に入るのは
手術が済んで約2ヶ月後。
そんな先では、
今すぐ不妊手術しても、
動物病院に払うお金がありません。
多ければ数十万円。
ボランティアだって
よく知らない人の高額な手術代を
立て替えることは簡単ではありません。
そのフォローとして、
その手術代を立て替えた方の
銀行口座に直接助成金が振り込まれる
という方法も可能になっています。
このおかげで、
当法人でも躊躇なく
立て替えができています。

これらが揃って現場では、
「速やかに手術をする」が、
稼働するようになりました。
『有効な対策がある』
これが、
早い段階で相談が入っている
大きな理由だろうと思います。
多頭崩壊の現場で、
猫たちの犠牲を目の当たりにして
学んだことは、
なんとしても
こんなことになる前に、
です。
なぜなら、
確実に不妊手術で
防げることだからです。




今日、福祉の方から
助成金で手術をしたい方がいると
連絡がありました。
猫の頭数は?
5匹と聞いて、
この問題にかかわってきて、
よかったなぁと思いました。
ですが、
これは出口。
蛇口が締まったわけではありません。
本気の未然防止の
仕組み作りは
これからです。

検察側は、
犬舎での劣悪な飼育状況を
撮影した動画を法廷で公開し、
「帝王切開を判断し指示していた」
との百瀬被告の供述内容の一部を
明らかにした。
信じ難いが、
麻酔をせず帝王切開をしていたことは、
現段階では
起訴されていないそうです。
なぜ?
検察は4月中に、
追起訴するかどうか判断する
見通しとのことですが、
長い長い時、
夥しい数の犬たちが犠牲になった
恐ろしい事実が
明らかになっても、
動物愛護法は、
まだ
ちゃんと動かないのか?
市外のとある場所
1ヶ月と8日。
捕獲のための餌付けに
通い続けています。
今日は
その捕獲の日。
普通の捕獲器では、
絶対に捕まらない状態なので、
ここはTNRアシストのTOKIさんに
お願いするしかないと、
事前に、
現場の様子や猫の状況を
やり取りしながら、
色々ドアドバイスをもらって
いよいよ当日。
TOKIさん、万全を期して、
最新バージョンの捕獲器を
使うとのことです。
スタッフ一同ド緊張、
それくらい私たちも
切羽詰まっていましたが、
TOKI さん難なく成功!
1匹の白猫さん
やっと、
無事に保護できました。
TOKIさん
ホント感謝です。
尼崎市議会 維新の会さんの
会派勉強会へ。
テーマは「動物愛護について」
TEAMねこのてさん
ふみふみさんから
それぞれの活動について
報告がありました。
TEAMねこのてさんも
ふみふみさんも
シェルター運営をされており、
市民から待ったなしの相談が
ひっきりなしです。
多くの猫を
受け入れているからこその
現場の声。
飼育放棄や多頭飼育崩壊など
猫の飼育放棄がいかに多いか、、、
とともに、
あまりに多くの猫が行き場を無くし、
その受け皿が無いに等しい
というこの事実が、
いかに切実な問題なのか
伝わってきます。
当法人からは、
2016年から取り組んできた
多頭飼育問題
高齢者とペット問題について
お話しいたしました。
質疑応答では、
議員の皆さんから質問が途切れず、
時間が足りないくらいでした。
それだけ
しっかり受け止めていただけたのだと
思います。
有意義な機会をいただき、
ありがとうございました。
日時:2月24日(木)10時
会場:中央北生涯学習プラザ
尼崎市連合婦人会さんの研修会で、
『地域で行う野良猫対策』をテーマに
お話しさせていただきました。
副理事長の桑畑から
20年の地域猫活動について。
ふみふみ代表の西尾さんからは、
尼崎市の野良猫対策活動について
お話ししました。
地域のことは地域でと、
野良猫対策活動にも
取り組んでくださっている
パワフルな会長さんにも
久々にお会いできました。
第二部の講演にも参加させていただき、
脳トレでポカポカ。
心身ともにリラックスしました。
野良猫問題も多頭飼育問題も、
高齢者とペット問題も、
一番の対策は未然防止です。
地域のリーダーの皆さんと
交流の機会をいただいて、
猫問題の早期発見、早期支援へ
つなげていきたいと思っています。
貴重な機会を
ありがとうございました。