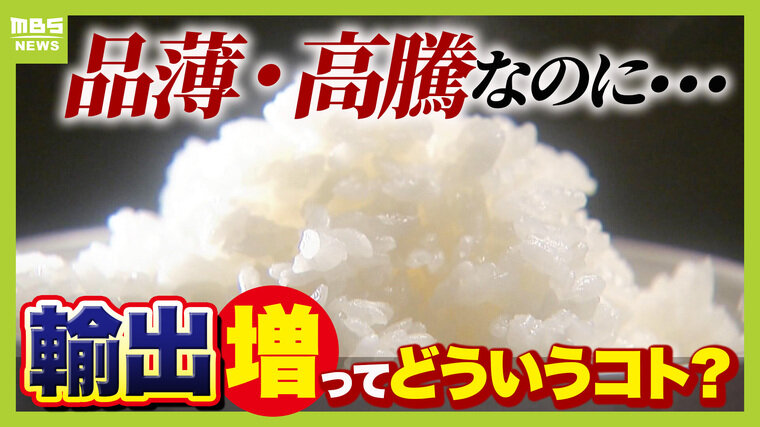今年はお米が大変です
そしてスーパーでのお米価格は最高値。
ニュース曰く、4,217円/5kgだそうです。
大阪万博用にお米を確保しているといった噂をSNSで見たような気がしますが、あの情報が本当だったら来年は大丈夫だよね、と思いたい。
でもお米農家の平均年齢が70才という現実を見ると、今後もお米の収穫量が漸減し、国産米を入手しづらい状況が恒常的な風景になるかもしれません。
昨年わたしがお米を作ったコストは原価だけで8,000円/10kgでした。
無化学肥料&無農薬なので出費は多くないはずですが、雑草だらけで収量が少なかった為、このくらいの原価になった次第です。
そんな私としては、今のお米価格高騰の状況は、単に安過ぎたお米価格が適正化されているので良い傾向なのでは?と思ったり…。
っていうか今の問題は価格ではなく、お米を買いたい人が購入できない状況になっていること。
一体お米はどこに行ったんでしょうね。
この状況を前向きに捉えるとしたら「このくらいのお米価格であれば農業やろうかな」という人が出てくるのでは?という長期的な希望かな。
- 実家に田んぼがある人は、今の仕事を続けながら自給できるくらいのお米づくりをする
- 田んぼがない人は、休耕田を使わせてもらい(※今の私)、お米づくりの経験と実績を培い、将来的には里山に移住して自給自足生活を満喫する
…みたいなことが日本中で進めばいいのになと思っています。
お米の一時的な輸入拡大案もあるようです。
でも、米国産のお米は輸送コストをかけているにも関わらず何故か国産米より安い。
なんか怪しい
一方、お米を輸出する意図もあるそうで。
President Onlineが掲載しているキヤノングローバル戦略研究所の方の記事がありました。
「コメ農家の時給10円説」はウソである…日本人に高いコメを買わせ続ける農水省・JA農協の"裏の顔"この記事に「■戦後の「農地改革」の大失敗」という章がありますが、失敗ではなく「誰かの思惑どおり」だったとしたら?
もしこの仮説に対して抗おうとした場合、必要なことは「常識を疑う力(非常識)」かなと思ったり
1837年(天保8年)に大坂(現在の大阪市)で起きた大塩平八郎の乱。
この背景には、天保の大飢饉による食糧不足と米価高騰、役人や豪商の不正がありました。
彼は民衆救済を奉行所に訴えましたが拒否され、自らの蔵書を売って救済にあたりましたが限界を感じ、武装蜂起を決意しました。
1837年2月19日、大塩は自宅に火を放ち、門弟や農民らとともに豪商や役人を討つために挙兵しましたが、反乱は半日ほどで鎮圧。
しかしこの乱は幕府や社会に大きな衝撃を与え、各地で一揆や反乱が相次ぐきっかけとなり、幕府の改革(天保の改革)にも影響を与えました。
今、社会的に必要なのは現代版大塩平八郎の乱かもしれません。
私は大塩平八郎のような動きをする自信を持ち合わせていませんが、せめておうちで食べるくらいのお米は自分で作れるように動きたいなと思います。
政治に対して言うべきことを言うってことはとても大事なことだなと思うようになってきました。
一方で自分は何が出来るのかを考えて、自分自身が何らかの行動に移すことも大事だなと思うようにもなりました。
これから必要な知識は、常識的には生成AI? AGI?
いやいや、やっぱり田んぼでお米をつくるスキルでしょ
これが現代の非常識でしょうかね