おいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ
正垣泰彦
日経BP社
ISBN978-4-8222-3348-8
おいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ/正垣泰彦
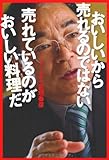
¥1,470
Amazon.co.jp
<目次>
第1章 「客数増」がすべて
第2章 十分な利益を確保するには
第3章 リーダーと組織の在り方
本書はサイゼリヤ創業者が書いた本です。
飲食業に関する経営を指南する本はたくさんありますが、本書ほどロジカルに端的に書かれているのが特徴的です。
ロジカルなのは、著者が理系出身だからかもしれません。
読んでみると、サイゼリヤの経営は科学的手法のように感じます。
つまり、仮説を立て、数字で検証し、結果を確認し、改善する。
PDCAのサイクルで経営していることです。
抽象的な方針であいまいに運営し、結果だけで成否を見るのでは、正しく成長できないのではないかと思います。
科学的ということは、不確実であることが前提であり、何かを行った場合、成功か失敗かといえば、失敗することが前提です。
昨今の成果主義からすると、失敗することが許されない風潮があると思いますが、途中経過の失敗を容認し、最終的に成功することを認めてもらえるならば、社員はトライしやすいのではないでしょうか。
もちろん企業ですから、短期間に成功にしなければならないでしょう。
理系的な経営は、曖昧な文系的経営よりも、実はドライな分、やりやすいのかもしれません。
正垣泰彦
日経BP社
ISBN978-4-8222-3348-8
おいしいから売れるのではない 売れているのがおいしい料理だ/正垣泰彦
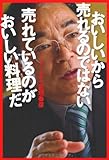
¥1,470
Amazon.co.jp
<目次>
第1章 「客数増」がすべて
第2章 十分な利益を確保するには
第3章 リーダーと組織の在り方
本書はサイゼリヤ創業者が書いた本です。
飲食業に関する経営を指南する本はたくさんありますが、本書ほどロジカルに端的に書かれているのが特徴的です。
ロジカルなのは、著者が理系出身だからかもしれません。
読んでみると、サイゼリヤの経営は科学的手法のように感じます。
つまり、仮説を立て、数字で検証し、結果を確認し、改善する。
PDCAのサイクルで経営していることです。
抽象的な方針であいまいに運営し、結果だけで成否を見るのでは、正しく成長できないのではないかと思います。
科学的ということは、不確実であることが前提であり、何かを行った場合、成功か失敗かといえば、失敗することが前提です。
昨今の成果主義からすると、失敗することが許されない風潮があると思いますが、途中経過の失敗を容認し、最終的に成功することを認めてもらえるならば、社員はトライしやすいのではないでしょうか。
もちろん企業ですから、短期間に成功にしなければならないでしょう。
理系的な経営は、曖昧な文系的経営よりも、実はドライな分、やりやすいのかもしれません。



