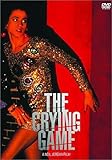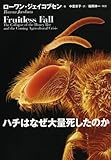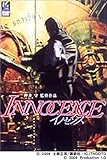- イノセンス スタンダード版 [DVD]
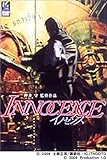
- ¥2,660
- Amazon.co.jp
NHKの沸騰都市という番組で、押井監督の製作チーム作成による
アニメーションが流れていました。
東京の未来を描いた秀作かと思いましたが
それをみていて、この映画のことも思い出していたのでした。
そういえば、この映画のことをブログに書いたのもNHK特集がきっかけでした。
というわけで再掲載します。
先日(2006年4月当時)放映していたNHKのプレミアム10「立花隆が探る サイボーグの衝撃」。
技術がここまで進んでいるのかということに驚きを隠せなかった。
脳の電気信号を外部に伝達して、考えるだけで遠く離れた場所の義体を動かせるし
逆に外部の刺激を脳に直接伝達することも可能らしい。
ということは、
体が麻痺してしまった人が、考えるだけでインターネットができたり、
義手でモノをつかんだり出来るし、しかも、そのつかんだ感触を
感じることもできるということ。
失明した人が、モノを見ることが出来るようになることも可能だ。
(実際は見ているように感じるだけだけど)
人間と機械の共生。
これが発展していけば、
考えるだけで、自分の思いを相手に伝えることが可能になる。
番組の中でも、
情報の共有の歴史が語られていて、
活版印刷→電信→電話→インターネットという流れがあるなかで
次のフェーズに来るものは脳だけでのコミュニケーションであろうということだった。
人間と機械の共生
語呂合わせでは無いが、これが一部の強力な権力者によって
強制的にもたらされるものだったとしたら・・・
脳に電極を埋め込まれ、キーボード操作の意のままに動かされるラット。
(本人は自分の意志で動いているように感じているんだろうな)
※生物の尊厳を踏みにじる行為だと思う。
→人間を意のままに操ることが出来るのかもしれない
記憶をつかさどる海馬の人工的な修正
(記憶=PCで言うところのメモリーという見方。記憶の外部化)
→記憶を自由自在に操ることが出来るのかもしれない。
もうこんなことも実用化に向けて動いているらしい。
全ての技術は軍事産業と密接に結びついて発展してきました。
パソコンができたのも、高度な計算を行う必要性があったからですし。
ということは、
恐らくは軍事的にこういった研究が利用される日もそう遠くないのかもしれませんね。
となると・・
ちょっと怖くなってきたのでここらへんにしておきます。
アカルイミライよりも
ちょっとした絶望を感じてしまいました・・
「こころ」は誰のものでもない。
それは、それが属する個人のものではないだろうか。
それを守るために。
我々は何が出来るのだろうか・・・