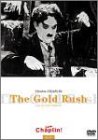※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
冬に楽しみたい映画たち~X'mas、Snowy Movie~
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

高倉健が北国を舞台にした素敵な映画を届けてくれました。
この映画を見たときに本当にそう感じたものです。
どうも僕の中では、高倉健というと、北国(北海道)というイメージが定着してしまっています。
『駅ーstation
』では、増毛町(ましけ)、『居酒屋兆治
』では函館、
そして『幸せの黄色いハンカチ
』では夕張・・
彼ほど雪の大地に、はまる俳優はいないのではないでしょうか?
この映画は、雪深い道央の架空の町「幌舞」が舞台です。
この駅前の風景が、僕が少年時代をすごした田舎町ととても似ていたんですよ。
駅前タクシー、駅前のお土産店、駅前の食堂・・・
北国のローカル線の田舎町におそらく共通するであろう要素たち・・
この風景だけで、涙がでるくらいの懐かしさを覚えた方も多いのではないでしょうか?
鉄道は、田舎の人の大切なインフラです。
人々は、それぞれの思いを抱えて、鉄道に乗り込んでいったことでしょう。
車掌は、そんな人々を長い間見つめ続けます。
でも、過疎化の波は確実に田舎町を襲います。
鉄道の廃止、バスへの移行。
80年代半ば以降、日本全国で見られた風景ではないでしょうか。
僕の町もそうでした。
心のゆりかごであった、鉄道がその役目を終えると同時に、
車掌もその生を終えます。
この映画のラストは涙なしにはみれないでしょう。
つらく長く、そして寒く厳しい冬を過ごしてきた北国のものにとってはなおさらだと思います。
高倉健も、小林念侍も、とてもすばらしい演技を披露してくれています。
でもこの映画に大切な要素は、きっと
彼らを包んでいる、北海道という大地なんだと思います。
大自然と、俳優達がうまく融合した
素敵な作品だと思います。
ぜひ、雪の降る町を訪れてみてください。
寒くても、きっと暖かい何かを感じることが出来るはずです・・・
このブログは再録です
初投稿:2005・11・21、再投稿2006・11・27