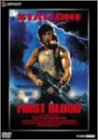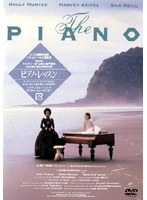- マイ・ブルーベリー・ナイツ オリジナル・サウンドトラック/サントラ
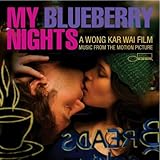
- ¥2,249
- Amazon.co.jp
映像がとても綺麗な映画でした。
やたら早く動く電車、早送りで登っていく太陽
たくさん出てくる青空。
そして夕焼けのシーン。
この映画も、その場所に居ないはずなのに、
行ったことがないのに何故か匂いを感じる映画ですね。
最後の方の言葉に
「道路を渡るのは簡単。それは向こう岸にいる人しだい」
というのが出てきます。
人と人の距離感の感じ方なんてのは
それこそ人それぞれ。
こっちが勝手に深いと思い込んだり
自分のしたいこと、やりたいことに没頭するための領域にたたずむことが
適度な距離だと思い込んだり
こういうのは往々にして、齟齬を生むもの。
ゆえに、まー七面倒なことがおこったりする
突然沸き起こる嵐は大体がそういうことに起因していたりする。
この映画に出演しているナタリー・ポートマンやレイチェル・ワイズ
演じる役柄はカジノに入り浸ったり、旦那のもとを離れて遊びまくったりと
自分の領域にたたずんでいる。
どことなく、何かの束縛から離れんとするために、そういうシチュエーションに
身をおいているような気もしないでもない。
きっと彼女たちにとって、それは心地よい距離なんでしょうね。
彼女たちの傍らにいる男性諸氏にとっては非常に居心地が
悪い領域ではあるんだけれど。
彼女たちなりの距離の置き方。
これが二人を隔てている道路の距離。。
でもその領域にたたずむことができていたのはきっと、
対岸にいる人がいてくれたから。
そんな事実に、対岸の人物を失ってから、たいていの人は気づく。
この二人との出会いを通して
ノラ・ジョーンズ扮する主人公は、おそらく自分なりの距離感を
つかんだのではないかな。そして元いた場所へ戻ってくる。
その場所は彼女にとっての対岸といえる場所だったりする。
「道路を渡るのは簡単。それは向こう岸にいる人しだい」
と言っては見たけれど、たぶん心の中では
「こちら側にいる自分しだい」なんて考えてるんかな?
なんて素敵なラストを見ながら考えておりました。
さてブルーベリーパイを食べに行こうかな。