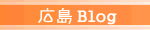6月21日パレスチナ報告会実施(その2)☆
前回の続きで、6月21日の体験型報告会の実施報告第二弾です![]()
今回はドラマアクティビティ体験について書かせていただきます![]()
前回の活動報告プレゼンの内容紹介が堅い感じになってしまったので、今回ははじけていきたいと思います(笑)![]()
当日のドラマアクティビティ体験では、大きく6つのワークを行いました![]()
一つ目はアイスブレーキングとして、リズムワーク![]()
輪になって、一人一人順番に足踏みをしてつないで、一周するというものです!![]()
最初は右、左、右、左…と素直に一回ずつ踏んで時計回り。
一周できたところで、次は二回足踏みをしたら逆回りになるというルールを加え、もう一周。
皆さん隣の方の足踏みに注意を払って、リズムよくつなげるよう、集中して行いました![]()
こうして参加者の皆さんに一体感(!)が生まれたところで、二つ目は自己紹介のワーク![]()
といっても、ただの自己紹介ではありません。![]()
一対一の自己紹介で相手と名前を「交換」しながら、次々に違う相手と「自己紹介」をしていきます。
例えば相手の名前が田中さんだったら、田中さんとの自己紹介の後は、あなたの名前は田中さんになります。そして次の自己紹介では自分の名前ではなく、「田中さん」を名乗ります。![]()
他人の名前を自分のものとして語るというのは、不思議な感じがするとともに、なんだか新鮮でもあります!![]()
三つ目は、ある特定の枠組みのなかで気持ちを語ってもらうというワーク![]()
最初は「天気」で今のお気持ちを表現していただくことに。
「曇りのち晴れ![]() です。」、「お隣の方よりかはちょっと明るめの曇り空かな~!
です。」、「お隣の方よりかはちょっと明るめの曇り空かな~!![]() 」などなど、皆さん天気を使って、雄弁にお気持ちを語って下さいました!
」などなど、皆さん天気を使って、雄弁にお気持ちを語って下さいました!![]()
次はなんと、「ニワトリの言葉」で気持ちを語るという難題です(笑)!![]()
皆さん最初はびっくりされていましたが、ファシリテーターの「コケコケコッコー???」という質問に対し、「コッココー」「クルックー!」など、ニワトリになりきって答えて下さいました!![]()
四つ目は、二人組で行う通称「二人羽織ワーク」![]()
1月の東京での報告会で行った際に好評だったワークです。![]()
一人が腰に手を当てて与えられたテーマについて語り、もう一人がその間から手を出して、手で話の内容を表現するというものです。![]()
これが見ているほうからしたらとっても愉快で盛り上がります!![]()
話す方の人は、自分の視界でブラブラ動いている手がなんだか気になりながら、どんな話をしたら手の役の人が表現しやすいかなんかも自然と考えながら話をすることになります。
一方、手の訳の人は話される内容を集中して聞きながら、どうやってそれらを手で表現するかを常に考え、頭はフル回転です!
皆さんやるのも見るのも、楽しんでいただけたようでした!![]()
最後は、簡単なロールプレイのワーク![]()
自分とは違う特定の立場の人になりきって歩いてもらうというものです。
こちらも、東京での報告会で反響があったワークです。![]()
お題は、①三つ子を妊娠している妊婦さん、②95歳のお年寄り、③身長50センチの小人、としました。![]()
「妊婦さんの歩きづらさも、妊娠何か月かによるかもね。」![]()
「小人が歩くって、どんな感じだろう!?」![]()
皆さんたくさん想像しながら、迫真の演技をして下さいました。![]()
全てのワークが終了後、皆さんで感想を共有しました。![]()
参加者の方々からが次のような声をいただきました。![]()
・ドラマアクティビティを体験したなかで、こういったワークを使うことで、短い時間で人と打ち解けられることに気が付いた!![]()
・普段とは違う振る舞いなどをすることによって、自分を客観的に見ることにもつながると思った。![]()
・ドラマアクティビティを実際に体験してみて、子ども(の心理ケア)だけでなく、お年寄り(の健康づくり)なんかにも効果がありそうだと思った。![]()
また参加いただいた方の中には、子どもさんと日常的に接するお仕事をされている方や、教育に携わっていらっしゃる方もいらっしゃいました。そうした方々からは、今回体験したワークをお仕事の場面で取り入れてみたいというお言葉もいただきました。
スタッフとしても、毎回報告会でドラマアクティビティの体験を行い、参加者の皆さんと感想を共有させていただく中で、ドラマ活用教育の効果を具体的に発見させていただいています。![]()
今回もそんな発見に富んだ報告会になりました!![]()
報告会にご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました。![]()
そして今回は参加できなかった方も、ぜひ次の機会にご参加ください![]()
お待ちしております![]()
 PBパレスチナ事務所のフェイスブックページ
PBパレスチナ事務所のフェイスブックページ
![]()
現地の活動の様子などをご紹介しています。
パレスチナ事業の内容をより近くにご覧いただけます。
www.facebook.com/PBpalestine
*パレスチナでの教育支援事業では随時ボランティアを募集しています。 日本語書類の英文化作業や、事業紹介、日本国内での広報活動などが主たる内容となります。 パレスチ問題にご関心のある方、詳しくはなくてもこれから知っていきたいという方、さらにはアラビア語ができるという方!!大歓迎です。 お気軽にメールにてお問い合わせください。
6月21日パレスチナ報告会実施(その1)☆
6月21日に広島市留学生会館にて、今年度第一回目のパレスチナ教育支援事業の報告会を行いました![]()
今回は現地駐在スタッフとスカイプで繋ぎ、現地から事業の活動報告を行うとともに、毎回好評をいただいている、ドラマ活用教育のアクティビティ体験も行いました!![]()
当日の報告会の内容について、これから2回にわたって紹介させていただきたいと思います!![]()
まず第一弾は、現地駐在スタッフからの活動報告の内容について。。。![]()
今回の活動報告では、昨年1年間の活動内容とその成果を中心に紹介させていただきました![]()
参加者の皆さまからは、「事業で行っているワークショップ(WS)の参加者は、ドラマ活用教育を職場でどのように実践しているの![]() 」、「事業を更に発展させていくための課題は
」、「事業を更に発展させていくための課題は![]() 」など、積極的なご質問をいただきました
」など、積極的なご質問をいただきました![]()
これらのご質問への回答も踏まえ、以下では当日の報告内容のポイントを紹介させていただきます![]()
****************************
★事業の活動の一つとして行っている「学校訪問」では、WS参加者(学校教員、ソーシャルワーカーなど)の81%が、ドラマ活用教育のアクティビティを子供たちに実践する能力を身に着けていることが確認された。![]()
たとえば、ある理科の先生は、身体の器官の仕組みを分かりやすく説明するため、お腹を壊した男の子に胃や腸が話しかけるという寸劇を子供たちと一緒に作って実践した。![]()
ワークショップでは、ドラマ活用教育の理論を紹介するだけでなく、実際の活用方法の体験ワークに重点を置いて実施してきたが、そのことが高い実践率へとつながったと考えている。
★学校でのドラマアクティビティの実践による子供たちの変化について、各受益者からは以下のような声が聞かれた。![]()
・学校管理職「長所や弱点を発見したり、心理的な負担を解放するのに役立っている」![]()
・WSに参加した教員「子供たちはよりよいリアクションを見せるようになった」![]()
・保護者「攻撃的だった子が落ち着いた」![]()
・子ども「人が怖くなくなって、自信が持てるようになった」![]()
★事業成果の拡大に向けて今後取り組んでいく課題は、次の4つ。![]()
①WS参加者がそれぞれの職場でドラマをより活用しやすい環境をつくるため、パレスチナ教育省やUNRWAへの一層の提言活動を行う。![]()
②WS参加者の継続的な支援とドラマ活用教育を用いた子供のケア体制を広げていくため、この分野に関わる専門家のネットワークをより拡充させる。![]()
③現在行っているヘブロンでの取り組みをモデルケースとして、ドラマ活用教育を用いた子供のケアの実践を他地域にも拡大させる。![]()
④事業の効果を測る上で、定量評価を確立する(子供の心理尺度を測るアンケートテストSDQテストの活用など)。![]()
活動報告の内容のポイントは以上です![]()
次回は、当日行ったドラマアクティビティ体験について、紹介させていただきます!
引き続き、ぜひご覧ください![]()
 PBパレスチナ事務所のフェイスブックページ
PBパレスチナ事務所のフェイスブックページ
![]()
現地の活動の様子などをご紹介しています。
パレスチナ事業の内容をより近くにご覧いただけます。
www.facebook.com/PBpalestine
*パレスチナでの教育支援事業では随時ボランティアを募集しています。 日本語書類の英文化作業や、事業紹介、日本国内での広報活動などが主たる内容となります。 パレスチ問題にご関心のある方、詳しくはなくてもこれから知っていきたいという方、さらにはアラビア語ができるという方!!大歓迎です。 お気軽にメールにてお問い合わせください。
ルワンダ大虐殺20周年追悼イベント

ピースビルダーズも新たな気持ちで取り組んで参りたいと思います

さて、この4月はルワンダの大虐殺から20年となります。
1994年4月6日から始まり、約3ヶ月の間に80万人もの人々の命が奪われるという未曾有の出来事は、アフリカの小国ルワンダの名を世界中に知らしめることになりました。
2005年の設立以来、「ホテル・ルワンダ」上映関連事業やルワンダ製エコバック「ピースバッグ」のフェアトレード事業などのルワンダ支援事業を行ってきたピースビルダーズは、去る3月29日に東京からチャールズ・ムリガンデ駐日特命全権大使をお迎えして、20周年追悼イベント「TWO of US~Rwanda & Hiroshima」を開催しました。

当日の大使のお話では、ルワンダが大虐殺という悲しい歴史を乗り越えて、近年目覚ましい発展を遂げているということが紹介されました。

その際、原爆により多くの人々の命が奪われた広島とルワンダとの相似性についても言及され、「ヒロシマがそうであったように、世界の人々の希望と勇気の源になるように発信していきたい」という力強いメッセージをいただきました。

また、ルワンダといえば、どうしても大虐殺のことが思い浮かべられがちですが、「千の丘」とも言われる山々や湖などの美しい自然、マウンテンゴリラをはじめとする貴重な動植物に恵まれているなど、ルワンダの溢れんばかりの魅力についてもお話しされました。


その後の質疑応答の時間には、ピースビルダーズの会員様から、「ともに凄惨な歴史を乗り越えて復興を遂げた広島市とキガリ市を姉妹都市にしたらどうか」というアイディアが提案され、大使もご関心を示して下さいました。

イベントの最後には、「ルワンダ&ヒロシマ」をテーマに一つの作品を作ろうという掛け声のもと、白い布に参加者の皆さんが思い思いのメッセージを寄せ書きしました。

この作品は、JICA中国さんが今年ルワンダで原爆展を開催される際に現地に持って行かれ、ルワンダの人々のメッセージが書き加えられる予定です。
 最終的にどのような作品に仕上がるか、とても楽しみですね!
最終的にどのような作品に仕上がるか、とても楽しみですね!

パレスチナ×ヒップホップ!(映画のご紹介)
春の陽気![]() が到来した3月中旬、話題のパレスチナ映画の上映が広島の横川シネマで始まりました
が到来した3月中旬、話題のパレスチナ映画の上映が広島の横川シネマで始まりました![]()
パレスチナのヒップホップムーブメントを取り上げたドキュメンタリー映画、
『自由と壁とヒップホップ』!!
2008年に作成され、日本では2009年の東京外国語大学での企画上映後、数か所で自主上映され、昨年末から全国各地の映画館で公開されています。![]()
春の陽気に誘われ、PBスタッフも先日観に行って来ました。とても考えさせられる映画でした。![]()
この映画に登場するパレスチナのヒップホップグループのメンバーたちは、音楽を通して、パレスチナの現状を発信するとともに、音楽の力を糧に、自分たちを取り巻く困難な状況に立ち向かっています。圧倒的な暴力を前にして、暴力に訴えるのではなく、芸術という形に変えて応答するということ、その手法を獲得していくということ。それは、ドラマ・イン・エデュケーションを用いたPBのパレスチナ事業につながるテーマだと思います。映画の中でヒップホップグループのメンバーの父親は、「何かを伝える手段としては暴力ではなく、芸術がいい」と語り、息子の活動を応援します。![]()
映画の大半の部分では、バックミュージックとしてヒップホップが流れています。
ズン、ズン、という胸にこだますリズムは、文字通り、人々の間にある様々な壁を越えて心を突き動かす何かがあるような、映画を観ながらそんな気がしてきました。![]()
家屋破壊、増殖する分離壁、度重なる検問による足止め―。「友人がイスラエル兵に殺された。この怒りと悲しみの気持ちをラップで表現したい」と訴え、ヒップホップグループのメンバーの協力の下、人々の前で自作の歌を披露した難民キャンプの少年は、後日、2年前の投石を理由に突然拘留され、懲役10年の刑を宣告されます。映画の中で映し出されるこうしたパレスチナの「日常」に対し、それでも尚、ヒップホップグループDAMのメンバーが「希望がある。その微かな光に賭けたいんだ」と語る場面は、胸に突き刺さります。
映画の終盤、同じパレスチナ人ラッパーとして固い絆で結ばれたイスラエル領リッダのグループDAMと占領地ガザのグループPRは、西岸ラーマッラーでのライブ共演を試みます。やっとの思いでガザから西岸への移動許可証を入手し(*)、ライブ会場に向かうPRですが、結局許可が覆され、当日は共演を叶えることが出来ませんでした。ストーリー自体はそこで終わるのですが、映画のエピローグの部分で、後日、両者の共演がついに叶ったことが伝えられます。![]() そして、最後にこのようなメッセージが添えられています。
そして、最後にこのようなメッセージが添えられています。
「この世もまだ捨てたものではない!」
この映画が発表されたのは2008年。
2009年12月末から2010年1月にかけて行われた大規模なガザ攻撃と2012年11月の再度の集中攻撃、そして現在まで引き続くガザの完全封鎖状態を思うと、この希望のメッセージに対する私たちの応答責任を痛感せずにはいられません。
「同情はもう十分。今パレスチナに必要なのは行動」。
大学時代に参加した講演会でユダヤ系アメリカ人の人権活動家アンナ・バルツァーさんが聴衆に訴えた言葉を、改めて胸に刻みたいと思います。
映画の詳しい情報は、下記の公式ホームページをご覧下さい![]() 予告編も観ることができます!
予告編も観ることができます!
http://www.cine.co.jp/slingshots_hiphop/
また、下記の監督のインタビュー記事も映画の背景が紹介されており、面白いです!
http://synodos.jp/international/6564
広島の横川シネマでは3月28日まで上映されています。全国の劇場でも随時公開になりますので、皆さまぜひ観に行ってみて下さい!!![]()
(*)パレスチナ、特にガザにおける移動の自由の制限の状況については、少し前の情報になりますが、下記のページの「2.パレスチナ占領地における支援」の項が参考になります。
・UNフォーラム フィールドエッセイ第14回 児玉千佳子さん
(UNDPパレスチナ人支援プログラム プログラム・アナリスト<当時>)
http://www.unforum.org/field_essays/14.html
*パレスチナでの教育支援事業では随時ボランティアを募集しています。 日本語書類の英文化作業や、事業紹介、日本国内での広報活動などが主たる内容となります。 パレスチ問題にご関心のある方、詳しくはなくてもこれから知っていきたいという方、さらにはアラビア語ができるという方!!大歓迎です。 お気軽にメールにてお問い合わせください。
Two of Us~Rwanda & Hiroshima~
少しずつ暖かくなって、春が近づいてきました。![]()
桜![]() の便りが待ち遠しい今日この頃です。
の便りが待ち遠しい今日この頃です。
さて、3月29日にルワンダ駐日大使をお迎えして、学生NGO L'harmonie~ラルモニー~と一緒に「Two of Us~Rwanda & Hiroshima~」と題してイベントを行います。![]()
1994年4月のルワンダジェノサイド(大虐殺)から20周年を迎えた今年、ヒロシマの地で平和についてルワンダ駐日大使が語ります。
ルワンダ駐日大使は、来日してすぐの2011年8月6日に広島を訪問され、平和記念式典に参加されました。
この時もピースビルダーズは、大使を平和記念資料館などにご案内しました。
*2011年8月駐日ルワンダ全権特命大使来広ブログは、こちら
*2012年4月ルワンダ虐殺追悼セレモニーブログは、こちら
今回も大使からぜひ広島の方々と平和について語りたいとのお話をいただき、学生NGO L'harmonieのご協力をいただいて、イベントを行うことになりました。![]()
タイトル&テーマ:Two of Us~Rwanda & Hiroshima~
日時:3月29日(土) 14時~16時
場所:広島県民文化センター6F ひろしまNPOセンター交流スペース
プログラム:
14:00~14:20 イントロダクション
14:20~15:20 ルワンダ駐日大使講話
15:20~15:30 休憩
15:30~16:00 特別企画「Two of Us」
特別企画「Two of Us」とは、当日の参加者全員で「ルワンダとヒロシマは仲間!」のメッセージを込めた1つの作品を作る予定です。![]()
申込み方法:
「氏名、所属」を明記の上、lharmoniewaon@gmail.com にメールを送付してください。
お問合せ:naoki.aka.naoki@gmail.com (赤澤:学生NGO L'harmonie~ラルモニー~代表)
皆様の参加をお待ちしております